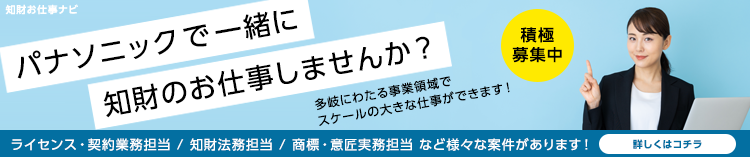| 関連審決 |
取消2022-300932 |
|---|
| 元本PDF |
裁判所収録の全文PDFを見る
|
|---|---|
| 元本PDF |
裁判所収録の別紙1PDFを見る
|
| 元本PDF |
裁判所収録の別紙2PDFを見る
|
| 元本PDF |
裁判所収録の別紙3PDFを見る
|
| 事件 |
令和
6年
(行ケ)
10087号
審決取消請求事件
|
|---|---|
|
5 原告 ディーパックファスナーズ(シャノン)リミテッド 同訴訟代理人弁護士 尾関孝彰 同 松阪絵里佳 10 被告Y 同訴訟代理人弁護士 山田威一郎 |
|
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
| 判決言渡日 | 2025/02/27 |
| 権利種別 | 商標権 |
| 訴訟類型 | 行政訴訟 |
| 主文 |
1 原告の請求を棄却する。 15 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を30日と定める。 |
| 事実及び理由 | |
|---|---|
|
請求
20 特許庁が取消2022-300932号事件について令和6年5月21日に した審決を取り消す。 |
|
|
事案の概要
1 本件は、商標法50条1項に基づく商標登録取消審判請求について、特許庁 が請求不成立とした審決の取消しを求める事案である。争点は、同条2項所定25 の期間に日本国内において、登録商標の商標権者、専用使用権者又は通常使用 権者のいずれかが請求に係る指定商品について登録商標の使用をしていたか否 1 かである。 2 特許庁における手続の経過等 ? 被告が商標権者である登録第6162919号商標(以下「本件商標」と いう。)は、「UNBRAKO」の文字を標準文字で書して成る商標であり、 5 平成30年10月20日商標登録出願され、第6類「金属製金具」を指定商 品として、平成31年4月12日登録査定され、令和元年7月19日設定登 録された。(甲1、2) ? 原告は、令和4年10月19日付けで本件商標の指定商品(第6類「金属 製金具」)について、商標法50条1項に基づく不使用取消審判請求(以下10 「本件審判請求」という。)をし、同年11月4日本件審判請求(取消20 22-300932)の登録がされた(同条2項所定の「その審判の請求の 登録前3年以内」とは、令和元年11月4日から令和4年11月3日まで (以下「要証期間」という。)である。)。 ? 特許庁は、令和6年5月21日に、本件審判請求は成り立たないとの審決15 (以下「本件審決」という。)をし、その謄本は、同月30日原告に送達さ れた。 ? 原告は、令和6年9月25日、本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起 した。 3 本件審決の理由の要旨20 ? 中島工機株式会社(以下「中島工機」という。)は、本件商標について商 標権者である被告から使用許諾を得た通常使用権者であるところ(甲12、 本件審決の乙1)、中島工機は、要証期間中の令和3年6月9日に、株式会 社小野に対し、アンブラコ製の使用商品(ボルト)100個を納入し(甲1 4、本件審決の乙3)、その納入に際して、使用商標(Unbrako)を25 付した包装箱(黒色の外箱。甲13、本件審決の乙2)に使用商品を収納し て譲渡又は引き渡したものである。 2 そして、使用商標は、包装箱に付された「Unbrako?」の構成など から「Unbrako」の文字が独立して自他商品識別標識としての機能を 果たすものであり、使用商標「Unbrako」の文字と、本件商標「UN BRAKO」の文字は、大文字と小文字の差はあるものの、綴りを共通にす 5 るから、社会通念上同一の商標である。また、使用商品「ボルト」は、「金 属製金具」の範疇に属する。 以上からすれば、通常使用権者が、要証期間に日本国内において本件審判 請求に係る指定商品(第6類「金属製金具」)の範疇に属する「ボルト」の 包装箱に、本件商標と社会通念上同一と認められる使用商標を付して譲渡又10 は引き渡した(商標法2条3項2号)と認めることができる。 ? よって、被告は、要証期間中に日本国内において、通常使用権者が審判請 求に係る指定商品について本件商標(社会通念上同一と認められる商標を含 む。)を使用していたことを証明した。 |
|
|
審決取消事由に関する当事者の主張
15 1 原告の主張 ? 中島工機が、株式会社小野に対し、本件審決の乙2に係る製品(甲13、 以下「乙2製品」という。アンブラコ製のボルト100個)を納入するに際 し、「Unbrako?」の文字を付した包装箱に「収納」して譲渡又は引 き渡した事実はない。包装箱に原告のロゴである「Unbrako?」を付20 したのも、製造した製品を「収納」したのも、原告である。 ? 商標法50条の「登録商標の使用」というためには、当該登録商標が商品 又は役務の出所を表示し、自他商品又は役務を識別するものと取引者及び需 要者において認識し得る態様で使用されることを要すると解するのが相当で あり、商標権者とは無関係の第三者が出所として特定されている場合には、 25 商標の出所表示機能(自他商品識別機能)は発揮されていないものといえる。 本件において、「Unbrako?」並びに「UNBRAKO」「Unb 3 rako」及び「アンブラコ」が原告の企業グループを指すことは周知であ る。乙2製品の包装箱での表示態様からも、取引者及び需要者に原告の製品 であることを強く印象付けており、復代理店のうちの1社の中島工機も「U NBRAKO」「Unbrako」及び「アンブラコ」は、メーカー名であ 5 ると明示して製品を販売してきたものである。原告は、被告による本件商標 の登録を許諾したことはなく、乙2製品の包装箱に付された「Unbrak o?」は、物品受領書/現品票(甲14、本件審決の乙3)と同様、本件商 標の登録とは無関係の製品メーカー名が表記されたにすぎない。 よって、被告による乙2製品の販売は、本件商標について被告とは無関係10 なメーカーを出所として特定し販売する行為であるから、出所表示機能を発 揮する態様での商標使用行為ではない。 ? 中島工機は、「UNBRAKO?」の付された乙2製品の販売による商標 使用の効果(出所表示機能、品質保証機能、宣伝広告機能等)を原告に帰属 させているため、原告を代理し原告のために前記ロゴを商標的に使用してき15 たといえる。 よって、乙2製品の販売は、被告が保有する本件商標の使用とはいえず、 商標法50条の「登録商標の使用」に該当しない。 2 被告の主張 ? 本件商標の通常使用権者である中島工機は、本件商標「UNBRAKO」20 と社会通念上同一の使用商標を付した包装に収納された「金属製金具」を令 和3年6月9日に株式会社小野に販売しており、商標法2条3項2号所定の 使用行為をした。原告が乙2製品を製造し、原告のロゴを包装箱に付し、原 告の企業グループがブランド名を広告したことなどは、いずれも通常使用権 者が要証期間に、商標法2条3項2号の使用行為をしたことを認めない理由25 にはならない。 ? 裁判例には、商標法50条の趣旨から同条所定の「登録商標の使用」は、 4 当該商標がその指定商品又は指定役務について何らかの態様で使用されてい れば足り、出所表示機能を果たす態様に限定されるものではないとするもの もあるから、原告の主張は一般的なものではない。商標法2条3項2号等の 規定は、生産者が登録商標を付した商品を卸売業者や小売業者が仕入れて転 5 売する行為も登録商標の使用に該当することを当然の前提としており、また、 海外の事業者により商品に付される商標が、日本の代理店や販売店等の名義 で商標登録されることも一般的である。 本件では、乙2製品を購入する需要者において、乙2製品を原告が海外で 製造した製品であると認識する可能性を否定することができないが、そのよ10 うな認識は、使用商標(Unbrako)が出所表示機能、自他商品識別機 能を発揮していることの裏付けである。中島工機は、原告の正規の復代理店 であり、正規の原告の製品を仕入れて販売する業者であるため、需要者は、 使用商標(Unbrako)が付された乙2製品を、原告が海外で製造した 製品と認識するのは当然であり、そのことをもって、本件商標について被告15 とは無関係のメーカーとして特定したとはいえない。 ? 中島工機は、原告の製品の正規の復代理店として、乙2製品等の原告の製 品を日本で販売し、自ら商標法2条3項2号の使用行為を行ってきたから、 中島工機の販売行為につき、原告を代理し原告のために前記ロゴを商標的に 使用してきたと評価することはできない。また、商標法50条の「登録商標20 の使用」の該当性の検討に当たり、登録商標が付された商品の販売による商 標的使用の効果が誰に帰属するかを論じる必要性はそもそもない。 |
|
|
当裁判所の判断
1 原告は、本件審決には商標法50条の「登録商標の使用」に係る判断の誤り があると主張するので、以下、検討する。 25 後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば、次の各事実が認められる。 ? 原告及びその企業グループは、アンブラコ・ブランドのボルト等のファス 5 ナー製品を製造販売しており、中島工機は、原告の日本総代理店の販売代理 店(原告の復代理店)の一つとして、遅くとも平成13年1月頃から継続し て、同製品を販売してきた(甲30、弁論の全趣旨)。 ? 被告は、令和元年7月19日に登録された本件商標「UNBRAKO」の 5 商標権者であり、中島工機は、同年8月1日、被告から、本件商標につき、 商品「金属製金具」、地域「日本全国」、期間「本件商標権の存続期間が満 了するまで」との範囲内で通常使用権の許諾を受けた(甲12、本件審決の 乙1)。 ? 中島工機は、株式会社小野に対し、アンブラコ製品のボルト100本(乙10 2製品)を販売し、令和3年6月9日にこれを納入した。中島工機は、その 際、包装箱に梱包済みの同製品を納入しており、同包装箱は、黒色で、上面 部及び左側面部にそれぞれ赤地に白色文字で「Unbrako?」との表記 があり、上面部の同表記の下方には白色文字で品質表示文言が記載され、上 面部から正面側面部にかけて貼付されたラベルには、上面部に「PART15 NO.1118936」「QUANTITY100」「SOCKET HE AD CAP」「8-32 UNC x3/4」「1960 Series」 「CERTIFICATE NO.75362M1639」などの、正面側 面部に「SOCKET HEAD CAP」「1118936」「8-32 UNC x3/4」「1960 Series」「SHANNON、IRE20 LAND」などの各記載がある(甲13、本件審決の乙2)。また、中島工 機は、販売の際に、同日付け物品受領書/現品票を作成し、株式会社小野か ら受領印を得ており、同取引書類には、メーカー「アンブラコ」、商品「C S#8NCX3/4」「CAP NC #8-32 x3/4」、数量「1 00」、単位「P」などの記載がある(甲14、本件審決の乙3)。 25 2 検討 ? 前記認定事実によれば、中島工機は、本件商標の通常使用権者であるとこ 6 ろ、本件商標は「UNBRAKO」の標準文字から成り、他方、乙2製品の 包装箱の「Unbrako?」との表記は、その構成から「Unbrako」 の文字部分が独立して自他商品識別標識として機能するものということがで きる。そして、本件商標「UNBRAKO」と乙2製品の使用商標「Unb 5 rako」は、大文字、小文字の相違はあるが、綴りが共通し、称呼も同じ になるから、社会通念上同一というべきである。また、乙2製品のボルトは、 指定商品「金属製金具」の範疇に属する。 そうすると、本件商標の通常使用権者である中島工機は、要証期間である 令和3年6月9日、株式会社小野に譲渡販売し、本件商標が表示された包装10 箱に梱包された金属製金具(ボルト100個)を納品したものと認めるのが 相当であり、指定商品について登録商標の使用(商標法50条、2条3項2 号)をしたというべきである。 ? 原告は、乙2製品の販売は、本件商標とは無関係なメーカーの出所を特定 し、販売するものであり、また、商標使用の効果を原告に帰属させるもので15 あるから、商標法50条の「登録商標の使用」にいう出所表示機能を発揮す る態様での商標の使用ではないなどと主張する。 しかし、商標法50条の趣旨は、登録された商標には排他独占的な権利が 発生することから、長期間にわたり全く使用されていない登録商標を存続さ せることは、当該商標に係る権利者以外の者の商標選択の余地を狭め、国民20 一般の利益を不当に侵害するという弊害を招くおそれがあるので、一定期間 使用されていない登録商標の商標登録を取り消すことを認めたものである。 そうすると、商標法50条所定の「使用」は、当該商標がその指定商品又は 指定役務について商標として使用されていれば足り、その商標としての使用 が商標権者を商品の出所として表示する場合に限定されるものではないとい25 うべきである。 そして、前記の中島工機による乙2製品の譲渡販売行為では、指定商品で 7 ある金属製金具の譲渡販売において、譲渡販売対象が「アンブラコ」という 商品であることが取引書類に記載されるとともに、本件商標の付された包装 箱に梱包された製品が納入されているのであるから、本件商標の通常使用権 を有する中島工機においては、その指定商品について、商標法50条所定の 5 「登録商標の使用」をしたものというべきである。原告は、中島工機による 乙2製品の譲渡販売行為は、商標使用の効果を原告に帰属させるものである から、同条所定の「登録商標の使用」に当たらないとも主張するが、前記の 同条の趣旨に照らすと、本件商標が原告を商品の出所として表示するために 使用された場合であっても、要証期間中に指定商品である乙2製品について10 本件商標が使用された事実が認められる以上、それが「登録商標の使用」に 当らないということはできない。よって、原告の主張を採用することはでき ない。 3 以上によれば、被告は、要証期間に日本国内において、通常使用権者が審判 請求に係る指定商品について本件商標(社会通念上同一と認められる商標を含15 む。)を使用していたことを証明したといえるから、本件審判請求を成り立た ないものとした本件審決の判断に誤りはない。 |
|
|
結論
よって、原告の請求は理由がないから、これを棄却することとして、主文の とおり判決する。 |
| 裁判長裁判官 | 25清水響 |
|---|