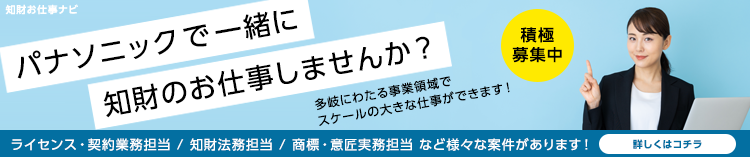| 関連審決 |
不服2022-6216 |
|---|
| 元本PDF |
裁判所収録の全文PDFを見る
|
|---|---|
| 元本PDF |
裁判所収録の別紙1PDFを見る
|
| 元本PDF |
裁判所収録の別紙2PDFを見る
|
| 元本PDF |
裁判所収録の別紙3PDFを見る
|
| 事件 |
令和
6年
(行ケ)
10105号
審決取消請求事件
|
|---|---|
|
原告株式会社Qvou 同訴訟代理人弁護士 水沼淳 同訴訟代理人弁理士 柴田富士子 同 柴田五雄 被告特許庁長官 同 指定代理人山根まり子 同 大島康浩 同 須田亮一 |
|
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
| 判決言渡日 | 2025/04/17 |
| 権利種別 | 商標権 |
| 訴訟類型 | 行政訴訟 |
| 主文 |
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 |
| 事実及び理由 | |
|---|---|
|
請求
特許庁が不服2022-6216号事件について令和6年10月29日にし た審決を取り消す。 |
|
|
事案の概要
1 特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。) (1) 原告は、令和2年8月17日、「のむシリカ」の文字を標準文字で表してな る商標(以下「本願商標」という。)について、第32類「シリカを含有する 1 飲料水」を指定商品として、商標登録出願をした(商願2020-10136 8)。 (2) 原告は、令和4年1月20日付けの拒絶査定を受けたため、同年4月25 日、拒絶査定不服審判を請求した。 特許庁は、上記請求を不服2022-6216号事件として審理を行い、 令和6年10月29日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決(以 下「本件審決」という。)をし、その謄本は同年11月13日原告に送達され た。 (3) 原告は、令和6年12月13日、本件審決の取消しを求める本件訴訟を提 起した。 2 本件審決の理由の要旨 本件審決の理由の要旨は、以下のとおりである。 (1) 本願商標は、その指定商品「シリカを含有する飲料水」に使用するときは、 それに接する需要者及び取引者をして、「飲む(ことで経口で摂取できる)シ リカ」程度の意味合いを認識、理解させるもので、単に商品の品質(摂取方 法、成分)を表示するにすぎない。本願商標は、その指定商品について、商品 の品質(摂取方法、成分)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからな る商標であるから、商標法3条1項3号に該当する。 (2) 本願商標は、原告提出の証拠によっては、原告に係るブランド名として、 その指定商品に係る一般需要者の間において、広く知られるに至っていると 認めることはできない。 したがって、本願商標は、原告により使用された結果、何人かの業務に係る 商品であることを認識することができるものになったとはいえず、商標法3 条2項の要件を具備しない。 3 取消事由 (1) 商標法3条1項3号該当性の判断の誤り(取消事由1) 2 (2) 商標法3条2項該当性の判断の誤り(取消事由2) |
|
|
当事者の主張
1 取消事由1(商標法3条1項3号該当性の判断の誤り)について (1) 原告の主張 ア 「シリカ」は「二酸化ケイ素の通称」であり、二酸化ケイ素は水に不溶で ある。また、「シリカ」という文言は吸湿剤である「シリカゲル」(固形) の略号としても、昔から需要者に広く知られているところ、シリカゲルは 第一次大戦中に毒ガスの吸着剤として開発されたものであり、食べてはい けないものであることが需要者の間で広く認識されていた。 このような需要者の認識に対応するため、水に不溶の「二酸化ケイ素」を 水に溶解性の「ケイ酸塩」にし、「摂取できる形のケイ素化合物が配合され た飲み物である」ことを明示する必要があった。 そして、シリカを含有する飲料水等の商品が世の中に広まり始めたのは 最近(令和3年)である。 本願商標は、従来は摂取不可と認識されていた有効成分であるシリカを 摂取することができるという特徴を端的に示した、「のむシリカ」全体とし て一語の造語であって、単に商品の品質を表示するのみならず、強い識別 力を有するものである。 イ 本件審決は、「飲む〇〇」と称する、経口で栄養成分などを摂取できる商 品(飲料、サプリメントなど)が広く流通しているとするが、これらの事例 は、固形の食品に含まれている成分を、人為的かつ意図的に液体に溶解又 は懸濁させて、形態を固体から液体に変化させたものである。本願商標の 指定商品は「ナチュラルミネラルウォーター」である「シリカを含有する飲 料水」であって、人為的又は意図的に製造されたものではない。したがっ て、本件審決が挙げる事例は、本願商標の商標法3条1項3号該当性を判 断する資料としては適当でない。 3 また、本件審決は、これらの事例に係る商品を、本願商標の指定商品と、 「健康食品として取引市場や需要者層は共通している」と認定しているが、 「健康商品」の明確な定義も示されておらず(なお、「健康商品」という指 定商品はない。 、 ) 例えば固形のサプリメントと液体のサプリメントは流通 経路が異なること等も無視するもので、不当である。 ウ 本件審決は、商標法3条1項3号該当性の判断について、需要者の認識 を問題としている。しかし、同項1号、2号該当性についての認識は取引者 を基準とするものとされている。 同項3号は、独占適応性のない商標の登録を認めないとするものである が、その趣旨は、「通常、商品を流通過程におく場合に必要な表示であるか ら、何人も使用する必要があり、かつ、何人もその使用を欲するものである から一私人に独占を認めるのは妥当でない」こと、及び「将来的に必ず使用 されるものであるから、これらのものに自他商品の識別力を認めることは 妥当でない」というもので、同項1号、2号のみならず同項3号も取引者の 認識を問題としている。 (2) 被告の主張 ア 本願商標の構成中「のむ」の文字部分は「口に入れて噛まずに食道の方に 送る。喉に流し入れる。」の意味を有する「飲む」の語に通じ、「シリカ」 の文字部分は「二酸化ケイ素の通称」の意味を有する。 ①「シリカ」は体に欠かせない成分として注目を集めており、それを含有 することをうたう飲料が広く流通しており、②「飲む○○」と称する、経口 で栄養成分などを摂取できる商品(飲料、サプリメントなど)が広く流通し ているという取引の実情がある。 そうすると、本願商標は、これに接する取引者、需要者に、全体として 「飲む(ことで経口で摂取できる)シリカ」程度の意味合いを容易に認識、 理解させるものであり、指定商品との関係において、商品の品質(摂取方 4 法、成分)を表示記述する標章であって、取引に際し必要適切な表示であ り、これを指定商品「シリカを含有する飲料水」に使用する場合、取引者、 需要者によって、商品の品質(摂取方法、成分)を表示するものと一般に認 識されるにとどまるといえる。 したがって、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質を 普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標 法3条1項3号に該当する。 イ 原告は、シリカは食べられないものとして認識されていたシリカゲルの 略称であること等を理由に、従来は摂取不可と認識されていた有効成分で あるシリカを摂取することができることを端的に示した本願商標は全体と して強い識別力を有する旨主張するが、①の取引の実情に鑑みると、需要 者が「シリカ」を食べられない「シリカゲル」の略称と理解するとは考えら れない。 商標法3条1項3号該当性の判断は、その指定商品に係る取引者、需要 者による一般的な認識が基準となるものであり、需要者の認識を除外する 原告の主張は独自の見解にすぎない。 2 取消事由2(商標法3条2項該当性の判断の誤り)について (1) 原告の主張 ア 本件審決は、本願商標が自他識別力を欠く理由として、本願商標の指定 商品に係る取引分野において、「『シリカ』を含有することをうたう飲料が 広く流通している取引の実情があり、また、『飲む〇〇』と称する、経口で 栄養成分などを摂取できる商品(飲料、サプリメントなど)が広く流通して いる取引の実情もある」ことを挙げる。 しかし、本件審決は、一方で、本願商標の指定商品を「本願商標の指定商 品に係る飲料水」と認定している。すなわち、本願の指定商品は、経口で栄 養成分などを摂取できる商品でもなければ、サプリメントでもない。また、 5 市販の「飲料水」であっても、単に飲料として使う場合と、調理用の水とし て使用する場合とでは、ミネラル含有量の多いものとそうでないものとは 使い分けがされている。本件審決は、これらの事情を無視して取引の実情 を認定するもので不当である。 イ また、本件審決は、原告の商品である「のむシリカ」と称する飲料水(以 下「原告商品」という。)の販売数が、令和4年夏に累計5000万本、令 和5年7月に累計1憶本を超えたこと、年間数十億円をかけたプロモーシ ョンを展開していたこと等を認定しながら、飲料水の取引市場を基準とす れば必ずしも長期間かつ大規模な販売数量とはいえず、一般需要者に向け て広く網羅的に到達するほどの宣伝広告規模ではないとしているが、商標 法3条2項の要件を判断するに当たっては、最近の広告・宣伝機関やその 技術の発達による大衆への浸透力、使用の期間と密度を考慮すべきである。 ウ 商標法3条2項が適用されるには、何人かの一定の業務に係る商品であ ることが判明しさえすれば、その氏名・名称等を認識する必要はないとさ れているにもかかわらず、本件審決が、「一般需要者の間における、請求人 の自他商品の出所識別標識としての認知度や知名度の程度を直接的かつ客 観的に示すような証拠は提出されていない。」と説示しているのは明白な 誤りである。 (2) 被告の主張 原告商品の販売数量や売上額が相対的に大きく、大規模なものと客観的に 評価することはできないし、原告商品の販売期間が長期間であるともいえな い。また、広告宣伝実績については、令和2年以降を中心として、継続的に広 告宣伝活動がされているものの、広告宣伝費の裏付けやそれを使用した広告 媒体ごとの内訳などが明らかにされていないし、その他、本願商標について、 一般消費者の間における、原告の自他商品の出所識別標識としての認知度や 知名度の程度を直接的かつ客観的に示すような証拠は提出されていない。 6 そうすると、本願商標は、原告提出の証拠によっては、原告の業務に係る商 品を表示するものとして、その指定商品に係る一般消費者の間において、全 国的に認識されるに至っているということはできないというべきである。 |
|
|
当裁判所の判断
1 取消事由1(商標法3条1項3号該当性の判断の誤り)について (1) 商標法3条1項3号は、「その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、 用途、形状(包装の形状を含む。・・・)、生産若しくは使用の方法若しくは 時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の 用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数 量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」 は、商標登録を受けることができない旨を規定しているが、これは、同号掲記 の標章は、商品の産地、販売地その他の特性を表示、記述する標章であって、 取引に際し必要な表示として誰もがその使用を欲するものであるから、特定 人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに、 一般的に使用される標章であって、多くの場合、自他商品・役務識別力を欠 き、商標としての機能を果たし得ないことから、登録を許さないとしたもの である。 (2) 本願商標は、「のむシリカ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構 成中の「のむ」の文字は、「口に入れて噛まずに食道の方に送る。喉に流し入 れる。」の意味を有する「飲む」の語に通じ、また、その構成中の「シリカ」 の文字は、「二酸化ケイ素の通称」を意味する(広辞苑第7版。乙1、2)。 (3) 本件審決の時点において、本願商標の指定商品に係る取引分野において、 シリカは体に欠かせない成分として注目を集め、シリカを含有することをう たう飲料が広く流通し(乙3~12)、また、「飲むミネラル」、「飲むコラ ーゲン」、「飲む高濃度ビタミンC」、「飲むカルシウム」、「飲むヒアルロ ン酸」、「飲むセラミド」、「飲む乳酸菌」等、「飲む○○」と称する、経口 7 で栄養成分などを摂取できる商品(飲料、サプリメントなど)が広く流通して いる実情もある(乙13~24)。 そうすると、本願商標は、これを指定商品「シリカを含有する飲料水」に使 用するときは、需要者及び取引者に、「飲むことができる(経口摂取すること ができる)シリカ」程度の意味を認識させるものであって、単に商品の品質 (摂取方法、成分)を表示するにすぎないものといえる。 (4)ア 原告は、本願商標は、 「シリカゲル」 従来 を示すもので、水に不溶であり、 摂取不可と認識されていた有効成分である「シリカ」を摂取することがで きるという特徴を端的に示した、「のむシリカ」全体として一語の造語であ って、単に商品の品質を表示するのみならず、強い識別力を有する旨主張 する。 しかし、「シリカ」が「シリカゲル」の略称として取引者、需要者に認識 されていたことや、「シリカ」が水に不溶であることが取引者・需要者に認 識されていたことを認めるに足りる証拠はない。原告商品を宣伝する業界 誌の記事(甲12。個別に言及する場合を除き枝番を含む。以下、枝番のあ る書証につき同じ。)をみても、「シリカ」と「シリカゲル」の関係につい ても、「シリカ」が水に不溶であることについても言及されておらず、原告 商品におけるシリカが人工的に配合されたものでなく、天然水(ナチュラ ルミネラルウォーター)に由来することを強調しているにとどまる。かえ って、シリカを含有することをうたう飲料が広く流通していることは前記 (3)のとおりである。 イ 原告は、本願商標の指定商品は「ナチュラルミネラルウォーター」である 「シリカを含有する飲料水」であって、人為的又は意図的に製造されたも のではないのに対し、本件審決が援用する「飲む〇〇」と称する、経口で栄 養成分などを摂取できる商品は、固形の食品に含まれている成分を、人為 的かつ意図的に液体に溶解又は懸濁させて、形態を固体から液体に変化さ 8 せたものであるから、本件審決が援用する事例は本願商標の商標法3条1 項3号該当性を判断するのに適切ではない旨主張する。しかし、本願商標 の指定商品は「シリカを含有する」に至るについて、人工的に配合されたも のであるか否か、また、飲料水が「ナチュラルミネラルウォーター」である か否かを区別していないのであり、原告の主張は採用できない。 また、原告は、本件審決が、本件審決の援用する事例に係る商品と本願商 標の指定商品とが、健康食品として取引市場や需要者層は共通している旨 認定したことについて、「健康商品」の明確な定義も示されておらず、例え ば固形のサプリメントと液体のサプリメントは流通経路が異なること等も 無視するもので、不当である旨主張する。しかし、本件審決の援用する事例 に係る商品と本願商標の指定商品に係る商品は、いずれも健康や美容のた めに栄養分を経口摂取する点で共通し、その需要者は、一般消費者であり、 販売場所もドラッグストア、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、 オンラインショッピング等で共通するものであって、原告の主張は採用で きない。 ウ 原告は、本件審決が、商標法3条1項3号該当性の判断について、需要者 の認識を問題としたことを不当である旨主張する。 しかし、前記(1)のとおり、同号に該当する商標の登録を許さないのは、 独占適応性の問題だけでなく、一般的に使用される標章であって、多くの 場合、自他商品・役務識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ないこと にもよるのであるから、本件審決が需要者の認識を問題としたことに何ら 不合理な点はない(商標法3条1項3号について需要者の認識も問題とな ることについて、最高裁昭和60年(行ツ)第68号同61年1月23日第 一小法廷判決・裁判集民事147号7頁参照)。 (5) 以上のとおりであって、取消事由1は理由がない。 2 取消事由2(商標法3条2項該当性の判断の誤り)について 9 (1) 商標法3条2項は、同条1項3号ないし5号に対する例外として、「使用 をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識す ることができるもの」は商標登録を受けることができる旨規定している。そ の趣旨は、特定人が当該商標をその業務に係る商品の自他識別標識として他 人に使用されることなく独占排他的に継続使用した実績を有する場合には、 当該商標は例外的に自他商品識別力を獲得したものということができる上に、 当該商品の取引界において当該特定人の独占使用が事実上容認されている以 上、他の事業者に対してその使用の機会を開放しておかなければならない公 益上の要請は薄いということができるから、当該商標の登録を認めようとい うものである。したがって、同条2項の要件を具備し、登録が認められるため には、審決時において、取引者・需要者において何人かの業務に係る商品であ ることを認識することができることを要するというべきである。 (2) 各種業界誌(甲12)には、「のむシリカ」の商品名を有する原告の製造に 係るナチュラルミネラルウォーター(原告商品)が平成29年4月に発売さ れたこと、当初はネット通販市場で販売されていたが、令和2年12月には 小売店での販売を開始し、累計販売数は、令和4年には5000万本に、令和 5年7月には1億本に達したこと、原告が年間数十億円をかけて、インター ネットをはじめ様々なメディアでプロモーションを展開していたこと等が記 されている。 また、原告は、令和2年以降、各種タレントを起用して、 「月刊のむシリカ」 と題する購入者向けの冊子を作成している(甲8)。 しかしながら、上記業界誌の各記事では同様の内容が繰り返されており、 1l当たり90mg、93mgのシリカを含有する競合品がある(甲12の 3の図表①のB社、D社)にもかかわらず、原告商品における「1l当たり9 7mg」というシリカの含有量を「断トツ」と表現する(甲12の3の本文) 等、その記載内容の正確性・客観性には疑義がある。上記各記事では、「シリ 10 カ水売上第1位」と謳うものもあるが(甲12の5等)、その実情は令和4年 1月のアマゾンにおける売上という、特定の時点における特定のプラットフ ォームにおける販売実績を繰り返し掲載しているにすぎず、 「楽天市場調べ」 で「シリカ水売り上げ第1位」とするもの(甲12の10)は時期も特定され ていない。 また、上記各記事における販売量に関する数値が正確なものであるとすれ ば、令和4年から令和5年の約1年間の原告商品の販売数は5000万本程 度であるところ、原告商品(500ml)1本あたりが108円(甲14の1 の税込金額を箱数と本数で割った数値。230万6880円÷890箱÷2 4本)とすると、その売上額は約54億円となる。令和5年のミネラルウォー ター類の販売金額が約4212億円(乙26)とされていることから、ミネラ ルウォーターの取引市場全体との対比において1%程度にすぎない。 また、上記各記事における宣伝費に関する数値が正確なものであるとして も、その内訳も不明であり、これが全国市場における一般需要者に到達する ほどの宣伝広告規模であったと認定するに足りる証拠はない。 その他、本願商標について、一般需要者の間における、原告を含む特定の取 引主体に係る出所識別標識としての認知度や知名度の程度を直接的かつ客観 的に示すような証拠は提出されていない。 そうすると、本願商標は、原告に係るブランド名として、その指定商品に係 る一般需要者の間において、広く知られるに至っていると認めることはでき ず、原告により使用された結果、何人かの業務に係る商品であることを認識 することができるものになったとはいえないから、商標法3条2項の要件を 具備しない。 (3)ア 原告は、本願商標の指定商品が、経口で栄養成分などを摂取できる商品 やサプリメントでないことを理由に、これらの商品を取引の実情に関し参 酌した本件審決を論難するが、前記1(4)イのとおり、本件審決の援用する 11 事例に係る商品と本願商標の指定商品に係る商品は、健康や美容のために 栄養分を経口摂取するものであること、需要者及び販売場所でも共通する のであって、本件審決の説示に誤りはない。 イ 原告は、商標法3条2項の要件を判断するに当たっては、最近の広告・宣 伝期間やその技術の発達による大衆への浸透力、使用の期間と密度を考慮 すべきである旨主張するが、その具体的内容は明らかでなく、前記(2)に説 示したところに照らし採用できない。 ウ 原告は、商標法3条2項が適用されるには、何人かの一定の業務に係る 商品であることが判明すれば足り、その氏名・名称等を認識する必要はな いのに、本件審決が、「一般需要者の間における、請求人の自他商品の出所 識別標識としての認知度や知名度の程度を直接的かつ客観的に示すような 証拠は提出されていない。」と説示したのは誤りである旨主張する。 商標法3条2項の適用については、需要者において特定の者の業務に係 る商品であることを要し、ただその具体的な氏名・名称等を認識する必要 はなく、「何人か」の業務に係る商品であることの認識があれば足りるとこ ろ、本件審決は、原告が、本願商標が「請求人の」取り扱う商品を表示する 商標として取引者及び需要者に広く認識されている旨主張したのに対応し て上記のように説示したものであり、引き続いて「本願商標は、請求人によ り使用された結果、何人かの業務に係る商品であることを認識することが できるものになったとはいえず、商標法第3条第2項の要件を具備しない。」 と説示していることに照らしても、原告の主張が失当であることは明らか である。 3 結論 以上によれば、本願商標は商標法3条1項3号に該当し、同条2項の要件を 具備しないから、原告主張の取消事由はいずれも理由がなく、本件審決にこれ を取り消すべき違法は認められない。 12 したがって、原告の請求を棄却することとして、主文のとおり判決する。 |
| 裁判長裁判官 | 増田稔 |
|---|---|
| 裁判官 | 本吉弘行 |
| 裁判官 | 岩井直幸 |