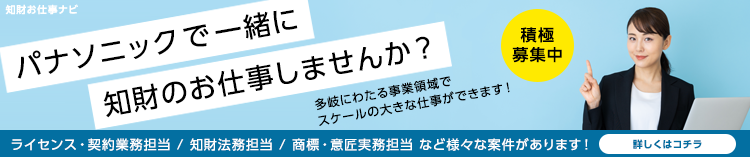この判例には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
| 審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
|---|---|---|
| 平成14ワ16786商標権に基づく差止請求権不存在確認等請求事件 | 判例 | 商標 |
| 平成17行ケ10030審決取消請求事件 | 判例 | 商標 |
| 平成15ネ3283商標権に基づく差止請求権不存在確認等請求控訴事件 | 判例 | 商標 |
| 平成16ワ23624商標権移転登録手続請求事件 | 判例 | 商標 |
| 平成17行ケ10028審決取消請求事件 | 判例 | 商標 |
| 関連ワード | 周知性 / 顧客吸引力(グッドウィル) / ただ乗り(フリーライド) / 権利濫用(権利の濫用) / 国内 / 差止 / 使用許諾 / 外国 / 継続 / 著名人 / |
|---|
| 元本PDF |
裁判所収録の全文PDFを見る
|
|---|---|
| 元本PDF |
裁判所収録の別紙1PDFを見る
|
| 事件 |
平成
14年
(ワ)
1018号
商標権に基づく差止請求権不存在確認等請求事件
|
|---|---|
|
原告A 原告B 原告C 原告D 原告E 原告ら訴訟代理人弁護士 田中清和 被告F 訴訟代理人弁護士 田中克郎 同 中村勝彦 同 長坂省 同 五十嵐敦 同 渡辺伸行 同 奥山倫行 |
|
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
| 判決言渡日 | 2003/09/30 |
| 権利種別 | 商標権 |
| 訴訟類型 | 民事訴訟 |
| 主文 |
1 被告が、被告の有する別紙商標目録1ないし8記載の商標権に基づき、原告らに対し、空手の教授に関する広告、空手の興行の企画・運営又は開催に別紙標章目録1ないし8記載の標章を使用すること、及び空手の教授を行うに際して空手着に別紙標章目録1ないし8記載の標章を使用することの差止めを求める権利を有しないことを確認する。 2 被告は、原告A、同B及び同Cに対し、各金50万円、原告D及び同Eに対し各金30万円、並びに上記各金員に対する平成14年2月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用はこれを5分し、その3を被告の負担とし、その余を原告らの負担とする。 |
| 事実及び理由 | |
|---|---|
|
原告らの請求
1 主文第1項同旨。 2 被告は、原告らに対し、各金1000万円及びこれらに対する平成14年2月9日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 |
|
|
事案の概要
本件は、別紙標章目録1ないし8記載の標章(以下併せて「本件商標」といい、個々の標章は「本件商標1」のように表記する。)を使用して空手の教授等を行っている原告らが、別紙商標目録1ないし8記載の商標権の商標権者である被告が原告らに本件商標の使用の差止めを求めることは権利の濫用に当たるとして、被告に対し、原告らが空手の教授等において本件商標を使用すること等の差止めを求める権利を有しないことの確認と、被告の行為によって生じた原告らの損害の賠償を求めた事案である。 1 前提事実(当事者間に争いのない事実等) (1) 原告ら及び被告は、いずれも亡Gが創設した空手の流派である「国際空手道連盟極真会館」(以下「極真会館」という。)に、Gの生前から属していた者である。 (2) Gは、直接打撃制の武道空手を特徴とする極真空手を推進し、普及させることを目的として、昭和39年に極真会館を創設した。極真会館は、平成6年時点において、日本国内に、総本部、関西本部のほか、55支部、550道場、会員数50万人を有し、世界130か国、会員数1200万人を超える勢力に達していた。 (3) 本件商標は、Gが率いる極真会館に属する者が、極真会館及び極真空手を示す標章として、空手の教授や空手大会の開催等に際して使用してきたものであり、遅くとも平成6年4月時点では、空手及び格闘技に興味を持つ者のみならず、 一般人の間でも極真会館、極真空手を表す標章として広く認識されるに至っていたが、G自身は存命中に本件商標につき商標登録出願をすることはなかった。 (4) Gは、平成6年4月26日死亡した。 (5) 被告は、Gの死後、極真会館の後継者であると主張し、 極真会館の館長を称して、極真空手の活動を行っている。被告は、平成6年5月18日に本件商標1ないし5及び8を、平成7年2月20日に本件商標6を、同月24日に本件商標7をそれぞれ商標登録出願した。 本件商標1ないし5及び8は平成9年7月11日に、本件商標6は同年8月8日に、本件商標7は同年10月17日に、それぞれ商標登録された(以下、本件商標の商標権を「本件商標権」という。)。 (6) 原告らは、極真空手の道場を多数開設・運営し、空手の教授等を行うに際して、本件商標を使用しており、開設する道場への入門案内として、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社(NTT)のタウンページに、極真会館・極真空手であることを示す広告を掲載してきた。 (7) 被告は、本件商標登録後、NTT(ないしエヌ・ティ・ティ番号情報株式会社)に対し、本件商標を使用する原告らの行為は被告の有する本件商標権を侵害するから掲載してはならない旨申し入れた。被告の申入れを受けたNTTは、原告らが平成13年度版タウンぺージに広告掲載を申し込んだ際に、広告掲載できない旨の通知を行った。 (8) 原告A、同B及び同Cは、被告を相手方として、大阪地方裁判所に、上記原告ら3名の空手道場の広告を掲載することの妨害禁止の仮処分を申し立てた。同裁判所は、平成12年12月28日、担保を立てさせた上で、仮処分申立てを認容する仮処分決定をした。被告はこれに対し保全異議を申し立てたが、大阪地方裁判所は、平成13年4月4日、上記仮処分決定を認可する旨の決定をした(甲18)。被告は、更に保全抗告をしたが、大阪高等裁判所は、同年10月2日、保全抗告を棄却する旨の決定をした(甲19)。 一方、原告D及び同Eは、被告を相手方として、東京地方裁判所に、上記原告両名の空手道場の広告をタウンページに掲載することの妨害禁止の仮処分を申し立てた。同裁判所は、平成13年12月20日、上記原告両名の申立てを却下した(乙1)。 2 争点 (1) 被告が、本件商標権に基づき、原告らが空手の教授等を行うに際して本件商標を使用することの差止めを求めることは、権利濫用となるか。 ア 原告らは極真会館を離脱したのか、それとも極真会館はいくつかの会派に分裂したのか。 イ 極真会館がいくつかの会派に分裂したにすぎない場合、本件商標権者たる被告が、極真会館に属していた者に、本件商標を使用することの差止めを求めることは権利濫用となるか。 ウ 原告らの個別事情 (2) 被告の不法行為及び原告らの損害 |
|
|
争点に関する当事者の主張
1 争点(1)(被告が、本件商標権に基づき、原告らが空手の教授等を行うに際して本件商標を使用することの差止めを求めることは、権利濫用となるか) (1) 争点(1)ア(原告らは極真会館を離脱したのか、それとも極真会館はいくつかの会派に分裂したのか)について 【原告らの主張】 次のとおり、Gの死後、極真会館はいくつかの会派に分裂したものであり、原告らが極真会館を離脱したわけではない。 ア 被告は、原告らに対し、極真会館の2代目館長であることを主張できない。 (ア) G死後、同人の平成6年4月19日付け危急時遺言(以下「本件危急時遺言」という。)が存在し、被告を極真会館の後継者とする旨記載されているとの発表がなされたため、全国の支部長らは、その後に初めて開催された全国支部長会議において、全員一致で被告を館長とすることを承認した。 しかるに、本件危急時遺言の確認の審判申立てに対し、東京家庭裁判所は、平成7年3月31日、本件危急時遺言は、遺言者が遺言事項につき自由な判断の下に内容を決定したものか否かという点で疑問が強く残るというほかなく、遺言者の真意に出たものと確認することが困難であるとして、同申立てを却下する審判を行った。東京高等裁判所は、平成8年10月16日、ほぼ同様の理由で抗告を棄却し、最高裁判所も平成9年3月17日 、特別抗告を却下した。このように、本件危急時遺言の確認の審判申立てが裁判所において却下され、Gの遺言としての効力を有しないことが確定した以上、被告を極真会館におけるGの後継館長であると主張する根拠は失われた。 (イ) 一度は被告を極真会館館長とすることを承認した全国の支部長らの多くは、被告の極真会館の私物化、独断専行、経理処理の不透明等に不信の念を強めていった。そして、平成7年4月5日、極真会館48支部の支部長会議において、被告の館長解任動議が提出され、賛成35名、反対3名、欠席10名により、 被告の館長解任が決議された。 (ウ) 被告は、Gが被告を後継者とする旨述べていたと主張するが、被告以外にも、Gから「君が後継者だ」と言われた者はいた。 被告は、G死後、被告こそ統一した組織としての極真会館を承継した唯一の代表者であり、これを認めない者らは、極真会館を脱退したものであって、 極真会館を名乗る資格がない、と主張するが、そのような主張は、被告の独断的かつ一方的な主張である。 イ 諸会派について 被告の館長解任決議の結果、極真会館は、G死後1年にして、当時の支部長が、遺族派(当時9支部長が属する。)、支部長協議会派(当時30支部長が属する。)及びF派(当時12支部長が属する。)に分かれた。さらに、平成15年5月31日現在、G死亡時の53名の支部長のうち、現役者は、H派(旧遺族派の残り)3名、I派(旧支部長協議会派の残り)12名、F派(被告側)17名、 全日本極真連合会(原告ら側)14名、極真館(J派)3名、無所属3名と分かれている。 そして、各会派は、いずれも極真会館・極真空手の名前と本件商標を使用して従来の道場を運営し、新たに道場を開設しており、各種選手権大会も個別にあるいは複数会派が共同して、別個にG生前から行われていた名称(オープントーナメント全日本空手道選手権大会、全日本ウエイト制空手道選手権大会、全世界空手道選手権大会など)を使用して開催している。 各会派とも、備品等の関係で極真会館と取引のあった業者と取引を継続したり、昇段状、表彰状、修了証等をGの生前に使用していたものと全く同じ体裁で使用していたりしている。 このような状況は、Gの死後、極真会館が諸会派に分裂したことを意味するというべきであって、誰かが極真会館を離脱したという状況ではない。 ウ 被告は、これまで極真会館を離脱したり除名された者の例を挙げ、原告らも極真会館を離脱したと主張する。 しかし、この主張は、F派のみが極真会館であるとの独断を前提としている上、上記の者らが除名され、あるいは離脱したのは、1つの極真会館が存在していた時期であり、そのカリスマ的指導者たるGがこれらの者の不祥事等を理由に除名、破門したのであるから、これらの者が極真を名乗れないのはむしろ当然のことであって、原告らの事案と全く次元を異にする。原告らは、F派には属さないが、生前のG率いる極真会館に属する者である。 【被告の主張】 被告は、Gの遺志を継いだ、極真会館の正当な2代目館長である。このことは、次のとおり、被告が置かれていた客観的状況やGの側近の証言等から明らかである。そして、被告が2代目館長であることを否定し、別組織を作った原告らは、いずれも極真会館から離脱したというべきである。 ア 被告が置かれていた客観的状況 (ア) Gからの信望 Gは生前、極真会館の後継者の条件について、強くなければならないこと、すなわち、全日本大会を3連覇する、世界チャンピオンになる、百人組手をやる、この3つを達成したことであると公言していた。 この条件を満たす者は、G存命中は、被告しか存在しなかったし、G自身も、被告の実力を認めていた。 また、Gは、自分の後継者には若くて空手家としても超一流の人材を起用しようとする意思を有していた。 被告は、全世界大会優勝後の昭和62年に現役を引退したが、Gから極真会館から離れることを引き留められていた。また、被告は、Gから請われて極真会館に戻った後、支部長認可を受ける際に、Gから本部でも指導するようにと言われ、本部の分館という意味での本部直轄の道場でGの傍に置かれることになった。被告以外に、Gからこのような扱いを受けた者は存在しない。 さらに、G逝去当時の極真会館の中に、被告以外に館長になるべき人物はいなかったというのが当時の他の支部長らの率直な意見であり、被告が極真会館の館長になることについては、他の支部長らから全く異議はなかった。G逝去後初めて開かれた全国支部長会議(平成6年5月10日)において、被告を館長として極真会館としての活動を行っていくことが支部長会議出席者の全員一致で確認されている。 (イ) 被告が任されていた役目等について 被告は、極真会館が主催する空手の各種大会において審判員、模範演技や大会運営委員会の支部長代行委員を務め、世界20か国余りの道場を指導員として訪問し、Gの晩年には、Gの名代としてKと共に、ネパール王室に空手の演舞を献上するために同国へ行っている。 また、被告は、G及び極真会館にとって非常に重要な新会館建設の建設委員会第2次建設委員長にGから直接任命された。 さらに、極真会館では、Gが極真会館の総本部で黒帯の道場生に直接指導する黒帯研究会を開催していたが、被告はGからこの指導を直接委任されていた。 被告は、平成4年4月、Gから直接支部長として任命され、本部直轄浅草道場の運営を任された。 (ウ) 小括 以上で述べたように、被告以上にGからの特別の信望を受け、Gの後継者として数々の重要な職務を任されていた人物は、被告の他には存在しない。Gが逝去した当時、極真会館には、被告以外にGの遺志を継いで極真会館の館長となるのにふさわしい人物は存在しないという客観的な状況にあったことが明らかである。 イ Gの側近の証言等 (ア) Lの陳述書(乙9、10)及び極真カラテ手帳(乙11) 極真会館事務局の一員として、Gの任命を受けて身の回りの世話をしていたLは、G入院中も常にGの側に居続けた。Lは、Gの入院中、Gから直接、 被告を二代目館長とする旨の発言を2度にわたり聞いている。また、Lは、平成6年4月20日、Gから後継者を被告とするという発言をメモするようにと指示され、Lの極真カラテ手帳(乙11の平成6年4月20日欄に「F2代目総裁協力する様に」と記載した。 以上からすれば、Gは被告を極真会館の後継者にする遺志を有していたと認められる。 (イ) K、J、M、Nらの証言 被告を後継館長とするGの遺志については、K、J、M、NなどGから直接聞いている者が存在する。これらの者は、Gと師弟関係にあった者であり、 特に、Kに至ってはG道場時代からGに師事し、G生前の極真会館において全国支部長協議会会長を務めた、いわばGの側近中の側近ともいえる人物である。 したがって、これらの証言からも、Gが生前から被告を後継者とする遺志を有していたことが認められる。 (ウ) 遺言作成時の5人の証人の証言 極真会館の新会館建設の第1次建設委員長であったOは、GがJやMに被告を頼む旨述べたのを聞いている。また、遺言書作成に立ち会った他の証人であるP、Q、R及びSは、それぞれ、Gがはっきりと被告を2代目にすると発言したのを聞いている。これらの者は、いずれも被告と特別の関係があった者ではなく、ことさら被告に有利な事実を述べる理由などは何ら存在しないから、5人の証人がGの遺言を聞いているという事実は、被告が極真会館の後継者であることを裏付けている。 ウ 本件危急時遺言 原告らは、被告がGの死後11か月の間極真会館の館長に就任していた根拠は本件危急時遺言にあったところ、本件危急時遺言は、確認の審判申立てが裁判所で却下されたのであるから、被告がGの後継者であるとする被告の主張の根拠は失われたと主張する。 しかしながら、被告は遺言書の存在を根拠に極真会館の館長に就任したわけではなく、その背後にあるGの遺言、さらにはその奥にあるGの遺志に基づいて極真会館の館長に就任したのである。 本件危急時遺言は、形式的な要件に不備があったために有効性が確認されなかったにすぎず、本件危急時遺言確認の審判申立が却下されたことが、直ちにGが被告に極真会館の館長を継がせる意思を有していたことを否定するものではない。 したがって、本件危急時遺言の確認が裁判所で認められなかった事実は、被告がGの正当かつ唯一の後継者であることに、何ら影響を与えるものではない。 エ 平成7年4月5日の支部長「会議」について 原告らは、平成7年4月5日の支部長「会議」において、被告は解任されていると主張する。 しかし、この会議には、被告を解任する権限はない。この会議は、もともと支部長協議会として開催されたものであり、支部長協議会と支部長会議は明確に異なるものである。支部長会議は当時、池袋の極真会館の本部会館で開かれることになっていたが、当日の会議は、東京駅八重洲口のホテルで行われており、支部長会議を名乗ったとしても、実体は支部長協議会にすぎなかった。また、仮に、支部長会議であるとしても、極真会館の規約上も慣習上も支部長会議及び支部長協議会には極真会館の館長を解任する権限などは存在しないから、被告が解任され得るはずはない。原告らは、何の権限も存在しない会議において一方的に被告を解任したといって、極真会館から脱退していったにすぎないというのが真相である。 オ G率いる極真会館と、被告率いる極真会館の同一性 現在被告が館長を務めている極真会館は、Gが創設した極真会館と比較して、総本部の構成・機能、支部・道場の編成の同一性、各種選手権大会開催の継続性、内弟子制度の継続性、各種証書・備品の同一性、取引関係の継続性、関連雑誌の同一性などが認められるから、団体としてGが創設した極真会館をそのまま承継したというべきである。したがって、被告が館長を務める極真会館から離脱した者は、極真会館を離脱し、同団体に所属しないものとなったのである。 (2) 争点(1)イ(極真会館がいくつかの会派に分裂したにすぎない場合、本件商標権者たる被告が、極真会館に属していた者に、本件商標を使用することの差止めを求めることは権利濫用となるか)について 【原告らの主張】 被告が、G生前の極真会館において同人の承認の下に本件商標を用いて空手の教授、空手大会等の興行等を行っていた者(支部長、分支部長、道場責任者及び道場指導員)に対して、本件商標権に基づき本件商標の使用差止めを求めることは、次のとおり、権利の濫用に当たる。 ア 本件商標は、G館長が死亡した時点(本件商標登録出願前)において、 G率いる極真会館を表すものとして、空手及び格闘技に興味を有する者(需要者)の間では広く知られるところとなっており、これはG生前の極真会館に属する各構成員が、長年にわたり、「極真会館」の名称の下に、道場における極真空手の教授や地方大会の開催等に携わることによって、本件商標の周知性の確立に貢献してきたことによりもたらされたものといえる。したがって、本件商標が出所を表示する主体は、本件商標登録出願前から、原告ら及び被告を含む全国の本部、支部並びにその下部道場を包括した任意団体である「極真会館」として需要者の間に認識されており、この状況は、本件登録出願後も変わっていないといえる。 本件は、Gの死後、本来本件商標が出所を表示する主体である極真会館という団体が少なくとも3派に分裂し、互いに別個の道場を開設したり、各種選手権大会を開催するに至ったという事案であるが、このように複数の事業者から構成されるグループ(極真会館)が特定の役務を表す主体として需要者の間で認識されている場合、その中の特定の者が、当該表示の独占的主体であるといえるためには、需要者に対する関係又はグループ内部における関係において、その表示の周知性・著名性の獲得がほとんどその特定の者の行為に基づいているなど、その表示に対する信用がその特定の者に集中して帰属しており、グループ内の他の者は、その者からの使用許諾を得て初めて当該表示を使用できるという関係にあることを要するものと解される。 そして、被告が本件商標登録出願当時、グループ内部において、独占的な表示主体となることが承認されていたことの根拠は、専ら本件危急時遺言の存在にあるというべきところ、前述のとおり、本件危急時遺言の確認の審判申立てが裁判所において却下され、Gの遺言としての効力を有しないことが確定した以上、少なくとも、現時点において、被告は、 グループ内部の者(G生前の極真会館において、同人の承認の下に本件商標を用いて空手の教授、空手大会の興行等を行っていた者)に対しては、G館長の後継館長であることを主張し得る根拠を失ったものというべきである。 イ これに対し、被告は、極真会館においては支部長認可制、テリトリー制が採られており、また、標章使用についてはGに正式に認可された支部長のみがこれを許され、かつ無断使用が禁止されていたことをもって、上記グループ内の者は、厳格な要件を満たした支部長のみである旨主張する。しかし、この主張は、以下のとおり失当である。 (ア) 支部長認可制、テリトリー制について 極真会館における組織運営は、形式的な規約、組織系統図等にかかわらず、実際には創設者でありカリスマ的指導者であるGの一存によって運営されていた。 支部長の認可についていえば、国内支部規約書(乙11)には「支部長の決定は、本部の委員会において承認を得、その裁可は会長又は総裁がなすものとする。」と規定されているが、すべての場合、Gが自分の意にかなった者を支部長に指名し、後日、支部長会議の席などで事後報告するだけであった。そして、Gの支部長指名には、具体的な地域指定さえない場合もあった(原告Cの場合など)。 また、テリトリー制についても、規約上はともかく、実際にはGの判断一つで決められ、実情に合わせて運営されており、1県1支部の原則にこだわらなかった。支部長が2つの支部を持った場合もあり、支部長認可の際に地域を限定されたものではなく、必要に応じて追加された。大きい県や大都市では、数か所に分割して支部が作られた。さらに、Gは、全日本チャンピオン、世界チャンピオンは、自分の好む場所に道場を出すことができるとしていた。 (イ) 分支部長について 分支部長は、支部長に比して、支部長会議への出席義務等はなかったが、その他の点では事実上支部長と同様であった。ちなみに、本件危急時遺言にも「本部直轄道場責任者、各支部長、各分支部長は、これに賛同し、協力すること」との表現が2度も出ていることから推測されるように、当時の極真会館においては、分支部長の地位は支部長に近く、あるいは準じる地位にあると認識されていたのである。 (ウ) 本件商標の使用について 被告は、認可された支部長は、極真会館の一員として必要な範囲内で本件商標や極真の表示を使用することができ、支部長以外の者は極真のマークを使用することは許されなかったと主張する。 しかし、被告が指摘する支部規約のうち、昭和47年版と昭和51年版には、極真のマークの使用に関する規定は全くない。また、昭和52年版と平成6年版には、「支部は、既に登録してある極真のマークを委員会の承認なしに無断で使用できない。」との規定があるが、当時極真のマークは登録されていなかったし、そもそもG存命中には委員会なるものが機能した事実もない。さらに、昭和54年版と昭和57年版と昭和63年版には、「支部長の禁止事項」の一つとして「極真マーク等の無断使用及び付属物一切の販売」という規定がある。しかし、これは、同標章の一般の無断使用禁止が眼目ではなく、極真会館総本部の重要な財源である同標章入り商品(空手着、トレーニング・スーツ、Tシャツ、スポーツタオル、ベルト等)を支部長が勝手に作成・販売することを規制したものにすぎない。 G自身は、存命中、極真のマークについて海外で意匠登録がなされたという問題が発生した後も、本件商標の商標登録出願をすることはなかった。そして、支部認可の手続さえしっかりしていればよいと考え、認可された支部道場が本件商標を使用することを包括的に認めていた。支部が分支部を設置し、それに伴い開設された道場に対しても、同様である。 原告らは、G存命中、道場運営や大会開催において、本件商標を、Gや総本部の許可を得ることなく自由に使用してきたが、Gや総本部から、その使用を禁じられたことなかった。 (エ) 被告は、原告らが支部長あるいは分支部長としての義務(認可料等の支払、大会への選手派遣等)に違反しあるいは履行していないから、本件商標を使用することはできない旨主張する。しかし、極真会館が分裂した以上、F派に属さない者が、被告に対して認可料、登録料等を支払わず、F派が主催する大会に選手を派遣せず、自己の属する会派に認可料等を支払い、自己の属する会派が主催する大会に選手を派遣するようになったのは、当然の成り行きである。 (オ) なお、被告は、G存命中に、除名され、あるいは離脱した者は、たとえ従前は支部長たる立場にあっても、極真等の標章を使用することはなく、新しい標章の下に独自の活動を展開している、と述べ、いわゆるF派に属さない者は極真会館を離脱した者であるから、上記の者と同じく極真等の標章を使用すべきではない旨主張している。 しかし、被告が指摘する者らが標章等を使用していないのは、カリスマ的指導者たるGにより彼らの不祥事等を理由に除名、破門されたり、自ら独自の流派を作りたいと出て行ったりしたためであって、彼らが極真を名乗れないのはむしろ当然である。 【被告の主張】 ア 被告による商標権の取得及び行使の正当性 (ア) 被告による商標権取得の正当性 被告は、極真会館の館長に就任した後、Gの遺言の立会人らからの商標権確保を行った方が良いとの提言に基づいて、商標登録を行ったのであり、決して被告がその独断で商標登録したものではない。また、極真会館では、従来、商標権管理に十分な配慮がなされていなかったために、海外の支部長が無断で極真会館の商標登録をしてしまったという事件があり、G存命中から極真会館が商標登録を行って商標を管理していくことは一つの懸案事項になっていた。以上のとおり、被告が商標登録を行った動機は、Gから引き継いだ極真会館を未来永劫残していくために法律に基づく権利関係を整備するというものであり、極真会館館長としての当然の責務であった。 (イ) 被告による商標権行使の必要性と正当性 a 被告による商標権行使の必要性 「極真会館」、「国際空手道連盟」等の名称は、組織を表すものであり、これらの名称を冠した組織が複数存在した場合には組織間の誤認・混同が生じるのは明らかである。かかる組織間の誤認・混同を防止するため、複数の組織がかかる名称を使用できる状態が作出されるべきではない。 実際に、極真会館の承諾がないのに極真会館に関する表示や名称を使用する者がいることにより、極真会館に入門したいという者が誤解し、無断で極真会館を名乗る道場に入門してしまうという事態が生じている。このような事態を防止するために、被告が極真会館の館長として商標権を行使することの必要性には何ら疑問の余地はない。 b 被告による商標権行使の正当性 本件商標はG存命時から、Gが率いる組織により用いられてきたことからすると、現在本件商標を使用することができるのはGが率いていた組織と実質的に同一であると評価できる組織に限られるべきである。そして、現在被告が館長を務めている極真会館は、Gが創設した極真会館と比較して、総本部の構成・機能、支部・道場の編成の同一性、各種選手権大会開催の継続性、内弟子制度の継続性、各種証書・備品の同一性、取引関係の継続性、関連雑誌の同一性などが認められるから、団体としてGが創設した極真会館をそのまま承継したというべきである。したがって、被告が館長を務める極真会館が、本件商標の正当な権利者であることは明らかである。 イ 極真会館の商標権を使用できる者の範囲 (ア) 極真会館の組織運営 極真会館は、G存命中から、極真会館総本部を中心とし、国内支部、 直轄道場、海外地区連盟、海外支部等を展開する会員数50万人超に至る大組織であり、本件商標は、極真会館全体の活動を示すものとして使用されてきたものであるが、極真会館における空手活動は、極真会館総本部とGないし総本部から認可を受けた支部において行われてきたものである。 そして、かかる大規模な組織の運営は、一定の規約に則った組織運営の基盤がなければできないものであり、極真会館の規約は、時代ごとにその内容に変遷があるものの、遅くとも昭和48年には、活動の中心を総本部とし、各地における活動は総本部から承認を受けた支部によって行うという、極真会館の組織運営の大原則を確立していたものということができる(なお、昭和48年以前において、既にかかる組織運営の大原則が確立されていたことを否定するものではない。)。そして、かかる極真会館の組織的運営の大原則を徹底しかつ維持するために、支部長認可、テリトリー制、支部長の義務の履行という制度が確立されたのである。 これらの制度が確立されたことにより、総本部及び支部(長)以外に、極真会館の活動を主体的に行うことのできる地位というものは存しなくなった。したがって、極真会館の周知性の確立に貢献し、本件商標を主体的に使用できた者は、正式に支部長としての認可を得、支部長認可証の交付を受け、定められた義務を果たしてきた支部長に限られるのであって、それ以外の各構成員が本件商標を自由に使うことができる地位にあったなどということはあり得ない。 仮に、単に極真会館の一員である者、あるいは極真会館の一員であったにすぎない者に本件商標の使用を認めるとすると、現在極真会館の一員であり又は過去において極真会館の一員であった者すべてに対して、本件商標の使用を容認することになりかねない。しかし、極真会館は、本件商標の下、組織として統一性を保ちつつ、経済的・社会的な活動を行っているのであり、構成員すべてに本件商標の使用を認める場合、極真会館としてその使用に歯止めをかけることには限界があり、個々人が好き勝手に本件商標を使用することにより、極真会館の組織として統一された活動及びそれを表象する本件商標の価値は著しく損なわれるおそれがあることは想像に難くない。 また、支部長としてGから認可を受けた者であっても、既に極真会館という組織を脱退・離脱した者に極真等の名称や表示の使用権限を認めることはできない。極真会館の支部長以外の者や既に極真会館の組織から脱退した者に対して本件商標の使用を認めた場合、例えば、以上のような者が新たに第三者に本件商標の使用を認めた場合、あるいは別途組成した新たな団体の構成員が更に当該団体を脱退した場合に、当該第三者又は脱退者にも極真等の名称や表示の使用を認めるという結論が導かれることになりかねない。この場合、無権限者による本件商標の不当な使用が際限なく正当化されていくおそれが生じ、法律の定める商標権の保護は全くの画餅に帰してしまう。かかる事態に至った場合、極真会館あるいは極真空手の社会的価値、ブランド、伝統は完全に害され、極真会館としての活動に致命的な打撃を与えることは一見して明白である。 (イ) 支部長 極真会館の支部長とは、極真会館の支部規約に定められた一定の資格要件を満たした上で、極真会館の代表者たるGないし総本部から正式に支部長としての認可を得、支部長認可証の交付を受けた者である。このようにして認可された支部長は、認可された地域の範囲内では道場や分支部を開設することができたが、 その地理的範囲は支部長認可の際に定められた地域に限定されていた。 支部長は、道場を運営し、極真空手の教授を行っていくに際して、極真会館の一員として必要な範囲内で本件商標や極真の表示を使用することができた。しかし、支部長以外の者が極真のマークを使用することは許されなかった。 一方、支部長の主な義務としては、支部規約等において、①支部として加入する際に認可料を本部に支払うこと、支部単位での年会費を本部へ納入すること、昇段者登録料等を本部に支払うこと、②本部で行われる支部長会議及び支部長講習会へ出席すること、③本部主催で行われるオープントーナメント全日本空手道選手権大会等の大会に選手を送り、大会遂行に協力すること、④総本部合宿へ参加すること等が挙げられる。なお、支部長から本部へ支払われる認可料、年会費、 昇段者登録料等は、極真会館の主たる財源の一つであって、かかる収入がなければ各種大会の開催、広告宣伝活動など極真会館の運営を行っていくことは不可能であった。 このような支部長としての地位は、第三者に譲渡・転貸することは規約において禁じられており、支部長が交代する場合には、たとえ親子間であっても、新たに支部長としての認可を得て、認可証の交付を受けることが必要とされた。また、支部規約等に違反した場合には、所定の手続を経て支部長認可を取り消し、除名処分などを行うことが規約に規定されており、実際、著名な支部長が除名処分に付されている。なお、除名処分された者が極真等の標章を使用することはなかった。 なお、極真会館は昭和52年の時点において、すべての支部長について一斉に支部長認可証を交付する手続を行っている。したがって、昭和52年時点において支部長であった者はすべて認可証の交付を受けている。 極真会館の活動において、総本部と支部という関係は、組織的活動の基本として不変のものであり、総本部及び支部(長)以外に、極真会館の活動を主体的に行うことのできる地位というものはあり得ない。 (ウ) 分支部長 分支部長は、その所属している支部の支部長によって任命され、分支部における道場の道場生の指導に当たる者である。一般に、分支部長は、支部長から指導料の支払を受けて道場生を指導することを職務とし、道場を運営する権限を持たなかったが、一部の支部においては、分支部長が支部長による道場開設の許可の下に道場を開設して、その道場を運営する場合もあった。 分支部長は、あくまで支部長がその判断と責任において任命するものであり、その際、Gないし総本部の承認を経ることはない。分支部長の活動は、支部長から認可された地域内で認められるものにすぎず、その地位の根拠は支部長に存し、支部長は自ら任命した分支部長を解任する権限を有している。 そして、このことは極真会館の組織運営の基盤になるものであり、支部が異なって、個々の分支部の運営形態が独立採算であろうと、給料制で運営されようと、それは支部長の責任の下で実行されるものであるので、分支部長という立場自体には若干の差異は生じるかもしれないが、分支部長の地位はすべて支部長の地位に基づいているという根本的な部分には相違がない。 その他、支部規約上、分支部長の地位・権限に関する記載がないこと、分支部長を対象とした認可証はないことなど、支部長の地位と分支部長の地位が全く異なることは明白である。 (エ) テリトリー制 極真会館では、支部は基本的には最大の地方行政区画毎に1つ置かれたが、東京都、大阪府、神奈川県といった一部の大規模な都府県においては、更に複数のテリトリーに分割され、その分割されたテリトリー毎に1つの支部が置かれていた。 テリトリー制は多くの支部が共存・共栄していくためには不可欠なものであった。仮に、同じ地域に複数の支部長が競合することになれば、各支部間に軋轢が生じ、秩序を維持することはできなくなる。したがって、テリトリー制は極真会館の組織としての存立の基盤である。 原告らは、2県以上の認可を受ける支部長もいたこと、都道府県によっては複数の支部があったことなどを指摘するが、これらはいずれも、支部の共存・共栄という観点から説明でき、テリトリー制の本質に反するものではない。また原告らは、全日本チャンピオン等が自由に道場を開設できたことを指摘するが、 これはまさに全日本チャンピオン等になった者だけに許される例外にすぎず、これをもってテリトリー制を否定することはできない。 なお、認可された支部長は複数の道場、更には分支部を開設することができたが、その地理的範囲は支部長認可の際に定められた地域に限定されていた。そして、実際、認可される地域は認可証に明記されていた。 支部長が自己の支部の管轄以外の区域に道場を開設することは規約違反であり、Gないし総本部が知った場合、特別の事情から事後的な承認を与えることがあったとしても、原則として、これらを容認することはあり得なかった。 (オ) 原告らのフリーライド 原告らは、Gの存命中から本件商標を使用してきたことを主張する。 しかし、Gの存命中であっても、本件商標の使用が支部長に無償で認められてきたわけではない。前述したように、正式に認可を得た支部長は認可料や年会費、昇段者登録料等を極真会館に支払う義務を負担しており、かかる収入は極真会館の各種大会の運営費や組織の維持費として費消されたが、その反面で、各種大会が成功することによって、更に極真会館の知名度・名声は高まり、各支部の道場への入門者は増大していくという関係にあったのである。 この点、原告A及び原告Cは、単体道場として活動してきたとのことであり、極真会館に対する認可料や年会費、昇段者登録料等の支払義務を負担することなく、一方で被告らが多大な費用と労力をかけ、国際的な組織を運営し、大規模な国内・国際大会を開催すること等により築いた極真会館の名声・グッドウィルにフリーライド(ただ乗り)して入門者を獲得していることは明らかである。原告らは、全日本極真連合会へは会費等を支払っている旨の主張をするが、本来、被告が館長を務める極真会館に対して支払を行わなければ認められない本件商標の使用が、極真会館から離脱・脱退した者によって組織される団体への会費等の支払によって、認められる理由はない。 このように、原告らは、いずれも本件商標の名声・グッドウィルにフリーライドしている者であって、このような者らに対して、あえて例外的に権利濫用の抗弁を認める必要は全くない。 (カ) 原告らの主張の不当性 原告らは、「極真マークの使用に関してみれば、極真会館の道場を開設し運営する支部長や分支部長らにとって、本来それを使用するのが当然であり、 事前も事後も一切許可の手続をとることなく、堂々と使用してきたというのが実情である。」旨主張する。しかし、本件訴訟で提出されている証拠からはそのようなことは何ら明らかではない。 確かに、昭和47年の「国内支部設立契約書」及び昭和51年の「支部規約」には、極真会館のマーク等についての規定が存在しないが、その当時であっても、極真会館の構成員であれば誰でも自由に極真会館のマーク等を使用できたわけではなく、むしろ、無断使用の禁止は当然のこととされていたので記載されていなかったにすぎない。そして、昭和52年の支部規約12条は、「支部は既に登録してある極真のマーク(カンク、連盟マーク、胸章等)を委員会の承認なしに無断で使用できない。」と定め、極真マーク等の無断使用を禁止していた。これは従来から極真マーク等の無断使用が禁止されていたところ、海外等における無断使用等の問題が生じてきたため、規約上明文化したものであり、以後、支部規約においては一貫して極真マーク等の無断使用が禁止されている。原告らは、支部規約の条項は、Gの一存でいつでも変更されたと主張するが、上記のように極真マーク等の部分に限っても昭和52年以降は変更されることなく一貫しているのであって、かかる主張は失当である。原告らは極真マーク等が商標登録されていなかったため「既に登録してある極真のマーク」という支部規約の規定が死文であるかのごとき主張をする。しかし、商標登録が実際になされていたかということと、極真マーク等の無断使用が禁止されていたこととの間には何ら関係がない。 また、原告らは、単なる一会派の長である被告が商標権の行使をすることにより他の会派による本件商標の使用を妨げることは権利の濫用である旨主張している。しかし、原告らは、要するに、全国的な組織に所属した場合に不可避的に存在するテリトリー制に基づく制限、各種金銭の支払義務など、組織に属することによる制約や義務を免れつつ、自己に都合のいいように本件商標を利用することを企図しているものに他ならない。 さらに、一方において単体道場であると主張しながら、「○○支部」、「国際空手道連盟」など、組織の存在を前提とする呼称の使用を求めることは、明らかにそれ自体矛盾する主張である。このような名称をあえて原告らが使用するのは、まさに被告が館長を務める、国際的な組織である国際空手道連盟極真会館の名声にフリーライドしようとする意図があることの表れである。 そもそも、原告らの従前の立場、主張を前提とするならば、国際空手道連盟極真会館と自称していた支部長協議会派が、被告が館長を務める極真会館の組織を離脱した以降に、極真等の標章の使用を継続することは明らかに自己矛盾する行為である。実際、これまでも、極真会館を離脱した者や除名された者は、たとえ従前は支部長たる立場にあっても、極真等の標章を使用することはなく、新しい標章の下に独自の活動を展開してきている。 (3) 争点(1)ウ(原告らの個別事情)について 【原告らの主張】 原告らには、次のような事情があり、いずれの原告も、G生前の極真会館において同人の承認の下に本件商標を用いて空手の教授、空手大会等の興行等を行っていた者(支部長、分支部長、道場責任者及び道場指導員)ということができる。したがって、被告が、原告らに対し、本件商標権に基づき本件商標の使用の差止めを求めることは、権利の濫用に当たる。 ア 原告Aについて 極真会館関西本部(以下「関西本部」という。)は、東京の総本部直轄として、昭和53年10月開設された。その運営は、Gが管理監督し、その人事及び財政等も全面的に支配下においていた。しかし、当時関西ではまだ極真会館の地盤は弱く、昭和54年4月、原告Aは当時の極真関西本部の責任者Tから関西本部の運営に携わるよう要請され、これに応じ、関西本部に入門した。 翌55年、Gは、娘婿のUを5年間の任期で関西本部に派遣することを決め、また、原告Aに対し、関西本部相談役に就任するよう要請した。関西本部相談役というのは、一般の支部相談役と異なり、G直接任命の地位である。原告Aは、Gの要請、すなわち任命を受けて相談役に就任し、昭和62年、極真会館みどり橋道場を開設した。 その後、Tが関西地区の総責任者に転出したため、関西本部はUと原告Aの2人体制となり、大阪で毎年開催される全日本ウエイト制空手道選手権大会は、原告Aが中心となって準備し、開催した。平成4年6月に開催された第9回全日本ウエイト制空手道選手権大会の大会冊子には、最高審判長Gの載るページに原告Aが運営副委員長として記載されている。 平成5年10月、Gは、原告AとUに対し、来年にはUは総本部に戻ること、原告AはUの跡を継いで関西本部長に就任することを言い渡した。ところが翌6年4月Gが急逝したため、Gの上記任命を実行するためにUが総本部宛の文書を作成し、同年8月、原告Aが関西本部長に就任した。 なお、原告Aは、平成3年4月、Gから極真空手3段を認可されている。 イ 原告Bについて 原告Bは、昭和42年に極真会館に入門し、昭和45年に開催された第2回全日本空手道選手権大会において優勝した者であり、被告の極真会館入門(昭和51年)のはるか前から極真会館の著名人として本件商標の周知性・著名性の確立に貢献してきた者である。 原告Bは、Gから昭和46年1月に徳島県の支部長を認可され、さらに昭和52年10月には愛知県の支部長も認可された。原告Bは、両県において極真会館の道場を11か所開設した。 なお、原告Bは、平成5年6月、Gから極真空手5段を認可されている。 ウ 原告Cについて 原告Cは、昭和46年に極真会館に入門し、昭和50年9月にGから支部長に任命され、極真会館仙台道場等で指導を行った。また、昭和52年には空手東北地区大会で準優勝した。 その後、原告Cは、歯科医師国家試験、麻酔認定医試験のため、活動を中断していたが、昭和63年、神奈川県で歯科診療所を開業するとともに、神奈川県北支部長となり、ボランティアとして極真会館道場3か所を開設した。 原告Cは、昭和50年9月、Gから、当時まだ数少ない極真空手初段を認可され、活動再開後の平成5年3月、2段を認可されている。また、Gが毎年5月に国内外の支部長・幹部らを指導した「湯ヶ原合宿」というものがあるが、原告Cはこれに平成2年より参加していた。 エ 原告Dについて 原告Dは、昭和50年に極真会館に入門し、昭和54年指導員となり、 昭和59年には東京都下城西支部長Vから分支部長に任命され、町田道場ほか3か所の道場を開設した。同支部には、6つの分支部が開設されたが、原告Dは筆頭分支部長であり、支部長のVが道場の運営から手を引いた後はその道場を引き継いだ。 また、原告Dは、極真会館の正式な行事、すなわち、全日本空手道選手権大会、昇段審査会、鏡開き等に支部長と並んで参加し、Gの指示で号令をかける役目をさせられることもあった。さらに昭和58年には、Gの指名によって、フランス空母ジャンヌダルク号に極真空手黒帯精鋭団として派遣されたこともあるなど、極真会館の幹部の一人として活動してきた。 なお、原告Dは、平成5年6月、Gから極真空手4段を認可されている。 オ 原告Eについて 原告Eは、昭和56年、極真会館に入門し、昭和61年指導員となり、 平成5年東京都下城南支部長Wから分支部長に任命され、田町道場を開設した。また、空手の教授とともに各種選手権大会にも積極的に出場し、平成2年の第7回全日本ウエイト制空手道選手権大会で2位に入賞している。 原告Eの東京都下分支部長としての地位、役割は原告Dと同様、支部長に準じる幹部といえるものであり、G死去までの14年間の活動は本件商標の周知性の確立に大いに貢献したものである。 なお、原告Eは、平成5年6月、Gから極真空手2段を認可されている。 【被告の主張】 原告らにはそれぞれに次に述べるような事情があり、いずれも、正式に支部長としての認可を得、支部長認可証の交付を受け、定められた義務を果たしてきた支部長ということはできないから、被告が原告らに対して本件商標権に基づく権利行使をすることは権利濫用に当たらない。 ア 原告Aについて (ア) 原告Aは、極真会館関西総本部長を自称して、無断で近畿一円に極真会館を名乗る道場を開設している者にすぎず、かつて支部長の地位にあった者ではない。 (イ) 原告Aは、関西総本部長となる前には、「関西本部相談役」であった旨主張し、しかも、「関西本部相談役」は、一般の支部相談役とは異なる地位であることを主張する。 そもそも関西本部は、Gが総本部の直轄として開設したものであり、 その運営の最終決定もGが行っていた。したがって、関西本部はあくまで総本部の一部であって、総本部直轄であるとはいえその実態は各支部以上の機能を有するものではなかった。 関西本部がこのようなものであった以上、原告Aがその地位にあったと主張する関西本部相談役は、あくまで上記のような機能を有する関西本部のアドバイザー的な立場で、関西本部の責任者の裁量で認められた立場にすぎず、いわば支部の相談役と性質をほぼ等しくするかあるいはそれ以下の地位にあるものであった。 関西本部相談役たる地位が、このような地位である以上、Gないしは総本部から直接任命を受けるということは想定できない。 (ウ) 原告Aは、平成元年6月に開催された第6回全日本ウエイト制空手道選手権大会の大会冊子、平成4年6月に開催された第9回全日本ウエイト制空手道選手権大会の大会冊子に、原告Aが運営副委員長として掲載され、実務的中心的役割を果たしていたことを強調するが、大会のパンフレットに大会運営副委員長と記載されていることと、Gから本件商標を使用して空手活動を行うことについての承認を与えられたこととの間に関連性は存在しない。この点、原告A本人も、大会運営副委員長という地位では、自ら大会の開催や道場の開設などの行為はできないことを自認している。 全日本ウエイト制空手道選手権大会は、慣例により大阪で開かれる都合上、当時、関西本部長であったUが大会運営委員長となり、関西本部相談役であった原告Aが便宜上大会運営副委員長という肩書になったにすぎない。さらに大会運営副委員長という立場は、大会運営に関わる現場のスタッフの現場監督的な、又は現場監督補佐的な位置付けにすぎず、大会の開催等最終的な意思決定等を行えるような地位ではない。 なお、原告Aは、支部長会議に正式な支部長として出席したことはなく、また、極真会館の総本部の状況等については全く関知していなかった。極真会館の総本部において仕事をしていた被告が、原告Aは関西本部の壮年部の1人であり、その当時責任者をしていたUの友人という認識しか有していなかったことは当然のことであり、これらの事実のみをもっても、原告Aが支部長と同様の立場でなかったことは明らかである。 (エ) 原告Aは、平成5年10月にGから関西本部長就任を言い渡され、 さらに、Gの死後において、関西本部長(支部長)に就任した旨主張するが、この点の原告Aの供述等の証拠は信用性に欠けるものである。 (オ) 原告Aは、現在、大阪府にとどまらず、京都府、兵庫県、奈良県にも道場を有している。これは、G存命中に関西本部が開くことができる道場が少なくとも大阪府内に限られていたことに明らかに反するものであって、Gが築いた秩序を乱すものと評価できる。このような者に、権利濫用を例外的に主張させる必要性は全くない。 以上より、原告Aが、極真会館の支部長あるいは支部長と同様の地位にある者として、本件商標を使用する権限を有しているとは到底認めることができない。 イ 原告Bについて (ア) 原告Bは、第1回オープントーナメント全日本空手道選手権大会で3位、第2回オープントーナメント全日本空手道選手権大会で優勝し、昭和46年に極真会館の支部長に就任している。そして平成6年にGが逝去した後に、いったんは、被告を正当な館長として認めながらも、他の多数の支部長とともに被告の館長を解任するという形式を取って、支部長協議会派を結成している。 (イ) しかしながら、被告の館長解任は、年齢的にも若く、支部長としての経験も浅い被告が館長であることに感情的な不満を持つ一部の支部長によって画策されたものであり、その当時、決議に参加した支部長らの真意に基づくものではなかった。また、極真会館においては館長解任の手続が定められておらず、かかる館長解任決議なるものが効力を持つことはあり得ない。Gの遺志を継いで館長に就任した被告を一部の支部長らが一方的に解任することなど認められるはずはないから、原告Bらの行った被告の館長解任決議には何らの効力も認められるものではない。そして、正当な代表者をそれと認めず、新たな組織を結成するという行為は、 自ら所属する組織、すなわち極真会館を脱退したものと評価せざるを得ない。 (ウ) また、原告Bは、本人尋問において、被告を極真会館の正当な館長として認めて、被告と行動を共にした理由として、「総裁が残した遺言ですから、 それに従うのが当然だと、その当初は思いました。」と供述している。 被告はGの遺志を継いで極真会館の館長に就任したのであり、形式的な遺言書に従って極真会館の館長に就任したのではない。被告はGの遺言又はその奥にあるGの遺志に従って極真会館の館長に就任したのであるから、形式的な遺言書の有効性が確認されなかったという理由で極真会館を離れて他の会派を設立する行為は、Gの創設した極真会館から離脱・脱退する行為に他ならない。 (エ) 以上より、原告Bは、極真会館という組織を自ら脱退したのであり、原告Bは、既に極真会館の支部長として本件商標を使用する地位を失っている。 ウ 原告Cについて (ア) 昭和50年に支部長認可を受けたとの主張について 原告Cは昭和50年9月にGから正式に支部長認可を受けたと主張するが、かかる主張は、全く事実に反する(詳細は被告の平成15年6月16日付け準備書面(5)の32ないし42頁参照)。 (イ) 昭和51年から昭和63年まで 原告Cの本人尋問での供述を前提としても、原告Cは、宮城支部長がcからdに交代したことを契機に、昭和51年には仙台支部長の地位を退いている。 さらに、平成15年3月15日付けの原告Cの陳述書や本人尋問における供述によれば、原告Cは、昭和52年の空手東北地区大会(なお、この大会は極真会館が主催する大会ではない。)で準優勝したあと歯科医師国家試験の受験勉強に専念することとなり、現役復帰したのは昭和63年とのことである。実際、例えば、昭和53年には仙台市において第1回オープントーナメント全東北空手道選手権大会が開催されているが、この大会役員の中や大会運営組織図の中はもちろんのこと、出場選手の中にも原告Cの名前は一切出てこない。 したがって、少なくともこの間(昭和51年から昭和63年まで)、 原告Cは、正式な選手の指導や大会の開催等といった極真空手に関する活動は何も行っていなかったことになる。 (ウ) 昭和63年の神奈川県北支部長就任という主張について 原告Cは昭和63年に神奈川県北支部長に就任したと主張する。しかし、これについては、①支部長認可証が存在しないこと、②その他の客観的な証拠が存在しないこと、③原告Cが神奈川県北支部長に任命されたと主張する昭和63年当時、神奈川県は東支部と西支部にわかれて、それぞれk支部長とm支部長の下、支部活動が行われていたのであって、元全日本のチャンピオンでもない原告Cが神奈川県での道場の開設等を認められるはずがないこと、④原告Cは、ボランティアとして道場を運営していると主張するが、原告Cのようなやり方では、組織としての極真会館や支部長としての義務を果たしている正当な支部長の道場経営が破綻してしまうことは明らかであること、⑤原告Cが仮処分命令申立事件において提出した名刺(乙102)には、極真会館j道場の最高顧問(麻酔認定医)の肩書が記載されているだけで、神奈川県北支部長といった記載は一切なされていないこと、からすれば、原告Cが主張する上記事実が存在するとは到底考えられない。 (エ) 原告Cの現在の活動について 原告Cは、現在、極真空手極真神奈川における責任者として、神奈川県南足柄市、足柄上郡山北町、同郡大井町のみならず、小田原市、横浜市、更には相模原市において、広範囲に極真空手の道場を開設している。これは、明らかに、 G総裁の生前時に足柄地方で行ってきた原告Cの独自の活動よりも広いものとなっている。 (オ) 小括 以上からすれば、原告Cは、「グループ内部の者(G生前の極真会館において、同人の承認の下に本件商標を用いて空手の教授、空手大会の興行等を行っていた者)」に該当しないことは明らかである。 また、原告Cは、現在、上記(エ)のとおり、極真空手極真神奈川における責任者として、広範囲に極真空手の道場を開設し、明らかに、G総裁の存命中生前足柄地方で行ってきた原告Cの独自の活動よりも広いものとなっているが、これは、Gが築いた秩序を乱すものと評価できる。このような者に、権利濫用を例外的に主張させる必要性は全くない。 エ 原告Dについて (ア) 原告Dは、極真会館東京城西支部の支部長であるVから分支部長に任命されて、Vが開設した道場の一部を任され、G存命中からの極真会館の幹部であり、本件商標の周知性の確立に大いに貢献してきたと主張する。 (イ) しかし、 分支部長という立場は、支部長会議への出席の権限も義務もないこと、総本部への会費の支払義務もないことなどから、支部長の意思を前提としていて、あくまでも、支部長が認めた範囲内で、支部としての活動を補佐的に行っていく立場にすぎなかったことが明らかであり、原告Dの主張は虚偽を含むものである。 なお、原告Dは、支部長の意向に反し極真会館を離脱した者である。 (ウ) 分支部長は、Gから直接認可を受けるものでないこと、支部長会議への出席義務がないこと、極真会館総本部に対し直接金銭を納付する義務がないこと、道場を開設するには支部長から許可を受ける必要があること、支部長に対して分支部会費等を納入する義務があること、支部長の権限によりその地位から解任され得ることなどについて、原告Dもその本人尋問において自認しており、これらの事実からすれば、認可された地域の範囲内で本件商標を使用して空手活動を行うことができる支部長とは全く異なる立場であることは明らかである。 また、城西支部においては、総本部からの連絡は支部に対してのみなされ、それを支部長のVから分支部長に分支部長会議で伝達していたものであり、 各種大会に城西支部から選手を送り出す時にも、選考試合に立ち会ったり、茶帯を集めて月1回指導することなどもVが自ら行っていた。城西支部においても、分支部長は、明らかに支部長の補佐的な立場にすぎなかったのである。 かかる立場の分支部長が、支部から独立して極真会館に関する商標その他の表示を使用することはできなかった。原告Dにおいても、その道場の広告には、必ず「館長G 支部長V 師範D」という表記を用いており、支部長の支配下にあることを明記していた。逆に、支部長の氏名等を記載せずに極真会館の表示を使用した広告をすることが不可能であったことは、原告D本人も認めている。 なお、原告Dは、極真会館の行事で一定の役目を任されたり、一定の成績を収めたり、Gと共に写った写真が雑誌に掲載されたことを主張するが、これらは、原告Dが過去に極真会館の一員として活動していたことの証拠にはなるものの、本件商標の使用権限を根拠付けるものでは全くないことはいうまでもない。 (エ) また、原告Dが、Vの下で開設が認められていた代田橋、町田、千歳烏山、狛江のほか、橋本、百合ヶ丘、新百合ヶ丘、幡ヶ谷、永福町、東村山等にも道場を有していることに十分留意する必要がある。これは、明らかに、G生存中に東京城西支部が開くことができる道場が東京城西支部のテリトリーの範囲に限られており、少なくとも横浜市や川崎市等神奈川県にまで道場を開設することは認められてはいなかったことに反するものであって、Gが築いた秩序を乱すものと評価できる。このような者に、権利濫用を例外的に主張させる必要性は全く存在しない。 (オ) 原告Dは極真会館を離脱した後に、G存命中に支部長の許可がなければ開設できなかった地域に続々と道場を開設しているほか、支部長への会費等の支払義務も止めてしまっている。このように極真会館の存立の基盤であるテリトリー制や支部会費の支払を中止していることは、極真会館における分支部長の地位を放棄したことの現われでもある。 (カ) したがって、原告Dは、分支部長という地位にはあったものの、そもそも本件商標を使用する地位にはなく、現在は、かかる分支部長の地位さえも放棄し、G存命中の極真会館の規律に反して本件商標を使用するものであるから、原告Dの主張する権利濫用の抗弁は成立しない。 オ 原告Eについて (ア) 原告Eは、極真会館東京城南支部の支部長Wから東京城南川崎支部の分支部長に任命され、田町道場を開設して以降、極真会館の幹部であり、本件商標の周知性の確立に大いに貢献してきたものと主張する。 (イ) しかしながら、分支部長は、前述のとおり、認可された地域の範囲内で本件商標を使用して空手活動を行うことができる支部長とは全く異なる立場である。 実際、原告Eは、支部長のWから許可を得た田町以外の地区である向ヶ丘に道場を出そうとしたが出せなかった経緯があり、この点について、原告Eは自分の意思で他の分支部長に譲ったかのような主張をするが、原告E自身が認めているように、最終的には支部長からの許可が得られなければ、支部長から許可を得た範囲以外に道場を開設することはできなかったのである。 (ウ) また、原告Eは、Wに従わずに、極真会館から離脱した者である。 そもそも、上述のとおり、G存命中の極真会館において、原告Eは支部長の許可なく道場を開設することは認められていなかった。それにもかかわらず、原告Eは、Wから許可された田町以外にも千葉県八千代台や神奈川県都筑に道場を次々に開設している。このように、極真会館の組織としての活動を無視して、 自分勝手に道場を開設する行為は、Gが築いた秩序を乱すものであり、また、極真会館という名声ないしブランドを不正に利用する行為であって、このような者に、 権利濫用を例外的に主張させる必要性は全くない。 (エ) なお、原告Eは、極真会館の行事で一定の役目を任されたり、一定の成績を収めたり、Gと共に写った写真が雑誌に掲載されたことを主張するが、これらは、原告Eが過去に極真会館の一員として活動していたことの証拠にはなるものの、本件商標の使用権限を根拠付けるものでは全くないことはいうまでもない。 前述の極真会館の組織構造及びその運営の実態(特に、極真会館の規約においては、支部長を権利義務の主体として定めた規定こそあれ、分支部長を主体として定めたものは一切存在しない。)を見た場合、支部において支部長の下で活動する分支部長、師範、一道場生が、極真会館の周知性の確立に主体的に貢献するということはあり得ず、総本部ないし被告の許可なく極真会館の商標を使用することはできないことは明らかである。まして、段位や副審資格の有無などは商標を使用できる地位とは全く関係がない。 (オ) したがって、原告Eはそもそも本件商標を使用する地位にはなく、 しかもG存命中の極真会館の規律に反して本件商標を使用するものであるから、原告Eの主張する権利濫用の抗弁は成立しない。 2 争点(2)(被告の不法行為及び原告らの損害) 【原告らの主張】 (1) 被告の不法行為 原告らは、それぞれの開設する道場への入門案内として最も有力な方法として、NTT発行のタウンページに、極真会館・極真空手の道場であることを示す広告を掲載してきた。これに対し、被告は、平成11年から12年にかけて、NTTに対し、本件商標を使用する原告らの広告は本件商標権を侵害するから、掲載してはならない旨申し入れた。被告の申入れを受けたNTTは、原告らに対し、平成12年からのタウンページへの広告掲載拒否の通知を行い、原告らは従前の広告を掲載することができなくなった。これは、被告による本件商標権行使の権利濫用行為であり、原告らに対する不法行為に当たる。 さらに、被告は、原告らの道場の近隣にF派の道場を開設し、本件商標を使用したタウンページ広告を掲載したり、原告らは本件商標を使用できず「ニセ極真」であると宣伝したりした。 被告のこれらの行為により、原告らの道場の入門者や道場生が減少した。 (2) 原告らの損害 原告らは、タウンページの代替手段となる広告の代金を支出しなければならなくなったほか、入門者の減少による月謝等の収入が減少するという経済的損害と、その結果に関する精神的損害を被った。 精神的損害は、原告らそれぞれにつき300万円を下らない。そして、原告らの個別事情による財産的損害を加えると、原告らのそれぞれの損害は次のとおりとなる。 ア 原告Aについて 原告Aは、NTTのタウンページの大阪版、兵庫版及び奈良版に、毎年「極真空手・極真会館関西総本部」と記載した道場案内の広告を出してきたが、被告の妨害により、平成13年度の1年間は広告を出すことができなかった。 平成12年5月10日申込みのタウンページ広告費は、167万4000円であった。多額の広告費を支出するのは、それによって新道場生を獲得し相当の収入が期待できるからである。平成13年度については、タウンページに広告を出せなかったため、新聞折込み広告、ポスター、看板等、ありとあらゆる手段をとった。しかし、平成12年度に比べると、道場入門者は半分以下となった。そのため道場生も減少し、平成13年中に玉造道場、伊丹道場、東成スポーツセンターの3道場の閉鎖を余儀なくされた。 平成14年3月から、仮処分決定により再びタウンページに広告を掲載できるようになったが、前年度のタウンページにF派の道場の広告のみが掲載され、更にF派が道場を増やしたことで、1年間の空白を取り戻すことは非常に困難な状況が生じた。このため、他の広告手段も引き続きとらざるを得ず、結局多額の支出を余儀なくされた。 以上による経済的損失は、少なくみても800万円を下らない。 また、弁護士費用として、仮処分命令申立事件と本件訴訟により、86万円を要した。 よって、原告Aの損害は、慰謝料も含めると1186万円を下らないところ、内金として1000万円を請求する。 イ 原告Bについて 原告Bは、徳島県に4道場、愛知県に13道場を開設しており、タウンページの広告費は、徳島版で36万9600円、愛知版で79万6800円、合計116万6400円である。 タウンページ広告に対する被告の妨害や、徳島県や愛知県にF派が新道場を進出させたことにより、道場生が激減した。原告Bもまた、ポスターその他の広告費に多額の支出を余儀なくさせられた。 以上による経済的損失は、少なくみても900万円を下らない。 また、弁護士費用として、仮処分命令申立事件と本件訴訟により86万円を要した。 よって、原告Bの損害は、慰謝料も含めると1286万円を下らないところ、内金として1000万円を請求する。 ウ 原告Cについて 原告Cは、新たに開設されたF派の道場について悪評が立ち、極真会館の名が汚れると考え、真の極真会館道場の存在をアピールしようと平成12年6月にタウンページの広告掲載を申し込んだところ、被告の妨害により拒否された。 広告掲載を妨害された原告Cは、原告Aらと共に大阪地方裁判所に妨害排除の仮処分申立てを行った。その結果平成13年6月からタウンページに広告掲載ができるようになったが、広告費は50万7780円であった。 弁護士費用として、仮処分申立事件と本件訴訟により86万円を要した。 また、原告Cは、被告による妨害の排除のため余儀なくされた訴訟及びその準備活動のために、本業の歯科診療所を約30日休業した。1日の収入が約23万円であるから、690万円の損害となる。 よって、原告Cの損害は、慰謝料も含めると1078万円を下らないところ、内金として1000万円を請求する。 エ 原告Dについて 原告Dは、東京都下城西支部の分支部長であったところ、平成3年、支部長Vから、代田橋道場を譲り受け、以後5道場・2教室を開設、運営し、タウンページに広告を掲載し、広告費は218万6415円を支出していた。 しかるに、被告の妨害により、平成13年3月から広告掲載ができなくなり、道場への入門者募集に甚大な被害を被っている。その上、F派は、その道場を原告Dの道場と同じ道路の並びに新設するなどしており、入門して日の浅い道場生がニセの極真とのデマにおどらされ、F派の道場に移る者も現れている。 タウンページの代わりに、ポスター、看板等に多額の支出を余儀なくされているが、この状況では、経営縮小、道場の移設も考えなければならず、その支出は1000万円以上が予測される。 以上による経済的損失は、1200万円を下らない。 また、仮処分命令申立事件、本件訴訟による弁護士費用として71万円を要した。 よって、原告Dの損害は、慰謝料を含めると1571万円を下らないところ、内金として1000万円を請求する。 オ 原告Eについて 原告Eは、平成5年4月、東京都下城南支部の分支部長として港区に田町道場を開設したのを皮切りに5道場を開設、運営し、タウンページに広告を掲載し、広告費は153万6000円を支出してきた。 しかるに、被告の妨害により平成12年から広告掲載ができなくなり、 道場への入門者募集に甚大な被害を被っている。 そうした中で、近くにF派の新道場が次々に開設し、原告Eの道場を妨害しているのは、原告Dの場合と全く同じである。またポスターや看板で対抗を余儀なくされているのも同様である。 以上による経済的損失は、1000万円を下らない。 また、仮処分命令申立事件、本件訴訟による弁護士費用として、71万円を要した。 よって、原告Eの損害は、慰謝料を含めると1371万円を下らないところ、内金として1000万円を請求する。 【被告の主張】 (1) 原告らは、①被告が本件商標の商標権者として、NTT(正確にはエヌ・ティ・ティ番号情報株式会社)に対し、本件商標に関する権利を侵害する標章をタウンページに掲載しないよう申し入れたこと、②被告が、「原告らの道場は極真会館を脱退した者のニセの道場だ」などと宣伝したこと、③被告が館長を務める極真会館が新たに道場を開設していること、は違法であると主張する。 しかしながら、①については、被告は極真会館の館長であり、また本件商標の商標権者であるから、極真会館の館長の責務として、また権利者の正当な権利行使として、本件商標権を侵害する行為がなされないよう、予めNTT等に申入れを行うことには、何ら違法性はない。 また、②については、被告が当該誹謗中傷行為を行った事実はない。 さらに、③については、被告が極真会館の館長として、組織の拡大を図るために新道場を開設することは正当な行為である。 (2) 原告ら主張の損害の発生及び額は争う。 |
|
|
争点に対する判断
1 争点(1)(被告が、本件商標権に基づき、原告らが空手の教授等を行うに際して本件商標を使用することの差止めを求めることは、権利濫用となるか)について (1) 争点(1)ア(原告らは極真会館を離脱したのか、それとも極真会館はいくつかの会派に分裂したのか)について ア 前提事実と証拠(甲1の1ないし8、甲2の1ないし8、甲3ないし5、6の1及び2、甲7、9ないし12、21、30、31、48、50、60の1ないし3、69ないし73、乙2ないし18、24、25、31ないし33、35、36、44ないし78、88、90ないし93、原告ら及び被告各本人)及び弁論の全趣旨を総合すれば、次の事実が認められる。 (ア) G(大正12年生)は、空手の修練を積み、日本国内のほか、欧米その他の外国で格闘家と対決するなどして名声を高め、直接打撃制の武道空手を特徴とする「極真空手」を創始し、国内外に弟子を育てたが、極真空手を推進し、普及させることを目的に、昭和39年に極真会館を創設し、「館長」「総裁」と呼称された。極真会館は、平成6年時点において、日本国内に、総本部、関西本部のほか、55の支部、550道場、会員数50万人を有し、世界130か国、会員数1200万人を超える勢力を有していた。空手武道家としてのGは、同人の半生や武道家としての活躍を描いた著作も多数出版され、劇画にもなったことなどや、その率いる極真会館の隆盛によって、少なくとも、空手及びその他の格闘技に興味を持つ者の間に広く知られる存在になっていた(甲3)。 (イ) Gは、平成6年4月26日に病気のため東京都内の病院で死亡したが、入院中であった同年4月19日付けで、死亡危急時遺言の方式による遺言書である本件危急時遺言が作成された(甲4)。本件危急時遺言は、「遺言書」と題する書面と「遺言書(追加)」と題する書面の2通があり、同日、病室において、 P、O、S、R、Qの5人の証人の立会の下に、遺言者Gが証人Pに遺言の趣旨を口授し、同人が筆記した旨記載されており、その内容は、「遺言者死亡のときは、 次のとおり処理すること」として「極真会館、国際空手連盟を一体として財団法人化を図ること」、「Oは、財団法人極真奨学会理事長、株式会社グレートマウンテン社長を勤めて欲しい。」、「極真会館、国際空手道連盟のGの後継者をFと定める。世界各国、日本国内の本部直轄道場責任者、各支部長、各分支部長は、これに賛同し、協力すること。」、「Fは、極真会館新会館建設の第二次建設委員長として新会館を建設すること。」、「Oは、極真会館、国際空手道連盟、財団法人極真奨学会、株式会社グレートマウンテン、有限会社パワー空手等、極真空手道関連事業を監督し、Fの後見役として勤めて欲しい。Sは、Oを補佐して協力して欲しい。R、Qもこれを補佐し協力して欲しい。P、Xもこれに協力して欲しい。」、 「池袋の極真会館の土地建物(同所内所在動産も同じ。)は、新会館の土地も含めて、極真会館、国際空手道連盟、極真奨学会、グレートマウンテンに寄贈する。これらに対する出資等も同じ。」、「Y、Z、a、bは極真空手道には一切関係しないこと。」等の条項(その他、妻や娘に対して与える財産や妻らに毎月支払ってもらいたい金銭の額等を定めた条項もある。)が含まれ、遺言執行者に弁護士のPを指定するものであった。ちなみに、Gの妻はY、長女はZ、次女はa、三女はbである。 (ウ) Gの葬儀・告別式は、平成6年4月27日に極真会館葬として行われ、被告が葬儀委員長を務めた。出棺の際、本件危急時遺言の証人の一人であるOが「G館長は、遺言でFを後継館長に指名された。」と発表し、被告も、 同日行われた支部長会議において、自ら後継館長に就任する意思を明らかにした。 なお、この時点では本件危急時遺言は公開されず、また死亡危急時遺言であることやそのため遺言の日から20日以内に家庭裁判所に確認を求める審判申立てを行わなければならないことなどは一切説明されなかった。 Oの発表は葬儀・告別式に出席していた極真会館支部長らにとって唐突であったが、極真会館支部長らは、Gの遺言があるとなればその内容には絶対に従うとの考えから、平成6年5月10日開催された支部長会議において、全員一致で被告の館長就任を承認した。 (エ) Gは、本件商標につき、その存命中、商標登録出願をしなかった。 被告は、平成6年5月18日、被告個人の名義で、本件商標1ないし5及び8の商標登録出願をし、その後、平成7年2月20日に本件商標6につき、同月24日に本件商標7につき、同じく被告個人名義で商標登録出願をした。被告は、当初、これらの商標登録出願をしたことを、支部長協議会や支部長会議において、支部長らに説明しなかった。 (オ) 本件危急時遺言の証人の一人である弁護士のPは、平成6年5月9日、東京家庭裁判所に対し、本件危急時遺言の確認を求める審判申立てをしたが、 Gの遺族らは、同遺言に疑義を表明して争った。東京家庭裁判所は、平成7年3月31日、上記審判申立てを却下したが、その理由は、主として、本件危急時遺言は、証人となった5人(そのうちのOは、同遺言により遺言者の財産の遺贈を受ける法人の理事・代表取締役であり、証人欠格者であるとしている。)が、当時、病状の進行により体力、気力ともに衰えた遺言者(G)を2日間という長時間にわたり、証人らと利害の対立する立場にある家族を排除した状況の下で取り囲む中で作成されたものであり、遺言者が遺言事項の全部につき自由な判断のもとに内容を決定したものか否かという点で疑問が強く残るというほかなく、遺言者の真意に出たものと確認することが困難であるというものであった(甲4)。 東京高等裁判所は、平成8年10月16日、ほぼ同様の理由により抗告を棄却し(甲5)、最高裁判所も、平成9年3月17日、特別抗告を却下した(甲6の1)。 (カ) 一方、Gの未亡人Yは、Gの死後の一連の流れが被告一派による極真会館乗っ取り工作であると主張し、平成7年2月15日、自ら極真会館2代目館長を襲名することを宣言するとともに、それまでに被告により破門されていた5人の支部長と共に「遺族派」を結成した(甲7)。 また、Yは、平成7年3月31日、東京家庭裁判所で本件危急時遺言の確認の審判申立てが却下された後、被告に対し、極真会館総本部道場建物からの退去を求めて東京地方裁判所に提訴した。被告は、和解により、Yに同建物を明け渡した(乙90)。 (キ) 平成6年5月10日の支部長会議において被告の館長就任を承認した支部長の中には、その後、被告の極真会館館長としての言動に対して反発を抱く者が複数現れ、相互に連絡を取り合って被告の館長としての態度等に関する批判を行っていた。 平成7年4月5日には支部長協議会の開催が予定されていたが、同協議会は途中から、支部長会議に変更された上、緊急討議として、被告の館長解任動議が提出され、賛成35名、反対3名、欠席10名により、被告の館長解任が決議された。 これに対し、被告は、Gの遺志により館長となった者を支部長協議会や支部長会議で解任することはできないので、解任決議は無効であると主張し、引き続き極真会館館長の地位にあることを宣言した。 被告の館長解任動議に賛成した支部長らは、支部長協議会議長を中心に極真会館を運営すると主張して、いわゆる「支部長協議会派」を結成した。支部長協議会派は、平成7年4月5日、記者会見を行い、声明文を発表したが、その中で、上記支部長協議会で被告の館長解任決議を行った理由として、「極真会の私物化、独断専行、不透明な経理処理」の3点を挙げていた。 (ク) このようにして、極真会館は事実上3つの派に分裂した状態になった。 平成7年4月の時点では、支部長協議会派には30支部長(以下、複数の支部の支部長を兼ねている者は1名と数える。)、「遺族派」には9支部長、 被告を支持する勢力(以下「F派」という。)には、K、Jなどの12支部長が属していた。 その後、館長解任動議に賛成した「支部長協議会派」(後に代表者のIの名から「I派」と称するようになり、平成12年10月10日付けで、「特定非営利活動法人国際空手道連盟極真会館」の名称で法人登録した(乙88)。)の中からW、Nなどの9支部長が「F派」に移り、1名が支部長を辞めたため、平成7年12月時点で、「F派」は21支部長、「支部長協議会派」は21支部長、 「遺族派」(後に「H派」と称するようになる。)は9支部長が属している状態となった。 さらにその後、「支部長協議会派」に属していた支部長が、離脱して無所属となったり、平成13年12月に立ち上げられた日本空手道連盟極真会館全日本極真連合会(以下「全日本極真連合会」という。)に移ったりした。また、 「F派」からJやWが離脱して別会派「極真館」を立ち上げた。その結果、平成15年5月31日現在、G死亡時の支部長のうち現役者は、「H派」3名、「I派」12名、「F派」17名、「全日本極真連合会」12名、「極真館」3名、無所属3名となっている。 (ケ) 極真会館では、Gの存命中、全日本ウエイト制空手道選手権大会、 オープントーナメント全日本空手道選手権大会、オープントーナメント全世界空手道選手権大会などを開催していたが、平成7年以降は、それぞれの会派が個別にあるいは合同で、各種大会を極真会館の名前で引き続き、同じ名称で開催し、それぞれ属する会派の選手を参加させている(甲10ないし12、乙51ないし58等)。 また、F派は、G存命中備品等の関係で極真会館と取引していた業者との間での取引を継続し(乙74ないし78)、その他、Gの生前と同様の、総本部の構成・機能、支部・道場の編成、内弟子制度、関連雑誌の発行等を継続している。しかし、他の会派においても、本部・支部・道場制あるいはこれに類する組織構造を採ったり、証書等についてG存命中と同様の体裁のものを使用したりしている(甲69ないし72)。 (コ) 被告が出願していた本件商標1ないし5及び8については、平成9年7月11日に、本件商標6については同年8月8日に、本件商標7については同年10月17日に、それぞれ商標登録された。 イ 以上の事実によれば、極真会館は、極真空手の創始者であるGが一代で築き上げた組織であり、同人の生前、法人化されておらず、館長選任の手続についての定めもなかったから、その後継者が誰になるかということは、専らGの意思に係っていたものであるところ、被告が、Gの跡を継いで「極真会館」の「館長」となることが極真会館に属する者らによりいったんは承認されたことの根拠は、専ら、「極真会館、国際空手道連盟のGの後継者をFと定める。世界各国、日本国内の本部直轄道場責任者、各支部長、各分支部長は、これに賛同し、協力すること。」、すなわち、被告を極真会館の2代目館長にする旨のGの遺言(本件危急時遺言)の存在であり、それ以外には、Gが被告を極真会館の後継者にするとの意思を表明したものとして極真会館の関係者から認められるようなものは存在せず、それ故に、本件危急時遺言の確認の審判申立てが東京家庭裁判所で却下された後、極真会館は、大きく3派に分裂したものと認められる。したがって、上記審判申立てが東京家庭裁判所で却下され、同決定に対する抗告が東京高等裁判所で棄却され、 更に特別抗告が最高裁判所で却下され、本件危急時遺言がGの遺言としての効力を有しないことが確定した以上、被告は、少なくともGが生前率いていた「極真会館」に属する者に対しては、自己がGの後継「館長」であることを主張し得る根拠を失ったというべきである。 ウ これに対し、被告は、本件危急時遺言の効力が裁判所において否定されても、被告を極真会館の2代目館長とすることがGの遺志であることは諸般の事情から認められると主張するので、以下検討する。 (ア) 被告は、Gが生前に極真会館の後継者について述べていた条件(全日本チャンピオンや世界チャンピオンになること、百人組手を完遂すること、若いことなど)からすれば、Gは被告を後継者とする意思を有していたと主張し、Gがそのような条件を述べていた旨記載された雑誌「極真空手 Vol.2」(平成7年10月20日発行)掲載のインタビュー記事(乙4)が存在する。 しかし、この記事は、その内容からすると、本件危急時遺言の証人らが、G死後支部長らが館長としての被告を批判したため極真会館が混乱した時期に受けたインタビュー記事であり、この記事の掲載された雑誌の号は、被告及びF派の協力によって発行されているものである(乙4)。したがって、この記事をもって、Gが真実生前から後継者の条件を述べていたことを認めることはできない。一方で、「G総裁緊急追悼号」と銘打った雑誌「ゴング格闘技」平成6年6月号(乙3)には、G自身に対して行った生前のインタビュー記事が掲載されているが、その中で、Gは自分の弟子たちについて語り、被告の強さを認めているものの、被告を後継者にする旨あるいは後継者の条件については述べていない。その他、Gが後継者について被告の指摘するような条件を明確に課していたことを認定するに足りる証拠はない。Kの陳述書(乙5)には、Gは常々「極真会館を継ぐ人間は若くなくてはいけない。そして、最強を追い求めてきた極真空手である以上、圧倒的に強い人間でないといけない。敢えていえば、世界チャンピオンになった人間である。 百人組手を達成した者であればいうことはない。」と言っていたとの記載があるが、この陳述内容によっても、Gが後継者の条件を明確に定めていたとまではいえない。 したがって、Gが、生前被告の主張する条件を後継者の条件とし、この条件に合致する被告を後継者とすることがGの遺志であったと断定することはできない。 (イ) 被告は、Gが極真会館を去ろうとする被告を引き留めたこと、被告が極真会館に戻った後には本部の分館という意味で本部直轄の道場でGの傍らに置かれたこと、被告は極真会館において重要な職務を務めていたこと、これらの事情は被告以外の者には存在しないことをを根拠として、Gが被告を後継者とする意思を有していたと主張する。 しかし、これらの事実は、被告を道場指導者として、空手演武の名代として、あるいは新会館建設委員長として適任であるとGが判断したことを裏付けるにすぎず、必ずしも、平成6年時点で、被告を極真会館の次期館長とする意思を有していたことを裏付けるものということはできない。 (ウ) 被告は、Gが生前被告を後継者とする旨述べていたことを、Gの側近等が聞いていると主張する。 a G生前の極真会館事務局の一員としてGの身の回りの世話をし、同人の入院中もその側に居続けたLは、その陳述書において、Gが再入院した平成6年4月15日から死亡(同月26日)までの間に、病室において、Gから直接2回、被告を2代目館長とする旨の発言を聞いたと述べ(乙9、10)、さらに、Lの極真カラテ手帳(乙11)には、平成6年4月20日の欄にその旨の記載がある。 しかし、上記手帳(乙11)には、Gが入院した平成6年4月15日の欄に「総裁入院する」という記載があり、同月20日の欄に「F先輩2代目総裁協力するように」等の記載があるほかは、Gの入院中である同月16日から19日、23日、24日の欄はすべて空欄となっており、記載部分が果たしてその当時作成されたものかどうか疑問がある。また、Gが、後継者を被告とするというような重要事項を、見舞いに訪れた極真会館組織内で重要な地位にある者に対して告げた上で、その言葉を文書にとどめるよう述べたという事実はうかがわれないのに、 身の回りの世話をするにすぎないLに対して後継者を被告とする旨述べた上でそれを「メモするように」と述べたというのは不自然である。そして、その他Lの陳述等を裏付けるに足りる証拠はないから、Lの陳述書(乙9、乙10)及びLの極真カラテ手帳(乙11)にある、GがLに対し、被告を2代目館長にするとの発言をしたとの内容はにわかに措信し難い。 b Kの陳述書(乙5)には、Gが死亡する直前、Kと被告がネパール遠征に行く前日に見舞いに言った際、Gが「Fが私の名代だからな。」と繰り返し話し、Kが、Gは2代目館長を被告に決めていると感じたと記載されている部分があるが、上記陳述は、Gの病床における発言を聞いた時のKの感想を述べるものにすぎず、Kが極真会館の古参の幹部の一人であり、Gと近い関係にあったことを考慮しても、これをもって、Gが、生前に極真会館館長の地位を被告に承継させることを明言したものとはいえない。 c また、Jの陳述書(乙6)及びNの陳述書(乙8)中の被告の極真会館館長としての正当性について述べる部分は、被告が後継館長にふさわしいという、同人らの意見を表明するものにすぎず、いずれも、Gが生前に被告を後継者に指名したことを証するものではない。 d Mの陳述書(乙7)には、Mは、Gが死亡する5日程前、同人から、第2次新会館建設委員会のメンバーとして、被告を筆頭とする数名の氏名が記載された紙を渡され、「君もいろいろ不満はあるだろうが、Fを中心にやっていく。何とか見守ってやってくれ。」と言われ、「分かりました。何の不服もありません。」と答えたという部分、Mは、これを聞いて、これからはすべて被告中心となり、Gはゆくゆくは被告に自分の跡を継がせるのだと思ったという部分がある。 しかし、Mの陳述書に記載されたGの発言自体は、後継館長に関するものではなく、会館建設に関するものであり、後継館長に関する部分はMの推測であることによれば、Mの上記陳述をもって、Gが生前に極真会館館長の地位を被告に承継させることを明言したものとはいえない。 e Oのインタビュー記事には、Gが、Jに対して「第2次建設委員長をFにしたから応援してやってくれよ。」、Mに対して「Fを中心にするから後は頼むよ。組織は和合が大切なんだよ。」と述べたとの記載がある(乙4)。しかし、これらは後継館長に関する発言ではなく、会館建設に関する発言にすぎない。 f 以上からすれば、Gが、生前、被告を極真会館の後継館長とする旨側近等に明言していたとは認められない。 (エ) 被告は、本件危急時遺言は形式的不備があったので有効性が確認されなかったにすぎず、本件危急時遺言の確認が裁判所で認められなかった事実は、 Gが極真会館の館長を継がせる意思を有していたことを否定するものではない、と主張する。 確かに、東京家庭裁判所の審判(甲4)には、本件危急時遺言確認の審判申立てを却下した理由として、遺贈を受けた財団法人や株式会社の理事や代表者代表取締役であるOが5人の証人のうちの1人として立ち会ったことの問題点(同人には証人欠格事由があること)を指摘する部分はあるが、上記ア(オ)のとおり、本件危急時遺言は、作成の経緯等からみて、遺言者の真意に出たものと認めることが困難であるという理由(Oを除いても、欠格事由のない証人が4人立ち会っているから、民法976条の定める方式は充足する。)により却下されたものであるから、後継館長の指名に関する部分についても、他にこの部分がGの真意に出たものであることを裏付ける証拠がない限り、遺言者であるGの生前の意思に基づくものとみることはできない。 エ 被告は、平成7年4月5日に行われた支部長会議には被告を解任する権限はないから、原告らは一方的に被告を解任する旨述べて極真会館から脱退したにすぎないと主張する。 しかし、平成7年4月5日に開かれた支部長会議が極真会館館長の解任決議をなし得る権限を有しないとしても、そもそも、被告の館長就任自体が、本件危急時遺言が有効なものとの前提の下に、平成6年5月10日に開催された支部長会議で承認されたものである。そのような館長就任の手続は、予め極真会館において定められていたわけでもなかったのであり、本件危急時遺言がGの遺言としての効力を裁判所で否定された以上、被告が、上記支部長会議における解任決議の法的効力を云々することは失当というべきである。 オ 被告は、F派がGの率いていた極真会館と同一組織であるから、F派を離脱した者は極真会館を離脱した者であると主張する。 しかし、上記ア(ケ)のとおり、F派以外の派でも本部・支部・道場制あるいはこれに類する組織構造を採っていること、G存命中と同一名称にて各種大会を開催していること、G存命中の極真会館において使用されていた各種証書等と同様の体裁を有するものを使用していることなどからすれば、F派を離脱した者が即極真会館を離脱した者であるということはできず、その他被告の主張を裏付けるに足りる証拠はない。 カ 以上によれば、Gの死後、同人が率いていた極真会館は複数の会派に分裂したものとみるのが相当であり、被告が館長を承継した極真会館から原告らが離脱したということはできない。 (2) 争点(1)イ(極真会館がいくつかの会派に分裂したにすぎない場合、本件商標権者たる被告が、極真会館に属していた者に、本件商標を使用することの差止めを求めることは権利濫用となるか)について ア 証拠(甲7、24ないし、26、39、68、乙11、19ないし24、26、27、37ないし41、79、82、83、85ないし87、90ないし92、原告B、原告D及び被告各本人)によれば、次の事実が認められる。 (ア) 支部について Gは、昭和39年に極真会館を創設した後、極真空手の指導をするにふさわしいと思われる者に対し、指定した地域において空手指導を行うよう命じ、 これを極真会館の支部としていった。 そして、遅くとも昭和48年(証拠上、支部に関する規約の存在が認められる年)には、活動の中心を総本部とし、各地における活動はG(手続的には総本部)から認可を受けた支部によって行うという組織運営(支部制)が確立し、 「支部規約」(昭和51年当時(乙21)、昭和52年当時(乙22)、昭和54年当時(乙23)、昭和57年当時(乙20)、昭和63年当時(乙24))、 「国内支部設立契約書」(昭和48年当時(乙19))、「国内支部規約書」(平成4年、5年当時(乙91、92))などの形で明文化して公表されていった。これらの支部規約等は、年毎に若干の変遷はあるものの、支部あるいは支部長に関しては、①支部として加入する際に認可料を本部に支払うこと、②年会費を支部単位で本部に支払うこと、③昇段者登録料等を支部単位で本部に支払うこと、④本部で行われる支部長会議等に出席すること、⑤本部主催で行われるオープントーナメント全日本空手道選手権大会等の大会に選手を送り、大会遂行に協力すること、などが義務付けられ、これらの規約等に違反した場合には、支部認可の取消し、除名処分等を行うことが規定されていたほか、支部長の地位の譲渡・転貸は禁じられ、その交代は新たな支部長としての認可によって行われることとされていた。そして、 昭和52年には、すべての支部長について一斉に支部長認可証を交付する手続を行い(乙26、27)、以後、支部長の認可は支部長認可証の交付を伴うこととされ、またその地理的範囲は支部長認可証に明記されることとなった。 支部長の認可に当たっては、1領域に1支部長とすることを原則とし、同一地域内に複数の支部長が競合しないような仕組み(テリトリー制)になっていた。ただし、例外的に、全日本チャンピオン、世界チャンピオンは、自分の好む場所に道場を出すことができることとされており、その限りにおいて競合することがあり得た。 もっとも、このような支部制・テリトリー制といった制度の導入や支部規約等の制定により極真会館の組織は整備されていったものの、極真会館は、極真空手の創始者であるGが一代で築き上げた組織であり、多分に、同人のカリスマ性に依拠して運営されてきたものであったため、支部長に誰を当てるかといったことや、組織の運営については、Gの意思に係る部分が大きく、最終的には、すべてGの意思決定によって運営されていた。 (イ) 分支部について 支部長は、分支部を設けることが認められていた。支部長は、事前にその設置を本部に対して申請する必要はあったものの(乙20、23、24等)、 分支部長の任命・解任、分支部長の権限の範囲、経営方法(支部との関係において独立採算制か給料制か等)等についてはその判断に委ねられていた。分支部が設置された場合には、その責任者として分支部長等が置かれ、空手の教授等は当該分支部長等の責任においてなされていた。以上の点は、当然にGの了承下にあった。 ただし、分支部は、上記(ア)の①ないし③、⑤に関しては支部を通じて行うことを原則とし、また、上記(ア)の①ないし⑤の支部長の義務を分支部長は負わなかった。 (ウ) 標章等に関する取扱いについて 昭和52年の支部規約(乙22)や平成6年の国内支部規約書(乙11)には、「支部は、既に登録してある極真のマーク(カンク、連盟マーク、胸章等)を委員会の承認なしに無断で使用できない。」といった規定が存在する。ただし、当時、極真会館に関する標章の登録はいまだなされていなかった。 また、昭和54年の支部規約(乙23)、昭和57年の支部規約(乙20)、昭和63年の支部規約(乙24)には、「支部長の禁止事項」の一つとして、「極真マーク等の無断使用及び付属物一切の販売」という規定があった。ただし、極真会館の活動趣旨に添う限り、極真会館の支部長は、道場や各種大会等において本件商標を自由に使用することができたし、分支部長も、支部長の個別の許可等なくして、道場において本件商標を自由に使用することができた。総本部において、極真マーク(本件商標等)の使用態様等を明確に規制していたことをうかがわせるに足りる証拠はない。 さらに、Gは、存命中、本件商標の商標登録を出願しなかったが、この点について、G著「極真カラテ21世紀への道」[平成4年1月31日初刷](甲68)には、「他の組織が無断で使用しない限り、IKO(国際空手道連盟の略称)傘下にある極真会館支部道場がこれを使用するのは自由であり、支部を認可するに際しての手続きさえしっかりしていれば、“マークの使用”について総本部は何らこれについて規制を加えるようなことはない。」との記載がある。 (エ) 被告による商標登録出願について 被告は、前記のとおり、Gの死後、極真会館の支部長会議において館長への就任がいったんは承認されるとともに、本件商標につき、自己名義で商標登録出願をし、登録を得ているが、このことにつき、被告自身は、法人格のない極真会館の後継者にGの遺志を継いで就任したので、責任上、被告の名義で出願した旨述べている(甲7)。 イ そこで、上記ア認定事実を踏まえ、本件商標の商標権者である被告が、 G生前の極真会館に属していた者に対して本件商標権を行使することが権利濫用となるかについて、検討する。 (ア) 商標は、自分の商品と他人の商品、自分の役務と他人の役務を区別するために、事業者が商品又は役務につける標章である。しかるところ、複数の事業者から構成されるグループが特定の役務を表す主体として需要者の間で認識されている場合、その中の特定の者が、当該表示の独占的な表示主体であるといえるためには、需要者に対する関係又はグループ内部における関係において、その表示の周知性・著名性の獲得がほとんどその特定の者に集中して帰属しており、グループ内の他の者は、その者からの使用許諾を得て初めて当該表示を使用できるという関係にあることを要するものと解される。そして、そのような関係が認められない場合には、グループ内の者が商標権を取得したとしても、グループ内の他の者に対して当該表示の独占的な表示主体として商標権に基づく権利行使を行うことは、権利濫用になるというべきである。 (イ) 上記(1)ア(ア)のとおり、本件商標は、Gが死亡した平成6年4月26日時点(本件商標登録出願前)において、G「総裁」、「館長」が率いる「極真会館」という団体を表すものとして、空手及びその他の格闘技に興味を有する者(需要者)の間では広く知られるところとなっていたが、このような本件商標の周知性・著名性は、Gというカリスマ性を有する人物の存在と、G存命中の極真会館に属する各構成員による、極真会館の名称下での、長年にわたる道場での極真空手の教授や地方大会の開催等の活動によってもたらされたものといえる。 したがって、Gの生前、本件商標は商標登録出願されることがなく、 また、極真会館は法人化されていなかったものであるが、本件商標につき、商標権者たるべき者は、(生前の)G又は(法人化した後の)極真会館を措いて他には考えられない。 しかるところ、本件商標の周知性・著名性の獲得が集中していたともいい得るGは、その存命中、極真会館の構成員が本件商標を使用することについて特段の制限を設けなかった。また、Gから任命された支部長や、更に支部長によって任命された分支部長が道場での極真空手の教授等の極真会館の活動を行うに際して、本件商標を使用することは当然のこととされていた。 G死亡後も、本件商標はあくまでG率いる極真会館を表すものとして需要者の間で広く知られており、その周知性・著名性の獲得にはG存命中の極真会館に属する各構成員の貢献も寄与していたという状況に何ら変わりはなかった。したがって、被告は、本件危急時遺言の存在によって初めてグループ内において独占的な表示主体となることが承認されていたと考えられるところ、前記(1)ア(オ)のとおり、本件危急時遺言の確認審判申立てが却下されGの遺言としての効力を有しないことが確定した以上、少なくとも、現時点において、被告は、グループ内部の者(G存命中の「極真会館」において、同人の承認の下に本件商標を用いて空手の教授、空手大会の興行等を行っていた者)に対しては、Gの後継館長であることを主張し得る根拠を失ったというべきである。 以上によれば、被告が前記のように、極真会館の後継者であることの根拠が存在しない以上、被告は、対外的(極真会館の外部の者に対する関係)にはともかくとして、極真会館内部の構成員に対する関係では、自己が商標登録を取得して、商標権者として行動できる正当な根拠はないのである。被告が、被告個人を商標権者として商標登録した本件商標権に基づき、生前のGから承認を得て、本件商標を用いた空手の教授、空手大会の興行等を行った極真会館の構成員に対して、 本件商標の使用の差止めを求めることは、権利濫用に当たるというべきである。 なお、上記(1)ア(ク)及び(ケ)のとおり、現在存する会派の中ではF派に属する支部長が数の上では比較的多数を占めていること、F派では、Gの生前と同様の、総本部の構成・機能、支部・道場の編成、各種選手権大会開催、内弟子制度、各種証書・備品等の取引関係、関連雑誌の発行等が継続していることが認められる。しかし、このことは、被告が本件商標に関する独占的表示主体と認められないという前記判断を左右するものではない。 (ウ)a この点につき、被告は、極真会館における空手活動は、極真会館総本部とGないし総本部から認可を受けた支部において行われてきたものであり、 各地における活動は総本部から承認を受けた支部によって一定の地理的範囲内で行うという、極真会館の組織運営の大原則が昭和48年には確立されていたから、総本部以外で本件商標を使用できるのは、Gないし総本部から認可を得、支部長認可証の交付を受けた支部長が、その地理的範囲内で道場を開設して行う場合だけである旨主張する。 b なるほど、極真会館が組織的に拡大することに伴い、活動の中心を総本部とし、Gないし総本部から支部長認可証の交付を受けた支部長が、支部長認可証にも記載される地理的範囲(テリトリー)で活動を行うことが原則となっていたことは、前記ア(ア)で認定したとおりである。原告Bも、本人尋問において、1領域1支部長とする制度をGが採ってきた旨明言し、さらに、自らも支部の存在しなかった岐阜県に道場を開設した後岐阜支部が設置されたときには、同支部の支部長に道場を譲った旨供述している。したがって、原告らにおいても、G存命中に整備されていた支部長制やテリトリー制を受け入れ、これを前提として活動していたということができ、これらの制度の存在及び運用を否定することはできない。 しかしながら、支部長制度やテリトリー制度が存在したことをもって、Gが、支部長以外の者が極真会館の活動の趣旨に添って本件商標の使用をすることまで制限していたということはできない。しかも、前記ア(ア)及び(ウ)記載のとおり、G存命中の極真会館は、制度こそ整備されていたものの、運営の最終的な決定権限はGに集中していたものである。したがって、Gの生前、その承認の下に道場を開設し、極真空手の教授等の活動を行っていた者は、必ずしも支部長でなくとも、極真会館や本件商標の周知性の獲得に貢献したものというべきであり、このような者に対し被告が本件商標権を行使することも権利の濫用に当たるというべきである。 (3) 争点(1)ウ(原告らの個別事情)について ア 原告らの個別事情について、検討する。 (ア) 原告Aについて 証拠(甲9、22、23、27ないし31、50、66、67、乙7、13ないし16、20、29、106、原告A本人)によれば、次の事実が認められる。 a 原告Aは、もともと他流派で空手を行い、有段者で流派の役員もしていたが、昭和53年に開設された関西本部(Gの直轄道場であり、本部直轄大阪道場ともいう。)の責任者Tに請われて、昭和54年4月極真会館に入門した。当時、極真空手は、関西においてさほど勢力はなかった。 b 原告Aは、昭和55年ころ、Gから相談役として関西本部を支えて欲しいと言われ、これを受諾した。なお、総本部の相談役には、衆議院議員、大学理事長、会社社長等が就くこともあり、また、支部の相談役には支部長の個人的関係から支部の運営を支援するにすぎない者も存在する。 昭和55年、関西本部にGの娘婿Uが派遣され、Tが関西地区総監に任命された後は、Uが関西本部の責任者となった。極真会館では、関西本部において支部長と同等の立場にあるのは関西本部責任者であるUであると認識されていた。原告Aは、引き続き関西本部相談役として、渉外事務等の実務を中心になって行い、Uを支え続けた。 c 原告Aは、G存命中に大阪で開催された全日本ウエイト制選手権大会では、大会運営副委員長を務めたこともある。 d 原告Aは、昭和62年に、大阪市東成区に自ら「みどり橋道場」を開設して空手の指導を行うようになり、平成3年4月に3段を認可された。 e 原告Aは、Gの存命中、支部長として認可されたことはなかった。 また、全日本ウエイト制空手選手権大会の報告を兼ねて大阪で開催される支部長会議には出席していたが、東京で行われる支部長会議に出席したことはなかった。もっとも、原告Aは、Gに個人的に 信頼されており、平成5年には、Gから、Uはそろそろ東京に戻し、関西本部の責任者を原告Aにする趣旨の話をされていた。また、Gが死亡する前日の平成6年4月25日に、Uと共にGを病室に見舞って話をしている。 f Gが死亡した後、原告Aは、Uと話し合い、Gの遺志を受けて、自らが関西本部を継ぐことにした。 原告Aは、平成6年9月13日、被告と会合した際、当時の関西本部の建物の所有者から被告を応援して欲しいと要望されたが、これを断り、関西本部の建物から退去し、みどり橋道場に移って、極真会館関西総本部の名称を名乗るようになった。 その後、原告Aは次々道場を開設し、近畿一円において30数か所の支部道場を結成し、1000人を超える道場生を指導している。 原告Aは、極真会館分裂当初は独立の立場をとっていたが、その後全日本極真連合会に常任理事として参加し、月額2万円を同連合会に納付している。 (イ) 前記認定事実によれば、Gは、空手の経験等のある原告Aに、極真会館関西本部の責任者を支えて欲しい旨依頼しており、大阪で開催された全日本ウエイト制選手権大会への関与についても了承し、支部長としての認可を与えてはいないものの、みどり橋道場の開設もGの了承があったものと推認される。したがって、Gは、その存命中、原告Aに、本件商標を使用して空手の教授や空手大会の興行等を行うことの承認をしていたものと認めることができる。 (ウ)a 被告は、関西本部相談役という立場は、関西本部の責任者の裁量で認められた立場にすぎず、大会の開催や道場の開設を行い得る立場にはないと主張し、あるいは全日本ウエイト制空手道選手権大会における大会運営副委員長としての地位は、大会運営に関わる現場のスタッフの監督的地位にすぎないと主張し、 原告A自身、Gの許可なくして自ら大会の開催や道場の開設を行うことはできない旨述べている。 確かに、総本部の相談役に、大会の開催や道場の運営とは無関係と思われる人物が就いていることが認められる。また、大会運営副委員長が行うことは、大会運営における実務上の事柄であろうことは推認される。しかしながら、原告Aが、G存命中の昭和62年よりみどり橋道場を開設して極真空手を教授していたことが認められ、その際に本件商標を使用していたであろうことも推認でき、かつ、Gが原告Aの道場開設や極真空手の教授、あるいは本件商標の使用を、禁止したり制限したりしたことは証拠上うかがえないから、原告Aもまた、Gの生前、その承認の下に道場を開設し、極真空手の教授等の活動を行っていた者であるということができる。 b 被告は、原告Aが、現在、G存命中に関西本部が開くことのできなかった場所に道場を開設していることをもって、そのような者に権利濫用を主張させる必要性はないと主張する。 しかしながら、被告の指摘は、極真会館が分裂状態になった後のことであって、同原告がGの存命中、極真会館内部にあって、空手の道場の営業主体として本件商標を使用していた事実を左右するものではないことはもとより、被告による本件商標権の行使が権利の濫用であることの判断を左右する事情にもならないものというべきである。 イ 原告Bについて (ア) 証拠(甲24、32、33、50、53、58、61、乙20ないし24、26、32,34、49、50、原告B本人)によれば、次の事実が認められる。 a 原告Bは、昭和42年に極真会館に入門し、昭和44年9月に開催された第1回オープントーナメント全日本空手道選手権大会で3位に入賞し、翌年の第2回オープントーナメント全日本空手道選手権大会で優勝した後、Gの認可を得て、昭和46年1月、郷里徳島県に徳島支部を開設した。当時は、まだ極真会館の支部長は数人しかいない時代であった。また、昭和52年10月1日には、Gから認可を得て、名古屋市に愛知支部を開設した。なお、原告Bは、昭和52年に支部長認可証の交付を受けている。 b 原告Bは、その後も支部長として空手指導等を行っていたが、平成7年4月5日の支部長会議において、被告の館長解任動議に賛成し、その後支部長協議会派に属していた。原告Bは、支部長協議会派においても、愛知と徳島の支部長として、空手指導等を行っていた。 c 原告Bは、その後支部長協議会派の主張内容に疑問を感じ、同会派を脱退し、現在全日本極真連合会に属し常任理事となり、引き続き、愛知と徳島において合計17道場を開設して空手指導を行っている。そして、全日本極真連合会に月額1万円を納付している。 (イ) 前記認定事実からすれば、原告Bは、Gから支部長として正式に認可された者として、本件商標を使用して空手の教授や空手大会の興行等をすることを承認されていたということができる。 (ウ) 被告は、これまでも極真会館を離脱したり、除名されたりした者は、たとえ従前は支部長たる地位にあっても、本件商標等の標章を使用することはなく、新しい標章の下に独自の活動を展開してきているところ、原告Bが同組織を離脱したにもかかわらず、「極真会館」や「国際空手道連盟」など、組織の存在を前提とする呼称を使用するのは、まさに被告が館長を務める極真会館の名声にフリーライドしようとする意図があることが明白である旨主張する。 しかしながら、被告が主張するように、G自身によって極真会館を除名され、または自ら離脱した者が、その後本件商標等を使用しないことは当然である。これに対し、原告Bは、Gによって極真会館を除名されたり、自ら離脱したわけではなく、また昭和46年以降、Gにより本件商標の使用許諾を否定されたことはないのである。また、極真会館がGの死後複数の会派に分裂した状況下においては、F派に属さない原告Bが、F派に対し、従前の支部長としての義務を果たさないことはむしろ当然であって、これをもって前記認定が覆るものではない。 ウ 原告Cについて (ア) 証拠(甲33ないし36、50、54、55、59、67、乙14、21、26ないし30、80、81、99ないし102、103の1及び2、 乙104、105、原告C本人)によれば、次の事実が認められる。 a 原告Cは、少年時の昭和41年ころ一度極真会館に入門し、その後16歳の昭和46年ころ再度極真会館本部に入門した。 b 原告Cはその後東北歯科大学に入学し、空手部で副将の立場にあったが、昭和50年9月、Gより宮城支部長のc(仙台放送勤務)を助けるためという理由で仙台支部長を任命され、東北歯科大学内の道場にて空手指導をしたほか、 仙台においても空手の指導を行うようになった。しかし、昭和51年に仙台支部長はdとされた結果(その地理的範囲は宮城県内とされた。)、原告Cは仙台支部長の任を解かれ、さらに昭和52年には国家試験受験の準備等を行う必要があったため、空手活動自体を中止した。なお、昭和50年当時、原告Cは初段位にあった。 国際空手連盟及び極真会館等が昭和50年10月に発行した第1回オープントーナメント全世界空手道選手権大会のプログラム(甲33)中の「日本各地区支部長一覧」と題する頁には、原告Cの氏名が仙台支部長として顔写真と共に記載されており、昭和51年の極真会館世界勢力図カレンダー(甲34)にも、原告Cの氏名と顔写真が掲載されている。 c 原告Cは、その後昭和63年ころから、空手指導を再開した。その際、支部長として認可状の交付を受けた事実は認められないが、Gから、神奈川県小田原市近辺で支部長をやるようにとの指示を直接受けて、始めたものであった。 原告Cは、歯科医師をしながらボランティアで空手の指導をしている。 d 原告Cは、現在、神奈川県下において、南足柄市体育協会所属道場、山北町体育協会所属道場、足柄上郡大井町道場、横浜市港南台道場(原告Eと共同開設)、相模原市橋本道場(原告Dと共同開設)を開設し、約220名の道場生に空手を教授している。 e 原告Cは、極真会館分裂後はしばらくの間独立の立場をとっていたが、医療法人極真会を作りその理事となったり、極真会館最高顧問の名称を名乗ったりしており、また、現在は全日本極真連合会の副理事長の地位にある。 なお、原告Cは、空手活動再開後の平成5年3月当時2段位であった。 (イ) 前記認定事実によれば、原告Cが昭和50年に一度支部長として認可され、その後いったんは支部長を辞めたが、再び、昭和63年ころにGから直接支部長になることを指示され、空手の教授を行ってきたものである。原告Cが支部長の認可状の交付を受けていないことは、同原告がGの承諾の下に道場を開設して極真空手の指導を行ってきたことを否定するものではない。 (ウ)a 被告は、原告Cは、昭和50年当時支部長認可を受けていないと主張し、当時原告Cが支部長をしていたとの認識はないとする極真会館関係者の陳述書(乙28ないし30)がある。 しかしながら、上記(ア)bのとおり、昭和51年度の極真会館世界勢力図カレンダーには明確に原告Cが仙台支部長である旨明記されている(これがGの意思に反してなされたとは考え難い。)。そして、上記(2)ア(ア)のとおり、極真会館においてはGの一存による支部長の認可があり得たことからすれば、原告Cが宮城支部長が存在するにもかかわらず仙台支部長とされていることをもって、上記認定が左右されるものではない。 b 被告は、原告Cが、昭和63年に神奈川県北支部長に任命されたことはないと主張するところ、確かに、支部認可証のような任命の事実を客観的に裏付ける証拠はない。 しかしながら、原告Cは、昭和63年以降、ボランティアと称して神奈川県にて極真空手の教授等を行っており、しかも、当時神奈川県には極真会館の支部が東西に分かれて存在したにもかかわらず、極真会館側が原告Cに対して極真空手の教授をやめるよう指示した事実が認められないことからすれば、原告Cもまた、Gの承諾の下に道場を開設して極真空手の指導を行ってきた者というべきである。 c 被告は、原告Cが、G存命中に行っていた活動範囲を超え、広範囲に極真空手の道場を開設していることや、ボランティア活動を行っていることを指摘し、このような行為はGの築いた秩序を乱すものであるから、権利濫用の主張をさせる必要性はないと主張する。 しかしながら、原告Cのボランティア的な極真空手の教授は、Gに了承されていたというべきであるし、原告Cの現在の活動範囲は、極真会館が分裂状態になった後のことであるから、被告による本件商標権の行使が権利の濫用であることの判断を左右する事情にもならないものというべきである。 エ 原告Dについて (ア) 証拠(甲25、26、37ないし40、46、47、50、56、 69、乙32、37、39、41、82ないし84、原告D本人)によれば、次の事実が認められる。 a 原告Dは、昭和50年極真会館山梨支部に入門し、昭和54年に東京都下城西支部に移籍し、昭和55年6月、初段となって指導員として稽古するかたわら、選手として各種大会を目指すようになった。 b 城西支部の支部長であったVは、昭和52年にGから支部長認可を受け、東京都渋谷区参宮橋に道場を開設したのを皮切りに、東京都世田谷区代田橋等次々と道場を開設していった。 原告Dが城西支部に移籍したころ、同支部は優秀な選手を多数輩出し、実力ある選手・指導員が増えていた。Vは、昭和58年ころから、城西支部に分支部を作って道場を信頼のある弟子に任せることにし、当時の弟子である原告Dのほか、e、f、g、h、iらを分支部長とし、原告Dには町田道場を、fには三軒茶屋道場を、gには昭島道場をそれぞれ任せた。Vはその後も適当と考える者を分支部長として道場経営を行わせていた。 Vは、城西支部と分支部の間において、分支部会費を支払うこと及び昇級審査会費の半分を城西支部に支払うことを内容とする契約を締結し、分支部の運営については独立採算制を採ることと定めていた。 分支部の開設については総本部に対して分支部認可料を支払わなければならないが、Vが支部長として支払うほか、分支部長もこれを支払った。 城西支部では、入会申込書は支部長宛とされていた。 支部では、各種大会において選手を参加させなければならなかった。Vは、当初は分支部からの参加申込みをまとめて総本部に対して提出していたが、その後、直接総本部に対して申し込むように分支部長に指示した。 分支部長が新たに道場を開設したいと考えたときには、分支部長は支部長であるVの許可を得ねばならず、許可を得ないまま道場を開設した分支部長に対して、Vが注意したことがあった。また、分支部長を任命した後の言動が問題となったときには、Vが、独自の判断で、分支部長を解任した。 c 原告Dは、町田道場に次いで、Vの経営していた代田橋道場を引き継ぎ、さらにVの許可を得て、千歳鳥山及び狛江の道場を開設した。 原告Dは、道場の開設の広告を出すときは、必ず館長であるGの名と支部長であるVの名を出しており、支部長名なしに広告することはできないと認識していた。また、原告Dは、本件商標の使用については、Vの使用できる範囲内で使用可能であると認識していた。 原告Dは、支部長協議会等に出席したことはなく、その権限もなかった。 なお、原告Dは、平成5年6月、4段位となった。 d 原告Dは、支部長間で被告を解任する話が取り交わされていたときは、Vと共に被告についていくことを考えたが、結局被告の言動に疑問を抱くに至り、平成7年4月5日の支部長会議において被告解任動議が決議された後、Vの下を離れ、支部長協議会派に属し、支部長に任命された。平成12年からは単体道場として活動していたが、その後全日本極真連合会に参加し、常任理事となり、月額2万円を全日本極真連合会に納付している。 なお、原告Dは、平成12年に神奈川県相模原市に橋本道場を、平成13年には神奈川県川崎市に百合ヶ丘道場を開設し、支部長として道場経営を行っているが、この2道場については従前のVの地理的範囲外であった。 (イ) 前記認定事実からすれば、原告Dは、GがVに対して本件商標の使用を許可した範囲内において、Vの承諾を得て、独立採算制により、道場の経営主体として本件商標を使用していたものであるが、これは、当然に、Gの了承の下に本件商標を使用して、空手の教授等を行ってきたものということができる。 (ウ) 被告は、原告Dが、平成7年4月5日の支部長会議における被告の館長解任決議後、自己が属していた支部の支部長の下を離れ、従来の支部の地理的範囲外に道場を開設していること、支部長への会費等の支払を中止したことなどの事実を指摘し、これらは極真会館の分支部長の地位の放棄であり、またGが築いた秩序を乱すものであるから、原告Dに権利濫用の主張をさせる必要性はないと主張する。しかしながら、これらはいずれも極真会館が分裂状態になった後のことであるから、同原告がGの存命中、極真会館内部にあって、空手の道場の営業主体として本件商標を使用していた事実を左右するものではないことはもとより、被告による本件商標権の行使が権利の濫用であることの判断を左右する事情にもならないものというべきである。 オ 原告Eについて (ア) 証拠(甲26、41ないし46、50、57、60、70、乙33、38、40、85ないし87、89、原告E本人)によれば、次の事実が認められる。 a 原告Eは、昭和56年12月極真会館東京城南支部に入会し、昭和61年に初段を取得した。 b 東京城南川崎支部の支部長Wは、昭和53年にGから支部長認可を受け、東京城南川崎支部(地理的範囲は、港区、品川区、神奈川県川崎市)を開設した。その後、蒲田、五反田、恵比寿、学芸大学、旗の台、田町、大井町、自由が丘、武蔵小杉、溝口、川崎に道場を開設したが、蒲田、五反田、恵比寿以外の道場については、Wの弟子を分支部長に任命し、責任者として運営を任せていた。 Wは、分支部長の任命に当たっては、選手の実績、人格、指導・運営能力等を総合的に考慮して決め、また各分支部長が受け持つ道場の数や場所を調整していた。 城南川崎支部では、分支部認可料は支部がすべて負担することとしていた。また、分支部では道場生から月謝を徴収し、道場生一人当たりの一定割合を支部に納める義務があったが、その残りは分支部の取り分とする独立採算制を採っていた。昇段登録料については、分支部において集め、支部でまとめて総本部に支払っていた。 城南川崎支部の分支部における入門者の誓約書は、分支部の道場に入門する場合であっても、W支部長宛とされた。 総本部からの連絡は、必ず城南支部を通して分支部長に伝えられていた。 c 原告Eは、平成3年、Wから分支部長を任命され、田町道場を任せられた。 なお、原告Eは、平成5年6月、2段位となった。 d 平成7年4月5日、Wは、被告の館長解任動議に賛成し、いったんは支部長協議会派に属していたが、その後、F派に属するようになった。原告Eは、Wに従って支部長協議会派に属していたが、WがF派に属するに当たってこれと袂を分かち、支部長協議会派の作った特定非営利活動法人国際空手道連盟極真会館の理事などを務めたが、その後、全日本極真連合会に参加し、理事として、空手の教授等を行い、全日本連合会に月額2万円を納付している。 原告Eは、平成8年4月には東京都品川区に武蔵小山道場を、平成11年3月には東京都葛飾区に新小岩道場を、東京都台東区に三ノ輪道場を開設し、平成13年には東京都墨田区に押上道場を、東京都荒川区に町屋道場(三ノ輪道場の移設)を、平成14年には東京都江戸川区に篠崎道場を、横浜市に港南台道場を、千葉県に八千代道場を開設している。なお、これらの道場のうち、武蔵小山道場以外は、従前のWの地理的範囲外にある。 (イ) 前記認定事実からすれば、原告Eは、GがWに対して本件商標の使用を許可した範囲内において、Wの承諾を得て、道場の経営主体として本件商標を使用していたものであるが、これは、当然、Gの了解の下にあったということができる。また、原告EがW支部長と袂を分かち、従前の同支部長の地理的範囲外にも道場を開設している事実は、極真会館が分裂状態となった後の事実であるから、被告が原告Eに対し本件商標権を行使することが権利濫用であることを否定する事情にはならない。 (4) 以上によれば、被告が、原告らに対して空手の教授等に関して本件商標権に基づく権利を行使することは、権利濫用となるものというべきである。 2 争点(2)(被告の不法行為及び原告らの損害)について (1) 被告は、前記第2、1(7)のとおり、本件商標登録後、NTTに対し、本件商標を使用する原告らの行為は被告の有する本件商標権を侵害するからその広告を掲載してはならない旨申し入れ、被告の申入れを受けたNTTは、原告らが平成13年度版タウンページに広告掲載を申し込んだ際に、広告掲載できない旨の通知を行ったものである。 前記1で検討したとおり、被告が原告らに対し本件商標権を行使して、原告らが空手の教授に関する広告等に本件商標を使用することの差止めを求めるようなことは、権利の濫用として許されない。被告の上記行為は、直接にはNTTに対して原告らによる本件商標を使用した広告の掲載をしないように申し入れたものであるが、実質的には、NTTによるタウンページへの広告の掲載拒否を通じて、原告らに本件商標を使用させないようにしたものであって、原告らに本件商標権に基づいて本件商標の使用を禁止するものに他ならない。したがって、被告の上記行為は、原告らとの関係では権利の濫用であり、違法性があり、また、そのことにつき被告に過失があるものと認めるのが相当である。 (2) 次に、原告らは、被告が、原告らは本件商標を使用できず、「ニセ極真」であると宣伝したと主張し、原告ら作成の陳述書等(甲54、61)や原告ら各本人尋問中にはこれに沿う供述部分がある。 しかしながら、原告らの供述以外に、これを裏付ける証拠はないから、上記の原告らの供述はにわかに採用し難く、原告ら主張のような事実の存在を認めることはできない。(3) さらに、原告らは、被告が、F派の道場を、原告らの道場の近隣に開設し、その際、本件商標を使用したタウンページ広告をしたことも、不法行為として主張している。 しかしながら、本件は、これまで認定したとおり、極真会館が複数の会派に分裂した事案であるから、分裂後にF派が道場を開設することや、本件商標を用いた広告をすることは、ただちに違法となるものではなく、これらの行為を原告らに対する不法行為ということはできない。 (4) そこで、原告らの損害について検討する。 ア 原告らは、タウンページへの広告掲載のための代替措置により多大な支出を余儀なくされたと主張する。 しかし、タウンページへの広告を掲載しないために支出を免れた金額と、 代替措置により支出した金額の比較においていくらの損害が生じたのかを認めるに足りる証拠は提出されていない。 イ 原告らは、それぞれ、タウンページに本件商標を使用した広告が掲載できなくなったことにより、開設している道場の入門者が減少したと主張する。 まず、原告Bについて検討すると、原告B作成の報告書(甲61)及び原告B本人尋問の結果中には、上記主張に沿う部分がある。 しかし、原告Bは、本人尋問において、平成6年が最も入門者が減少したと述べ、また、平成12年ころから生徒数が減少しているが、その理由はタウンページにはない旨供述している。その他、原告Bが、有効期間を平成13年11月以降とするタウンページにおいて本件商標を使用した広告が掲載できなくなったときの生徒数の減少が必ずしも被告側の妨害行為によるものではない旨供述していること、原告Bの道場については、道場生やネット会社によってインターネット上でホームページを開設することによって広告活動が可能となっていること(乙34)、 インターネット上にある「国際空手道連盟極真会館OFFICIAL HOME PAGE」(乙32)と題したホームページ中の「極真会館全国支部・道場案内」において愛知支部の原告Bの道場のホームページにリンクできるようになっていることなどの事情からすれば、原告Bが本件商標を使用した広告をタウンページに掲載できなくなったことと、原告Bが開設している道場の入門者が減少したこととの間に因果関係を認めることはできない。 他の原告らについても、タウンページに本件商標を使用した広告を掲載できなかったことにより開設している道場の入門者が減少したことにつき、原告ら各本人尋問での供述や陳述書等(甲51、54、56、57、64)にはこれに沿う部分もあるが、いずれも客観的な裏付けがなく、採用することができず、他にこれを認めるに足りる証拠はない。 ウ 原告Cは、被告の妨害排除のために余儀なくされた訴訟及びその準備活動のために本業の歯科診療所を休業したことによる損害も主張するが、同原告の主張する上記損害が、被告の不法行為と相当因果関係のある損害であることを認めるに足りる証拠はない。 エ そうすると、結局、原告ら主張の不法行為については、原告らが、それぞれ、本件商標を使用してタウンページへの広告ができなかったことについて、仮処分申立てを行い本件訴訟を提起したことによる弁護士費用相当額のみを、被告の不法行為によって発生した損害と認めることができる。本件事案の内容、仮処分及び訴訟の経過及び結果等に照らせば、その額は仮処分申立事件と本件訴訟を併せて、 原告A、同B及び同Cにつき各50万円、原告D及び同Eにつき各30万円とするのが相当である。 オ なお、原告らは、それぞれ精神的苦痛による慰謝料の請求もしているが、 本件で認め得る被告の不法行為の態様、結果に照らせば、原告らに慰謝料を賠償しなければならないほどの精神的苦痛が生じたとは認め難い。 3 よって、原告らの請求は、被告が、原告らに対し、被告の有する本件商標権に基づき、空手の教授に関する広告、空手の興行の企画・運営又は開催に本件商標を使用すること、及び空手の教授を行うに際して空手着に本件商標を使用することの差止めを求める権利を有しないことを確認すること、並びに、被告が原告A、同B及び同Cに対し各50万円、原告D及び同Eに対し各30万円及び各金員に対する不法行為の後である平成14年2月9日から支払済みまで民法所定の遅延損害金を支払うよう求める限度において理由があるからこれを認容し、その余は失当であるから棄却し、訴訟費用の負担につき、民事訴訟法61条、64条本文を適用して、主文のとおり判決する。 |
| 裁判長裁判官 | 小松一雄 |
|---|---|
| 裁判官 | 中平健 |
| 裁判官 | 大濱寿美 |