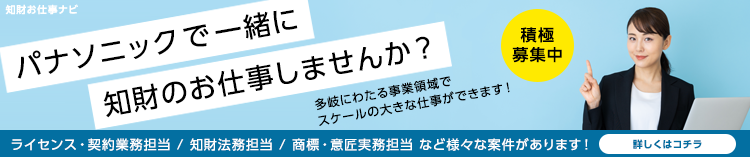| 関連審決 | 審判1997-1261 |
|---|
この判例には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
| 審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
|---|---|---|
| 平成15行ケ174審決取消請求事件 | 判例 | 商標 |
| 平成11行ケ79審決取消請求事件 | 判例 | 商標 |
| 平成13行ケ418審決取消請求事件 | 判例 | 商標 |
| 関連ワード | 識別力 / 役務の提供 / 出所表示機能 / 品質保証機能 / 質保証機能 / 識別機能 / 指定商品 / 記述的商標(3条1項3号) / 3条2項 / 周知性 / 公序良俗(4条1項7号) / ただ乗り(フリーライド) / 取引の実情 / 国内 / 警告 / 差止 / マドリッド / パリ条約 / 国際登録 / 外国 / 継続 / 有名ブランド / |
|---|
| 元本PDF |
裁判所収録の全文PDFを見る
|
|---|---|
| 元本PDF |
裁判所収録の別紙1PDFを見る
|
| 事件 |
平成
11年
(行ケ)
80号
審決取消請求事件
|
|---|---|
|
原告 ルイヴィトン マルチエ 代表者 【A】 訴訟代理人弁護士 高松薫 同 岡本好司 同 鈴木銀治郎 同 中野通明 同 鈴岡正 同 上沼紫野 同 前田則政 訴訟代理人弁理士 【B】 被告 特許庁長官【C】 指定代理人 【D】 同 【E】 |
|
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 判決言渡日 | 2000/08/10 |
| 権利種別 | 商標権 |
| 訴訟類型 | 行政訴訟 |
| 主文 |
特許庁が平成9年審判第1261号事件について平成10年10月23日にした審決を取り消す。 . 訴訟費用は被告の負担とする。 |
| 事実及び理由 | |
|---|---|
|
請求
主文同旨 |
|
|
前提となる事実(争いのない事実)
1 特許庁における手続の経緯 原告は、平成5年11月12日、別紙1の構成からなる商標(以下「本願商標」という。)について、指定商品を商品及び役務の区分第18類の「かばん類、袋物、携帯用化粧道具入れ」として商標登録出願(平成5年商標登録願第113583号)をしたが、平成8年9月27日に拒絶査定を受けたので、平成9年1月27日、拒絶査定不服の審判を請求した。 特許庁は、同請求を平成9年審判第1261号事件として審理した結果、平成10年10月23日に「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、その謄本は同年11月25日に原告に送達された。 2 審決の理由 別紙2の審決の理由の写しのとおり、 (1) 本願商標は、青色の横縞風の模様を正方形に描いてなるところ、その模様が単に連続しているため、単なる地模様と認識され得るものであり、本願商標と酷似又は類似する柄を使用した請求人(原告)以外の者の製造販売に係るバッグ等の商品が認められることから、本願商標を指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、単にその商品の型押し柄の一類型であると認識、理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質(型押し柄)を表示し、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであり、商標法3条1項3号に該当すると認定判断し、 (2) 請求人は、本願商標は同法3条2項の規定によって登録されるべきであると主張しているが、指定商品に本願商標が使用されているのは、いずれも素材として商品の表面全体にわたった自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない単なる地模様の使用であり、商標の使用とは認められないから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるとは認められないと判断した。 |
|
|
原告主張の審決取消事由の要点
審決は、本願商標は商標法3条1項3号に該当し登録することができない旨誤って認定判断し(取消事由1)、また、仮に、同号に該当するとしても、本願商標は、使用をされた結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものであるから、同条2項に該当し、登録することができるものであり(取消事由2)、本件審判請求を成り立たないものとした審決は違法であるから、 取り消されるべきである。 1 取消事由1 (1) 本願商標の特徴、沿革及び自他商品識別力 本願商標は、正方形の中に青色(トレド・ブルー)を用いて麦の穂を図案化したものであり、原告の独創に係る図形商標である。 すなわち、本願商標は、正方形の中に、山と谷で形作られた特殊な態様と、その特殊な態様である山と谷に濃淡によってコントラストを持たせた(濃い色の谷の中に明るい色を配した)特殊な図形であり、この「エピ・マーク」、「エピ・ライン」ないし「エピ・レザー・ライン」と呼ばれる本願商標は、もともとフランス語で「麦の穂」を意味する「epi」の言葉をネーミングに付けたことからも分かるように、麦の穂が風にたなびく様子をイメージした図柄をベースに、原告が1986年(昭和61年)に創作した新しい商品ラインの表示である(甲第9号証の1)。 このエピ・マークが原告によって初めて創作されて使用されたのは、1926年(昭和元年)であり、フランスで、原告がインドのバローダ王のために作製した「ティーケース」と呼ばれたピクニック・ケースにおいてであった。その後、「ティーケース」が評判になったため、エピ・マークは、顧客からの特別な注文に基づいて原告が製造、販売した旅行鞄等の製品に使用されてきた。そして、原告は、1986年(昭和61年)に、このティーケースに使用されたエピマークを一般顧客向けに復活させた「エピ・レザー」を使用した旅行鞄、ショルダーバッグ、財布等の小物を発売した。発売当初の1986年には、トレド・ブルー(甲第13号証の本願商標)、ボルネオ・グリーン、クリール・ブラック、ケニアン・ブラウンと呼ばれる4色の製品が発売された。続いて、1987年にカスティリアン・レッド、1980年にジパング・ゴールド、1993年にはタッシリ・イエローがさらに加わった(甲第35号証)。 このエピ・マークを表示している原告のエピ・ラインの商品においては、素材の皮革が丹念に鞣された後深く染色され、表面に「麦の穂」を思わせるエピ・マークを型押しし、さらにその上に一段と深い色を重ねて乗せている点に特徴がある。エピ・マークの模造品の中には、単なる型押しのみでその上に色を重ねていないものも見られるが(乙第7号証等)、そのような製品は全く品質感に乏しく、エピ製品の模造品ではあってもエピ・マークを正しく理解したものではない。被告の挙げる原告以外の者によるエピ・マークに類似する標章の使用例は、かような単なる型押しのみと思われるものがほとんどであり、模倣品としてかなりずさんなものといわざるを得ない。 審決は、本願商標を、単に、商品の品質(型押し柄)を表示するにすぎない旨の判断をしており、また、被告は、本願商標について、商品の素材を普通に表示するものである旨の主張をしているが、上記のとおり、本願商標は、単なるパターンの繰り返しや、普通に使用されているありふれた図形ではなく、麦の穂をイメージした独特の形状を呈しており、原告の創作にかかる識別性を有する表示として、原告の一定の商品の出所を表示するものとして機能しているのであり、商品の柄模様のみからなる商標というものではない。 また、本願商標は、上記のように正方形の中に表わされた図柄であって、商品の材料そのものを表わすものでも、また指定商品の「かばん」自体を表わすものでもなく、さらに、本願商標は商品に使用される素材(皮革、織物、紙等々)について何等の情報を提示するものでもないので、本願商標は商品の材料自体からも、指定商品自体からも十分に区別し得るものである。 さらに、商標法は、識別性がある限り、商品の原材料に使用された図柄模様からなる商標であっても、その登録を禁じる規定を有しているものではない。 そして、後記2のとおり、本願商標を使用した原告の商品は、エピ・ラインと通称され、本願商標は原告のエピ・ラインの商品のグループを表わす商標として使用されており、エピ・ラインの商品は、日本においても1987年(昭和62年)以来今日に至るまで販売されてきたのであって、需要者・取引者においても、本願商標をエピ・ラインと称し、原告の商品中の一群の商品を表わす図形商標として広く認識している。本願商標は、その需要層において圧倒的な認知度を誇っており、もはや我が国において著名であるといい得るが、このことはとりもなおさず、本願商標が出所表示機能を有することの証左である。 このように、現実の取引では、本願商標の図形自体に自他商品識別標識としての機能があるために、需要者・取引者には商標であると認識されているのである。 (2) 商標の社会的役割と本願商標 商標は、標章をある者の商品に付し、あるいは、役務の提供に当たって用いることにより、その商品・役務の出所を表示する機能を有するものである(出所表示機能)。この出所表示機能は、商標の識別力に由来し、商標の第一義的機能であるが、この出所表示力によって、需要者が、同一の商標の付された商品・役務には、 同一の品質を期待しており、また商標がそのような期待に応えた作用をすることになる(品質保証機能)。さらには、需要者は商標を記憶し、あるいは、商標自体に一定のイメージを思い浮かべるに至り、その商標を付した商品・役務に対し愛着を覚えさせる傾向を持つに至る場合があり、そのような場合、商標は、単なる品質保証を越えた機能を有することになる(広告宣伝機能)。 以上のような商標の社会的機能のうち、基本となるのは出所表示機能であるが、 原告提出の甲第38号証のアンケート調査の結果からも明らかなように、本願商標は、既にこのような出所表示機能を十二分に有しており、商標として保護されるべきである。 さらに、本願商標を付して日本においても広く販売されているいわゆるエピ・シリーズの商品については、需要者において本願商標の表示を見るだけでこれを原告の製品と認識するだけでなく、本願商標の表示が、高級な皮革を素材として手作りでひとつひとつ丁寧に作られた高品質のものであることを保証していると認識されているものであり、正に品質保証機能をも有しているといえる。 (3) 世界各国及び特許庁における登録例 ア 世界各国における本願商標の登録状況 原告は、世界各国に本願商標をはじめとするエピ・マークの商標を登録すべく出願しており、既に、アメリカ、イギリス、カナダ、ドイツ、フランスをはじめとするほとんどの先進国や多くの途上国においても登録されているが(甲第5、第6号証、第14号証ないし第27号証、第34号証)、これは、本願商標が独創的に創作されたもので、商標として十分識別機能を有すると判断されたからに外ならない。 また、本願商標であるエピ・マークのブルーに関しても、原告の本国であるフランスをはじめ、イギリス、ドイツ、スペイン、イタリアなどEU加盟国においては登録済であり(甲第14号証)、またアメリカ合衆国においても使用による登録を最近認められるに至っており(甲第33号証)、OECD加盟先進各国において登録を拒否している主要国は日本だけという状況である。したがって、我が国のみが本願商標の登録を拒否するのは、かような世界的趨勢に真っ向から反する結果となるのである。 イ 特許庁の登録例 我が国における特許庁の審査例としても、横長の四辺形を3つの部分に塗り分けただけの商標が、識別性について問題とされることなく公告されているし(甲第7号証)、登録例として、布地を長方形に切り取った図形について、商標登録が認められている例が多数存在している(甲第11、第12号証)。 これらの商標は、審決の理由においていうように「素材として商品の表面全体にわたった自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない単なる地模様としての使用」と判断される可能性のあるものであるが、現実に識別性を認められて登録されているのである。これらの登録例と対比して考察すると、本願商標だけを「素材として商品の表面全体にわたった自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない単なる地模様としての使用」にすぎないと判断し、一方、先登録例はそうではないと判断することは不可能であるので、殊更本願商標が登録を拒絶されるべき理由はないと考えざるを得ない。本願商標と同様の商品の地模様と認められる図形商標が一方で識別性を認められて登録されているのに対して、本願商標の識別性が否定されるとすれば、従来の判断基準を信頼した者が混乱することは必至であり、審査の差異や、その妥当性が疑われるものである。 また、特許庁の先登録例として、エピ・ラインの商品に匹敵する原告のもうひとつの商品群である「モノグラム・ライン」(甲第11号証の2記載の表示を使用した商品群)がその登録を認められている(甲第11号証の1、2)。このモノグラム・ラインと本願商標のエピ・ラインとは、ともに、被告が主張するところによれば「商標の使用とは認められず、それは自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない単なる地模様としての使用であり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できないもの」であるはずであるにもかかわらず、モノグラム・ラインについては登録が認められ、一方、本願商標についてはその登録が拒絶されるのは、全く一貫性を欠くものである。 (4) 商標の国際保護の必要性と本願商標 ア パリ条約 日本も加盟しているパリ条約第6条の5(テルケル条項)A(1)は、「本国において正規に登録された商標は、この条で特に規定する場合を除くほか、他の同盟国においても、そのままその登録を認められかつ保護される。」と規定する。 本願商標は、前記のとおり、フランス本国はもちろんその他の主要各国においてその登録を認められており、上記の規定の趣旨からいっても、我が国においても登録を認められるべきである。 また、パリ条約第6条の5Bは、「この条に規定する商標は、次の場合(①第三者の既得権を侵害する場合、②識別性を有しない場合等、及び③公序良俗に反する場合)を除くほか、その登録を拒絶され又は無効とされることはない。」と規定する。 本願商標について問題となるのは、上記②であるが、前記のとおり、本願商標がその需要層において高い認知度を示す以上、識別性を有しているというべきであり、上記②には該当せず、したがって、その登録を拒否されるべき理由はない。 さらに、パリ条約第6条の5C(1)は、「商標が保護を受けるに適したものであるかどうかを判断するに当たっては、すべての事情、特に、当該商標が使用されてきた期間を考慮しなければならない。」と規定する。 前記のとおり、本願商標は既に原告によって商標として長年にわたって使用され、その結果、周知性及び著名性を獲得しており、この規定の趣旨からいっても、 その登録が認められるべきである。 イ WTOにおけるTRIPS協定 「関税及び貿易に関する一般協定」第20条(d)は、知的所有権を保護する観点から実施する輸入制限については、これを例外的に認めているが、そのただし書は「それらの措置を、同様の条件の下にある諸国の間において任意の若しくは正当と認められない差別待遇の手段となるような方法で、又は国際貿易の偽装された制限となるような方法で、適用しないことを条件」としている。ここにいう「正当と認められない差別待遇の手段」や「国際貿易の偽装された制限」とはいかなる場合が該当するのか等は明確ではなかったが、日本も参加している「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定」(TRIPS協定)によってこれらが明確にされた。 TRIPS協定は、前文で「国際貿易にもたらされる歪み及び障害を軽減させることを希望し、並びに知的所有権の有効かつ十分な保護を促進し並びに知的所有権の行使のための措置及び手続自体が正当な貿易の障害とならないことを確保する必要性を考慮し」て制定されたことを宣言している。 そして、TRIPS協定第15条第2項は、パリ条約に反しない限り商標の登録を拒絶することができる旨規定する。しかるに、被告の主張する本願商標の登録拒絶の理由は、上記のとおりパリ条約が規定しないものであり、したがって、本願商標の登録を拒絶することはTRIPS協定第15条第2項の趣旨にも反することになる。 ウ マドリッド・プロトコール 我が国も加盟しているマドリッド・プロトコールは、1国の出願をベースとし希望の国を指定した出願を、本国官庁を経由して国際事務局に提出することにより、 国際登録を可能にするものであるところ、前記のとおり本願商標が先進諸国において登録を認められているにもかかわらず、ひとり我が国のみがその登録を拒否するのは、かような精神に悖るものといえる。 被告は、「我が国に商標登録出願された商標は、あくまでも、我が国商標法及び我が国の商品取引の実情に照らして登録されるか否かが判断されるものであり、外国で登録されている事実は、審決取消事由に該当しない。」とし、パリ条約第6条(1)及びマドリッド議定書第5条(1)から「本願商標が自他商品の識別力を有するかどうかの判断は、各締約国の判断に任されているものであり、原告の主張するようにマドリッド協定議定書の精神に反するものでもない。」と主張する。 しかし、正に問われているのは、「我が国商標法及び我が国の商品取引の実情に照らして登録されるか否かが判断される」場合における被告の判断基準自体が、 「マドリッド協定議定書の精神」に反するか否かである。そして、先進諸国のほとんどにおいてその登録が認められた本願商標について、世界的に通用し難い独自の審査基準により登録を拒否する被告の判断自体が問われなければならない。 (5) 被告提出の乙号証について 被告は、「本願商標と酷似又は類似の柄、文様からなる生地、素材を使った原告以外の者の製造販売に係るバッグ等の商品が認められる」旨主張して、証拠を提出している。 しかし、例えば、被告が本件訴訟の当初に提出した乙号証記載のものを見ると、 この中には、素材の表面の型押し模様が本願商標に似ているだけでなく、さらにバッグ全体の形状も原告の人気商品に似ていたり(乙第1号証のうち201頁記載のもの、第4号証)、型押し模様を本願商標に酷似させるなど(乙第7号証、第9、 第10号証)、原告のエピ・ラインのコピー商品であるとしかいいようがないものや、反対に、素材表面の型押し模様が、単なる平行線状であったり、全体に皺が寄ったような形状になっていたり、型押しの線の間隔が広く間延びした印象であったり、極く細長い菱形を形成しているような形状であったり、不揃いで統一がとれていないなどの形状をしており、本願商標が、緩やかな波形を描き、横方向が統一的に強調され、緊密に波状の線が描かれ、全体として統一的なリズム感を生み出しているという形状と対比して、類似しているとは全く言い難いもの(乙第1号証のうち229頁及び230頁記載のもの、第2号証のうち2枚目記載のもの、251頁記載のもの、第3号証、第5、第6号証、第8号証、第11、第12号証)も含まれており、両者ともに本願商標の登録を拒否する被告の主張の根拠とはなり得ないものである。 また、このように、本願商標の名声にただ乗りをした類似品が存在することから本願商標の識別性を否定しようとする被告の論理展開は、正に本末転倒というべきである。むしろ、かような類似品が存在することこそ、本願商標の登録を認め商標法上の保護を及ぼすべき必要性があることの証拠である。 また、実際に、製造・販売業者においても、かような類似品の製造、販売が法律上許容し難いものであるとの認識が広まりつつある。被告提出の乙号証の多くの商品に関しても、その多くは原告のエピ・ラインの商品の人気に便乗して大なり小なり似せて作った、若しくはそのままコピーして付したいわゆる偽コピー商品であるが、原告は、これらと同様な商品が出回っていることを発見し次第、各販売元又は製造元に対し、当該コピー商品の販売ないし製造を直ちに停止するよう、不正競争防止法に基づき警告を発し、ほとんどの場合、警告状の送付によってそのような販売は停止している(甲第30、第31号証参照)。また、実際に、不正競争防止法に基づいて、エピ・ラインのコピー商品の製造、販売等の差止等を認めた裁判例もある(大阪地方裁判所平成10年2月19日判決、平成8年(ワ)第1984号事件、平成9年(ワ)第4912号事件)。 被告は、「本願商標と酷似又は類似の柄、文様からなる生地、素材が多数存在する事実により、本願商標が出所表示機能を有しないと被告が判断したことに対しては、納得いく反論がなされていない。」と主張している。 しかし、そもそも本願商標が被告のずさんな挙例による他の標章と酷似又は類似するか否かの問題については、前記のとおり反論している。さらに、本願商標と酷似又は類似の柄、文様からなる生地、素材が多数存在するとしても、本願商標がその需要層において抜群の認知度を示すという事実によっても、本願商標が出所表示機能を有しないとする被告の主張は破綻しているというべきである。 被告は、「『シャルル ジョルダン』、『レノマ』、『KENZO』、『ヴァレンティノ・ガラバーニ』、『ハナエ・モリ』、『株式会社サンリオ』等の著名なデザイナー及び会社の商品、豊島岡女子高等学校の通学かばん等」は「エピ製品の模造品の挙例として、簡単に片付けられるものでもない」と主張している。 被告の「エピ製品の模造品の挙例として、簡単に片付けられるものでもない」との主張は、具体的にどのような意味を有するのか明確ではないし、また、前記のとおり、本願商標がその需要層において抜群の認知度を示すという事実によっても、 また本願商標が主要国において既に登録を認められている事実からも明らかなように、これらの挙例と本願商標とは、明確に区別され得るものである。 したがって、上記の例を根拠とする被告の反論は妥当でなく、本願商標の登録を拒否する理由とならない。 (6) 以上によれば、本願商標は商標法3条1項3号に該当しないから、この認定判断を誤った審決は違法であり、取り消されるべきである。 2 取消事由2 (1) 日本におけるエピ・ラインの商品の宣伝及び売上高等 本願商標は、原告が「かばん」をはじめ原告の各種商品に付して、日本をはじめとする世界各国において使用して、名声を博しているものであり、需要者・取引者も、本願商標を使用する商品が原告の商品であることを十分に理解しているものである(甲第3号証のアンケート調査において、国籍、性別、年令を問わず、過半数の調査対象者が本願商標をルイ・ヴィトンの商品を示す表示だと認識していることが判明している。)。また、原告は各種のメディアにおいてエピ・ラインと総称される本願商標を含む商標についての広報を行っており、原告の各種商品は、有名ブランド品として多数の雑誌の記事等に繰り返し紹介されている。 このように、原告の本願商標を含む商標を付したエピ・ラインの商品は、世界各国で人気を博しているが、日本の市場は原告にとって最重要市場の一つであり、原告が日本国内で年間約2000万円から1億5000万円に及ぶ広告宣伝費を費やす等の営業努力をしたことによって、日本における販売数量は極めて高いものとなっている。 すなわち、日本におけるエピ・ラインの商品の販売は、日本における発売当初の昭和62年(1987年)における宣伝広告費が約2300万円、売上高が約8億円であり、平成8年(1996年)では、宣伝広告費が約1億5600万円に上り、売上高が236億円を記録して10年前の30倍近くになっており、著しく増加している。また、日本におけるエピ・ラインの商品の売上高が原告の全商品の日本における売上高に占める割合は、昭和62年(1987年)の6・7パーセントから、平成7年(1995年)には40・6%に、平成8年(1996年)には38・8パーセントを占めるに至っている(甲第9号証の2、3)。 そして、例えば、エピ・ラインの商品の主な購買層と重なる読者を対象とする雑誌である「Oggi」は、その記事の中でエピ・ラインの歴史、商品のラインナップ等を詳細に紹介しているが(甲第10号証の1)、これは原告の広告宣伝ではなく、 自発的に人気の出てきたエピ・ラインに注目し、いわば消費者である読者の求めに応じて特集しているのであり、このような各種雑誌における同様な紹介記事は多数掲載され(甲第10号証の2ないし67)、最近においても多数掲載されている(甲第28号証の1ないし13及び第29号証)。これだけ多数の雑誌が自発的にエピ・ラインを取り上げている以上、本願商標が出所識別力を獲得したといわざるを得ないものである。そして、エピ・ラインの商品がこのような著名商品となったために、近年、本願商標を付したいわゆるコピー商品が多数出回るようになっている。 なお、審決は、原告による本願商標の使用について、「単なる地模様の使用であり、商標の使用とは認められない」としているが、特許庁において商標登録されているバーバリー等の商標の実際の使用も、商標公報等に本来記載されている「枠」に入れられて使用されているわけではなく、いわば、連続して、正に地模様として使用されている(例えば、甲第12号証及び甲第29号証の158頁の「バーバリー」の欄参照)。本願商標の使用の実例においても、バーバリー等の実際の使用と同様に、商標としての使用と認められるべきである。また、原告の前記の「モノグラム・ライン」の商標に関しても、一見するとこの表示は、製品の表面に繰り返されるパターンのように思われるが、このような使用に関しては、最高裁判例によって商標としての使用が肯定されており、有効な登録商標の使用であることが是認されている(最高裁判所昭和63年1月18日判決(昭和62年(オ)第12985))。 (2) 需要者におけるエピ・マークの認知度 エピ・シリーズの製品の購買層は、20代後半から30代前半が60パーセント前後と最も多く、その次には30代後半から40代前半が約20から30パーセントと続く(甲第36号証75頁)。 そして、平成10年に日本において実施されたアンケート調査によると、日本において、「エピ・マーク」を表示した製品がルイ・ヴィトンの商品であることを認識している女性の割合は、74・9パーセントに上っている(甲第36号証36頁)。 このように、1986年(昭和61年)の一般顧客向けの発売以来、本願商標を含むエピ・マークを表示したエピ・レザー製品は、日本においても、独特のしぼと鮮やかな色彩、ユニークなデザインで、主に20代から30代の女性を魅了し、モノグラム・キャンバスと並ぶ代表的なルイ・ヴィトン製品となり、その人気が定着しており、消費者は、「LV」などのマークがなくても、本願商標だけでルイ・ヴィトンの商品であることを十分認識しているのである。 被告は、「甲第36号証の36頁、37頁、75頁は、原告の商品シリーズ(モノグラム、エピ、タイガ及びダミエ)の認知率及び購買傾向をまとめただけのものであり、本願商標の認知度を立証したものでない。」と主張する。 しかし、上記の調査は、具体的な商品を前にして消費者が当該商品に使用された本願商標を実際に見た上でその認知の有無を回答したものである。その結果として、本願商標が具体的な指定商品たる原告の商品において使用され、それを購買層が認知し得ることが明白になったという事実を前にすれば、被告のいうように「本願商標の認知度」と本願商標を使用した「原告の商品シリーズの認知度」とを区別することに意味はない。被告の主張は、商標が具体的な状況の中で使用されるという実情を全く無視した机上の空論であるといわなければならない。 また、被告は、甲第36号証の調査票における質問は原告によって「エピ」と名付けられた原告の商品を知っているかどうかとしての質問であり、本願商標(型押しの柄)を知っているかどうかとの質問ではない旨の主張をしている。 しかしながら、回答者は現実に商品の写真を見た上で当該質問に対して回答している。すなわち、回答者は、実際に本願商標の付された商品の写真を見てこれを識別した上で回答しているのであり、片仮名文字のみを見て回答している訳ではない。本願商標が回答者の識別に関して絶大な貢献をしていることには何ら変わりはないというべきある。かかる場合に「エピ」なる片仮名文字のみをもって当該商品を識別したという被告の主張は一方的といわざるを得ない。 確かに、「エピ」なる片仮名文字を排除した形式で質問を行えば、本件との関係ではより完璧なものであったとはいえるが、そうではないことを理由に、甲第36号証の証拠力を一切排斥することは、証拠の評価としては失当である。 さらに、原告は、本件訴訟提起後に、甲第36号証の調査に加えて、平成12年5月13日から同月15日にかけて、「エピ」なる片仮名文字を排除した形式で、 純粋に本願商標だけ、あるいは本願商標を付したバッグ(本物の商品には付されている「LV」等の表示は意図的に削除。)の写真を回答者に見せて、本願商標がいかなる者に属するか、あるいは本願商標を使用した製品のシリーズ名は何かを問うアンケート調査を行った(甲第38号証)。 このアンケート調査の結果によると、本願商標を付したバッグの写真による質問に対して、回答者の62・8%が原告のものであることを認識しており、さらに本願商標だけの写真による質問に対しては、回答者の実に70%が原告のものであることを認識しているとの結果が得られた。 これは、前記のとおり、本願商標を含む商標を付した原告のエピ・シリーズの商品が日本における発売以来、またたく間に人気商品となり、過去約10年間で90回以上各種雑誌において有名ブランド商品として採り上げられたために、甲第38号証のアンケート調査の結果においても明らかになったように、本願商標は著名ないし周知になっており、需要者は、本願商標によって、それが原告の商品であることを十分認識しているといわざるを得ないものである。 (3) 外国における登録例等 本願商標と同様な標章が、商標登録に際して実質審査を行うアメリカ合衆国においても使用による登録が認められており、これは、とりもなおさず、本願商標の識別性が認められたことの結果である(甲第33号証)。また、フランスにおいても本願商標と同様な標章の識別性が裁判所によって認められている(甲第4号証の1、2)。 (4) 商標法の目的等について 商標の目的は、商標の付された商品の出所を示すことにより需要者をも保護することにある。商標法3条第1項は、商標としての成立性のない商標を消極的な登録要件として掲げるものであるが、本願商標を付した商品が原告の商品であることを需要者・取引者が認識している以上、商標の成立性について問題にすべき点は存在しないというべきである。むしろ、現実に商標として機能している本願商標の登録を拒絶することによって第三者が使用することを容認することになり、それによって生ずる商標権者側の不利益を十分に考慮すべきである。原告は、前記のとおり、 本願商標の「エピ・ライン」を模倣した商品を、不正競争防止法を用いて差し止めているが、このように、取引の実際において「エピ・ライン」を模倣した商品が現われている事実は、「エピ・ライン」が原告の業務に係る商品であることを需要者・取引者が認識していることの証左でもある。 これらの現実を考えるとき、不正競争防止法の保護だけでは不十分といわざるを得ず、商標法による迅速かつ画一的な保護を与えるべきであり、商品標識を保護対象とする商標法から除外して保護を拒絶することは、取引秩序の維持を図ろうとする商標法の目的に沿うものではない。 さらに、前記のパリ条約第6条の5C(1)の規定によっても、本願商標が長年使用されてきた事実、及び、本願商標を見る者が原告の商品であることを十分に認識する事実を十分に考慮すべきである。 (5) 以上によれば、仮に本願商標が商標法3条1項3号に該当し、本来識別性のない商標であったとしても、原告による過去10年以上の本願商標の使用によって、本願商標が出所識別力を獲得したのは明らかであり、本願商標は同条2項の適用によって登録されるべきである。 |
|
|
被告の反論の要点
1 取消事由1について (1) 原告は、本願商標は特殊な図形である旨主張するが、本願商標は、青色の横縞風の模様を正方形に描いてなり、その模様が単に連続していることから、単なる地模様と認識され得るものであり、各種商品の生地、素材の図柄として普通に使用されている形状の域を脱し得ないありふれた図形であって、決して特殊な図形といえるものではない。 また、原告は、本願商標は、それ自体は何ら商品の素材を示すものではなく、また指定商品を普通に表示するものでもない旨の主張をしている。 しかしながら、商標法3条1項3号に該当するか否かの判断時期は審決時であり、その時において、乙第1号証ないし第32号証に示すように、本願商標と酷似又は類似の柄、文様からなる生地、素材を使った原告以外の者の製造販売に係る商品が多数見られるところであり、その中には、「シャルル ジョルダン」、「レノマ」、「KENZO」、「ヴァレンティノ・ガラヴァーニ」、「ハナエ・モリ」、「株式会社サンリオ」等の著名なデザイナー及び会社の商品、豊島岡女子高等学校の通学かばん等が含まれており、原告の主張するように、エピ製品の模造品の挙例として簡単に片付けられるものでもない。 そして、本願商標の出願日以前は勿論のこと(乙第1、第2号証、第13号証ないし第19号証)、原告が本願商標につき麦の穂をイメージした図柄をベースに1986年(昭和61年)に創作した商品ラインの標章である旨の主張をしている当該時期の以前にも、「シャルル ジョルダン」の婦人靴、「バレクストラ」のハンドバッグ、「フェンディ」の財布(乙第13号証ないし第15号証)に本願商標と酷似又は類似の型押し柄が認められるものである。 したがって、単なる地模様にすぎない本願商標をその指定商品に使用しても、取引者、需要者は、単に商品の型押し柄の一類型として理解するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識し得ないものであり、自他商品の識別機能を果たし得ないものであるから、商標法3条1項3号に該当するものである。 (2) 原告は、エピ・マークの特徴及び沿革について種々主張して、被告の挙げるエピ・マークに類似する標章の例は、単なる型押しのみと思われるのがほとんどであり、模倣品の挙例としては、かなりずさんなものといわざるを得ず、また、乙号証記載のものの中には、原告のエピ・ラインのコピー商品であるとしかいいようがないものがある旨の主張をしている。 しかしながら、被告は、乙号証を、本願商標と酷似又は類似の柄、文様からなる生地、素材を使った原告以外の者の製造販売に係る商品が多数存在する証拠として提出したものであり、模倣品の挙例として提出したものではないし、コピー商品の有無は、本願商標が商標法3条1項3号に該当するかどうかとは関係ないことであり、原告がいかなる主張をしたいか不明である。さらに、原告は、エピ商品の模造品、模倣品と述べるのみで、本願商標と酷似又は類似の柄、文様からなる生地、素材が多数存在する事実により、本願商標が出所表示機能を有しないと被告が判断したことに対しては、納得いく反論をしていない。 (3) 原告は、我が国の先登録例を挙げて、本願商標が登録を拒絶されるべき理由はないと主張するが、地模様が本願商標と類似する登録第2412923号(甲第11号証の3)ですらも、「L」と「V」のモノグラムがある点において顕著な差異を有しており、その他の登録例(甲第11、第12号証)は、本願商標とはいずれも事例を異にするものである。 (4) 原告は、実際に、不正競争防止法に基づいて、エピ・ラインの商品の製造、販売等の差止等を認めた裁判例もあるとして、大阪地裁の判例を挙げるが、これらは、不正競争防止法に基づく差止等請求事件であり、本願商標のように商標の自他商品識別性に関する事案でない。また、この事件の判決は、「本件全証拠によるも、原告以外の他メーカーが原告商品と同様のシボ状型押し模様の皮革を用いた鞄類を製造、販売しているとの事実が認められないのみならず、単に右のシボ状型押し模様(エピ生地)だけをもってこれが商品表示性、周知性を取得していると認定したわけではなく」、「各形態をもってこれが商品表示性、周知性を取得していると認定したものである。」と判断しているのであり、上記判決は、地模様だけをもって、商品表示性及び周知性を取得していると認定したものではない。 (5) 原告は、世界各国におけるエピ・マークの商標登録の状況を述べて、我が国のみが本願商標の登録を拒否するのは、世界的趨勢に真っ向から反する結果ともなり、我が国も今般加盟した商標の国際的調和を図るためのマドリッド協定議定書の精神にも反するものといえる旨主張している。 しかしながら、我が国に商標登録出願された商標は、あくまでも、我が国の商標法及び我が国の商品取引の実状に照らして登録されるか否かが判断されるものであり、外国で登録されている事実は、審決取消事由に該当しない。 このことは、1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にヘーグで、1934年6月2日にロンドンで、1958年10月31日にリスボンで、1967年7月14日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約第6条(1)に「商標の登録出願及び登録の条件は、各同盟国において国内法令で定める。」となっているように、商標登録の条件、各国の商標保護の独立が規定されており、また、標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書第5条(1)においても「締約国の官庁は、関係法令が認める場合には、当該締約国においては当該標章に対する保護を与えることができない旨を拒絶の通報において宣言する権利を有する。」と規定されているように、本願商標が自他商品の識別力を有するかどうかの判断は、各締約国の判断に任されているものであり、この登録を拒絶しても、原告の主張するようにマドリッド協定議定書の精神に反するものでもない。 (6) 以上のとおり、原告の主張はいずれも失当であって、本願商標は、商標法3条1項3号に該当するものであると認定判断した審決に誤りはない。 2 取消事由2について (1) 原告は、本願商標が本来識別性のない商標であったとしても、本願商標は古くから使用され長年にわたる使用により識別性を獲得したものであり、商標法3条2項の適用を受けるべきものである旨主張している。 しかしながら、原告が提出した証拠は、すべて本願商標と同じ柄が、バッグ等の素材の表面全体にわたっての型押しの柄として使用されているものであり、商標の使用とは認められず、それは原告以外の者の製造販売に係る商品の柄として多数使用されている自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない単なる地模様としての使用であり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものである。 (2) 原告は、最高裁判所昭和63年1月19日判決を挙げ、甲第11号証の2の記載の表示を使った商品群に関しても、一見するとその表示は、製品の表面に繰り返されるパターンの様に思われるが、このような使用に関しては、最高裁判例によって商標としての使用が肯定されており、有効な登録商標の使用であることが是認されている旨主張している。 しかしながら、これは、「L」、「V」のモノグラムを含んだ自他識別機能を有する商標の事例であり、本願商標のように、他人が多数のかばん等の商品に本願商標と酷似の型押しの柄(品質)として使用している自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない単なる地模様でないから、本願商標とは事例を異にするものである。 (3) 原告は、本願商標を付した商品が原告の商品であることを需要者・取引者が広く認識している以上、商標の成立性について問題にすべき点は存在しない旨主張し、需要者におけるエピ・マークの認知度に関して、甲第36号証のアンケート調査の結果を提出し、消費者は、「LV」などのマークがなくても、「エピ・マーク」だけで、ルイ・ヴィトンの商品であることを十分認識している旨主張している。 しかしながら、甲第36号証の36頁、37頁、75頁は、原告の商品シリーズ(モノグラム、エピ、タイガ及びダミエ)の認知率及び購買意向をまとめただけのものであり、本願商標の認知度を立証したものでなく、乙第1ないし第32号証で提出した原告以外の者の製造販売に係る商品に多数使われている本願商標と酷似又は類似の柄、文様からなる生地、素材が原告のものであると取引者、需要者が認識するかどうかの立証は原告によって何らなされていない。 このアンケートで使用された調査票の問18は、参考としてあげられた原告の商品シリーズである4つのバッグの写真(その下にそれぞれ「モノグラム」、「エピ」、「タイガ」及び「ダミエ」の文字が記載されている。)の中からどれを知っているかについて選ばせるもので、それは、原告によって「エピ」と名付けられた原告の商品を知っているかどうかとの質問であり、本願商標(型押しの柄)を知っているかどうかとの質問ではない。 (4) 以上のとおり、本願商標について商標法3条2項を適用することなく、同法3条1項3号に該当するとした審決に誤りはない。 理 由 1 取消事由1について (1) 本願商標の構成及び本願商標に係る指定商品が第18類の「かばん類、袋物、携帯用化粧道具入れ」であることは争いがなく、甲第13号証によると、本願商標は、青色の濃淡によって、横方向の緩やかな波形が緊密に連続して構成され、 全体として青色の横縞風の模様を正方形の枠内に描いてなるものであることが認められる。 そして、本願商標は、商品の素材となる皮革に対する型押しと染色によって表示され、商品の全体に使用されるものであることは原告が自認するところであり、この本願商標の商品における現実の使用態様(甲第10号証の1ないし67、第28号証の1ないし13、第29号証及び第37号証)を参酌すると、本願商標をその指定商品について使用した場合、一般的にはこれに接する取引者、需要者に、商品の地模様と認識され得るものであると認められる。 ところで、商品の地模様であっても、そこに特徴的な形態ないし特異性が見いだされれば、自他商品の識別機能を有する場合もあり得るものではあるが、乙第1ないし第37号証により認められる原告以外の者の商品の生地、素材の模様や図柄と対比してみても、本願商標は、商品の地模様として普通に使用されている形状及び色彩と明らかに異なった特殊性を有しているとはいい難く、地模様の形態を超えて、それ自体で自他商品識別機能を一般的に果たし得るような特徴的な形態を備えていることを肯定することは困難であるといわざるを得ない。 以上によれば、「本願商標は、その指定商品に使用しても、単に、該商品の品質(型押し柄)を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない」とした審決の認定判断部分に誤りがあるとはいえない。 (2) 原告は、本願商標を使用した原告の商品は、エピ・ラインと通称されて、原告のエピ・ラインの商品のグループを表わす商標として長年使用されており、本願商標は、需要者・取引者においても、原告の商品中の一群の商品を表わす図形商標として広く認識されており、このことは、本願商標が出所表示機能を有することの証左である旨の主張をしている。 しかしながら、本願商標が商品に使用された結果として出所表示機能を有するに至ったとしても、そのことは、次に検討する商標法3条2項規定の使用による識別機能の獲得の有無の問題であって、本願商標の形態自体が本来自他商品の識別機能を有することを直ちに根拠付けるものではなく、そのことを考慮に入れても、上記(1)に判示したとおり、本願商標それ自体が自他商品の識別機能を一般的に果たし得るような特徴的な形態を備えていることを認めるには足りないといわざるを得ない。 また、原告は、特許庁における他の登録例と対比して、本願商標についても登録されるべきである旨の主張をしているが、例えば、原告が他の商品群に使用している商標であるとする「モノグラム・ライン」の商標は、「L」と「V」の文字のモノグラムを含む特徴的な図形によって構成される商標であるなど、いずれも本願商標とは構成を異にするものであって、原告の上記主張を採用することはできない。 (3) その他原告は、本願商標の諸外国における登録状況や国際保護の必要性等に関する主張をするが、これらの事情をもってしても、上記(1)の判断を覆すことはできず、したがって、原告主張の取消事由1は理由がない。 2 取消事由2について (1) 本件証拠(後記括弧内に掲記のもの。)によれば、次の各事実が認められる。 ア 本願商標を含むエピ・ラインの標章の創作の経緯等(甲第8号証の1、第9号証の1、第35号証、弁論の全趣旨) 本願商標は、前記のとおり、青色の横縞風の模様を正方形の枠内に描いてなるものであるが、その図形をほぼ同じくして色彩をそれぞれ異にする形態の標章が、本願商標を含めて、原告によって「エピ」、「エピ・マーク」と呼ばれ(以下「エピ・マーク」という。)、商品の素材となる皮革に対する型押しと染色によって商品の全体に表示されて、原告の一群の商品において使用されている。この皮革は「エピ・レザー」と呼ばれ、このシリーズは「エピ・ライン」ないし「エピ・レザー・ライン」と呼ばれ、「エピ」、「エピ・レザー」とも略称されている。この名称は、原告が麦の穂が風にたなびく様子をイメージした図柄をベースに図案化したために、フランス語で「麦の穂」を意味する「epi」の言葉をその標章のネーミングに使用したものである。これらのエピ・ラインの商品には、いずれも、原告の社名の頭文字である「L」と「V」の文字を組み合わせたモノグラムが同色で表示されている。 原告は、このエピ・マークを、1926年(昭和元年)に、インドのバローダ王のために作製した「ティーケース」と呼ばれたピクニック・ケースにおいて初めて創作して使用し、その後、これが評判になったため、顧客からの特別な注文に基づいて原告が製造、販売した旅行鞄等の製品にエピ・マークを使用していた。 そして、原告は、1986年(昭和61年)に、このエピ・マークを一般顧客向けに復活させ、耐水性、耐久性を高めたエピ・レザーを使用した旅行鞄、ショルダーバッグ及び財布等の小物(袋物)の発売を開始した。発売当初の1986年には、本願商標であるトレド・ブルー(スペインの古い町トレドを流れるタジ川にちなんでいるとされる。)の色彩の他に、ボルネオ・グリーン、クリール・ブラック、ケニアン・ブラウンと呼ばれる合計4色の製品が発売され、続いて、翌1987年に、カスティリアン・レッド、1990年にジパング・ゴールド、1993年にはタッシリ・イエローの色彩の製品が加わった。 イ エピ・ラインの商品の売上げ及び宣伝等(甲第8号証の1、2、第9号証の2、3、第35号証、弁論の全趣旨) 原告は、我が国をはじめとして世界各国において、かばん、バッグ等の皮革商品を販売しており、その社名である「ルイ・ヴィトン」の名称は著名なブランド名となっている。そして、エピ・レザーを使用したエピ・ラインの商品も世界各国で販売されており、日本の市場が原告にとって最重要市場の一つであることから、原告は、日本における発売当初の昭和62年(1987年)以降、日本国内で、エピ・ラインの商品について数千万円から一億円を超える広告宣伝費を費やして、随時広告を行っており、その日本国内での売上も高額となっている。 すなわち、日本におけるエピ・ラインの商品(本願商標の指定商品であるかばん類、袋物、携帯用化粧道具入れを含む。)の売上高は、昭和62年(1987年)に約8億円であったものが年々増加して、平成8年(1996年)には、236億円に達している。また、日本におけるエピ・ラインの商品の売上高が原告の全商品の日本における売上高に占める割合は、昭和62年(1987年)の6・7パーセントから、平成7年(1995年)には40・6%に、平成8年(1996年)には38・8パーセントを占めるに至っている。このように、エピ・ラインの商品は、「L」と「V」の文字を組み合わせたモノグラムを商品の全面にデザイン化した原告の極めて著名な商品群である「モノグラム」と並ぶ代表的なルイ・ヴィトンの商品となっており、「いまやルイ・ヴィトンには二つの顔があるといわれています。代表的なモノグラム・ラインと、大胆な色使いのエピ・レザーと。」と紹介する雑誌もある(「SOPHIA」講談社平成6年2月1日発行、甲第10号証の24)ほど、そのブランド商品としての人気が定着している。なお、ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社の社員が平成12年2月14日に作成した陳述書(甲第35号証)では、日本におけるのルイ・ヴィトン製品の売上げのうち、モノグラム・ラインが約5割を占め、エピ・ラインは、約2割程度で、年間160億以上の売上げがあり、 原告のバッグ類の2番目に重要な製品ラインとなっているとしている。 また、エピ・ラインの商品の需要者である女性の読者を対象とする雑誌である「Oggi」(小学館平成5年7月1日発行、甲第10号証の1、第37号証)や「SOPHIA」(講談社平成5年12月1日発行、甲第10号証の2)がエピ・マークが麦の穂をデザインしたものであることやエピ・ラインの歴史、商品のラインナップ等を詳細に紹介する記事を掲載するなど、平成10年10月の本件の審決時までの間に、主に女性向けの多くの雑誌において、原告のエピ・ラインの商品が多数回掲載されており(甲第10号証の3ないし67、第28の1ないし6)、最近においても同様の状況にある(甲第28号証の7ないし13、第29号証)。これらの雑誌の記事では、原告のエピ・ラインの商品として、かばん、各種バッグ、キンチャクショルダーや、財布、名刺入れ、アクセサリーケース、キー・ケース、携帯用化粧品入れ等の小物の皮革商品が紹介されており、また、その一部では、ベルトの商品(甲第10号証の1、3、29)やウエスト・バッグ(甲第10号証の3、 27、35)も紹介されている。 ウ 日本における需要者に対するアンケート調査の結果 原告が平成10年に日本において実施したアンケート調査によると、エピ・ラインの商品のうち、バッグの写真を例として挙げた質問に対して、原告のエピ・ラインのシリーズを認識していると回答した女性の割合が74・9パーセントに上っており、モノグラム・ラインの97・0パーセントに次ぐ認知率を示している(甲第36号証36頁)。 また、原告が株式会社社会調査研究所に依頼して、本件訴訟提起後の平成12年5月13日から同月15日にかけて、本願商標を単独で、あるいは、実際の商品に付されている「LV」のモノグラムの表示を削除して、本願商標のみを付したバッグを回答者に見せて、本願商標がいかなる者に属するか、あるいは本願商標を使用した商品のシリーズ名は何かを問うアンケート調査を、同社のホームページにアクセスして回答するという方法で行ったところ、本願商標を付したバッグの写真による質問に対して、回答者の62・8%が原告の商品であることを認識しており、さらに本願商標のみの写真による質問に対して、回答者の70%が原告のものであることを認識しているという調査結果が得られている(甲第38号証)。 エ エピ・マークの識別力に関する外国の諸団体による証明書の存在 デンマーク皮革業者組合が発行した1990年(平成2年)11月9日付けの証明書では、エピ・マークは原告の商品の特徴的なマークとして一般に知られているとしており、また、1995年(平成7年)9月11日付けの証明書でもそのことを確認した上で、以前に見られた類似の皮革商品は姿を消しているとしている(甲第2号証の1)。また、英国皮革協会の販売部長による法廷宣誓書によると、出所を伏せたエピ・レザーのサンプルについて、原告の商品であることを認識したとしている(甲第2号証の2)。 (2) 上記(1)の事実を総合すると、本願商標を使用した本件の指定商品は、日本における昭和62年の一般顧客向けの発売以来、審決時の平成10年までの間に多額の売上げを達成し、また、原告による宣伝広告と女性向けの多くの雑誌による多数回にわたる紹介がされており、これらの結果、少なくとも本件の審決時までには、その購買層である女性の需要者の間において、本願商標をその指定商品に用いた場合に、本願商標のみの表示によって、原告の商品であることが広く認識されていたことが認められる。 上記(1)のウの原告が本件訴訟提起後に実施したアンケートの調査結果は、この認定を端的に裏付けるものであるというべきである。また、上記(1)のエの外国の諸団体によるエピ・マークの識別力に関する証明書の内容は、前判示のとおり、世界各国においても原告によってエピ・マークを使用したエピ・ラインの商品が宣伝、販売されており、その結果、エピ・マークが当該国内の需要者や取引者の間において出所識別力を取得するに至っていることを証するものであり、このことは、我が国においても同様の状況にあることを推測させるといえよう。 このように、本願商標は、指定商品に使用された結果需要者が何人かの業務に係る商品であることが認識することができるものとなったことを肯定することができる。 (3) 被告は、本願商標やエピ・マークと同様の標章(地模様)を使用した他の者の商品の存在として、乙第1号証ないし第32号証を提出しているが、原告も指摘するように、これらの中には、乙第1号証の229頁及び230頁に記載のもの、 第3号証、第5号証の2枚目に記載のもの、第12号証、第14号証、第16号証、第21号証の87頁に記載のものなど、一見して本願商標とは類似していないものがあるし、本願商標と類似すると認められる標章についても、それらの標章が付された商品の販売期間(特に、本件の審決時点である平成10年10月における販売継続の有無)、販売場所、売上高、需要者のその出所に関する認識の状況等が明らかではなく、また、これらの標章が使用された商品が他の者の商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたことを認めるに足りる証拠はない。したがって、これらの証拠によっては、審決の時点において、本願商標と同一又は類似の標章が本願商標の指定商品の生地や素材の柄として広く使用されていた事実を認めるのには十分でないといわざるを得ないから、これらの証拠は、本願商標の出所識別力が生じていたという上記(2)の認定の妨げとはならないし、また、本願商標の指定商品に本願商標を用いた場合、それが原告の商品であることを表示するほど本願商標が周知となっていたという上記(2)の認定を左右するものではないというべきである。 また、被告は、原告が本願商標の使用例として提出した証拠は、すべて本願商標と同じ柄が、バッグ等の素材の表面全体にわたっての型押しの柄として使用されているものであり、商標の使用とは認められず、それは原告以外の者の製造販売に係る商品の柄として多数使用されている自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない単なる地模様としての使用であり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない旨の主張をしている。 しかしながら、上記(1)のウのとおり、原告が本件訴訟提起後に実施したアンケートの結果によると、本願商標がその指定商品に使用された結果、現実には本願商標のみの表示によって、需要者が広く原告の商品であると認識し、識別することができるものとなっていることを肯定し得る調査結果が得られているのであり、このアンケートの結果についてはその信用性を強く疑わしめる事情は見いだし難く、本件において提出された証拠による限り、上記(2)の認定を覆すことは困難であるといわざるを得ない。 (4) したがって、第18類の「かばん類、袋物、携帯用化粧道具入れ」を指定商品とする本願商標の登録について、商標法3条2項の適用を否定した審決には誤りがあるというべきである。 3 結論 以上のとおり、原告の本訴請求は理由があるので、これを認容することとし、主文のとおり判決する。 |
| 裁判長裁判官 | 永井紀昭 |
|---|---|
| 裁判官 | 塩月秀平 |
| 裁判官 | 橋本英史 |