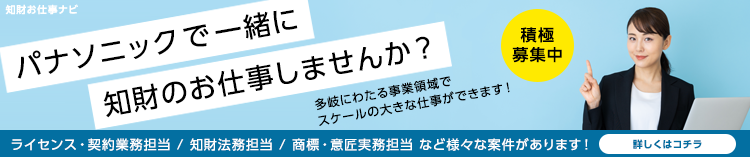| 関連審決 |
審判1966-3319 |
|---|
この判例には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
| 審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
|---|---|---|
| 平成11ワ3134商標権侵害差止請求事件 | 判例 | 商標 |
| 平成13ネ5748商標権侵害差止等請求控訴事件 | 判例 | 商標 |
| 平成12ワ366商標権侵害による損害賠償請求事件 | 判例 | 商標 |
| 平成20ワ19774商標権侵害差止等請求事件 | 判例 | 商標 |
| 平成22ワ32483商標権侵害差止等請求事件 | 判例 | 商標 |
| 関連ワード | 包装 / 指定商品 / 周知商標 / 周知性 / 不正競争の目的 / 不使用 / 先使用(32条) / 称呼(称呼類似) / 国内 / 差止 / 連合商標 / 使用許諾 / 無効審判 / 更新登録 / 商標権の放棄 / 先使用権 / 継続 / 商号 / 利益額 / |
|---|
| 元本PDF |
裁判所収録の全文PDFを見る
|
|---|---|
| 元本PDF |
裁判所収録の別紙1PDFを見る
|
| 事件 |
昭和
59年
(ワ)
6210号
|
|---|---|
| 裁判所のデータが存在しません。 | |
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
| 判決言渡日 | 1987/10/14 |
| 権利種別 | 商標権 |
| 訴訟類型 | 民事訴訟 |
| 主文 |
一 被告報国製薬株式会社は原告に対し、金五五二二万八四九三円及びこれに対する昭和五九年九月四日から完済まで年五分の割合による金員を支払え。 二 被告Aは原告に対し、金二九四五万四七九七円及びこれに対する昭和五九年九月四日から完済まで年五分の割合による金員を支払え。 三 原告の被告らに対するその余の請求をいずれも棄却する。 四 訴訟費用はこれを一〇分し、その一を原告の負担とし、その余を被告らの負担とする。 五 この判決の第一、二項は仮に執行することができる。 |
| 事実及び理由 | |
|---|---|
|
当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨1 被告報告製薬株式会社は原告に対し、金六〇九〇万五二八六円及びこれに対する昭和五九年九月四日から完済まで年五分の割合による金員を支払え。 2 被告Aは原告に対し、金三二四七万七六二〇円及びこれに対する昭和五九年九月四日から完済まで年五分の割合による金員を支払え。 3 訴訟費用は被告らの負担とする。 4 仮執行の宣言二 請求の趣旨に対する答弁(被告ら)1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 |
|
|
当事者の主張
一 請求原因1 原告は、別紙目録第一記載の商標(以下「本件商標」という。)について、左記の商標権(以下「本件商標権」という。)を昭和五五年一一月八日に放棄するまで有していた。 記登録番号 第四一四二六六号出願 昭和二五年七月一九日出願公告 昭和二六年一二月二六日指定商品 旧第一類 小児用薬剤(丸薬)登録 昭和二七年八月四日更新登録 昭和四八年三月一〇日2 被告A(以下「被告A」という。)は、昭和四三年八月一日被告報国製薬株式会社(以下「被告会社」という。)に対し、別紙目録第二記載の商標(以下「被告商標」という。)の使用を許諾し、被告会社は、爾後昭和五五年一一月七日に至るまでの間被告Aに使用料を支払つて、その製造する小児用薬剤「竒應丸」(以下「本件商品」という。)の包装に被告商標を附して販売してきた。 3(一)被告商標中の「樋屋十世」の文字部分は、それ自体独立しても自他商品の識別標識としての機能を果し得るものであり、「樋屋十世」の文字のうち「十世」の文字部分は「十代目の子孫」の意を表したと容易に理解せしめるものであるから、その要部は「樋屋」の文字の部分である。そうすると、被告商標は、右の「樋屋」の文字に相応して「ヒヤ」の称呼も生ずる。他方、本件商標中に独立して横書きされた「樋屋」の文字は、それ自体独立して自他商品の識別標識としての機能を果し得るものであり、この文字に相応して「ヒヤ」の称呼も生ずる。 したがって、被告商標と本件商標は、「ヒヤ」の称呼を共通にする類似の商標である。 (二)また、被告会社が被告商標を用いていた本件商品は、本件商標の指定商品に属する。 4 以上のとおり、被告Aは法律上の原因なくして被告会社に対し原告の有する本件商標に類似する被告商標の使用を許諾して商標使用料を不当に利得し、被告会社は右被告商標を使用して本件商品を販売して利益をあげて不当に利得し、それぞれ原告に損失を及ぼした。 5(一)昭和四九年九月一日から同五五年一一月七日までの間に被告会社が被告商標を使用した本件商品を販売して得た売上額及び被告Aに支払つた商標使用料の額は、次のとおりである。 <12697-001> なお、右のうち(1)、(2)及び(8)の期間の売上額及び使用料は被告らにおいて開示しないので、次のとおり推定した。 まず、右(3)ないし(7)の各期間の売上額をグラフにすると別紙添付のとおりであり、右各売上額が比較的単調な直線上にほぼ並ぶので、この直線を延長することにより、昭和四八年一一月一日から同四九年一〇月三一日の売上額を六〇〇〇万円、昭和四九年一一月一日から同五〇年一〇月三一日の売上額を五一〇〇万円、 昭和五五年一一月一日から同五六年一〇月三一日の売上額を一〇〇〇万円と推定し、次に日割計算によつて、(1)、(2)及び(8)の各期間の売上額を前記表記載のとおり求めた。そして、被告会社が支払つた商標使用料は売上額の一六パーセントであるから、右各売上額に〇・一六を乗じて各商標使用料を推定した。 (二)以上のとおり、被告会社は、昭和四九年九月一日から原告が本件商標権を放棄した日の前日である昭和五五年一一月七日までの間に少なくとも二億〇三〇一万七六二二円分の本件商品を販売し、被告Aに支払つた商標使用料を除いて、少なくとも右売上額の三〇パーセントに当る六〇九〇万五二八六円の純利益をあげて右金額を不当に利得し、原告に同額の損失を与えた。 (三)また、被告Aは、前記期間に被告会社から本件商品に対する被告商標の使用料として合計三二四七万七六二〇円を受領して右金額を不当に利得し、原告に同額の損失を与えた。 6 よつて、原告は、不当利得返還請求として、被告会社に対し金六〇九〇万五二八六円、被告Aに対し金三二四七万七六二〇円及び右各金員に対する本件訴状送達の日の翌日である昭和五九年九月四日から完済まで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。 二 請求原因に対する被告らの認否1 請求原因1の事実は認める。 2 同2のうち、被告Aが被告会社に対し被告商標の使用を許諾し、被告会社が被告Aに使用料を支払つて本件商品の包装に被告商標を附して販売してきたことは認める。 被告会社は、昭和四四年に訴外亡Bから被告商標の使用許諾を受け、昭和四六年六月一日B死亡後は、同人の養子で相続人である被告Aから使用許諾を受けているものである。 3 同3(一)の事実は否認する。被告商標には「本家樋屋第十世故C氏直傳」と記載されており、「樋屋」の部分のみを分離して考察することはできないから、本件商標と類似しない。 4 同4は争う。 5(被告会社) 同5(一)の表のうち(3)ないし(7)の期間の本件商品の売上額及び使用料が原告主張のとおりであること、被告会社が被告Aに支払つた被告商標の使用料が売上額の一六パーセントであることは認めるが、同5のその余の事実は否認する。 (被告A)同5の事実は否認する。 (被告ら) 竒應丸の製薬メーカーは全国に多数存在し、関西地区においても数社が製造販売している。また、竒應丸以外にも小児薬は「宇津救命丸」「救心小児丸」等多数存在する。したがつて、原告主張の期間中被告会社が竒應丸を売らなかつたとしても、その分すべてを原告において売れたとは限らず、被告会社のあげた利益額がそのまま原告の損失になるとはいえない。そもそも、原告は、その主張の期間本件商標とは色彩、文字、構成等の異なる商標を使用していたものであり、損失は生じていない。 三 被告らの主張1 被告商標は、商標登録第七七三七九七号(出願昭和四〇年一一月六日、登録昭和四三年三月九日、更新登録昭和五三年七月三日、指定商品第一類丸薬)をもつて被告Aを商標権者として登録されていたところ、東京高等裁判所昭和五五年(行ケ)第二三号審決取消請求事件の同年一二月一〇日判決において、被告商標は本件商標に類似するとして被告商標の登録を無効とした審決の取消請求が棄却され、右判決は上告がなく確定した。しかし、右判決言渡日より前の昭和五五年一一月八日に原告は本件商標権を放棄していながら右事実を隠蔽していたものであるから、右判決は無効である。したがつて被告商標の登録は有効に存在している。 2 仮に東京高裁の前記判決が有効であり、被告商標が本件商標に類似するとすれば、本件商標は、それより先願・先登録で被告Aを商標権者とする第二六六六六九号の登録商標(出願昭和九年一〇月二三日、登録昭和一〇年七月九日、指定商品第一類、丸薬、錠薬、散薬其ノ他本類ニ属スル商品)に類似する。すなわち、右第二六六六六九号億商標も「樋屋」の文字を含む商標であり、前記判決と同様の理由により「樋屋」の文字を共通にする本件商標と類似することになるから、本件商標は登録の無効事由がある。したがつて、被告Aは右第二六六六六九号商標に基づき原告に対し本件商標の使用を差止めることができるのであるから、被告商標が本件商標権を侵害したとはいえない。 3 被告Aは、商標法32条1項の規定する先使用により被告商標を本件商品に使用する権利を有する。 すなわち、被告Aの祖父訴外亡Dは、明治二八年三月第一一世Cから樋屋竒應丸の製造販売についての暖簾分けを受けた。Dは、明治三二年から同人が死亡した昭和八年まで「乾知生堂」の屋号で樋屋竒應丸の製造販売をし、昭和八年から同四四年までは、Dの女婿で被告Aの養父である訴外亡Bが乾知生堂の営業を承継して樋屋竒應丸(昭和九年以降は「本家樋屋第十世故C氏直傳竒應丸」の名称を使用)を製造販売し、右Bは昭和四六年六月一日死亡し、被告Aが相続した。被告商標(ないしは被告商標と要部が同一の商標)は、右暖簾分け以来乾知生堂が製造販売する本件商品の商標として不正競争の目的なく継続して使用され、本件商標の登録出願時には消費者の間に広く認識された商標となつていた。 四 被告らの主張に対する原告の認否、反論1 被告らの主張1のうち、被告商標がかつて被告ら主張のとおり登録されていたこと、被告ら主張の東京高裁の判決がなされ、右判決は上告がなく確定したことは認めるが、その余は否認する。 本件商標は、原告において商標整理をした際、一番違いの商標登録第四一四二六五号商標との錯誤により昭和五六年八月三日受付をもつて同五五年一一月八日放棄を原因として登録抹消がなされたが、被告ら主張の東京高裁昭和五五年(行ケ)第二三号審決取消請求事件は、同年一〇月二〇日に口頭弁論が終結されており、本件商標権放棄の事実は右判決の効力に何ら影響を及ぼさない。 2 同2のうち、本件商標より先願・先登録で被告Aを商標権者とする第二六六六六九号の登録商標が存在することは認めるが、その余は否認する。 被告らは、本件商標権には無効事由があると主張するが、次の理由により失当である。 (一)原告は、右第二六六六六九号商標より更に先願で、かつ「樋屋」の文字を共通にする登録商標「樋屋竒應丸」(登録番号第三〇一六八五号、出願昭和九年五月一九日、登録昭和一三年五月二日、指定商品第一類、丸薬)及び同「本家樋屋」(登録番号第三〇一六八六号、出願昭和九年五月一九日、登録昭和一三年五月二日、指定商品第一類、丸薬)の商標権者であるから、被告との主張を推し進めれば右第二六六六六九号商標も登録無効事由を有することになり、本件商標の登録が無効になるいわれはない。 (二)大審院昭和九年(オ)第三一二一号商号使用禁止請求事件の昭和一〇年四月二六日判決(民集一四巻八号七〇七頁)によつて、被告Aは「樋屋」を含む商号の使用を禁止されている。 (三)右第二六六六六九号商標の登録出願前から「樋屋」の商標は原告の家庭薬の商標として周知商標であつた。右第二六六六六九号商標は、商標法4条1項10号の規定に違反して登録になつたものであるから無効事由が存在し、原告は無効審判を請求することができる。 (四)右第二六六六六九号商標については、現在、不使用による取消審判(昭和四一年審判第三三一九号)が請求され係属中であるから、取消される可能性が強い。 3 同3のうち、Dが昭和八年に死亡したこと、BがDの女婿で被告Aの養父であり、昭和四六年六月一日死亡したことは認めるが、その余は否認する。 商標法32条1項による先使用権が成立するのは、登録商標の出願前に使用してきた商標と同一の商標を使用する場合に限られる。被告商標が本件商標の出願前に使用されていたとしても、右使用は、「樋屋ナル文詞」の使用を禁じた前記大審院昭和一〇年四月二六日判決に反してなされたものであるから、不正競争の目的で使用されたものというべきであり、また、被告商標が本件商標の出願時に取引者又は需要者に広く認識されていた事実はない。さらに、Bは昭和三二年四月一五日から訴外大阪プリント株式会社の取締役をしており、少なくとも右時期から昭和四〇年代に被告会社が被告商標の使用を始めるまでの間は、被告商標の使用は中断されている。 |
|
|
証拠(省略)
理 由一 請求原因1の事実(原告が本件商標権を昭和五五年一一月八日に放棄するまで有していたこと)は、当事者間に争いがない。 二 同2のうち、被告Aが被告会社に対し被告商標の使用を許諾し、被告会社が被告Aに使用料を支払つて本件商品の包装に被告商標を附して販売してきたことは、 当事者間に争いがない。 成立に争いのない甲第一五号証、弁論の全趣旨により真正に成立したものと認める丙第二号証、被告A、被告会社代表者各本人尋問の結果によれば、遅くとも昭和四三年八月一日までには、被告Aの養父である訴外亡Bが被告会社に対し被告商標の使用を許諾し、同人が昭和四六年六月一日に死亡した後は被告Aがその地位を相続により承継したこと、被告会社は右使用許諾を受けた後少なくとも昭和五五年一一月七日までは被告商標を本件商品の包装に附して販売してきたことが認められ、 右認定を左右するに足りる証拠はない。 三 被告商標は別紙目録第二記載のとおりの構成から成るものであるところ、右構成中の翁の肖像の図形の上の「樋屋十世」の文字の部分は自他商品の識別標識としての機能を果し得るものであることが明らかであり、右「樋屋十世」の文字のうち「十世」の文字部分は「十代目の子孫」「十代目の承継者」の意を表したものと容易に理解されるところであるから、本件商品たる小児用薬剤の需要者が「樋屋」の部分に惹きつけられ、これだけで自他商品の識別標識としての機能を果し得るものとの認識をもつであろうことも否定できない。そうすると、被告商標からは「ヒヤ」の称呼も生ずるものというべきである。 一方、本件商標の構成は別紙目録第一記載のとおりであり、右構成中に独立して横書きされた「樋屋」の文字の部分は、それ自体で自他商品の識別標識としての機能を果し得るものであることが明らかであり、右文字に相応して、本件商標から「ヒヤ」の称呼が生ずる。 したがつて、被告商標と本件商標とは「樋屋」の文字と「ヒヤ」の称呼を共通にし、類似する商標であるということができる。 また、被告商標の使用に係る商品である小児用薬剤が本件商標の指定商品である小児用薬剤(丸薬)と同一又は類似する商品であることは明らかである。 四 被告らの主張について検討する。 (一)被告らの主張1について 被告商標がかつて商標登録七七三七九七号として登録されていたこと、東京高裁昭和五五年(行ケ)第二三号審決取消請求事件の同年一二月一〇日判決において、 被告商標は本件商標に類似するとして被告商標の登録を無効とした審決の取消請求が棄却され、右判決は上告がなく確定したことは、当事者間に争いがない。 被告らは、原告が右判決言渡日より前に本件商標権を放棄していながら右事実を隠蔽していたものであるから右判決は無効であり、被告商標の登録は有効に存在していると主張する。 しかし、被告ら主張のような事由が存在したとしても、右の確定判決が当然に無効となるいわれはないから、被告らの主張は主張自体失当である。付言するに、原告が本件商標権を放棄した日が昭和五五年一一月八日であることは当事者間に争いのない事実であるが、商標権の放棄は登録しなければその効力を生じないものであるところ(商標法35条、特許法98条1項1号)、成立に争いのない甲第二号証の一によれば、本件商標について右放棄を原因とする抹消登録がなされたのは、前記東京高裁の判決言渡より後の昭和五六年八月三日であることが認められるし、成立に争いのない甲第一四号証によれば、右審決取消請求事件の口頭弁論は本件商標権の放棄の日より前の昭和五五年一〇月二〇日に終結されていることが認められる。さらに、商標権放棄の効力は遡及するわけではないから、商標登録が商標法4条11号の規定に違反したことを理由とする商標登録無効の審判の請求(同法46条1項1号)は、先願の登録商標の商標権が後に放棄されたからといつて許されなくなるわけではないのである。 したがつて、被告らの主張1は失当である。 (二)被告らの主張2について 被告らは、本件商標は、「樋屋」の文字を共通にする点でそれより先願・先登録の第二六六六六九号商標に類似するから登録無効事由が存在した旨主張する。 しかし、本件商標より先願・先登録の商標として被告ら主張の第二六六六六九号の登録商標が存在するとしても、いずれも成立に争いのない甲第七、八号証の各一、二同第九号証によれば、原告は右商標より更に先願の登録商標として指定商品を第一類、 丸薬とする「樋屋竒應丸」なる商標(登録番号三〇一六八五号)及び「本家樋屋」なる商標(登録番号三〇一六八六号)を有することが認められるから、本件商標が先願の第二六六六六九号商標に「樋屋」の文字を共通にするのゆえをもって類似し登録無効事由ありというのであれば、それよりも前に右第二六六六六九号商標そのものが右の原告の有する二つの先願の登録商標に同じく「樋屋」の文字を共通にするのゆえをもつて類似し登録無効事由ありということになるべき筋合である。 したがつて、前掲被告ら主張のような理由をもつて原告の本訴請求を不当視することは許されず、被告らの主張2は失当である。 (三)被告らの主張3について 被告らは、被告商標を本件商品に使用するについて先使用権の存在を主張する。 しかし、商標法32条1項の規定に基づく先使用権が成立するためには、少なくとも、当該商標と同一の商標を他人の商標登録出願前から当該商品に使用し、かつその商標が他人の商標登録出願の際に自己の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたことを要するところ、被告らないしはその被承継者が本件商標の登録出願日である昭和二五年七月一九日より前から被告商標と同一の商標を本件商品に使用し、かつその商標が本件商標の登録出願時に自己の業務に係る商品の表示として周知性を獲得していたことを認めるに足りる証拠はない。 したがつて、その余の点につき判断するまでもなく、被告らの主張3は失当である。 五 以上によれば、原告の本件商標権が放棄により消滅するまでの間、いずれも法律上の原因なくして被告会社は本件商標に類似する被告商標を本件商標の指定商品と同一又は類似する商品に使用して右商品を販売し、被告Aは被告商標の使用を被告会社に許諾して使用料を得て来たものであることは明らかであり、そのことによつて被告会社が販売利益を、被告Aが使用料相当の利益を得て来たことは容易に推認しうるところである。 六 不当利得返還請求の金額について検討する。 (一)昭和五〇年一一月一日から同五五年一〇月三一日までの間に被告会社が被告商標を使用した本件商品を販売して得た売上額及び被告Aに支払つた商標使用料の額が原告主張の請求原因5(一)の表(3)ないし(7)記載のとおりであることは、原告と被告会社との間では争いがなく、原告と被告Aとの間では、被告会社代表者本人尋問の結果により真正に成立したものと認める丙第一号証の一ないし五及び同本人尋問の結果によつてこれを認めることができる。 昭和四九年九月一日から同五〇年一〇月三一日及び同五五年一一月一日から同月七日までの間に被告会社が被告商標を使用した本件商品を販売して得た売上額及び被告Aに支払つた商標使用料の額については、これを直接立証する証拠は存在しない。原告は、右期間の売上額について、昭和五〇年一一月一日から同五五年一〇月三一日までの各年度の売上額をグラフにすると直線上に並ぶのでこの直線を延長することによつて推定することができると主張する。なるほど、右昭和五〇年一一月一日から同五五年一〇月三一日までの各年度の売上額をグラフに表すと別紙添付のグラフ記載のとおりであるから、右下りの直線に近い線に概ね添う形で並んでいるといえなくもない。しかし、右五年間の売上額の推移が右のような傾向を示しているといっても、たかだか五年間のことであるから、右期間の前後も同じ直線の延長線上に売上額があつたものと推認するのは早計である。けだし、昭和四九年九月から同五五年一一月までの間被告会社の本件商品の売上額が一方的に減少していつたとの事実を裏付ける証拠は存在せず、かえつて、被告会社代表者本人は、本件商品の売上は昭和五〇年一一月から同五一年一〇月までがピークであつたと供述しており、右供述部分の信用性を否定するだけの事情も見出し難いからである。したがつて、原告の右主張は採用できないが、前記昭和五〇年一一月一日から同五五年一〇月三一日までの間の売上額の推移及び右被告会社代表者本人尋問の結果からすれば、昭和四九年九月一日から同五〇年一〇月三一日までの一四か月間の本件商品の売上額については、少なくともそれに続く三年間すなわち昭和五〇年一一月一日から同五三年一〇月三一日までの年間売上額の平均値程度の年間売上額はあつたものと推認するのが相当である。それによれば右一四か月間の売上額は次の計算式により四二一〇万七三五七円となる。 (48,069,043+31,746,006+28,461,012)÷3×14/12●約42,107,357また、昭和五五年一一月一日から同年一一月七日までの間の本件商品の売上額については、右期間が前年度に接した極わずかの期間であることに照らせば、少なくとも、原告主張の金額である、同年一一月一日から昭和五六年一〇月三一日までの一年間の売上額を前記グラフにより一〇〇〇万円と推定し、これから日割計算によつて求めた金額一九万円を下ることはないものと推認することができる。そして、被告会社代表者本人尋問の結果によれば、昭和四九年九月一日から同五五年一一月七日までの間被告会社が被告Aに支払つてきた被告商標の使用料は本件商品の売上額の一六パーセントであることが認められる(このことは、原告と被告会社の間では争いがない。)から、昭和四九年九月一日から同五〇年一〇月三一日までの間の使用料は、前記認定の右期間の売上額四二一〇万七三五七円に〇・一六を乗じて得られる六七三万七一七七円であると認められる。同様に、昭和五五年一一月一日から同月七日までの間の使用料は、原告主張の三万円を下らないものと認められる。 以上をまとめると、昭和四九年九月一日から同五五年一一月七日までの間に被告会社が本件商品を販売して得た売上額及び被告会社が被告Aに支払つた被告商標の使用料の額は、次のとおりとなる。 <12697-002><12697-003>(二)証人Eの証言によれば、家庭薬においては、一般に製薬メーカーの売上高から原料費、包装材料費、労務費、設備の減価償却等の費用を控除した利益率は売上高の六〇ないし八〇パーセント程度であることが認められるところ、被告会社が本件商品を製造、販売するにあたつて宣伝広告費その他の経費に格別多額の出費をしたとの事情も窺われないから、被告会社は、被告Aに支払つてきた本件商品の売上高の一六パーセントに相当する被告商標使用料を控除してもなお、原告主張のとおり、本件商品の売上高の三割を下らない金額の純利益を本件商品の製造販売によつて得たものと推認するのが相当である。 そうすると、昭和四九年九月一日から同五五年一一月七日までの間に被告会社が本件商品を製造、販売して得た純利益の額は、同期間の売上額一億八四〇九万四九七九円の三割である五五二二万八四九三円であると認められる。 (三) いずれも成立に争いのない甲第二号証の一、同第一二号証の一ないし三、 乙第三五号証の一、二、第三六号証、弁論の全趣旨により真正に成立したものと認める甲第一三号証の一ないし三、第三二ないし第四二号証の各一、二、証人Eの証言によつて真正に成立したものと認める甲第四九号証の一ないし六及び同証言並びに弁論の全趣旨によれば、原告はその前身である樋屋合資会社をも通じると明治年代から「樋屋竒應丸」の名称の漢方小児用薬剤を製造、販売してきており、原告の「樋屋竒應丸」は需要者の間に広く知られた商品であること、原告の「樋屋竒應丸」は主として西日本で販売されており、昭和五〇年代前半では近畿や九州で販売されている漢方小児薬の九〇パーセント前後のシエアがあつたこと、本件商標そのものは昭和五〇年代頃には原告の「樋屋竒應丸」の包装箱には使用されてはいなかつたが、本件商標は「樋屋」「竒應丸」の各文字を要部とするものであり、多数の連合商標を有するものであるところ、右要部を要部とする商標は右の昭和五〇年代頃にも原告の「樋屋竒應丸」の包装箱に使用されていたし、原告の「樋屋竒應丸」の商標として著名であつたこと、一方被告会社が製造、販売している本件商品たる竒應丸は国内ではもつぱら西日本で販売されていること、昭和五〇年代前半の近畿、九州地区で販売された漢方小児薬中のシエアは高くて七パーセント位、低いと〇・五パーセント以下であつたこと、被告商標も前記本件商標の要部を要部とする商標であり、そのため需要者の中には現実に被告会社の竒應丸を原告の「樋屋竒應丸」と誤認して購入する例も少なからず発生していたこと、被告会社が被告Aに支払つてきた被告商標の使用料である売上額の一六パーセントという数字は一般の家庭薬の場合の商標使用料に比して相当高いことが認められ、右認定の事実を左右するに足りる証拠はない。 右認定の事実によれば、被告会社による本件商品は売上にはもつぱら被告商標の使用が寄与したものと推認することができ、前記のとおり昭和四九年九月一日から同五五年一一月七日までの間被告らが原告の本件商標権を侵害したことにより得た利得の額は、被告Aについては前記被告商標使用料として受領した二九四五万四七九七円、被告会社については前記被告商品の製造、販売によつて得た利益額である五五二二万八四九三円であると認められる。一方、前記認定の事実によれば、原告は、被告らの本件商標権侵害行為がなければ、その分原告の「樋屋竒應丸」を製造、販売することができ、被告らの右利得合計額程度の利益をあげられたであろうことは推認するに難くなく、被告Aとの関係ではその利得額と同額の二九四五万四七九七円が、被告会社との関係ではその利得額と同額の五五二二万八四九三円が、 それぞれの利得と直接の因果関係のある原告の損失であると認めるのが相当である。 そうだとすれば、原告に対し、被告会社は五五二二万八四九三円、被告Aは二九四五万四七九七円の各不当利得金返還義務を負うものというべきである。 七 以上の次第で、原告の本訴請求は、被告会社に対し不当利得金五五二二万八四九三円、被告Aに対し不当利得金二九四五万四七九七円、及び各金員に対する本件訴状送達の日の翌日であることが記録上明らかな昭和五九年九月四日から各完済まで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから右限度でこれを認容し、その余は失当であるから棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法92条本文、89条、93条1項本文を仮執行の宣言につき同法196条をそれぞれ適用して、主文のとおり判決する。 |
| 裁判官 | 露木靖郎 |
|---|---|
| 裁判官 | 小松一雄 |
| 裁判官 | 青木亮 |