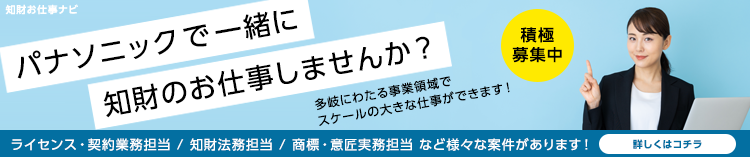偙偺敾椺偵偼丄壓婰偺敾椺丒怰寛偑娭楢偟偰偄傞偲巚傢傟傑偡丅
| 怰敾斣崋乮帠審斣崋乯 | 僨乕僞儀乕僗 | 尃棙 |
|---|---|---|
| 徍榓47儚2732 | 敾椺 | 彜昗 |
| 徍榓43僱1937 | 敾椺 | 彜昗 |
| 徍榓58儚27 | 敾椺 | 彜昗 |
| 暯惉5儚1111 | 敾椺 | 彜昗 |
| 暯惉17儚25426懝奞攨彏惪媮帠審 | 敾椺 | 彜昗 |
| 娭楢儚乕僪 | 朄忋偺彜昗偺巊梡 / 幆暿椡 / 曪憰 / 弌強昞帵婡擻 / 昳幙曐徹婡擻 / 幙曐徹婡擻 / 幆暿婡擻 / 巜掕彜昳 / 晛捠柤徧(3忦1崁1崋) / 晛捠偵梡偄傜傟傞曽朄 / 廃抦惈 / 崿摨傪惗偢傞偍偦傟(崿摨傪惗偠傞偍偦傟) / 晄惓栚揑(晄惓偺栚揑) / 晄惓嫞憟偺栚揑 / 屭媞媧堷椡(僌僢僪僂傿儖) / 椶帡惈(椶斲敾抐) / 愭巊梡(32忦) / 奜娤(奜娤椶帡) / 徧屇(徧屇椶帡) / 娤擮(娤擮椶帡) / 敾掕 / 彜昗偺岠椡 / 嵎巭 / 楢崌彜昗 / 椶帡彜昗 / 愭巊梡尃 / 宲懕 / 旕椶帡 / 彜崋 / |
|---|
| 尦杮PDF |
嵸敾強廂榐偺慡暥PDF傪尒傞
|
|---|---|
| 尦杮PDF |
嵸敾強廂榐偺暿巻1PDF傪尒傞
|
| 帠審 |
徍榓
50擭
(僱)
2172崋
|
|---|---|
| 嵸敾強偺僨乕僞偑懚嵼偟傑偣傫丅 | |
| 嵸敾強 | 搶嫗崅摍嵸敾強 |
| 敾寛尵搉擔 | 1981/03/30 |
| 尃棙庬暿 | 彜昗尃 |
| 慽徸椶宆 | 柉帠壖張暘 |
| 庡暥 |
旐峊慽恖乮晬懷峊慽恖乯偺晬懷峊慽傪婞媝偡傞丅 峊慽恖乮晬懷旐峊慽恖乯偺峊慽偵婎偯偒尨敾寛拞峊慽恖乮晬懷旐峊慽恖乯攕慽晹暘傪庢徚偡丅 旐峊慽恖乮晬懷峊慽恖乯偺怽惪傪媝壓偡傞丅 慽徸旓梡偼戞堦丄擇怰傪捠偠偡傋偰旐峊慽恖乮晬懷峊慽恖乯偺晧扴偲偡傞丅 |
| 帠幚媦傃棟桼 | |
|---|---|
|
摉帠幰偺媮傔偨嵸敾
堦 峊慽恖(晬懷旐峊慽恖) 庡暥摨巪偺敾寛丅 擇 旐峊慽恖(晬懷峊慽恖) 乽尨敾寛拞旐峊慽恖(晬懷峊慽恖)攕慽晹暘傪庢徚偡丅 峊慽恖(晬懷旐峊慽恖)偼丄暿巻栚榐(傾)偺彜崋傪巊梡偟偰偼側傜側偄丅 峊慽恖(晬懷旐峊慽恖)偼丄暿巻栚榐(僀)偺昗復傪丄偦偺惢憿偵學傞報復偺曪憰巻戃丄報復偵揧晅偡傞娪掕彂丒愢柧暥枖偼報復偺峀崘偵丄摨栚榐(僂)偺昗復傪塃愢柧暥枖偼峀崘偵丄摨栚榐偺(僉)丄(僋)偺奺昗復傪塃峀崘偵丄偦傟偧傟巊梡偟偰偼側傜側偄丅 慽徸旓梡偼戞堦丄擇怰傪捠偠峊慽恖(晬懷旐峊慽恖)偺晧扴偲偡傞丅乿偲偺敾寛丅 |
|
|
怽惪偺棟桼
堦 晄惓嫞憟杊巭朄偵婎偯偔惪媮1 旐峊慽恖偺抧埵摍(堦) 旐峊慽恖偼丄偐偹偰傛傝尐彂廧強抧媦傃搶嫗搒峘嬫偵揦曑傪愝偗丄報復偵娭偡傞堈妛偵懃偮偨報復偺惢憿斕攧傪嬈偲偟偰偄偨幰偱偁傞偑丄徍榓巐敧擭堦寧塃塩嬈傪姅幃夛幮擔杮報憡妛夛(埲壓乽慽奜夛幮乿偲偄偆丅)偵捓戄偟偨丅塃捓戄偺懳徾偵學傞塩嬈嵿嶻偺庡偨傞傕偺偼丄旐峊慽恖偑杮審偱庡挘偡傞丄彜崋丄搊榐彜昗媦傃枹搊榐彜昗側偳偱偁傞丅旐峊慽恖偑帺傜塩嬈偟棃偨偮偨帪婜偵偍偄偰傕丄傑偨丄偙傟傪捓戄偟偨屻偵偍偄偰傕丄塃塩嬈偺昞帵媦傃彜昳偺昞帵偲偟偰偦傟偧傟屻弎偺奺昗復偑巊梡偝傟崱擔偵帄偮偰偄傞傕偺偱偁傞丅 (擇) 晄惓嫞憟杊巭朄偺婎杮揑峔惉偼丄側傞傎偳塩嬈庡懱娫偺揔惓側嫞嬈拋彉傪掕傔傞傕偺偱偁傞丅偟偐偟丄偙偺偙偲偼丄嫞嬈庡懱娫偵偍偄偰掕傔傜傟傞塩嬈忋偺棙塿椺偊偽摨朄戞1忦戞1崁戞1崋丄戞擇崋偺廃抦昞帵傪撈愯揑偵巊梡偡傞尃棙偑尰嵼偺庢堷幮夛偺拞偱撈棫偺嵿嶻尃偲偟偰庢堷偺媞懱偲偝傟傞偙偲傪斲掕偡傞傕偺偱偼側偄丅摿嫋尃丄彜昗尃側偳偺岺嬈強桳尃偑撈棫偺嵿嶻尃偲偟偰忳搉丒捓戄偺栚揑偲側傞偺偲摨偠偔丄庢堷幮夛偵偍偄偰塃岺嬈強桳尃偵弨偢傞庢堷壙抣傪擣傔傜傟偨塃偺晄惓嫞憟杊巭朄忋偺棙塿側偄偟尃棙偑捓戄偺栚揑偲偝傟傞偙偲傪朄偑嫋梕偟偰偄傞偙偲偼摉慠偱偁傞丅彜昗朄戞32忦戞1崁偑乽摉奩嬈柋傪彸宲偟偨幰偵偮偄偰傕丄摨條偲偡傞丅乿偲掕傔偰偄傞偙偲傕丄偙偺偙偲傪摉慠偺慜採偲偟偰偄傞偺偱偁傞丅 傑偨丄旐峊慽恖偼丄塩嬈偺捓戄恖偲偟偰丄慽奜夛幮偵懳偟塩嬈嵿嶻偺毷懝柵幐傪杊巭偡傋偔偁傜備傞慬抲傪島偢傞媊柋傪晧偆傕偺偱偁偮偰丄偙傟傪懹傝丄偦偺毷懝柵幐傪曻抲偡傞偲偒偼丄捓椏尭妟偺懝幐傪栔傞偺偱偁傞丅 埲忋偺偙偲偐傜丄塩嬈偺捓戄恖傕傑偨晄惓嫞憟杊巭朄戞1忦偵婎偯偔嵎巭惪媮偺偱偒傞偙偲偼摉慠偱偁傞丅 2 旐峊慽恖偺昗復偲偦偺廃抦惈 旐峊慽恖偼丄偐偹偰傛傝丄帺屓偺塩嬈偱偁傞偙偲傪帵偡昞帵偲偟偰暿巻栚榐(A)偺昗復(埲壓扨偵乽(A)昗復乿偲偄偆丅)傪丄傑偨丄帺屓偺彜昳偱偁傞偙偲傪帵偡昞帵偲偟偰摨栚榐(B)側偄偟(E)偺昗復(埲壓偦傟偧傟偵懳墳偟偰乽(B)昗復乿乽(E)昗復乿側偳偲偄偆丅)傪桳偟丄偙傟傪挿擭偵傢偨傝巊梡偟偰棃偨偙偲偵傛傝丄抶偔偲傕徍榓巐屲擭枛摉帪(廬慜抶偔偲傕徍榓嶰乑擭偙傠偲庡挘偟偨偑丄偙偺傛偆偵夵傔傞丅)偵偍偄偰丄慡崙偵峀偔擣幆偝傟傞偵帄偮偰偄偨丅 偙偺偙偲傪徻弎偡傞偲丄師偺偲偍傝偱偁傞丅 (堦) 乽報憡妛乿偺摿庩惈偵偮偄偰 (A)昗復側偄偟(E)昗復偼丄偡傋偰乽報憡妛乿傪娷傓傕偺偱偁傞偑丄乽報憡妛乿側傞岅偼丄乽報憡乿偺岅偲偲傕偵丄柧帯巐乑擭偙傠丄旐峊慽恖偺慶晝亂A亃偵傛偮偰嶌傜傟偨憿岅偱偁偮偰丄寛偟偰晛捠柤徧偱偼側偄丅 偡側傢偪丄報復偺媑嫢敾抐傪堄枴偡傞岅偲偟偰偼丄廬棃嵟傕堦斒揑側傕偺偲偟偰丄乽敾偼傫偠乿丄乽敾宍愯乿丄乽報愯乿丄乽報宍愯乿偑梡偄傜傟偰偄偨丅亂A亃偼丄敾偼傫偠偺媄弍偺偆偪帺屓偑彸宲偟偨撈帺偺媄弍偵婎偯偔報復偵乽報憡妛乿偲柦柤偟丄偦偺屻丄亂A亃偺愯堈弍偼丄報憡妛偺昗復偲偲傕偵撈愯揑偵旐峊慽恖偵宲彸偝傟丄懠偵報復偺愯堈傪峴偆幰偼杦傫偳側偔丄傑偨丄乽報憡妛乿偺昗復傪梡偄傞幰偼丄偦偺梡朄偺偄偐傫傪栤傢偢奆柍偱偁偮偨丅偲偙傠偑丄徍榓巐榋擭偙傠丄挙報偺帺摦婡夿偑晛媦偟偨偙偲偵傛傝丄峛晎抧曽偵廤拞偡傞報崗巘偑戝検幐怑偡傞偵媦傃丄偙傟傪桱椂偟偨摨抧曽偺報復嬈幰偑堦惸偵旐峊慽恖偺柤惡偵曋忔偟偰報復偺愯堈傪昗炘偟丄捠怣斕攧偺曽朄偵傛傝崅壙側報復傪戝検偵斕攧偡傞偵帄傝丄報憡妛偺昗復傪朻梡偡傞幰偑尰傢傟丄偮偄偵丄嶨帍傗怴暦偺峀崘棑偵偼報憡妛偺昗復偑堨傟丄偁偨偐傕乽報憡妛乿枖偼乽報憡乿偲偄偆昗復偑報復偺堈愯枖偼偙傟偵婎偯偔報復偺晛捠柤徧偱偁傞偐偺傛偆偵榝傢偝傟傞忣嫷偑嶌傜傟偨偺偱偁傞丅偟偐偟丄徍榓巐敧擭枛偙傠偵側傞偲夁摉嫞憟偲慹惢棎憿偵傛傝丄偙傟傜偺幰偼丄怣梡傪幐捘偟宱塩擄偲側偮偰徚偊嫀傝丄尰嵼乽報憡妛乿偺昗復傪梡偄偰報復偺斕攧傪峴偍偆偲偡傞幰偼丄峊慽恖偺傎偐偼丄悢恖偺嬈幰偑偁傞偵偡偓側偄丅偦偟偰丄旐峊慽恖偼丄偙傟傜偺幰偵懳偟塃昗復偺巊梡偺嵎巭傪慽媮偟偨偲偙傠丄峊慽恖傪彍偒丄杦傫偳榓夝偵傛傝夝寛偡傞偵帄偮偨丅 偙傟傪梫偡傞偵丄乽報憡妛乿偺報娪偲偄偊偽丄旐峊慽恖(慽奜夛幮愝棫屻偼丄摨夛幮)偺惢嶌偵學傞桇摦旤傪傕偪丄偐偮丄強帩幰偺惈暿丄惗擭寧擔偦偺懠偺梫審傪偦側偊偨奺恖偵摿桳偺報偑梌偊傜傟傞傕偺偲偟偰丄彜昳偺弌強昞帵婡擻媦傃昳幙曐徹婡擻傪敪婗偟偰偄傞偺偱偁傞丅 偙偺傛偆偵丄乽報憡妛乿偺岅偼傕偪傠傫偺偙偲丄乽報憡乿偺岅傕壗傜晛捠柤徧偲偟偰梡偄傜傟傞傕偺偱偼側偄偑丄偙偺偙偲偼丄峀帿墤偵傕乽報憡妛乿偺岅偑宖嵹偝傟偰偍傜偢丄傑偨丄乽報憡乿偵偮偄偰偼宖嵹偝傟偰偼偄傞偑丄乽僀儞僝僂乿偲敪壒偟丄偦偺岅媊傕丄暓嫵梡岅偱偁偮偰丄塃偵弎傋偨偙偲偲偼柍娭學偺傕偺偱偁傞偙偲媦傃屻婰偺偲偍傝暿巻栚榐(F)偺昗復(埲壓乽(F)彜昗乿偲偄偆丅)偑彜昗搊榐傪宱偰偄傞偙偲偐傜傕柧傜偐偱偁傞丅 (擇) 旐峊慽恖偼丄塃偵弎傋偨報憡妛偵懃偮偨報復傪惢憿斕攧偟丄徍榓巐幍擭偺堦擭娫偵嶰屲乑乑屄梋偺報復傪攧傝忋偘傞偵帄偮偰偄偨丅傑偨丄旐峊慽恖偼丄徍榓堦堦擭挊彂乽報復偺媑嫢偺尋媶乿傪敪昞偟丄摨挊彂偼丄埲屻廫悢斉擇乑枩晹傪慡崙偵傢偨偮偰敪峴偝傟丄旐峊慽恖偼丄徍榓擇嬨擭偙傟傪乽報復偺媑嫢偺夝愢乿偲夵傔丄偦偺姫枛偵A昗復傪塩嬈偺昞帵偲偟偰梡偄丄旐峊慽恖偺報復偺愯堈弍偱偁傞報憡妛偼丄塃挊彂偺傎偐丄怴暦丄嶨帍丄僥儗價摍儅僗僐儈儐僯働乕僔儓儞偵傛偮偰徯夘丄峀崘偝傟偨丅 師偵丄彜昳昞帵偲偟偰偺(B)側偄偟(E)昗復傕丄塃(A)昗復偲偲傕偵徯夘丄峀崘偝傟丄傑偨丄旐峊慽恖偑偦偺惢憿偵學傞報復傪斕攧偡傞嵺偵偼丄(B)丄 (D)丄(E)偺奺昗復傪丄塃報復傪擺傔偨巻戃偵婰嵹偟偰梡偄丄(C)昗復偼丄 報嶞暔摍傪巜掕彜昳偲偡傞搊榐彜昗偱偁傞偙偲偐傜丄旐峊慽恖偺慜婰挊彂偺斕攧丄 峀崘傗報憡妛尋媶惉壥偺敪昞摍偵摉傝丄報嶞暔偵梡偄偰偄偨丅 (嶰) 旐峊慽恖偺曐桳偡傞奺昗復偼丄報娪傪懳徾暔昳偲偟偰偄傞娭學忋丄斕攧悢検摍偵偍偄偰斾妑揑彮側偄偲偟偰傕丄庢堷幰廀梫幰娫偵偍偄偰偼丄偦偺抦柤搙怹摟搙偼戝偒偄偺偱偁傞丅偡側傢偪丄恖偼丄報娪傪堦搙媮傔傞偲憡摉挿婜娫丄懡偔偼堦惗巊梡偡傞傕偺偱偁傞偐傜丄廀梫悢検偑挊偟偔惂尷偝傟傞偆偊丄偙傟傪媮傔傞幰偼丄帺傜偺塣柦傪戸偡傞偵懌傝傞椙偄報娪傪帩偪偨偄偲婓朷偡傞偺偱丄捠忢偺彜昳偵懳偡傞埲忋偵拲堄椡傪摥偐偣傞傕偺偱偁傞偐傜丄堦斒偺塩嬈昞帵傗彜昳昞帵偵斾偟偰婰壇惈媦傃揱払惈偵偍偄偰奿抜偺憡堘偑偁傞丅偟偨偑偮偰丄峀崘夞悢丄斕攧悢検摍偺傒偱廃抦惈傪敾抐偡傞偙偲偼偱偒側偄丅 3 峊慽恖偺昗復巊梡(堦) 峊慽恖偼丄報復偺惢憿斕攧偺嬈傪栚揑偲偟偰丄徍榓巐幍擭敧寧嶰堦擔愝棫偝傟偨夛幮偱偁傝丄徍榓巐敧擭偙傠偐傜丄怴暦摍偺峀崘棑偵報復偺斕攧峀崘傪宖嵹偟丄戝乆揑偵報復偺惢憿斕攧傪峴偮偰偄傞丅 (擇) 峊慽恖偼丄偦偺塩嬈傪昞帵偡傞偨傔偵丄搊榐彜崋偱偁傞暿巻栚榐(傾)偺彜崋(埲壓乽(傾)昗復乿偲偄偆丅)偺傎偐丄峊慽恖偺惢憿偟偨報復偺曪憰梡巻戃丄娪掕彂丄愢柧暥媦傃峀崘拞偵摨栚榐(僀)偺昗復(埲壓乽(僀)昗復乿偲偄偆丅)傪巊梡偟偰偍傝丄傑偨丄偦偺彜昳傪昞帵偡傞偨傔偵(僀)昗復傪塃偺偲偍傝奺暔審偵巊梡偟偰偄傞傎偐丄摨栚榐(僂)偺昗復(埲壓乽(僂)昗復乿偲偄偆丅)傪愢柧暥枖偼峀崘暥偵丄摨栚榐(僄)側偄偟(僋)偺昗復(埲壓偦傟偧傟偵懳墳偟偰乽(僄)昗復乿丄乽(僋)昗復乿側偳偲偄偆丅)傪峀崘偵巊梡偟偰偄傞丅 4 椶帡惈(堦) (傾)昗復(姅幃夛幮廆壠擔杮報憡嫤夛)偲(A)昗復(擔杮報憡妛夛) (傾)昗復拞乽姅幃夛幮乿偺晹暘偼丄彜朄忋晅壛偡傞偙偲偑媊柋偯偗傜傟偰偄傞偺偱晅壛偟偨偵偡偓側偄傕偺偱偁傞偐傜丄(僀)昗復偲(A)昗復偲偺懳斾娭學偲堎側傞偲偙傠偑側偄丅偲偙傠偱丄塃椉幰偼丄師偵弎傋傞偲偍傝椶帡偺昗復偱偁傞偐傜丄寢嬊丄(傾)昗復偲(A)昗復偲偼椶帡偡傞丅 (擇) (僀)昗復(廆壠擔杮報憡嫤夛)偲(A)丄(B)昗復(擔杮報憡妛夛) 昗復偺椶斲偼丄彜昳偲偺娭學傪峫椂偟偰嬶懱揑偵懳斾敾抐偝傟側偗傟偽側傜側偄丅杮審偵偍偄偰傕丄乽妛夛乿偺晹暘偲乽嫤夛乿偺晹暘偲傪懳斾偡傟偽丄奜娤丄徧屇丄娤擮偺偄偢傟傕椶帡偟側偄偲擣傔傜傟傞偑丄彜昳偑報娪偱偁傝丄偟偐傕乽報憡乿偺暥帤傪娷傒丄摿偵乽擔杮報憡妛夛乿偲乽擔杮報憡嫤夛乿偲寢崌偝傟傞偲偒偼丄庢堷幰廀梫幰偼丄乽擔杮報憡乧乧夛乿偺暥帤傪傛傝嫮偔擣幆偡傞丅摿偵丄杮審偱栤戣偲偝傟傞奺昗復偵娭偡傞庢堷幰廀梫幰偼丄報復偺愯堈偵嫮偄嫽枴傪書偄偰偍傝丄報娪偺憡傪峫椂偟偨報傪媮傔偰偙傟傜偺昗復偵愙偡傞傕偺偲峫偊傜傟傞丅偦偟偰丄偦偺傛偆側応崌丄奺峔惉暥帤偺昞尰椡偵寉廳偺嵎偑楌慠偲偟偰偄傞偲偒偵偼丄 斾妑揑寉帇偝傟傞暥帤偵憡堘偑偁偮偰傕懠偺暥帤偵偮偄偰徧屇丄娤擮偑崜帡偟偰偄傟偽丄慡懱偲偟偰椶帡偟偰偄傞偲偄偆傋偒偱偁傞丅偦偆偡傞偲丄庢堷幰廀梫幰偼丄 報憡妛側傞暥帤偵堦憌拲栚偟丄報憡妛偲報憡偲偺帤媊揑嵎堎偵偮偄偰尩枾側敾抐傪壛偊偰嬫暿偟側偄傕偺偲峫偊傜傟傞丅 師偵丄乽嫤夛乿偲乽妛夛乿偲偵偮偄偰傒傞偵丄傑偢丄尨敾寛偼丄乽嫤夛乿偑丄夛堳偑嫤椡偟偰愝棫丒堐帩偡傞慻怐懱傪堄枴偟丄乽妛夛乿偑妛幰憡屳娫偺楢棈丒尋媶偺懀恑丄妛栤偺怳嫽傪恾傞偨傔偺慻怐懱傪堄枴偡傞偲敾帵偡傞丅偟偐偟丄偦傟偼丄 塃奺昗復偺偆偪偐傜嫤夛偲妛夛偺傒傪拪弌偟偰偦偺堄枴傪帿揟偵婎偯偄偰婰弎偟偨偵偡偓偢丄昗復慡懱偺拞偵埵抲晅偗偨娤擮偺攃埇偱偼側偄丅(A)昗復偵妛夛側傞岅偑梡偄傜傟偰偄偰傕丄偦傟偼乽報憡乿偲寢傃偮偒丄報憡偵娭偡傞妛夛偲娤擮偝傟偰偙偦堄枴偑偁傞偺偱偁傝丄報憡偺媑嫢偵娭偡傞妛栤偼丄壗傜嬤戙壢妛偵婎偯偔懱宯揑側擣幆偲偟偰娤擮偝傟傞梋抧偼側偄丅偟偐傕丄乽擔杮報憡妛夛乿側傞昗復偼丄 奜側傜偸塩嬈昞帵偲偟偰巊梡偝傟偰偄傞偺偱偁偮偰丄偦偙偵偼丄塩棙偲偟偰報復偺惢嶌丒斕攧傪峴偆庡懱偲偟偰偺娤擮偑戝慜採偲側偮偰偍傝丄尨敾寛偺偄偆乽妛夛乿偺杮棃偺堄媊丒娤擮偲偼憡梕傟側偄傕偺偱偁傞丅偟偨偑偮偰丄塃奺昗復傪懳斾偡傞偵摉傝丄乽嫤夛乿偲乽妛夛乿偺憡堘偺傒傪拪弌偟偰偦偺娤擮揑椶斲傪榑偢傞偙偲偼岆傝偱偁傞丅偦偆偡傞偲丄(僀)昗復偲(A)丄(B)昗復偲偼丄乽報憡乿偲偄偆乽報復偺媑嫢枖偼偦偺敾抐乿偲偄偆娤擮偵偍偄偰嬤帡偟丄傑偨丄擔杮報憡妛夛偑丄 壗傜妛栤揑尋媶傪峴偆偺偱偼側偔丄旐峊慽恖偑惢嶌偟偨報復傪強帩偡傞幰偑夛堳偲側傝旐峊慽恖偺愯堈偺岠擻傪曬崘丒妋擣偟偦偺棟夝傪怺傔偙傟傪晛媦偝偣傞偙偲傪栚揑偲偡傞抍懱偱偁傞偙偲偲憡傑偮偰丄庢堷幰廀梫幰娫偵塃奺昗復偵偮偒岆擣崿摨傪惗偢傞偍偦傟偑偁傞丅 (嶰) (僂)昗復(報憡妛)偲(C)昗復(報憡妛) (僂)昗復偑(C)昗復偲摨堦傕偟偔偼椶帡偡傞傕偺偱偁傞偙偲偼懡尵傪梫偟側偄丅 (巐) (僄)昗復(報憡妛偺夛幮報)丒(僆)昗復(報憡妛偺報娪)丒(僇)昗復(報憡妛報娪)偲(D)昗復(報憡妛報復) 乽報憡妛乿側傞岅偑丄旐峊慽恖偺慶晝亂A亃偺憿岅偱偁傝丄愱傜旐峊慽恖偺搘椡偵傛偮偰丄旐峊慽恖偺彜昳幆暿婡擻傪桳偡傞昗復偲偟偰廃抦惈傪妉摼偡傞偵帄偮偨傕偺偱偁偮偰丄晛捠柤徧偱側偄偙偲偼丄婛偵弎傋偨偲偙傠偱偁傝丄偟偨偑偮偰丄 (僄)丄(僆)丄(僇)偺奺昗復偺梫晹偼乽報憡妛乿偺晹暘偱偁傝丄偙傟偵乽偺夛幮報乿丄乽偺報娪乿丄乽報娪乿偺岅傪晅壛偟偰傕丄摨媊斀暅偵傎偐側傜偢丄偙傟傜偺岅偑晅壛偝傟偰傕丄昗復慡懱偺娤擮忋偺憡堘傪偒偨偝側偄丅梫偡傞偵丄塃奺昗復偺彜昳昞帵偺婡擻偼乽報憡妛乿偺晹暘偺傒偱偁傝偙傟偵偮偄偰椶斲傪榑偢傟偽懌傝傞偺偱偁傝丄偟偨偑偮偰丄塃奺昗復偼丄偡傋偰摨堦偱偁傞丅壖偵偦偆偱側偄偲偟偰傕丄娤擮忋椶帡偡傞偙偲偼柧傜偐偱偁傞丅 (屲) (僉)昗復(報憡妛偺尮)丒(僋)昗復(報憡偺憤杮壠)偲(E)昗復(報憡妛廆壠) 偙傟傜奺昗復偺梫晹偑乽報憡妛乿枖偼乽報憡乿偱偁傝丄乽報憡妛乿丄乽報憡乿偑偄偢傟傕旐峊慽恖偺彜昳幆暿婡擻傪桳偟偰偄傞傕偺偱偁傞偙偲偼婛偵弎傋偨偲偙傠偱偁傞丅傑偨丄乽廆壠乿偺堄枴偼丄乽廆庡偨傞壠丄杮壠丄偦偆偐乿偱偁傝丄乽尮乿偵偼丄乽暔帠偺婲傞偼偠傔丄婲尮乿偺堄枴偑娷傑傟傞丅偦偟偰丄乽報憡妛偺尮乿偲偟偰梡偄傞側傜偽丄偦傟偼報憡妛偺婲尮偵婎偯偔堄媊傪傕偪丄乽報憡妛廆壠乿偑塃偺偲偍傝乽報憡妛偺杮壠乿偲偟偰偺娤擮傪桳偡傞偺偱偁傞偐傜丄偲傕偵乽報憡妛乿偵娭偡傞揱摑偺彸宲偲偦偺惓摑惈傪堄枴偡傞傕偺偲偟偰丄椉幰偼椶帡偡傞丅傑偨丄 乽憤杮壠乿偲偼丄乽懡偔偺暘壠偺暘傟弌偨杮壠丄偍偍傕偲偺杮壠乿傪堄枴偟丄偙傟傪乽報憡偺憤杮壠乿偲偟偰梡偄傞偺偱偁傞偐傜丄報復偺媑嫢敾抐偵娭偡傞揱摑偺宲彸偲偦偺惓摑惈傪堄枴偡傞傕偺偲偟偰丄椉幰偼椶帡偡傞丅 5 晄惓偺栚揑 峊慽恖偼丄慜弎偺偲偍傝旐峊慽恖偺搘椡偵傛傝廃抦惈傪妉摼偟偨昗復偵椶帡偡傞奺昗復傪巊梡偟偰丄峀崘愰揱傪偟丄戝乆揑偵報復偺惢憿斕攧傪峴偮偰偄傞偙偲偼丄 旐峊慽恖偺塩嬈偺怣梡偲柤惡傪棙梡偟傛偆偲偡傞晄惓偺栚揑偑偁傞偙偲偼柧傜偐偱偁傞丅 6 壖張暘偺昁梫惈 嬤帪偺媫懍側報復僽乕儉偺敪揥偲峊慽恖偺慜婰奺巊梡昗復傪傕偮偰偡傞戝乆揑愰揱偲偵傛傝丄旐峊慽恖偺挿擭偺搘椡偵傛偮偰宍惉偝傟偨怣梡偡側傢偪慜弎偺塩嬈昞帵丒彜昳昞帵偵傛傞屭媞媧堷椡傗弌強昞帵婡擻偼丄媫懍偵尭戅偟偮偮偁傝丄憗媫偵偙傟傪嵎巭傔側偗傟偽丄旐峊慽恖偵偍偄偰夞暅晄壜擻側懝奞傪栔傞偍偦傟偑偁傞丅 7 傛偮偰丄旐峊慽恖偼丄峊慽恖偵懳偟丄晄惓嫞憟杊巭朄戞1忦戞1崁戞2崋偵婎偯偔丄巊梡嵎巭惪媮尃曐慡偺偨傔(傾)丄(僀)偺奺昗復偺巊梡偺嵎巭傪丄摨朄戞1忦戞1崁戞1崋偵婎偯偔巊梡嵎巭惪媮尃曐慡偺偨傔丄(僀)丄(僂)丄(僄)丄 (僆)丄(僇)丄(僉)丄(僋)偺奺昗復偺巊梡偺嵎巭傪偦傟偧傟媮傔傞丅 擇 彜昗朄偵婎偯偔惪媮1 旐峊慽恖偺彜昗尃 旐峊慽恖偼丄 (堦) 暿巻栚榐(F)偺偲偍傝乽報憡妛乿偺暥帤傪墶彂偒偟偰側傝丄巜掕彜昳傪戞擇屲椶乽報復乿偲偡傞搊榐戞堦堦乑擇乑榋嬨崋彜昗(弌婅恖亂B亃丄弌婅擔徍榓巐幍擭敧寧擇嬨擔丄弌婅岞崘擔徍榓巐嬨擭嶰寧巐擔丄愝掕搊榐擔徍榓屲乑擭堦寧榋擔丅埲壓偙傟傪乽(F)彜昗乿偲偄偆丅)偺彜昗偵偮偄偰丄弌婅拞偱偁偮偨徍榓巐嬨擭擇寧擇屲擔丄亂B亃傛傝偦偺彜昗搊榐弌婅偵傛傝惗偠偨尃棙傪丄慽徸忋偺榓夝偵傛傝丄屻婰(G)彜昗偲偲傕偵丄屲乑乑枩墌偱忳傝庴偗丄強掕偺庤懕傪宱偰庢摼偟丄 (擇) 暿巻栚榐(G)偺偲偍傝乽擔杮報憡妛夛乿偺暥帤傪廲彂偒偟偰側傝丄巜掕彜昳傪戞擇屲椶乽報復偦偺懠杮椶偵懏偡傞彜昳乿偲偡傞搊榐戞嬨屲嬨榋堦乑崋彜昗(弌婅恖亂B亃丄弌婅擔徍榓巐巐擭堦堦寧擇敧擔丄弌婅岞崘擔徍榓巐榋擭幍寧擇嬨擔丄愝掕搊榐擔徍榓巐幍擭巐寧擇巐擔丅埲壓偙傟傪乽(G)彜昗乿偲偄偆丅)偺彜昗尃傪丄慜婰偺偲偍傝徍榓巐嬨擭擇寧擇屲擔亂B亃傛傝忳傝庴偗丄摨擭敧寧敧擔偦偺巪偺搊榐傪宱偰庢摼偟偨丅 2 峊慽恖偺昗復巊梡(堦) 峊慽恖偼丄慜弎偺偲偍傝(僂)丄(僄)丄(僆)丄(僇)偺奺昗復傪峀崘拞偵梡偄偰巊梡偟偰偄傞丅 峊慽恖偼丄塃奺昗復偼偄偢傟傕婰弎揑偵梡偄偰偄傞傕偺偱偁偮偰丄彜昗偲偟偰巊梡偟偰偄傞傕偺偱偼側偄偲偄偆偑丄(僄)丄(僆)丄(僇)偺奺昗復偼丄椺偊偽丄 乽柧帯僠儓僐儗乕僩乿丄乽怷塱僉儎儔儊儖乿側偳偲婳傪堦偵偡傞彜昗偲彜昳偲傪寢崌昞帵偟偨傕偺偱偁傝丄彜昗偺揟宆揑巊梡椺偱偁傞丅峊慽恖偼丄塃奺昗復偵傛偮偰丄(F)彜昗偱偁傞乽報憡妛乿偺柤惡偵曋忔偟傛偆偲偡傞堄恾偼柧敀偱偁傝丄偨偲偊愢柧暥偱偁偮偰傕丄報復偺斕攧傪彆挿偡傞偨傔偵彜昳偲寢崌偝偣偰婰嵹偟偰偄傞埲忋丄彜昗偺巊梡偱偁傞偙偲偼柧傜偐偱偁傞丅 (擇) 旐峊慽恖偼丄慜弎偺偲偍傝(僀)昗復傪報娪偵娭偡傞峀崘媦傃愢柧暥拞摍偵梡偄偰巊梡偟偰偄傞丅 3 椶帡惈(堦) (僂)丄(僄)丄(僆)丄(僇)偺奺昗復偲(F)彜昗 (僂)偺昗復偲(F)彜昗偲偑丄娤擮丄徧屇媦傃奜娤偺偄偢傟偺揰偵偍偄偰傕椶帡偡傞偙偲偼懡尵傪梫偟側偄丅 師偵丄乽報憡妛乿偑丄偦傟帺懱旐峊慽恖偺彜昳偱偁傞偙偲偺幆暿椡傪桳偡傞傕偺偱偁傞偙偲媦傃(僄)丄(僆)丄(僇)偺奺昗復偺梫晹偑乽報憡妛乿偺晹暘偱偁傝丄偙傟偵乽偺夛幮報乿丄乽偺報娪乿丄乽報娪乿偺岅傪晅壛偟偰傕丄昗復慡懱偺娤擮忋偺憡堘傪棃偨偝側偄偙偲側偳偵偮偄偰偼丄慜偵弎傋偨偲偍傝偱偁傞丅偦偆偡傞偲丄塃奺昗復偼丄(F)彜昗偲徧屇丄娤擮傪摨堦偵偡傞椶帡彜昗偱偁傞丅 (擇) (僀)昗復偲(G)彜昗 椉幰偑椶帡偡傞彜昗偱偁傞偙偲偼丄堦偺4偺(擇)偵弎傋偨偲偍傝偱偁傞丅 4 峊慽恖偺彜昗朄戞26忦偺庡挘偵懳偟偰 塃庡挘偼憟偆丅 乽報憡妛乿偼丄慜弎偺偲偍傝旐峊慽恖偺惢嶌偵學傞報復傪昞帵偡傞傕偺偲偟偰帺懠彜昳幆暿婡擻傪桳偡傞傕偺偱偁傞丅峊慽恖偺庡挘偡傞傛偆偵丄報憡妛偺岅偑報娪偺昳幙傪帵偡晛捠柤徧偱偁傞偲偄偆偺偱偁傟偽丄偙傟偵傛偮偰摿掕偺昳幙偑憐掕偝傟側偗傟偽側傜側偄偲偙傠丄報憡妛偺報娪偲偄偮偰傕丄摑堦偟偨昳幙傪嬶旛偟偰偼偄側偄丅報娪偺昳幙傪帵偡晛捠柤徧偲偄偊偽丄椺偊偽乽偮偘報娪乿丄乽悈徎報娪乿丄乽徾夊報娪乿偲偄偆傛偆偵丄偦偺巊梡嵽椏傪偄偆偺偱偁偮偰丄帤懺丄攝帤偦偺懠偺梫慺偵偮偄偰丄昳幙傪嬒摍偵昞尰偡傞晛捠柤徧偼側偄丅 5 峊慽恖偺愭巊梡尃偺庡挘偵懳偟偰 塃庡挘偼憟偆丅 (堦) 峊慽恖偼丄旐峊慽恖偑(F)彜昗傪巊梡偟偰偙傟偑庢堷廀梫幰娫偵峀偔抦傜傟偰偄傞偙偲偵拝栚偟丄偙偺柤惡偵曋忔偟偰丄偙傟偲娤擮忋摨堦偺(僇)昗復偺巊梡傪奐巒偟偨傕偺偱偁傞偐傜丄晄惓嫞憟偺栚揑偑側偐偮偨偲偼偄偊側偄丅偙偺偙偲偼丄峊慽恖偑徍榓巐榋擭榋寧偙傠偐傜丄(僇)昗復偺傎偐丄乽報憡妛夛偱桞堦乿丄乽報憡妛夛悘堦乿側傞岅傪峀崘偵梡偄丄偁傞偄偼乽報憡妛偺憤杮壠乿側傞岅傪巊梡偟偰偄傞帠幚偐傜傕柧傜偐偱偁傞丅峏偵丄峊慽恖戙昞幰亂C亃偼丄徍榓巐敧擭屲寧丄旐峊慽戙棟恖亂D亃傜偵丄旐峊慽恖偺柤惡傪棙梡偟偰報復傪敄棙懡攧偡傞堄恾偺偁傞偙偲傪弎傋偰偄傞丅 (擇) (僇)昗復偼丄(F)彜昗偺彜昗搊榐弌婅慜偵偼廀梫幰娫偵峀偔擣幆偝傟偰偄偨偲偼偄偊側偄丅旐峊慽恖偼丄峊慽恖傛傝偼傞偐埲慜偐傜(F)彜昗傪巊梡偟偰偄偨偲偙傠丄峊慽恖偼丄偙偺廃抦惈傪斲掕偟側偑傜丄(僇)昗復偑嬐偐堦擭娫偱廃抦惈傪庢摼偟偨偲偡傞偙偲偼丄柕弬偱偁傝丄偦偺庡挘偺嵦梡偱偒側偄偙偲偼柧傜偐偱偁傞丅 6 壖張暘偺昁梫惈 堦偺6偵弎傋偨偲偙傠偲摨堦偱偁傞丅 7 傛偮偰丄旐峊慽恖偼丄峊慽恖偵懳偟丄彜昗朄戞36忦戞1崁丄戞37忦戞1崋丄戞擇崋偵婎偯偔怤奞掆巭丒梊杊惪媮尃曐慡偺偨傔丄(僂)丄(僄)丄(僆)丄 (僇)偺奺昗復偺巊梡偺嵎巭傪媮傔傞丅 嶰 彜朄偵婎偯偔惪媮1 旐峊慽恖偑塩嬈偺昞帵偲偟偰(A)昗復傪桳偟偰偍傝丄偙傟傪尰嵼慽奜夛幮偵捓戄偟偰偄傞偙偲丄峊慽恖偑(傾)昗復傪桳偟偰偄傞偙偲媦傃屻幰偑慜幰偲偺娭學偵偍偄偰旐峊慽恖偺塩嬈偱偁傞偲岆擣傪惗偠偝偣傞偍偦傟偺偁傞椶帡彜崋偱偁傞偙偲偼丄堦偵庡挘偟偨偲偍傝偱偁傞丅 2 晄惓偺栚揑 (傾)昗復偲(A)昗復偲偺椶帡惈丄峊慽恖偺戝乆揑愰揱妶摦摍偵徠傜偟丄峊慽恖偺(傾)昗復偺巊梡偑旐峊慽恖偺塩嬈偺怣梡偲柤惡傪棙梡偟傛偆偲偡傞晄惓偺栚揑傪桳偡傞偙偲偼柧傜偐偱偁傞丅 3 壖張暘偺昁梫惈 堦偺6偵摨偠丅 4 傛偮偰丄旐峊慽恖偼丄峊慽恖偵懳偟丄彜朄戞21忦偵婎偯偔巊梡嵎巭惪媮尃曐慡偺偨傔丄(傾)昗復(彜崋)偺巊梡偺嵎巭傪媮傔傞丅 |
|
|
峊慽恖偺摎曎偲庡挘
堦 晄惓嫞憟杊巭朄偵婎偯偔惪媮偵偮偄偰1 旐峊慽恖偺1偺庡挘偵偮偄偰(堦) 1偺(堦)偺帠幚偼擣傔傞丅 (擇) 1偺(擇)偺庡挘偼憟偆丅 晄惓嫞憟杊巭朄戞1忦戞1崁偵偄偆乽塩嬈忋偺棙塿傪奞偣傜傞傞嬹偁傞幰乿偲偼丄帺屓偺塩嬈忋偺棙塿傪奞偣傜傟傞幰傪堄枴偡傞偙偲偼偄偆傑偱傕側偔丄偟偨偑偮偰丄摨忦崁偵婎偯偔嵎巭惪媮尃傪桳偡傞幰偼丄塩嬈幰偱偁傞偙偲傪梫偡傞丅偦偟偰丄塩嬈幰偲偼丄帺屓偺柤傪傕偮偰塩嬈傪側偡幰偱偁傞偲夝偡傋偒偲偙傠丄塩嬈偺捓戄庁偵偍偄偰偼丄塩嬈偵懏偡傞嵿嶻帺懱偼捓戄恖偵懏偡傞偲偟偰傕丄塩嬈峴堊偼捓庁恖偺柤傪傕偮偰峴傢傟丄塩嬈忋偺懝塿傕丄捓庁恖偵婣懏偡傞傕偺偱偁傞丅偟偨偑偮偰丄捓庁恖偼丄懠恖偺嵿嶻偵傛偮偰塩嬈傪側偡幰偱偁傞偑丄偙偺応崌丄捓庁恖偑塩嬈幰偱偁偮偰丄捓戄恖偼塩嬈幰偱偼側偄丅偦偆偡傞偲丄慽奜夛幮偵報復偺惢憿斕攧偵娭偡傞塩嬈傪捓戄偟偨旐峊慽恖偼丄塩嬈幰偱偼側偔丄摨朄摨忦崁偵婎偯偔嵎巭惪媮尃傪桳偟側偄傕偺偱偁傞丅 旐峊慽恖偼丄岺嬈強桳尃偑捓戄偺栚揑偲偝傟傞偺偲摨條丄晄惓嫞憟杊巭朄忋偺棙塿側偄偟尃棙偑捓戄偺栚揑偲偝傟傞巪庡挘偡傞偑丄偦偺晄惓嫞憟杊巭朄忋偺棙塿側偄偟尃棙偑塩嬈偲偼撈棫偵偦傟偩偗偱捓戄庁偺栚揑偲偝傟傞偙偲偼偁傝偊偢丄傑偨丄塩嬈偺捓戄庁偵偍偄偰偼丄捓戄偺栚揑偼塩嬈偱偁傝丄偦偺寢壥塩嬈幰偨傞捓庁恖偵晄惓嫞憟杊巭朄忋偺棙塿側偄偟尃棙偑敪惗偡傞偲偄偆傋偒偱偁傞丅旐峊慽恖偺塃庡挘偼丄偦偺慜採偵偍偄偰岆傑偮偰偄傞丅 2 旐峊慽恖偺2偺庡挘偵偮偄偰 旐峊慽恖偑丄偦偺庡挘偡傞奺昗復傪巊梡偟偰偄偨偙偲偼擣傔傞偑丄偙傟傜偑丄旐峊慽恖偺惢憿丒斕攧偵娭偟丄偦偺塩嬈昞帵枖偼彜昳昞帵偲偟偰慡崙偵峀偔擣幆偝傟偰偄偨偲偺揰偼斲擣偡傞丅塃奺昗復偑旐峊慽恖偺塩嬈昞帵枖偼彜昳昞帵偲偟偰峀偔擣幆偝傟傞偵帄偮偰偄側偐偮偨偙偲偼丄尨敾寛偺棟桼戞嶰崁偵婰嵹偺偲偍傝偱偁傞丅側偍丄旐峊慽恖偼丄摉怰偵偍偄偰廃抦惈妉摼偺帪婜傪徍榓巐屲擭枛偲夵傔偨偑丄尨敾寛偼丄徍榓巐敧丄嬨擭偛傠偺帠忣傑偱傕澪庌偟偰擣掕偟偰偄傞偺偱偁傞偐傜丄旐峊慽恖偑塃偺偲偍傝庡挘傪夵傔偰傕丄寢榑偵曄傝偑側偄丅 (堦) 旐峊慽恖偺(堦)偺庡挘偵偮偄偰 塃庡挘偼偡傋偰憟偆丅 旐峊慽恖偼丄乽報憡妛乿側傞岅偼丄旐峊慽恖偺慶晝亂A亃偺憿岅偵側傞傕偺偱晛捠柤徧偱偼側偄巪庡挘偡傞偑丄偙偺揰偵偮偄偰偼慳柧偑側偔丄塃庡挘偼帠幚偵斀偡傞傕偺偱偁傞丅壖偵丄乽報憡妛乿偺岅偑旐峊慽恖偺庡挘偺偲偍傝柧帯屻婜偵偍偗傞憿岅偱偁傞偲偟偰傕丄塃岅偼丄戞堦媊揑偵偼丄偄傢備傞乽敾偼傫偠乿丄乽敾宍愯乿丄乽報愯乿側偳偺岅偵戙傝報復偺媑嫢敾抐偵娭偡傞堈愯偺媄弍枖偼妛栤傪巜偡傞傕偺偲偟偰柦柤偝傟偨偙偲偼斲掕偱偒側偄丅偦偆偡傞偲丄壖偵亂A亃偑偦偺惢憿斕攧偡傞報復偵傕摨偠偔報憡妛偲偄偆昗復傪晅偟偨帠幚偑偁偮偨偐傜偲偄偮偰(傕偮偲傕丄偙偺帠幚帺懱壗傜慳柧偝傟偰偄側偄丅)丄報復偺媑嫢敾抐偵娭偡傞堈愯偺媄弍枖偼妛栤傪巜偡傕偺偲偟偰偺報憡妛偺岅偵偮偄偰丄偦偺柦柤幰偨傞亂A亃傗旐峊慽恖偑偙傟傪撈愯偟偆傋偒偄傢傟偼側偄丅偦傟偼丄柧帯埲崀壗恖偐偵傛傝怴偨偵柦柤偝傟偨懠偺妛栤偵懳偡傞柤徧偲摨條偩偐傜偱偁傞丅偙偺傛偆偵丄報憡妛偲偄偆岅偼晛捠柤徧偱偁偮偰丄報復偺媑嫢敾抐偵娭偡傞堈愯偺媄弍枖偼妛栤傪巜偡岅偲偟偰丄旐峊慽恖偑廃抦惈傪庢摼偟偨偲庡挘偡傞擔枖偼(F)丄(G)彜昗偺彜昗搊榐弌婅偺擔傛傝偼傞偐埲慜偐傜報復偵娭偡傞暥專偵峀偔婰弎揑偵梡偄傜傟丄傑偨丄峊慽恖埲奜偺報復惢憿斕攧嬈幰偺峀崘偵傕懡梡偝傟偰偄傞偺偱偁傞丅偙傟傜暥專傗岞崘拞偵偼丄乽報憡妛偵傛偮偰嶌偮偨報乿丄乽報憡妛偵偁傢側偄報乿丄乽報憡妛偺惓朄傪傆傑偊偨報乿丄乽報憡妛偵婎偔岾塣偺報乿側偳偲偄偆昞尰偑傒傜傟丄報憡妛偺岅偑丄報復偺傕偮偁傞摿惈傪帵偡傕偺偲偟偰堦斒偵巊梡偝傟偰棃偨傕偺偱偁傞丅屻弎偺偲偍傝丄峊慽恖偺峀崘媦傃愢柧暥偵偍偗傞報憡妛偲偄偆岅傕丄偙傟傜偺梡朄偲摨條丄晛捠柤徧偲偟偰巊梡偝傟偰偄傞傕偺偱偁傞丅 偙偺偙偲偼丄擔杮崙岅戝帿揟偵丄乽報憡乿偺戞嶰媊偲偟偰丄乽報復偺憡丅傑偨丄 偦傟傪傒偰帩庡偺塣傪嶡抦偡傞偙偲丅乿偲偁傞偙偲偐傜傕柧傜偐偱偁傞丅偟偨偑偮偰丄乽報憡乿偵娭偡傞妛栤偲偟偰報憡妛偲偄偆岅傕丄偡偱偵堦斒壔偟偰偄傞偲偄偊傛偆丅旐峊慽恖偼丄報憡妛偺岅偑晛捠柤徧偱側偄崻嫆偲偟偰丄(F)彜昗偑彜昗搊榐傪宱偰偄傞帠幚傪嫇偘偰偄傞偑丄慜弎偺偲偍傝丄塃偺岅偑(F)彜昗偺彜昗搊榐弌婅擔慜偐傜偝傑偞傑側暥專媦傃報復嬈幰偺峀崘拞偵峀偔梡偄傜傟偰棃偨傕偺偱偁傞偙偲偐傜偡傟偽丄報復偵偮偄偰偙傟傪梡偄偰傕丄壗傜帺懠彜昳幆暿椡傪桳偣偢丄 報憡妛側傞岅偼丄報復偵偮偄偰偼丄彜昗朄戞3忦戞1崁戞2崋丄戞嶰崋枖偼戞榋崋偺婯掕偵奩摉偟丄傕偲傕偲丄彜昗搊榐偺梫審傪寚偔傕偺偱偁傝丄摿掕恖偵撈愯揑偵巊梡偝偣傞傋偒傕偺偱偼側偄丅 (擇) 旐峊慽恖偺(擇)丄(嶰)偺庡挘偵偮偄偰 塃(擇)偺帠幚拞丄旐峊慽恖偑丄徍榓擇嬨擭偦偺挊彂乽報復偺媑嫢偺夝愢乿傪敪峴偟偨偙偲偼擣傔傞偑丄偦偺梋偺帠幚偼抦傜側偄丅摨(嶰)偺庡挘偼憟偆丅 3 旐峊慽恖偺3偺庡挘偵偮偄偰 塃庡挘帠幚偼擣傔傞丅扐偟丄慜弎偺偲偍傝丄乽報憡乿枖偼乽報憡妛乿偺岅偼丄晛捠柤徧偱偁偮偰丄報復偵偮偄偰壗傜塩嬈昞帵枖偼彜昳昞帵偲偟偰帺懠彜昳幆暿婡擻傪桳偟側偄偲偙傠丄(傾)丄(僀)偺昗復埲奜偺傕偺偵偍偗傞乽報憡乿枖偼乽報憡妛乿偼丄 偄偢傟傕晛捠柤徧偲偟偰偼婰弎揑偵梡偄傜傟偰偄傞傕偺偱偁偮偰丄彜昳偺昞帵側偄偟幆暿婡擻傪壥偡傕偺偲偟偰梡偄傜傟偰偄傞傕偺偱偼側偄丅 4 旐峊慽恖偺4偺庡挘偵偮偄偰 塃庡挘偼偡傋偰憟偆丅 (堦) (傾)昗復偲(A)昗復 屻婰(擇)偵弎傋傞偙偲偐傜傕丄塃椉昗復偑椶帡偟側偄偙偲偼柧傜偐偱偁傞丅 (擇) (僀)昗復偲(A)丄(B)昗復 塃椉昗復偑丄奜娤丄徧屇丄娤擮偺偄偢傟偺揰偵偍偄偰傕椶帡偡傞傕偺偱側偄偙偲偼丄尨敾寛偑棟桼戞屲崁(堦)側偄偟(嶰)偵偍偄偰敾抐偟偰偄傞偲偍傝偱偁傞丅 旐峊慽恖偼丄塃椉昗復偵偍偗傞乽擔杮報憡乧乧夛乿偺晹暘偺嫟捠惈傪嫮挷偡傞偑丄偙偺晹暘偺傒傪拪弌偟偰懳斾偡傞偙偲帺懱丄嬌傔偰湏堄揑偱崌棟揑崻嫆傪寚偔傕偺偱偁傞丅(僀)昗復偵偍偄偰傛傝嫮偔擣幆偝傟傞偱偁傠偆晹暘傪姼偰巜揈偡傞側傜偽丄乽廆壠乿偱偁傝丄傑偨丄乽報憡嫤夛乿偱偁傞偙偲偼宱尡懃忋柧傜偐偱偁傞丅傑偨丄乽擔杮報憡嫤夛乿偲乽擔杮報憡妛夛乿偲偺娤擮忋偺懳斾偵偮偄偰丄旐峊慽恖偼丄屻幰偼丄塩嬈昞帵偲偟偰巊梡偝傟偰偄傞偺偱偁偮偰丄偦偙偵偼報復偺惢嶌丒斕攧傪峴偆庡懱偲偟偰偺娤擮偑戝慜採偲側偮偰偄傞偲偄偄丄乽報憡偺媑嫢偵娭偡傞妛栤乿偼壗傜嬤戙壢妛偵婎偯偔懱宯揑側擣幆偲偟偰娤擮偝傟傞梋抧偼側偄偲傕偄偆偑丄偙偙偱栤戣偲側傞偺偼乽擔杮報憡妛夛乿偺幚懱偑壗偐偱偼側偔丄乽擔杮報憡妛夛乿偲偄偆昞帵帺懱偑悽恖偵偄偐偵娤擮偝傟傞偐偱偁傞偟丄傑偨丄乽報憡妛乿偑乽妛栤乿偲偄偆娤擮傪惗偠偝偣傞傕偺偱偁傞埲忋丄偦偺妛栤偑嬤戙壢妛偵婎偯偔懱宯揑側擣幆偱偁傞偐斲偐偼丄乽擔杮報憡妛夛乿偲偄偆昞帵偲乽擔杮報憡嫤夛乿偲偄偆昞帵偲偺娤擮忋偺椶斲敾抐傪壗傜嵍塃偡傞傕偺偱偼側偄丅峏偵丄報憡偵娭偡傞妛栤偨傞娤擮傪惗偠偝偣傞乽報憡妛乿偲丄摉奩妛栤偺懳徾偨傞乽報憡乿(報復偺憡)帺懱偲偑娤擮忋堎側傞傕偺偱偁傞偙偲偼偄偆傑偱傕側偄丅偦偟偰丄椉昗復偼丄 乽擔杮報憡乿偺暥帤傪嫟捠偵偼偡傞偑丄乽擔杮乿偼傕偪傠傫乽報憡乿傕晛捠柤徧偱偁傞偐傜丄奿暿偺幆暿椡偑側偄丅場傒偵丄乽妛夛乿偲乽嫤夛乿偲偺憡堘偵傛傝丄偦傟偧傟暿屄撈棫偺彜昗偲偟偰搊榐偝傟偰偄傞帠椺偼丄枃嫇偵偄偲傑偑側偔丄椉幰傪旕椶帡偲偡傞偙偲偼摿嫋挕偺堦娧偟偨庢埖偄偱傕偁傞丅 (嶰) (僂)昗復偲(C)昗復 乽報憡妛乿偺岅偑晛捠柤徧偱偁傞偙偲偼丄婛偵弎傋偨偲偍傝偱偁傝丄峊慽恖偑(僂)昗復傪梡偄偰偄傞偺偼丄峀崘暥拞偵報復偵娭偡傞堈妛偲偟偰偺晛捠柤徧偲偟偰丄婰弎揑偵巊梡偟偰偄傞偵偡偓側偄丅 (巐) (僄)丄(僆)丄(僇)昗復偲(D)昗復 (僄)丄(僆)丄(僇)偺奺昗復偼丄偄偢傟傕峊慽恖偺彜昳帺懱偵晅偝傟偰偄傞傕偺偱偼側偔丄偦偺怴暦峀崘拞偵婰弎偝傟偰偄傞傕偺偱偁傞偑丄偦偺峀崘偺婰嵹帺懱偐傜傕柧傜偐側偲偍傝丄偄偢傟傕丄乽報憡妛偵懃偮偨夛幮報乿枖偼乽報憡妛偵懃偮偨報娪乿偺庯巪偱偁傝丄晛捠柤徧偲偟偰婰弎揑偵梡偄偰偄傞傕偺偵偡偓偢丄彜昳昞帵側偄偟彜昳偺帺懠幆暿婡擻傪壥偡傕偺偲偟偰梡偄傜傟偰偄傞傕偺偱偼側偄丅 堦曽丄(D)昗復偼丄婛偵弎傋偨偲偙傠偐傜柧傜偐側偲偍傝丄旐峊慽恖偺撈愯巊梡偵學傞傕偺偱偼側偔丄乽報憡妛報復乿偲偺昞帵偵旐峊慽恖偺彜昳偵懳偡傞怣梡偑壔懱偝傟偰偄傞傕偺偱傕側偄丅 側偍丄峊慽恖偺傎偐懡偔偺報復嬈幰偑丄報復偺斕攧峀崘偵(僄)丄(僆)丄 (僇)偺奺昗復偵憡摉偡傞岅傪梡偄傞偺偼丄旐峊慽恖偺怣梡傪朻梡偡傞堄恾偵傛傞傕偺偱偼慡偔側偔丄廬慜傛傝堦斒偵巊梡偝傟偰偄傞梡岅朄偵傛偮偰報復偺偁傞摿惈(昳幙丄岠壥枖偼惗嶻曽朄側偳)傪昞帵偟偰偄傞偵偡偓側偄丅 (屲) (僉)丄(僋)昗復偲(E)昗復 旐峊慽恖偼丄塃椉幰偑偦傟偧傟娤擮忋椶帡偱偁傞偲庡挘偡傞偑丄乽報憡妛廆壠乿偑丄乽報憡妛偺杮壠乿偺娤擮傪惗偢傞偺偵懳偟丄乽報憡妛偺尮乿偼丄報憡妛帺懱偺婲尮偲偄偆娤擮傪惗偠丄椉幰偼娤擮忋傕憡堘偡傞偙偲偼柧傜偐偱偁傞丅傑偨丄乽報憡乿偲乽報憡妛乿偲偑娤擮忋椶帡偟側偄偙偲偼柧傜偐偱偁傞偐傜丄乽報憡偺憤杮壠乿偲乽報憡妛廆壠乿傕娤擮忋椶帡偟側偄偙偲偼摉慠偱偁傞丅場傒偵丄搊榐彜昗偱偁傞乽報憡妛廆壠乿偲巜掕彜昳傪摨偠偔偟偰乽報憡妛偺尮乿媦傃乽報憡偺憤杮壠乿側傞塃彜昗偑偦傟偧傟彜昗搊榐偝傟偰偄傞帠幚偼丄(僉)丄(僋)偺奺昗復偲(E)昗復偲偑椶帡偟側偄偙偲傪棤偯偗傞傕偺偱偁傞丅 5 旐峊慽恖偺5偺庡挘偵偮偄偰 旐峊慽恖偺昗復偑偄偢傟傕廃抦偺傕偺偱側偄偙偲丄峊慽恖偺巊梡偡傞奺昗復偑旐峊慽恖偺昗復偲椶帡偟側偄偙偲偐傜丄峊慽恖偵晄惓偺栚揑偑側偄偙偲偼偄偆傑偱傕側偄丅 6 旐峊慽恖偺6偺庡挘偵偮偄偰 塃庡挘偼憟偆丅 側偍峊慽恖偼丄(僆)丄(僇)偺昗復偵偮偄偰偼丄徍榓屲乑擭堦寧榋擔((F)彜昗偺彜昗搊榐擔)慜傛傝偡偱偵巊梡傪拞巭偟偰偄傞丅 擇 彜昗朄偵婎偯偔惪媮偵偮偄偰1 旐峊慽恖偺1偺庡挘偵偮偄偰 塃庡挘帠幚偼擣傔傞丅 2 旐峊慽恖偺2偺庡挘偵偮偄偰 塃庡挘帠幚偼擣傔傞丅扐偟丄慜弎偺偲偍傝丄乽報憡乿枖偼乽報憡妛乿偺岅偼丄晛捠柤徧偱偁傝丄報復偵偮偄偰壗傜帺懠彜昳幆暿椡傪桳偟側偄偲偙傠丄(僂)丄 (僄)丄(僆)丄(僇)偺奺昗復偵偍偗傞乽報憡妛乿偼丄偄偢傟傕晛捠柤徧偲偟偰婰弎揑偵梡偄傜傟偰偄傞傕偺偱偁偮偰丄彜昳偺昞帵側偄偟幆暿婡擻傪壥偡傕偺偲偟偰梡偄傜傟偰偄傞傕偺偱偼側偄丅 3 旐峊慽恖偺3偺庡挘偵偮偄偰(堦) 3偺(堦)偺庡挘偼憟偆丅 傑偢丄(F)彜昗偑帺懠彜昳幆暿椡傪桳偣偢丄彜昗朄戞3忦戞1崁戞2崋丄戞嶰崋枖偼戞榋崋偺奺婯掕偵奩摉偟丄彜昗搊榐梫審傪寚偒摿掕恖偵撈愯揑偵巊梡偝偣傞傋偒傕偺偱側偄偙偲偼丄堦偺2偺(堦)偵弎傋偨偲偙傠偱偁傞丅 (僂)偺昗復偼丄慜弎偺偲偍傝丄晛捠柤徧偱偁傝丄報復偵偮偄偰壗傜帺懠彜昳幆暿椡傪桳偟側偄偐傜丄椶斲傪榑偢傞傑偱傕側偄丅 師偵丄(僄)丄(僆)丄(僇)偺奺昗復偑(D)昗復偲椶帡偟側偄傕偺偱偁傞偙偲偼丄堦偺4偺(嶰)偵弎傋偨偲偍傝偱偁傞丅 偲偙傠偱尨敾寛偼丄(僄)丄(僆)丄(僇)偺奺昗復偲(F)彜昗偲偑奜娤媦傃徧屇偵偍偄偰堎側傞偲偟側偑傜丄娤擮偺椶斲偵偮偄偰丄(F)彜昗偑報復傪巜掕彜昳偲偡傞搊榐彜昗偱偁傞偙偲偐傜丄乽報憡妛乿偲偼丄乽報憡妛偺報(報娪丒報復)乿偺娤擮傪惗偢傞偲偟偰偄傞偑丄偙偺擣掕偼柧傜偐偵岆傝偱偁傞丅偗偩偟丄彜昗偵偮偄偰偄傢備傞娤擮偲偼丄摉奩昗復帺懱偺桳偡傞娤擮傪偄偄丄巜掕彜昳偲偺娭楢偵偍偄偰惗偢傞娤擮傑偱娷傓傕偺偱偼側偄丅偦偟偰報憡妛偲偼丄悽忋報偺媑嫢慞埆偺憡傪扵媶偡傞妛栤偱偁傞偲偝傟偰偍傝丄偟偨偑偮偰丄報憡妛偲偄偆昗復帺懱偐傜偼丄報憡偵娭偡傞宯摑揑擣幆偲傕偄偊傞拪徾揑巚憐偲偄偆娤擮偟偐惗偠側偄丅堦曽丄報丄報娪枖偼報復偲偼嬶懱揑宍徾傪傕偮偨暔偱偁傞丅偦偆偩偲偡傞偲丄塃偺拪徾揑巚憐偲傕偄偊傞報憡妛偺暥帤偐傜捈偪偵暔偱偁傞報丄報娪枖偼報復傪娤擮偡傞偙偲偼偱偒側偄丅場傒偵丄巜掕彜昳媽榋榋椶偵偮偄偰乽報憡妛報復乿偲偄偆搊榐彜昗偑偁傞偵傕偐偐傢傜偢摨椶偵偍偄偰乽報憡妛乿偲偄偆彜昗偑丄楢崌彜昗偲偟偰偱偼側偔撈棫偺彜昗偲偟偰搊榐偝傟偰偄傞帠幚偑偁傝丄偙傟偼塃偺偙偲傪棤偯偗傞傕偺偱偁傞丅 (擇) 3偺(擇)偺庡挘偼憟偆丅 (僀)昗復偲(G)彜昗偑椶帡偟側偄偙偲偼丄堦偺4偺(擇)偵弎傋偨偲偙傠偲摨抐偱偁傞丅 4 彜昗朄戞26忦偺庡挘 壖偵丄(僂)丄(僄)丄(僆)丄(僇)偺奺昗復偑丄旐峊慽恖偺庡挘偡傞傛偆偵彜昗偲彜昳偲偺寢崌昞帵偵奩摉偟丄傑偨乽報憡妛乿偑報復偵偮偄偰偙傟傪惢憿斕攧偡傞懡悢偺幰偵傛偮偰峀偔姷梡揑偵巊梡偝傟偰偄傞偲偼偄偊側偄偵偟偰傕丄彮偔偲傕乽報憡妛乿偺岅偼丄報復偺傕偮偁傞摿惈丄偡側傢偪丄昳幙丄岠擻枖偼惗嶻偺曽朄摍傪晛捠偵梡偄傞曽朄偱昞帵偟偰偄傞傕偺偱偁傞丅偟偨偑偮偰丄(F)彜昗偺岠椡偼丄彜昗朄戞26忦戞1崁戞2崋枖偼戞嶰崋偺婯掕偵傛傝丄(僂)丄(僄)丄 (僆)丄(僇)偺奺昗復偵偼媦偽側偄丅側偍丄旐峊慽恖偼丄昳幙傪帵偡晛捠柤徧偲偼丄偦偺巊梡嵽椏傪偄偆偲庡挘偡傞偑丄偙偺傛偆偵尷掕偟偰夝偡傋偒棟桼偼側偄丅 傓偟傠丄摨朄戞26忦戞1崁戞2崋偺婯掕偼丄彜昳偺摿惈偺婰弎揑昞帵偺婔偮偐傪椺帵偟偨偵偡偓偢丄偙傟偵尷掕偝傟傞傕偺偱偼側偄丅 5 愭巊梡尃偺庡挘 壖偵丄峊慽恖偺慜婰偺庡挘偑擣傔傜傟側偄偲偟偰傕丄峊慽恖偼丄(僇)昗復偵偮偄偰彜昗朄戞32忦偵婎偯偔偄傢備傞愭巊梡尃傪桳偡傞傕偺偱偁傞丅偡側傢偪丄峊慽恖偼丄徍榓巐榋擭偵慻怐偝傟偨廆壠擔杮報憡嫤夛偺塩嬈傪彸宲偟偨幰偱偁傞偑丄 塃廆壠擔杮報憡嫤夛偼丄(F)彜昗偺彜昗搊榐弌婅擔(徍榓巐幍擭敧寧擇嬨擔)慜偱偁傞徍榓巐榋擭榋寧偙傠偐傜丄懡妟偺愰揱旓傪搳偠偰丄曬抦怴暦丄僗億乕僣僯僣億儞丄僨僀儕乕僗億乕僣側偳懡悢偺怴暦偵帺屓偺惢憿偡傞報復偵娭偡傞峀崘傪宲懕偟偰宖嵹偟丄枖偼報復偵娭偡傞愢柧暥偵偙傟傪梡偄傞側偳偟丄傕偲傛傝偦傟偵偼壗傜晄惓嫞憟偺栚揑偼側偐偮偨偺偱偁傝丄偦偺寢壥丄塃奺昗復偼丄塃彜昗搊榐弌婅偺嵺偵峊慽恖偺嬈柋偵偐偐傞彜昳傪昞帵偡傞傕偺偲偟偰廀梫幰娫偵峀偔擣幆偝傟傞偵帄偮偰偄偨偺偱偁傞丅 6 旐峊慽恖偺6偺庡挘偵偮偄偰 堦偺6偵摨偠丅 嶰 彜朄偵婎偯偔惪媮偵偮偄偰1 旐峊慽恖偺1偺庡挘偵偮偄偰(堦) (傾)昗復(彜崋)偲(A)昗復偲偑椶帡彜崋偱偁傞偲偺揰傪斲擣偡傞偑丄偦偺梋偺庡挘帠幚偼擣傔傞丅 塃椉彜崋偑椶帡偟側偄偙偲偼堦偺4偺(堦)偵弎傋偨偲偍傝偱偁傞丅 (擇) 彜朄戞21忦戞2崁強掕偺嵎巭惪媮尃傪桳偡傞幰偼丄彜恖偨傞偙偲傪梫偡傞偲偙傠丄堦偺1偺(擇)偵傕弎傋偨偲偍傝丄塩嬈偺捓戄恖偨傞旐峊慽恖偼彜恖偱偼側偄偐傜丄塃偺嵎巭惪媮尃傪桳偟側偄丅 2 旐峊慽恖偺2偺庡挘偵偮偄偰 堦偺5偵摨偠3 旐峊慽恖偺3偺庡挘偵偮偄偰 塃庡挘偼憟偆丅 |
|
|
徹嫆娭學(徣棯)
棟 桼 |
|
|
晄惓嫞憟杊巭朄偵婎偯偔惪媮偵偮偄偰
堦 旐峊慽恖偺昗復偲偦偺廃抦惈偵偮偄偰1 旐峊慽恖偑(A)側偄偟(E)偺昗復傪丄偦偺庡挘偺偲偍傝丄塩嬈枖偼彜昳偺昞帵偲偟偰尰偵巊梡偟偰偄傞偙偲偼丄摉帠幰娫偵憟偄偑側偄丅 2 偦偙偱丄塃昗復偺廃抦惈偵偮偄偰専摙偡傞丅 (堦) 傑偢丄塃昗復偺廃抦惈偺擣掕偵摉偮偰偼丄偙傟傜偺昗復偺偡傋偰偵娷傑傟傞乽報憡乿側偄偟乽報憡妛乿偺岅偺桼棃偑栤戣偲偝傟偰偄傞偺偱丄偙偺揰偵偮偄偰峫偊傞丅 (1) 旐峊慽恖偼丄乽報憡妛乿偲偺柤徧側偄偟梡岅偼丄乽報憡乿偺岅偲偲傕偵丄 旐峊慽恖偺慶晝亂A亃偺柦柤偵學傞摨恖偺憿岅偱偁傝丄摨恖媦傃旐峊慽恖(慽奜夛幮愝棫屻偼摨夛幮)偑丄崱擔傑偱撈愯揑偵巊梡偟棃偮偨傕偺偱偁偮偰丄偦傟帺懱旐峊慽恖側偄偟慽奜夛幮偺惢嶌偵學傞報復偲偟偰弌強昞帵婡擻媦傃昳幙曐徹婡擻傪桳偡傞巪庡挘偟丄尨怰徹恖亂E亃(旐峊慽恖偺嵢)偺徹尵暲傃偵摉怰媦傃尨怰偵偍偗傞旐峊慽恖杮恖恞栤偺寢壥拞偵偼丄塃庡挘偵暃偆嫙弎晹暘偑偁傞丅 (2) 偦偙偱丄傑偢乽報憡乿偺岅偵偮偄偰傒傞偵丄側傞傎偳丄乽報憡乿偺岅偼丄 恖憡丄庤憡丄崪憡側偳偺岅偲斾妑偡傞偲丄偙傟傜偺岅傎偳偵擔忢峀偔巊梡偝傟偰偄傞傕偺偲偼偵傢偐偵偄偄擄偄偑丄乽報憡乿偺岅偵愙偡傞幰偼丄塃偺恖憡傗庤憡側偳偺岅偲摨條偵丄報復丄報塭偺憡側偄偟宍懺傪堄枴偡傞岅偲棟夝偡傞応崌偑彮側偔側偄偱偁傠偆偙偲偼悇應偡傞偵擄偔側偔丄偦偺堄枴偵偍偄偰丄偦偺岅偑偦傟帺懱摿堎側岅偲偄偆偙偲偼偱偒側偄丅偦偟偰丄惉棫偵憟偄偺側偄慲壋戞擇榋崋徹偵傛傞偲擔杮崙岅戝帿揟(彫妛娰徍榓巐敧擭嶰寧堦擔敪峴)戞擇姫乽報憡乿偺崁偺嘊偵偼丄 乽報復偺憡丅傑偨丄偦傟傪傒偰帩庡偺塣傪嶡抦偡傞偙偲丅憡報丅乿偲偺愢柧偑偁傞丅峏偵丄屻弌偺彂暔乽惓摑報憡妛偲惄柤妛乿(徍榓堦嶰擭屲寧堦擔敪峴)丄乽塣柦奐戱恄旈報復嫵杮乿(徍榓堦巐擭嬨寧堦乑擔敪峴)偦偺懠偺彂暔拞偵傕丄乽報憡乿側傞岅偑塃偺擔杮崙岅戝帿揟偵婰嵹偝傟偨偲摨條偺堄枴偺傕偲偵悘強偵梡偄傜傟偰偄傞偙偲偑擣傔傜傟傞丅 偙偺傛偆側彅帠幚偵屻婰偺乽報憡妛乿偵娭偡傞擣掕帠幚傪暪偣峫偊傞偲丄乽報憡乿偺岅偼丄偦偺柦柤偑壗恖偵傛偮偰側偝傟偨偐偼偲傕偐偔傕丄屆偔偐傜(抶偔偲傕徍榓擇乑擭埲崀偵偍偄偰偼)丄報復偺憡丄宍懺枖偼偙偺報復偺憡丄宍懺傪堈愯偺娤揰偐傜娤嶡偟丄偦偺報復帺懱枖偼報復偺帩庡偺媑嫢側偳偺塣傪敾掕偡傞偙偲傪堄枴偡傞岅偲偟偰梡偄傜傟偰偄偨傕偺偲夝偝傟傞丅 (3) 師偵丄乽報憡妛乿偺岅偵偮偄偰峫偊傞丅 乽報憡乿偺岅偑丄塃偺傛偆側堄枴偺傕偲偵丄屆偔偐傜梡偄傜傟偰偄偨偙偲媦傃堈愯偺暘栰偵偍偄偰丄堈妛丄庤憡妛丄惄柤妛側偳偲徧偝傟傞傛偆偵丄乽妛乿偺帤偑乽弍乿偺帤偲摨條偵丄偦傟偲傎傏摨偠堄枴偵偍偄偰丄堈愯偺懳徾偱偁傞乽庤憡乿傗乽惄柤乿偺岅偲寢崌偟偰梡偄傜傟偰偄傞偙偲偼宱尡懃偵徠傜偟偰峬擣偱偒傞偲偙傠偱偁傝丄偙偺傛偆側揰傪峫偊傞偲丄乽報憡妛乿偺岅傕丄偦傟帺懱摿堎側崌惉岅偲偄偆偙偲偼偱偒側偄丅偦偟偰丄惉棫偵憟偄偺側偄慲壋戞屲榋崋徹偵傛傞偲丄摨崋徹偼丄亂F亃傪挊幰偲偡傞乽惓摑報憡妛偲惄柤妛乿偲戣偟丄徍榓堦嶰擭屲寧堦擔偵敪峴偝傟偨彂暔偱偁傝丄摨彂偺拞偵偼丄乽報憡妛乿偺桼棃傗偙傟偵娭偡傞挊幰偺尒夝偑徻嵶偵婰弎偝傟偰偄傞偙偲偑擣傔傜傟丄傑偨惉棫偵憟偄偺側偄慲壋戞擇屲崋徹偵傛傞偲丄摨崋徹偼丄亂G亃傪挊幰偲偡傞乽塣柦奐戱恄旈報復嫵杮乿偲戣偟丄徍榓堦巐擭嬨寧堦乑擔偵敪峴偝傟偨彂暔偱偁傝丄摨彂偺拞偵偼丄報憡妛偑巟撨偵敪惗偟丄 悢愮擭偺楌巎傪宱偰崱擔偵帄偮偰偄傞偲偺婰嵹傪偼偠傔乽報憡妛乿偺岅偑悘強偵梡偄傜傟偰偄傞偙偲偑擣傔傜傟丄峏偵丄惉棫偵憟偄偺側偄慲壋戞嬨擇崋徹偺堦側偄偟屲丄戞嬨嶰崋徹偺堦側偄偟榋丄戞嬨巐崋徹偺堦側偄偟堦乑偵傛傞偲丄偙傟傜傕偡傋偰報復偵娭偡傞彂暔偱偁傝丄戞嬨擇崋徹偺傕偺偼徍榓嶰幍擭屲寧擇嶰擔丄戞嬨嶰崋徹偺傕偺偼徍榓嶰敧擭堦擇寧堦乑擔偵丄戞嬨巐崋徹偺傕偺偼徍榓巐屲擭堦寧堦屲擔偵偦傟偧傟敪峴偝傟偨傕偺偱偁傞偑丄偙傟傜偺彂暔偵傕丄乽報憡妛乿偑嬌傔偰屆偄楌巎傪傕偮傕偺偱偁傞偙偲傪偼偠傔丄乽報憡乿傗乽報憡妛乿偵偮偄偰偺婰弎偑擣傔傜傟傞偲偙傠丄慜宖奺徹嫆偵傛傞偲丄偙傟傜偺彂暔偵偍偗傞乽報憡妛乿偺岅偼丄報復偺憡丄宍懺枖偼峀偔報娪偵偮偄偰偺堈愯偺棫応偐傜媑嫢傪敾抐偡傞愯弍側偄偟妛栤偺堄枴偵梡偄傜傟偰偄傞傕偺偲夝偝傟傞丅 (4) 旐峊慽恖偑偦偺彜昗尃幰偱偁傞(F)彜昗媦傃(G)彜昗偼丄慜幰偑乽報憡妛乿偺暥帤傪墶彂偒偟偰側傞傕偺偱偁傝丄傑偨丄屻幰偑乽報憡妛乿偺暥帤傪娷傓傕偺偱偁傞偑丄偙傟傜偺彜昗偵偮偄偰偼丄彜昗尃媦傃彜昗搊榐弌婅偵傛傝惗偠偨尃棙傪丄怽惪偺棟桼擇偺1偵婰嵹偺偲偍傝丄偄偢傟傕丄旐峊慽恖偑慽奜亂B亃偐傜丄 戙嬥崌寁屲乑乑枩墌偱忳傝庴偗偰庢摼偟偨傕偺偱偁傞偙偲偼丄摉帠幰娫偵憟偄偑側偔丄慜宖旐峊慽恖杮恖恞栤偺寢壥偲曎榑偺慡庯巪偵傛傞偲丄塃慽奜亂B亃偼旐峊慽恖枖偼慽奜夛幮偺塩嬈偲偼慡偔娭學偺側偄戞嶰幰偱偁傝丄塃屲乑乑枩墌偲偺嬥妟偼丄旐峊慽恖偺塩嬈妶摦偺婯柾偐傜傒偰憡摉懡妟側傕偺偱偁偮偨偙偲偑擣傔傜傟傞偲偙傠丄偲傕偁傟丄旐峊慽恖偼偙偺傛偆側宱堒偺傕偲偵塃奺彜昗尃傪庢摼偡傞偵偄偨偮偨傕偺偱偁傞丅 (5) 塃(2)側偄偟(4)偵弎傋偨偲偙傠傪暪偣峫偊傞偲丄乽報憡乿媦傃乽報憡妛乿偺岅偑丄旐峊慽恖偺慶晝偺憿岅偱偁傞偐偺揰偼偟偽傜偔偍偄偰傕丄塃旐峊慽恖杮恖恞栤偺寢壥拞丄摨恖媦傃旐峊慽恖偑偙傟傪撈愯揑偵巊梡偟偰棃偨傕偺偱偁傝丄偦傟帺懱愱傜旐峊慽恖側偄偟慽奜夛幮偺惢嶌偵學傞報復偵偮偄偰偦偺昞帵婡擻傪桳偟偰偄傞巪偺旐峊慽恖偺嫙弎晹暘偼丄怣梡偡傞偙偲偑偱偒偢丄懠偵塃庡挘傪擣傔傞偵懌傝傞徹嫆偼側偔丄偐偊偮偰丄乽報憡乿丄乽報憡妛乿偼丄彮側偔偲傕報復偺惢嶌傗報復偵娭偡傞堈愯偺暘栰偵偍偄偰偼丄(2)媦傃(3)偱弎傋偨傛偆側堄枴偵梡偄傜傟偰偄傞傕偺偲偄偆傋偒偱偁傞丅 側偍丄惉棫偵憟偄偺側偄慲峛戞嬨崋徹媦傃摨戞堦乑崋徹偺奺擇偵傛傞偲丄乽報憡妛報復乿偺暥帤傪廲彂偒偟偰側傝丄巜掕彜昳傪戞榋榋椶乽恾夋丄幨恀媦傃報嶞暔椶(扐偟彂愋傪彍偔丅)乿偲偡傞彜昗偵偮偄偰丄徍榓擇敧擭堦堦寧屲擔旐峊慽恖偺彜昗搊榐弌婅偵傛傝丄徍榓擇嬨擭堦乑寧嶰乑擔彜昗搊榐偑偝傟丄傑偨丄惉棫偵憟偄偺側偄慲峛戞嬨崋徹媦傃摨戞堦乑崋徹偺奺巐偵傛傞偲丄乽報憡妛乿偺暥帤傪廲彂偒偟偰側傝丄巜掕彜昳傪慜摨條偲偡傞彜昗偵偮偄偰丄徍榓嶰嶰擭嬨寧堦擔旐峊慽恖偺彜昗搊榐弌婅偵傛傝丄徍榓嶰屲擭嶰寧擇巐擔彜昗搊榐偑偝傟偰偄傞偙偲偑擣傔傜傟傞偑丄慜(2)丄(3)偵弎傋偨偲偙傠偐傜偡傟偽丄偙偺傛偆側搊榐彜昗偑懚偡傞偙偲偩偗偱丄偵傢偐偵旐峊慽恖偺慜婰嫙弎晹暘偵懄墳偡傞庡挘傪擣傔傞偵廩暘偱側偄偙偲偼偄偆傑偱傕側偄丅 (擇) 偦偙偱丄(A)昗復丄(B)昗復傪偟偽傜偔偍偒丄塃(堦)偵弎傋偨偲偙傠傪傆傑偊偰丄(C)昗復丄(D)昗復媦傃(E)昗復偺廃抦惈偵偮偄偰専摙偡傞丅 (1) 傑偢丄塃奺昗復偺峔惉偵偮偄偰傒傞偵丄(C)昗復偺偦傟偼乽報憡妛乿偲廲彂偟偨傕偺偱偁傝丄(D)昗復媦傃(E)昗復偼偙傟偵丄乽報復乿枖偼乽廆壠乿偲偄偆擔忢峀偔巊梡偝傟傞岅偑晅壛偝傟偨偵偡偓側偄傕偺偱偁傝丄偟偐傕丄偙傟傜嶰幰偼丄偦偺帤懱偵偙傟偲偄偮偨摿挜偑傒傜傟側偄丅偟偐偟偰丄乽報憡妛乿偼偡偱偵慜(堦)偺偲偍傝丄屆偔偐傜晛捠柤徧偲偟偰報復偺惢嶌傗偦偺堈愯偺暘栰偵偍偄偰梡偄傜傟偰偄偨傕偺偱偁傞偐傜丄偙偺傛偆側岅偐傜側傞昗復偺応崌偵偼丄偦偺昗復偵傛傝旐峊慽恖偺惢嶌偵學傞報復偲偟偰彜昳偺弌強昞帵婡擻偑壥偝傟傞偲偲傕偵偦偺廃抦惈偑擣傔傜傟傞偨傔偵偼丄偙偺傛偆側昗復偑晅偝傟偨彜昳偑丄憡摉峀斖埻偵斝晍偝傟傞側偳摿抜偺帠忣偑側偗傟偽側傜側偄傕偺偲偄偆傋偒偱偁傞丅 (2) 偟偐偟偰丄旐峊慽恖偼丄徍榓巐幍擭摉帪堦擭娫偵嶰屲乑乑屄梋偺報復傪攧傝忋偘丄傑偨丄偦偺庡挘偺彂暔傪徍榓堦堦擭埲棃栺擇乑枩晹斕攧偟偨傎偐丄偙偺彂暔傪怴暦摍偵傛偮偰峀崘偟偨巪庡挘偡傞丅 偟偐偟丄傢偑崙偵偍偄偰報復偑恖乆偺擔忢惗妶忋晄壜寚側傕偺偲偟偰嬌傔偰廳梫側婡擻傪壥偟偰偍傝丄奺恖偑強帩偟枖偼擔偛傠斕攧偝傟傞報復偼偍傃偨偩偟偄悢偵偺傏傞傕偺偱偁傞偙偲偑梕堈偵悇應偱偒傞偙偲丄(C)昗復丄(D)昗復媦傃(E)昗復偼丄偦傟帺懱枖偼偦偺庡梫峔惉晹暘偱偁傞乽報憡妛乿偺岅帺懱偐傜彜昳偺幆暿婡擻傪廩暘偵壥偟偆傞傕偺偲偼摓掙擣傔擄偄偙偲媦傃曎榑偺慡庯巪傪暪偣峫偊傞偲丄偨偲偊丄旐峊慽恖偺惢嶌斕攧偟偨報復偺悢媦傃偦偺挊彂傗挊彂偺峀崘偑旐峊慽恖偺庡挘偳偍傝偱偁傞偲偟偰傕丄(C)昗復丄(D)昗復媦傃(E)昗復偑丄 愱傜旐峊慽恖偵學傞報徾傪昞傢偡傕偺偲偟偰丄偦偺庢堷幰廀梫幰娫偵峀偔擣幆偝傟偰偄偨傕偺偲偼擣傔傞偵懌傝偢丄懠偵偙傟傪擣傔傞偵懌傝傞徹嫆偼側偄丅 擇 師偵丄(A)媦傃(B)昗復偲(傾)媦傃(僀)昗復偺椶帡惈偵偮偄偰峫偊傞丅 (傾)昗復(彜崋)偼丄暿巻偺偲偍傝丄乽廆壠擔杮報憡嫤夛乿偺岅偺忋偵乽姅幃夛幮乿偺暥帤偑晅壛偝傟偨峔惉偱偁傝丄傑偨丄(僀)昗復偼丄暿巻偺偲偍傝丄乽廆壠乿偺暥帤偑偙傟偵懕偔廲彂偒偺乽擔杮報憡嫤夛乿晹暘偵斾妑偟偰彫偝偔丄偐偮丄 墶彂偒偵晅壛偝傟偰偄傞峔惉媦傃乽廆壠乿偺岅偑丄堦斒偵丄堦栧偺杮廆偨傞壠嬝丄 杮壠丄壠尦側偳偺堄偵峀偔梡偄傜傟傞傕偺偱偁傞偙偲偵挜偡傞偲丄(傾)昗復偵偮偄偰偼乽姅幃夛幮乿媦傃乽廆壠乿偺晹暘偑丄傑偨丄(僀)昗復偵偮偄偰偼乽廆壠乿偺晹暘偑偄偢傟傕棯偝傟偰丄乽擔杮報憡嫤夛乿偺晹暘偩偗偱徧屇偝傟傞応崌傕偁傞偱偁傠偆偙偲偼宱尡懃忋惀擣偱偒傞偲偙傠偱偁傞丅 偟偐偟偰丄(A)媦傃(B)昗復偺乽擔杮報憡妛夛乿偲(傾)媦傃(僀)昗復拞偺乽擔杮報憡嫤夛乿偲偵偍偗傞丄乽擔杮報憡乿偺晹暘偼丄乽擔杮乿偵偮偄偰偼傕偲傛傝丄乽報憡乿傕慜弎偺偲偍傝堦斒偵梡偄傜傟傞梡岅偱偁傞偙偲丄(A)媦傃(B)昗復偵偍偗傞乽妛夛乿晹暘暲傃偵(傾)媦傃(僀)昗復偵偍偗傞乽嫤夛乿晹暘偑偦傟偧傟乽擔杮報憡乿晹暘偲摨堦偺戝偒偝丄摨堦偺彂懱偱堦懱偵婰嵹偝傟偰偄傞峔惉偱偁傞偙偲偵偐傫偑傒傞偲丄偙傟傜偺昗復拞乽擔杮報憡乿偺晹暘偺傒偑丄 乽妛夛乿晹暘傗乽嫤夛乿晹暘偲暘棧偟偰徧屇偝傟傞偲偼峫偊傜傟偢丄(A)媦傃(B)昗復偺乽擔杮報憡妛夛乿偲(傾)媦傃(僀)昗復拞偺彮側偔偲傕乽擔杮報憡嫤夛乿晹暘偲偼丄偄偢傟傕堦楢偵徧屇偝傟傞傕偺偲夝偡傞偺偑憡摉偱偁傝丄偙傟偲暿堎偵夝偡傋偒摿抜偺帠忣偼擣傔傜傟側偄丅 偦偆偡傞偲丄(A)媦傃(B)昗復偺乽擔杮報憡妛夛乿偲(傾)媦傃(僀)昗復拞偺乽擔杮報憡嫤夛乿偲傪懳斾偟偰傒傞偵丄椉幰偼丄偦傟偧傟暿巻婰嵹偺偲偍傝偺峔惉偺傕偺偱偁偮偰丄偦偺嫟捠偺乽擔杮報憡乿偺晹暘偼丄忋弎偟偨偲偍傝堦斒揑側梡岅偺堟傪弌傞傕偺偱偼側偔丄偐偮丄乽妛夛乿偲乽嫤夛乿偺晹暘傕丄悽忋堦斒偵廫暘嬫暿偟偰擣幆偟巊梡偝傟傞岅偱偁傞偺傒側傜偢丄椉晹暘傪奺堦懱偲偟偰傒傞偲偒丄偦偺偄偢傟偐堦曽偑丄懠曽傪曪愛偡傞傛偆側娭學偵偁傞偲偐丄懠曽偲暘攈揑側娭學偵偁傞傗偵岆夝偝傟傞偙偲側偳傕峫偊傜傟側偄偙偲偵挜偡傟偽丄偝傜偵懡偔傪榑偢傞傑偱傕側偔丄偦偺奜娤媦傃徧屇偵偍偄偰偼傕偲傛傝丄娤擮忋傕椶帡偡傞傕偺偲偼擣傔傜傟側偄丅偟偨偑偮偰丄(A)媦傃(B)昗復偲(傾)媦傃(僀)昗復偲偼丄偦傟偧傟斵崯崿摨傪惗偢傞偍偦傟偑側偔丄椉幰偼椶帡偟側偄傕偺偲偄偆傋偒偱偁傞丅 傛偮偰丄峊慽恖偵偍偄偰(傾)媦傃(僀)昗復傪巊梡偡傞偙偲偑丄懠恖偱偁傞旐峊慽恖偺塩嬈枖偼彜昳偨傞偙偲傪帵偡昞帵偲摨堦枖偼椶帡偺傕偺傪巊梡偡傞傕偺偲偄偆偙偲偼偱偒側偄丅 嶰 慜堦丄擇偵弎傋偨偲偍傝偱偁傞偐傜丄旐峊慽恖偺晄惓嫞憟杊巭朄1忦1崁偵婎偯偔惪媮偼丄偦偺梋偺揰偵偮偄偰敾抐偡傞傑偱傕側偔棟桼偑側偄丅 |
|
|
彜昗朄偵婎偯偔惪媮偵偮偄偰
堦 旐峊慽恖偑怽惪偺棟桼擇偺1偵庡挘偡傞偲偍傝丄(F)媦傃(G)彜昗偺彜昗尃傪庢摼偟偨偙偲媦傃峊慽恖偑丄(僂)丄(僄)丄(僆)丄(僇)偺奺昗復傪峀崘摍偵巊梡偟偰偄傞偙偲偼丄摉帠幰娫偵憟偄偑側偄丅 擇 偲偙傠偱丄峊慽恖偼丄(僂)丄(僄)丄(僆)丄(僇)偺奺昗復偵娷傑傟傞乽報憡乿丄乽報憡妛乿偺岅偼丄傕偲傕偲晛捠柤徧偱偁傝丄峊慽恖偑峀崘摍偵(僂)丄(僄)丄(僆)丄(僇)偺昞帵傪偟偨偺傕晛捠柤徧偲偟偰婰弎揑偵梡偄偨偵偡偓側偄巪庡挘偡傞丅 惉棫偵憟偄偺側偄慲峛戞堦擇崋徹偺堦側偄偟巐偵傛傞偲丄偙傟傜怴暦峀崘拞偵婰嵹偝傟偰偄傞乽報憡妛乿偺昞帵拞偵偼丄側傞傎偳乽報憡妛乿偺桼棃傗堄媊側偳報憡妛偦傟帺懱偵娭偡傞婰弎偲傒傜傟傞傕偺傕嶶尒偝傟丄偙偺傛偆側傕偺偼丄彜昳偵偮偄偰巊梡偟偰偄傞傕偺偲偼夝偝傟側偄偐傜丄偙傟傪彜昗朄忋偵偄偆彜昗偺巊梡偲偼擣傔擄偄丅偟偐偟丄乽報憡妛乿偺岅偼丄慜弎偺偲偍傝丄扨偵報復偺憡偵娭偡傞妛栤偲偄偆偩偗偺堄枴偵偲偳傑傜偢丄報復偺憡側偳偵偮偄偰堈愯偺尒抧偐傜媑嫢傪敾抐偡傞堈愯弍側偄偟妛栤偺堄枴偵傕梡偄傜傟傞偐傜丄偙偺岅偑報娪偲寢崌偟偰梡偄傜傟傞偲偒偵偼丄彜昳偱偁傞報娪偺昳幙丄岠擻丄惗嶻偺曽朄側偳傪傕昞帵偡傞婡擻傪壥偡傕偺偲偄偊傞丅偦偆偡傞偲丄(僄)丄(僆)丄(僇)偺昞帵偼傕偲傛傝丄 (僂)偺昞帵傕丄慜宖慲峛戞堦擇崋徹偺堦偵傛傞偲丄乽報憡妛偵惗奤傪偐偗傞妭愇愭惗乿偲偄偆峀崘拞偺尒弌偟偺拞偱梡偄傜傟偨傕偺偱偁傝丄偦偺晹暘偵偼丄乽摨恖偑偦偺報憡妛偵婎偯偄偰偟偨尋媶偐傜報偺媑憡傪尒弌偟偰娪掕傪峴偄丄峊慽恖偺報娪偼丄偙偺傛偆側娪掕偵婎偯偄偰昳幙偑曐徹偝傟偰偄傞丅乿巪偺婰嵹偑偁傞偙偲偐傜偡傞偲丄峊慽恖偺彜昳偨傞報娪偵偮偄偰巊梡偝傟偰偄傞傕偺偲偄偆傋偒偱偁傝丄 偟偨偑偮偰丄彜昗朄忋偺彜昗偺巊梡偵奩摉偡傞傕偺偲夝偝傟傞丅 嶰 偦偙偱丄峊慽恖偺彜昗朄戞26忦偵娭偡傞庡挘偵偮偄偰専摙偡傞丅 慜宖慲峛戞堦擇崋徹偺堦側偄偟巐媦傃曎榑偺慡庯巪偵傛傞偲丄(僂)丄(僄)丄 (僆)丄(僇)偺奺昗復偼丄偄偢傟傕慜弎偺偲偍傝丄彮側偔偲傕報復偺惢嶌丄偦偺堈愯偺暘栰偵偍偄偰屆偔偐傜梡偄傜傟偰偄偨乽報憡妛乿偺岅傪偦傟帺懱偱枖偼乽報娪乿丄乽夛幮報乿偺岅偲崌傢偣偰丄慜弎偺偲偍傝偺晛捠偵梡偄傜傟傞梡岅朄偵廬偮偰梡偄丄偙傟偵傛偮偰丄峊慽恖偺彜昳偱偁傞報復偑偙偺傛偆側報憡妛偵婎偯偄偰惢嶌偝傟偨傕偺偱偁傞巪傪昞帵偡傞偨傔偵梡偄傜傟偰偄傞傕偺偱偁傞偙偲偑擣傔傜傟傞丅 偦偆偡傞偲丄塃偺奺昗復偼丄彜昗朄戞26忦戞1崁戞2崋偵偄偆(F)彜昗偺巜掕彜昳偲摨堦枖偼椶帡偺彜昳偺昳幙丄岠擻丄惗嶻偺曽朄側偳傪晛捠偵梡偄傜傟傞曽朄偵傛偮偰昞帵偡傞彜昗偲偄偆傋偒偱偁傞丅 偦偆偱偁傞偲偡傟偽丄(F)彜昗偵偮偄偰偺彜昗尃偺岠椡偼丄(僂)丄(僄)丄 (僆)丄(僇)偺奺昗復(彜昗)偵偼媦偽側偄偲偄偆傋偒偱偁傞丅 旐峊慽恖偼丄報娪偺昳幙偲偄偊偽丄偦偺巊梡嵽椏傪偄偄丄帤懱側偳偼偙傟偵娷傑傟側偄巪庡挘偡傞丅側傞傎偳丄報娪偵梡偄傜傟傞嵽椏偺偄偐傫偑報娪偺昳幙偵學傞偙偲偼摉慠偱偁傞偑丄偙傟偵尷掕偝傟傞傋偒崌棟揑棟桼偼側偔丄報塭傪昞弌偝偣傞偲偄偆報娪杮棃偺婡擻偵娪傒傞偲丄偙傟偵崗偝傟偨帤懱偺偄偐傫傕傑偨昳幙丄岠擻側偳偵學傞傕偺偱偁傞偙偲偼柧傜偐偱偁傞(場傒偵丄慜宖旐峊慽恖杮恖恞栤偺寢壥拞偵傕丄旐峊慽恖偺惢嶌偵偐偐傞報娪偼丄摨恖偺偄偆報憡妛偵懃傝桇摦旤偵偁傆傟偨帤懱偱偁傞偲偙傠偵摿怓偑偁傞偲偺庯巪偺嫙弎晹暘偑偁傞丅)丅偟偨偑偮偰丄慜弎偺偲偍傝報憡妛揑尒抧偐傜惢嶌偝傟偨傕偺偱偁傞偐斲偐偼丄報娪偺昳幙傪傕昞帵偡傞梫慺偲傒傞傋偒偱偁傝丄旐峊慽恖偺塃庡挘偼幐摉偱偁傞丅 巐 (G)彜昗偲(僀)昗復偲偑椶帡偟側偄傕偺偱偁傞偙偲偼丄戞堦偺擇偵弎傋偨偲偙傠偲摨條偱偁傞丅 屲 偦偆偡傞偲丄旐峊慽恖偺彜昗朄偵婎偯偔惪媮傕丄偦偺梋偺揰偵偮偄偰敾抐偡傞傑偱傕側偔丄棟桼偑側偄丅 |
|
|
彜朄偵婎偯偔惪媮
(A)昗復偲(傾)昗復偲偑椶帡偟側偄偙偲偼戞堦偺擇偵弎傋偨偲偍傝偱偁傝丄 塩嬈偵偮偄偰憡屳偵岆擣崿摨傪惗偤偟傔傞傕偺偲偼擣傔傜傟側偄丅 偦偆偡傞偲丄彜朄戞21忦偺婯掕偵婎偯偔杮審惪媮傕偦偺梋偺揰偵偮偄偰敾抐偡傞傑偱傕側偔丄幐摉偲偄傢側偗傟偽側傜側偄丅 |
|
|
寢榑
傛偮偰丄旐峊慽恖偺晬懷峊慽偼偡傋偰棟桼偑側偄偐傜丄偙傟傪婞媝偟丄峊慽恖偺峊慽偼棟桼偑偁傞偐傜丄尨敾寛拞峊慽恖攕慽偺晹暘傪庢徚偟丄晬懷峊慽恖偺杮審怽惪傪媝壓偡傞偙偲偲偟丄慽徸旓梡偺晧扴偵偮偒柉帠慽徸朄戞96忦丄戞89忦偺奺婯掕傪揔梡偟偰丄庡暥偺偲偍傝敾寛偡傞丅 |
| 嵸敾姱 | 峳栘廏堦 |
|---|---|
| 嵸敾姱 | 摗堜弐旻 |
| 嵸敾姱 | 惔栰姲曖 |