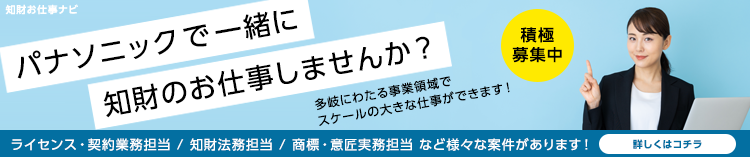この判例には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
| 審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
|---|---|---|
| 平成19ネ3057商標権侵害差止等請求控訴事件 平成20ネ420同附帯控訴事件 | 判例 | 商標 |
| 平成20ワ19774商標権侵害差止等請求事件 | 判例 | 商標 |
| 平成12ワ366商標権侵害による損害賠償請求事件 | 判例 | 商標 |
| 平成2ワ3599 | 判例 | 商標 |
| 平成9ワ10409 | 判例 | 商標 |
| 関連ワード | 指定商品 / 不正競争の目的 / 不使用 / 損害額 / 使用料相当額 / 消滅時効 / 先使用(32条) / 専用使用権 / 外観(外観類似) / 称呼(称呼類似) / 観念(観念類似) / 差止 / 損害額の推定 / 連合商標 / 先使用権 / 継続 / 非類似 / 商号 / 利益額 / |
|---|
| 元本PDF |
裁判所収録の全文PDFを見る
|
|---|---|
| 元本PDF |
裁判所収録の別紙1PDFを見る
|
| 事件 |
昭和
49年
(ワ)
1767号
|
|---|---|
| 裁判所のデータが存在しません。 | |
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
| 判決言渡日 | 1978/03/27 |
| 権利種別 | 商標権 |
| 訴訟類型 | 民事訴訟 |
| 主文 |
被告株式会社盛光は、その販売する金切鋏につき、別紙標章目録(一)、(二)記載の各標章を使用してはならない。 被告らは連帯して原告に対し,金六五〇万九四二八円及びこれに対する昭和四九年三月二一日から支払済みまで年五分の割合による金員の支払をせよ。 原告のその余の請求をいずれも棄却する。訴訟費用はこれを三分し、その二を原告の負担とし、その余を被告らの負担とする。 この判決は原告勝訴の部分に限り仮に執行することができる。 |
| 事実及び理由 | |
|---|---|
|
当事者の求めた裁判
一 原告1 被告株式会社盛光は、その製造、販売する金切鋏につき、別紙標章目録(一)、(二)記載の各標章を使用してはならない。 2 被告株式会社盛光は、その所有しかつ占有する別紙標章目録(一)、(二)記載の各標章を付した金切鋏及びその容器を廃棄せよ。 3 被告らは連帯して原告に対し、金五〇〇〇万円及びこれに対する昭和四九年三月二一日から支払済みまで年五分の割合による金員の支払をせよ。 4 被告株式会社盛光は、東京都台東区<以下略>日本刃物工具新聞社及び東京都千代田区<以下略>株式会社日本金物新聞社の発行する各新聞紙上に別紙謝罪広告目録記載の文面、体裁による謝罪広告を掲載せよ。 5 訴訟費用は被告らの負担とする。 との判決並びに4項を除き仮執行の宣言二 被告ら1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 との判決 |
|
|
当事者の主張
一 原告の請求の原因1 原告は、昭和四五年一二月一八日別紙原告商標権目録(一)記載の商標権(以下、「本件商標権」といい、その登録にかかる商標を「本件商標」という。)を取得した。 2 被告株式会社盛光(以下、「被告会社」という。)は、昭和四六年一月以降業として金切鋏を他から購入し、右鋏及びその容器に別紙標章目録(一)、(二)記載の各標章(以下、総称して「被告標章」といい、各別に「被告標章(一)」等という。)を付して販売している。 3 本件商標と被告標章とを対比すれば、次のとおりである。 すなわち、本件商標の構成は、「<12060-001>」の記号に「久」の漢字を「<12060-001>」の内側に配記し、その下部に「盛光」の二漢字を縦書きしたものであるところ、その要部は「盛光」の部分にあり、外観上も右の部分が看者の注意を強くひき、称呼上も「もりみつ」と呼称されやすく、観念上も「久」の部分は一種の符号にすぎず、「盛光」の部分から生ずる、光が盛んに輝きあふれるとの意味を懐かせる。一方、被告標章の構成は、「盛光」の二漢字を縦書きしたもの(被告標章(一))又は「盛光」の二漢字を縦書きしその上部に「登録」の二漢字を横書きしたもの(被告標章(二))であつて、後者の要部は「盛光」の部分にある。したがつて、本件商標と被告標章とは、その要部を共通にし、 外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似するものである。 なお、原告は、本件商標の連合商標として、別紙原告商標権目録(二)ないし(四)記載の各商標登録出願をし、出願公告中であるところ、これらの商標の構成は、順次「<12060-002>特製盛光」と縦書きしたもの、「<12060-002>」のみのもの及び縦書きした「盛光」の右側に「もりみつ」の平仮名を付したものであつて、このことは、本件商標の要部が「盛光」の部分にあり、したがつて本件商標と被告標章とが類似することを裏付けるものである。 そして、金切鋏は本件商標の指定商品に該当するから、金切鋏につき被告標章を使用することは本件商標権に対する侵害行為を構成する。 4(一) 被告会社は、金切鋏につき被告標章を使用することが本件商標権を侵害するものであることを知り、又は取引上必要な注意を用いれば知りえたにもかかわらずこれを知らなかつた過失により、前記のとおり業として他の業者から金切鋏を仕入れ、これに被告標章を付して販売しているものであるから、右侵害行為によつて原告が蒙つた損害を賠償する義務がある。 (二) また、被告【A】(以下、「被告【A】」という。)は、被告会社の代表取締役としてその業務を統轄掌理している者であるが、悪意又は重大な過失により、その代表取締役としての職責を懈怠し、被告会社の前記侵害行為を発生させたものであるから、商法第266条の3の規定により、被告会社と連帯して原告の損害を賠償する義務がある。 5 被告会社の前記侵害行為によつて原告が蒙つた損害は、次のとおりである。 (一) 被告会社は、昭和四六年一月から昭和四八年一二月までの三年間に、一か月平均六六九四丁、合計二四万〇九八四丁の金切鋏を仕入れ、これに被告標章を付したうえ販売し、一丁当たり平均金四四四円、合計金一億〇六九九万六八九六円の純利益を得ていたものであるから、右純利益の額が原告の損害の額と推定されるべきものである。 ところで、原告自身は前記期間中金切鋏の製造販売を行つておらず、本件商標の使用もしていなかつたものであるが、損害額の推定に関する商標法第38条第1項の規定は、その適用の有無につき商標の使用、不使用の別による限定を設けていないから、権利者がその商標を使用していない場合にも当然適用があると解すべきである。 仮に右規定の適用があるのは権利者自ら商標を使用している場合に限ると解すべきであるとしても、商標を使用しているか否かは形式論理的にではなく実質的に判断すべきであり、この見地からすれば原告もなお前記期間中本件商標を使用していたと同視されるべく、したがつて前記推定規定の適用を受けうるものである。すなわち、原告は昭和一二年鍛冶名を「盛久」と称する師匠【B】から「盛光」の鍛冶名を与えられて独立し、以来「盛光」もしくは「<12060-003>盛光」の刻印を付した金切鋏を製造販売していたが、その製品は極めて優秀であつたため、 たちまち「盛光」印金切鋏として全国的に周知著名になり、需要も増大するに至つた。そこで、原告は、従業員を増やし、工場設備の改善を図る一方、昭和二六年三月には有限会社茂盛光製作所(以下「訴外有限会社」という。)を設立し、自らその代表取締役に就任するとともに、原告個人の営業を同会社に承継させ、昭和四五年本件商標権を取得した後は同会社に本件商標の使用を許諾して現在に至つている。そして、原告が従前の個人営業を有限会社組織としたのは主として税務対策等への考慮によるものであつて、その前後で営業の実態には何らの変化もなく、一貫して原告自ら先頭に立つて業務に精励してきたものである。右の事実と、前記推定規定が損害額の立証の困難さを救済することを目的とするものであること及びその適用の有無につき前述のとおり明文上格別の限定がないことを合わせ考えると、原告の場合もなお前記推定規定の適用を受けると解するのが相当である。 (二) 仮に右の主張が認められないとしても、本件商標の通常使用料率は金切鋏の販売価格の三パーセントが相当であるところ、被告会社の販売する金切鋏の一丁当たりの平均販売価格は金一一二〇円であるから、一丁当たりの使用料額は金三三円六〇銭であり、一方前記期間中の被告会社による金切鋏の販売数量は二四万〇九八四丁であるから、その使用料相当額の総額は金八〇九万七〇六二円となり、原告は被告会社の前記侵害行為によつてこれと同額の損害を蒙つたものである。 また、原告は被告会社の前記侵害行為によつて後記6のとおり著しくその信用を毀損され、精神的苦痛を味わわされたものであり、これを金銭で慰藉するとすれば、金五〇〇万円が相当である。 6 被告会社の前記侵害行為により、その販売する金切鋏を原告の製造品と誤認する顧客が続出し、しかも被告会社の販売品が極めて粗製濫造のものであつたところから、その性能についての苦情が原告のもとに殺到するなどし、原告の信用は著しく毀損された。被告会社は、毀損された原告の信用を回復するための措置として、 別紙謝罪広告目録記載の文面、体裁による謝罪広告を前記日本刃物工具新聞社及び株式会社日本金物新聞社の発行する各新聞紙上に掲載する義務がある。 7 被告会社は、被告標章を付した金切鋏及びその容器を常時二〇〇〇組以上所有しかつ占有している。 8 よつて、原告は、被告会社に対し、その製造販売する金切鋏につき被告標章を使用することの差止、その所有しかつ占有する被告標章を付した金切鋏及びその容器の廃棄並びに前記謝罪広告の掲載を求め、また被告らに対し、前記損害金の内金五〇〇〇万円及びこれに対する前記侵害行為の後である昭和四九年三月二一日から支払済みまで民事法定利率年五分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める。 二 請求の原因に対する被告らの認否及び主張1 請求の原因1の事実は認める。 2 同2の事実中、被告会社が昭和四六年一月以降昭和四八年八月末までの間、業として金切鋏を他から購入し、容器ともども被告標章を付したうえ販売したことは認め、その余は否認する。 被告会社は、昭和四八年九月以降金切鋏につき被告標章を使用しておらず、また今後使用する意思もない。ちなみに、被告会社が右の時点以降金切鋏につき使用している標章は、別紙被告商標権目録(一)、(二)記載のとおりであり、いずれについても被告会社が指定商品第一三類につき商標権を有するものである。 3 同3の事実中、金切鋏が本件商標の指定商品に該当することは認め、その余は否認する。 本件商標と被告標章とは類似しない。すなわち、本件商標は「<12060-003>」と「盛光」が主従の区別なく一体として結合したものであるのに対し、被告標章は単に「盛光」とあるか、これに「登録」の文字を加えたものである。したがつて、本件商標からは「かねひさもりみつ」の称呼を生じ、「かねひさのもりみつ」との観念を生じるのに対し、被告標章からは単に「もりみつ」の称呼と「もりみつ」の観念を生じるにすぎない。 また、原告は別紙原告商標権目録(五)記載の商標権を有しており、その商標は「光」の字のはねを上方に延長して若干図案化してはいるが、明確に「茂盛光」と読解できるものであるところ、本件商標は右商標とは連合商標としてではなく、別個独立の商標として出願されかつ登録されている。このことからも被告標章が本件商標と類似しないことは明らかである。 4(一) 同4(一)の事実中、被告会社が昭和四六年一月から昭和四八年八月末までの間、金切鋏を他から仕入れ、これに被告標章を付して販売したことは認め、 その余は否認する。 (二) 同4(二)の事実中、被告【A】が被告会社の代表取締役としてその業務を統轄掌理していることは認め、その余は否認する。 被告【A】には、被告会社の代表取締役として、悪意又は重大な過失による任務懈怠はなかつた。すなわち、被告【A】は、後記抗弁3のとおり、昭和四七年一〇月までは本件商標権の存在を知らず、また知らなかつたことにつき過失もなかつたものであり、本件商標権の存在を知つた後も、後記抗弁1、2及び5のとおり、被告会社に被告標章を使用しうべき正当な権原があると信じ、またこのように信じたことにつき、少なくとも重大な過失はなかつたものである。 5(一) 同5(一)の事実中、被告会社が昭和四六年一月から昭和四八年八月末までの間、金切鋏を他から購入し被告標章を付したうえ販売したこと、その数量は合計五万六六六七丁であること、原告自身がその主張の期間中金切鋏の製造販売及び本件商標の使用をしていなかつたこと、昭和二六年三月訴外有限会社が設立されて原告がその代表取締役に就任し、原告の個人営業が同会社に承継されたことは認め、その余は否認する。 原告はその主張の期間中自ら金切鋏の製造販売をしていたわけではないから、仮に被告標章の使用が本件商標権を侵害するとしても、高々使用料相当額の損害を蒙つたにすぎない。 (二) 同5(二)の事実中、本件商標の通常使用料率は金切鋏の販売価格の三パーセントが相当であることは認め、その余は否認する。 6 同6の事実は否認する。 7 同7の事実は否認する。 三 被告らの抗弁1 先使用権の主張(一) 被告会社は、板金機械工具の販売を業とする会社であつて、昭和二三年株式会社テイケイ物産商会として発足し、昭和三七年九月一八日その商号を現商号に変更したものであるが、発足当初から原告と取引し、原告(昭和二六年三月以降は訴外有限会社)の製造した「<12060-003>盛光」の標章のある金切鋏を販売し、一時はその製造量の約八割を取り扱うほどであつた。ところが、原告は、 昭和二七、八年頃から被告【A】と意思の疎通を欠くようになり、訴外有限会社から被告会社への金切鋏の納入を停止させてしまつた。そこで、被告会社は、別紙被告旧商標権目録(一)ないし(三)記載の各商標権を取得し、ことに昭和三〇年五月一二日右(二)の商標登録を経由した後は、積極的に別途仕入れた金切鋏に「<12060-003>盛光」の標章あるいは被告標章を付して販売するに至つた。 (二) 被告会社にはもとより不正競争の目的はなかつた。すなわち、被告会社は右(二)の商標権に関し原告との間に紛争を生じたが、昭和三〇年七月八日原告と被告会社及び被告【A】との間で、右の紛争につき、右(二)の商標権は被告【A】が所有し、原告は無断でこれを使用しない旨の和解が成立した(乙第二三号証)。右の和解によつて、少なくとも昭和三〇年七月八日以降における被告会社の、「<12060-003>盛光」の標章及び被告標章の使用は、原告との関係で適法なものとなつたのであり、何ら不正競争となるものではない。また、原告がその頃から用いるようになつた後記(三)の「茂盛光」の標章と「<12060-003>盛光」の標章及び被告標章とは類似しないから、この点からも不正競争となるものではない。 (三) 一方、原告は、昭和二九年九月九日別紙原告商標権目録(五)記載の商標登録出願をするとともに、右出願にかかる「茂盛光」の標章を訴外有限会社の製造する金切鋏の標章として使用させるようになり、かつ自ら、「<12060-003>盛光」は当所では一切製作しておりませんので、市場に出ておりましても当所の製品ではありませんから、特に御注意願います、との宣伝広告をして、「茂盛光」を使用し「<12060-003>盛光」は使用しない旨を明らかにした。 (四) その結果、本件商標の登録出願日である昭和三三年九月二〇日以前において、「<12060-003>盛光」の標章ないし被告標章は被告会社の販売する金切鋏の標章として需要者間に広く知られるに至り、被告会社はその後もその使用を継続していた。したがつて、被告会社は、商標法第32条第1項の規定に基づき、被告標章について先使用による使用権を有するものである。 2 中用権の主張(一) 被告会社は、前記のとおり別紙被告旧商標権目録(一)ないし(三)記載の各商標権を有していた。 (二) 被告会社は、原告から右(一)の商標登録につき昭和三四年八月八日、右(二)及び(三)の各商標登録につき昭和三二年五月四日それぞれ無効の審判の請求を受け、右(二)及び(三)については、無効の審判の請求があつた旨、同月三一日に登録がされた。次いで、昭和四一年五月二六日右(一)ないし(三)の各商標登録の無効が確定し、昭和四二年三月三日その抹消登録がされた。 (三) そして、被告会社は右(二)及び(三)の各商標権に基づき金切鋏に被告標章を使用していたものであり、被告標章は前記無効の審判の請求の登録の日である昭和三二年五月三一日以前において、被告会社の販売する金切鋏の標章として需要者間に広く知られていた。もとより被告会社としては右(二)及び(三)の各商標登録に無効原因があることを知らなかつた。 (四) したがつて、被告会社は、商標法第33条第1項の規定に基づき、前記(二)及び(三)の各商標権を有していたことの効果として被告標章を使用する権利を有する。 3 無過失の主張(一) 被告会社は、本件商標の出願公告に対し、登録異議の申立をしていたため、右申立につき決定がなされるまでは本件商標の登録が経由されることはないと考えていたところ、右申立についての決定は昭和四五年八月二五日付でなされたにもかかわらず、その決定の謄本は昭和四七年九月二二日に至つて初めて発送され、 その後被告会社に送達された。 (二) このため、被告会社が本件商標の登録されたことを知つたのは昭和四七年一〇月以降のことであり、それまでは被告会社は本件商標権を侵害する故意のなかつたことはもちろん、本件商標権の存在を知らず、かつ知らなかつたことにつき過失もなかつたものである。(三) したがつて、少なくとも昭和四六年一月から昭和四七年九月末までの販売行為については、被告らに損害賠償義務が発生する余地はない。 4 時効の主張 原告主張の損害賠償請求権の消滅時効期間は三年であるところ、原告が右請求権を主張して本訴を提起したのは昭和四九年三月九日であるから、昭和四六年三月九日以前の損害に対応する請求権はすでに時効により消滅しているものである。 よつて、被告らは本訴において右時効を援用する。 5 損害賠償額の決定に関する主張 被告会社には、以下に述べるとおり、本件商標権の侵害につき少なくとも重大な過失はなかつたから、損害賠償額の決定につきこれらの事情を参酌すべきである。 (一) 被告会社は、板金機械工具の卸売業者であるが、金切鋏も板金加工に不可欠の道具であるため、板金工具の一種として取り扱つている。 (二) そして、被告会社は、旧八類利器及び尖刃器について有していた別紙被告旧商標権目録(一)ないし(三)記載の各商標権は無効とされたものの、板金機械と工具類については別紙被告商標権目録(三)ないし(六)記載の各商標権を有しており、しかも被告会社の取扱い商品としては板金機械工具が九割以上を占めているため、板金機械工具における「盛光」の標章は被告会社の商品を示すものとして周知となつている。 (三) ところが、現実の商品としては工具と金切鋏の限界を画することは困難であり、現に業界においては金属切断用の鋏が工具の一種として取り扱われている実情にあり、被告会社においても被告標章の金切鋏への使用を自己の登録商標の使用と考えていたものであつて、本件商標権の侵害につき少なくとも重大な過失はなかつたものである。 四 抗弁に対する原告の認否1(一) 抗弁1(一)の事実中、被告会社が被告ら主張のような会社であつて、 昭和二三年その主張の商号で発足し、昭和三七年九月一八日現商号に変更したこと、被告会社は発足当初から原告又は訴外有限会社の製造した「<12060-003>盛光」の標章のある金切鋏を販売していたが、その後右金切鋏の納入が停止されたこと、被告会社が被告ら主張の各商標権を取得し、別途仕入れた金切鋏に被告ら主張の標章を付して販売したことは認め、その余は否認する。 被告会社による金切鋏の取扱い量は、原告又は訴外有限会社の製造量の概ね二割弱であり、多いときでも三割を超えたことはない。また、訴外有限会社が被告会社への金切鋏の納入を停止したのは昭和三〇年八月であり、被告会社はその頃から別途仕入れた金切鋏に被告ら主張の標章を付して販売するようになつたものである。 (二) 同1(二)の事実は否認する。 被告会社は、従前から原告又は訴外有限会社と取引し、「<12060-003>盛光」ないし「盛光」の標章が原告らの製造販売する金切鋏の標章として使用されていたことを知悉していたから、不正競争の目的がなかつたとはいえない。 (三) 同1(三)の事実中、原告が被告ら主張の商標登録出願をしたこと、訴外有限会社が右出願にかかる標章をその製造販売する金切鋏に使用したことは認め、 その余は否認する。 被告会社の販売する「<12060-003>盛光」の標章のある金切鋏は品質が粗悪であつたところから、訴外有限会社は、出所を混同した顧客から苦情を持ち込まれ、信用を害されるに至つたため、昭和三一年やむなく右標章の使用を中断し、これに代えて「茂盛光」の標章を使用していたが、昭和四八年一二月一日からは右「<12060-003>盛光」の標章の使用を再開している。 (四)同1(四)の事実は否認する。 本件商標の登録出願日当時、「<12060-003>盛光」ないし「盛光」の標章は訴外有限会社の製造販売する金切鋏の標章として需要者間に広く認識されていたものである。 2(一) 同2(一)の事実は認める(二) 同2(二)の事実は認める。 (三) 同2(三)の事実中、被告会社が昭和三二年五月三一日以前から金切鋏につき被告標章を使用していたことは認め、その余は否認する。 (四) 同2(四)の事実は否認する。 3 同3の事実中、被告会社が本件商標の出願公告に対し登録異議の申立をしたこと、右申立についての決定、その謄本の発送、送達が被告ら主張のようになされたことは不知、その余は否認する。 4 同4の事実は、本訴提起の日が被告ら主張のとおりであることを除き否認する。 5 同5の事実中、被告会社が板金機械工具の卸売業者であることは認め、その余は不知。 |
|
|
証拠関係(省略)
理 由一 原告が昭和四五年一二月一八日本件商標権を取得したこと、被告会社が昭和四六年一月から昭和四八年八月末までの間、業として金切鋏及びその容器に被告標章を付して販売したことは、当事者間に争いがない。 二 そこで、本件商標と被告標章との類否につき判断する。 成立に争いのない甲第三号証によれば、本件商標はその構成に照らして「かねひさもりみつ」という比較的長い称呼を有することが明らかであるが、一方、簡易迅速を旨とする取引社会では一般に長い名称の一部を省略して呼称する傾向がみられるうえ、本件商標の構成中「<12060-003>」の部分と「盛光」の部分との間には、意味内容における直接の明確な牽連性や主従の区別を認め難いことも経験則上明らかであるから、「かねひさもりみつ」と一連にのみ呼称すべきものとする特段の証拠のない本件では、本件商標からは右「かねひさもりみつ」のほか、<12060-003>の部分から「かねひさ」、「盛光」の文字から「もりみつ」の称呼をも生じるものと認めるのが相当である。これに対し、原告主張のような構成であることについて被告らも明らかに争わない被告標章(一)からは「もりみつ」、被告標章(二)からは「とうろくもりみつ」ないし単に「もりみつ」との称呼を生じることがそれぞれの構成に照らして明らかである。 右のとおり、本件商標と被告標章とは、ともに「もりみつ」の称呼を生じる点において共通の称呼を有するから、外観及び観念の点につき対比するまでもなく類似するというべきである。 被告らは、本件商標と被告標章とが類似しないと主張し、その根拠として、原告は別紙原告商標権目録(五)記載のとおりの「茂盛光」の構成を有する商標につき商標権を有するところ、本件商標は右商標の連合商標としてではなく、別個独立の商標として登録されている事実をあげる。そして、前掲甲第三号証、成立に争いのない甲第四号証、乙第三号証の一、二によれば、被告らが非類似の根拠として掲げる右事実を認めることができるけれども、本件商標の登録出願に対する審査の過程で、本件商標と先願である右「茂盛光」の商標との類否等につきいかなる見解がとられたかは、ひとたび登録を経た本件商標の範囲の確定とは別個の問題であるから、右の事実の存在は前記結論を左右するものではなく、ほかにこの結論を左右するに足りる資料はない。 三 金切鋏が本件商標の指定商品に該当することは当事者間に争いがない。したがつて、被告会社がその販売する金切鋏につき被告標章を使用することは、被告ら主張の先使用権及び中用権に関する抗弁が立たないかぎり、本件商標権に対する侵害行為を構成するものというべきである。 四 そこで次に、被告らの抗弁につき判断することとし、まず先使用権の主張につき検討する。 被告会社が板金機械工具の販売を業とする会社であつて、昭和二三年株式会社テイケイ物産商会として発足し、昭和三七年九月一八日その商号を現商号に変更したこと、被告会社が当初は原告の、また昭和二六年三月訴外有限会社が設立された後は同会社の製造した「<12060-003>盛光」の標章のある金切鋏を販売していたことは、当事者間に争いがなく、右争いのない事実に、前掲乙第三号証の一、二、成立に争いのない甲第五ないし第一〇号証、第二八、第二九号証、第三一ないし第三九号証、乙第四ないし第七号証の各一、二、第一三号証の一ないし四、 第一四号証の一ないし六、第一五号証及び第一六号証の一ないし四、被告会社代表者兼被告本人【A】の供述により真正に成立したものと認められる乙第一八、第一九号証の各一、二及び第二二号証、弁論の全趣旨により真正に成立したものと認められる乙第二五号証、証人【C】、同【D】(ただし、後記措信しない部分を除く。)、同【E】、同【F】、同【G】及び同【H】の各証言、原告及び被告会社代表者兼被告【A】の各供述(ただし、後記措信しない部分を除く。)並びに弁論の全趣旨を総合すれば、次の事実を認めることができ、この認定に反する趣旨の、 証人【D】の証言部分、被告会社代表者兼被告【A】本人尋問における供述部分は、にわかに措信することができない。 (1) 被告会社は、原告を代表者とする訴外有限会社の製造した「<12060-003>盛光」の標章のある金切鋏を仕入れ、東京都、大阪府、山陽及び山陰方面に販売し、訴外有限会社の製造量の概ね二割程度を取り扱い、これが被告会社の主力商品の一つとなつていたが、昭和二八年末頃、被告会社で仕入れ業務等を担当していた【G】が、代表者である被告【A】と意思の疎通を欠いて退職し、独立して営業を開始したのを機に、訴外有限会社から被告会社への金切鋏の納入量は漸次減少し、昭和三〇年頃にはその納入が全く停止されるに至つたこと。 (2) そこで、被告会社は、金切鋏の販売における銘柄の重要性に鑑み、別途仕入れた金切鋏に「<12060-003>盛光」の標章を付して販売することとし、別紙被告旧商標目録(一)ないし(三)記載の各商標権を取得する一方(右商標権取得の点は当事者間に争いがない。なお、右(一)、(二)の各商標登録出願は被告【A】が行い、後にその登録を受ける権利が被告会社に譲渡された。)、昭和二九年一〇月頃から他の業者の製造した無銘の金切鋏を仕入れ、これに主として「<12060-003>盛光」の標章を付して販売し、ことに右(二)の商標登録を経由した昭和三〇年頃からはより積極的にこれを行うようになり、業界紙に「<12060-003>盛光金切鋏発売元TK物産商会」との広告を掲載し、あるいは出張販売をするなどして販路の拡張にも努めたこと。 (3) 一方、原告は、昭和一二年鍛治名を「盛久」と称する師匠【B】から「盛光」の鍛治名を与えられて独立し、以来「盛光」の刻印を付した金切鋏の製造販売をし、戦時中一時中断したものの、昭和二一年三月復員するや直ちにこれを再開し、その製品が昭和二三年一一月東京都主催の利器工匠具展示会において東京都経済局長賞を得た後は「<12060-003>盛光」の銘を用いるようになつたが、その製品は極めて優れた品質のものであつたところから、「<12060-003>盛光」印もしくは単に「盛光」印の金切鋏として次第に周知となり、需要も増大するに至つたため、製造設備、人員の拡充を図り、昭和二六年三月には訴外有限会社を設立して自ら代表取締役に就任するとともに、従前の個人営業を同会社に承継させ(右会社設立、営業承継の点は当事者に争いがない。)、遅くとも昭和二八年末頃には同会社の製造する金切鋏の販路は被告会社を含む約一〇店の販売業者を通じてほとんど全国に及んでいたこと。 (4) ところが、前記(2)の事情により、原告と被告らとの間に商標権の帰属及び標章の使用をめぐつて紛争が生じたため、原告は、紛議を避け、被告会社の販売商品との誤認混同を回避すべく、ひとまず前記「<12060-003>盛光」の標章の使用を見合わせることとし、昭和三〇年初め頃からは訴外有限会社の製造販売する金切鋏に、すでに昭和二九年九月九日付で自ら商標登録の出願をしていた別紙原告商標権目録(五)記載の「茂盛光」の標章を使用させるようになり、合わせて業界紙に「『<12060-003>盛光』は当所では一切製作しておりませんので、市場に出ておりましても当所の製品ではありませんから、特に御注意願います。」との広告を掲載したが(前掲乙第一六号証の一ないし四)、昭和三四、五年頃までは被告会社の販売商品についての苦情や返品が原告もしくは訴外有限会社宛になされることも少なくなかつたこと。 以上の認定事実を総合すれば、「<12060-003>盛光」ないし「盛光」の標章は遅くとも昭和二八年末頃には訴外有限会社の製造にかかる金切鋏であることを示す標章として需要者間に広く認識されており、前記(4)の経緯により訴外有限会社が「<12060-003>盛光」の標章の使用を中断して専ら「茂盛光」の標章を使用するに至つた後も事態に格別の変化はなく、本件商標の登録出願日である昭和三三年九月二〇日当時においても、「<12060-003>盛光」ないし「盛光」の標章は右に述べたようなものとして需要者間に周知であつたと認めるのが相当である。 この点に関して、被告らは、本件商標登録出願の際、「<12060-003>盛光」の標章ないし被告標章が現に被告会社の販売する金切鋏を表示するものとして需要者間に広く知られていた旨主張し、被告会社代表者兼被告【A】は、本人尋問において右主張に符合する供述をし、また証人【D】の証言の一部に右主張に添うかにみえる部分があるが、証人【F】の証言、原告本人尋問の結果に照らし直ちに信用できない。他に前記認定をくつがえして右主張事実を肯認するに足りる証拠もない。 したがつて、被告らの先使用権の主張は、その余の点につき判断するまでもなく、理由がない。 五 次に、いわゆる中用権の主張につき判断する。 被告らは、被告標章が昭和三二年五月三一日(これが被告ら主張の無効の審判の請求の登録の日であることは、当事者間に争いがない。)当時において、被告会社の販売する金切鋏の標章として需要者間に広く知られていたことを前提として、被告会社が商標法第33条第1項の規定に基づき被告標章を使用する権利を有すると主張する。 しかしながら、右の前提事実を肯認し難いことは、前項に説示したところから明らかであるから、被告らの中用権の主張も、すでにこの点において理由がない。 六 ところで、被告会社は、昭和四八年九月以降は金切鋏に被告標章を使用しておらず、また今後使用する意思もないと主張する。そして、前掲甲第三四ないし第三六号証、乙第二五号証、成立に争いのない乙第一、第二号証の各一、二、被告会社代表者兼被告【A】の供述によれば、被告会社は昭和四八年九月一日以降その販売する金切鋏につき被告標章の使用を中止し、代わりに自ら指定商品第一三類につき商標権を有する、別紙被告商標権目録(一)、(二)記載の各標章を使用していることが認められるけれども、一方、右の各証拠によれば、被告会社は昭和四四年頃から金切鋏につき主として被告標章を使用していたところ、昭和四八年八月被告【A】が検察官から呼出を受け、本件商標権を侵害したことによる商標法違反等の容疑で取調べを受けるに至つたため、被告【A】としては被告会社に被告標章を使用しうべき正当な権限があると考えていたものの、弁護士の助言もあつて、被告会社は同月末限りひとまず被告標章の使用を中止することとしたものであることが認められ、この認定に反する証拠はない。 右認定事実、就中被告会社が被告標章の使用を中止するに至つた経緯に弁論の全趣旨を総合すれば、被告会社は今後なおその販売する金切鋏につき被告標章を使用するおそれがあると認めるのが相当である。 したがつて、被告会社は原告に対し、被告会社の販売する金切鋏につき被告標章を使用してはならないとの不作為義務を負うものである(もつとも、原告はさらに、被告会社の製造する金切鋏についても、被告標章の使用の差止を請求しているが、被告会社は金切鋏を他から購入してこれを販売していると主張するのみで、被告会社が現に金切鋏を製造し、又は将来製造するおそれがあることについては、なんらの主張、立証もないから、この点の請求は理由を欠くものといわなければならない。)。 なお、原告は、被告会社が被告標章を付した金切鋏及び容器を常時二〇〇〇組以上保有していると主張するけれども、これを認めるに足りる証拠はなく、かえつて、被告会社が被告標章の使用を中止して以来相当の時日が経過していることからすれば、被告会社はもはや右侵害品の在庫を所有していないものと推認するのが相当である。 したがつて、原告の被告会社に対する右侵害品の廃棄請求は理由がない。 七 進んで、損害賠償及び謝罪広告掲載の請求の当否につき判断することとし、まず被告らの責任原因につき検討する。 原告による本件商標の登録出願につき昭和四二年一〇月二六日出願公告がなされたことは当事者間に争いがなく、前掲甲第三四ないし第三六号証、乙第二五号証、 成立に争いのない甲第一四号証、乙第九号証、被告代表者兼被告【A】の供述によれば、被告【A】は、被告会社の代表者として、右の出願公告に対し登録異議の申立をしたところ、昭和四五年八月二五日付で、右申立は理由がない旨の決定がなされ、その謄本は同年一〇月九日被告会社宛発送されたものの、何らかの事情で到達しなかつたため、改めて昭和四七年九月二二日発送され、その後被告会社に送達されたことが認められる。そして、被告らは、被告会社が本件商標権の存在を知つたのは右決定謄本が送達された昭和四七年一〇月以降のことであると主張し、前掲甲第三六号証、乙第二五号証及び被告【A】の本人尋問における供述中には、被告【A】が本件商標権の存在を知つたのは昭和四八年八月同被告が検察官の取調べを受けた際であるとの供述記載ないし供述部分がある。 しかしながら、右各証拠は、前掲甲第三六号証、乙第二五号証、成立に争いのない甲第二〇、第二一号証に照らして、にわかに信用できないのみならず、仮に被告会社ないし被告【A】においては、前記登録異議の申立に対する決定がなされるまでは登録が経由されることはないと考えており、そのために、本件商標権の存在を知つたのが昭和四七年一〇月頃(もしくは昭和四八年八月)になつたとしても、この一事をもつて、昭和四七年九月末日までの本件商標権に対する侵害行為につき、 被告会社に過失がなかつたということはできない。けだし、被告会社としては、本件商標の登録出願につき登録異議の申立をしていたからといつて、右申立に対する決定がなされるまでの間に限り、設定登録の有無等に関する調査義務を免れるいわれはないからである。 右のとおり、被告らの無過失の主張は理由がないから、結局被告会社は、昭和四六年一月から昭和四八年八月末までの侵害行為につき、過失責任を負うものというべきものである。 また、被告【A】が右侵害行為の当時被告会社の代表取締役として同会社の業務の全般を統轄していたことは当事者間に争いがなく、前掲甲第三四ないし第三六号証、被告会社代表者兼被告【A】の供述に弁論の全趣旨を総合すれば、被告【A】は、被告会社の営業活動の実際には関与せず、これを長男である【I】にまかせていたが、重要事項の決裁や経理事務等は自ら担当し、ことに商標に関する問題には従前から強い関心を持ち、被告会社の販売商品に使用すべき標章の選択等は自ら行つていたこと、被告会社がその販売する金切鋏に被告標章を使用することとしたのも被告【A】の決定に基づくものであることが認められ、この認定に反する証拠はない。 そうすると、被告【A】は、被告会社の代表取締役として、同会社による被告標章の使用を制止すべき職務上の義務を負つていたところ、これを怠つたばかりか、 かえつて右侵害行為を決定、遂行させたのであるから、その任務の懈怠につき悪意又は少なくとも重大な過失があつたというべきである。 なお、被告【A】は、同被告に悪意又は重大な過失による任務懈怠はなかつたと主張し、その根拠としてあれこれ事由を述べるが、いずれも前記侵害行為についての過失に関する事情にすぎず、任務懈怠につき悪意又は重大な過失がなかつたことを窺わせるものとはいえないから、到底前記結論を左右するに足りない。 以上によれば、被告会社は民法第709条、被告【A】は商法第266条の3の各規定に基づき、連帯して、被告会社の本件商標権に対する侵害行為によつて原告が蒙つた損害を賠償する義務を負うことになる。 八 次に、時効の主張につき判断する。 被告会社が昭和四六年一月から昭和四八年八月末まで本件商標権に対する侵害行為を継続したことは前に説示したとおりであるところ、原告が右侵害行為による損害及び加害者を知つた時期につき明確な証拠の見当らない本件では、原告は右侵害行為と同時に損害及び加害者を知つたものと認めるほかはない。 ところで、右侵害行為すなわち不法行為に基づく損害賠償請求権のいわゆる消滅時効期間は三年であること民法第724条の規定から明らかであり、原告が右請求権の行使として本訴を提起したのが昭和四九年三月九日であることは本件記録上明らかであるから、昭和四六年三月九日以前の損害(すなわち侵害行為)に対応する請求権はすでに時効により消滅しているものというべきである。 九 次に、原告が賠償を受けるべき損害の額につき判断する。 原告は、商標法第38条第1項の規定を援用して、被告会社がその侵害行為によつて得た純利益の額が原告の損害の額と推定されるべきであると主張する。 しかしながら、昭和四六年ないし昭和四八年当時、原告個人が金切鋏の製造販売を行つておらず、本件商標の使用をしていなかつたことは、当事者間に争いがないから、被告らの侵害行為により原告が本件商標の使用を停止せざるをえなくなつたなど特別の事情の認められない本件に、右規定が適用される余地はないものというべきである。けだし、右の規定がその文理上権利者において登録商標を使用している場合にのみ適用されるとの趣旨の限定を設けていないことは原告の指摘するとおりであるけれども、同規定が、商標権又は専用使用権の侵害に対する損害の賠償の請求をいわゆる一般の不法行為に対する損害の賠償の請求としてとらまえていることはその規定の体裁上明らかであり、不法行為により蒙つた損害の賠償の請求は権利者において損害の発生を主張、立証すべきこと多言を要しないことであるから、 同規定は、商標権又は専用使用権に対する侵害行為によつて商標権者又は専用使用権者が蒙つた営業上の損害の額についてその立証が困難であることに鑑み、これを救済することを目的とするものであつて、権利者が蒙つた損害の額を推定するにとどまり、侵害者が侵害行為により受けた利益額と同額の損害を権利者において蒙つたとまで推定するものではないと解すべきものである。したがつて、原告が、右規定の適用を受けるためには、原告が自ら業として登録商標を使用しており、かつその商標権に対する侵害行為によつて現に営業上の損害を蒙つたことを主張立証する必要がある。 原告は、個人として金切鋏の製造販売を行つていたときと訴外有限会社を設立してその営業を承継させた後とで営業の実態には何らの変化もなかつたとして、本件にも右の規定が適用されるべきであると主張するが、原告と訴外有限会社とは法律上別個独立の存在と認めるほかはないから、右主張は採用できない。 したがつて、原告は、前記侵害行為による損害の賠償として、本件商標の使用に対し通常受けるべき使用料に相当する額の金員を請求しうるにとどまるものである。 そして、前掲甲第三七号証、成立に争いのない甲第二四ないし第二七号証、第三〇号証に弁論の全趣旨を総合すれば、被告会社は、昭和四六年一月一日から昭和四八年七月三一日までの間、株式会社坪田刃物工場、【J】らから合計二三万九八九七丁の金切鋏を仕入れる一方、清新産業株式会社、大倉金物株式会社らに対し合計二三万〇五八九丁を販売したこと、右販売分の各年別の内訳は、昭和四六年八万二二八〇丁、昭和四七年八万九八六三丁、昭和四八年(七月末日まで)五万八四四六丁であること(前掲甲第二七号証)、右販売分のうちには、被告標章を付したいわゆる「盛光」印のもののほか、「<12060-004>光」印及び「<12060-005>萬歳久光」印のものも含まれているが、「盛光」印のものが主力商品であつて、全体の九割を占めていたことが認められる。もつとも、前掲甲第二六号証中には前記期間における「盛光」印金切鋏の販売数量は合計五万六五六六丁であり、販売高にして金六三三六万〇三三五円相当であるとの記載が見受けられるけれども、同号証の他の記載部分によれば、右の販売数量は納品伝票上「盛光」印と明示されたもののみを集計したものにすぎず、右伝票において特に銘柄の記載がないものもその約九割は「盛光」印の金切鋏であることが窺われるから、必ずしも前記認定と矛盾するものではなく、ほかにこの認定を左右するに足りる証拠はない。なお、被告会社は前述のとおり昭和四八年八月末まで被告標章を付した金切鋏を販売したが、同年八月中の販売数量を証拠により確定することは困難である。 前記認定事実に基づき、各年別の金切鋏の販売数量に一〇分の九を乗じて侵害品の販売数量を算出すれば、昭和四六年七万四〇五二丁、昭和四七年八万〇八七六丁、昭和四八年(七月末日まで)五万二六〇一丁となる。ところで、昭和四六年三月九日以前の侵害行為に対応する損害賠償請求権がすでに時効により消滅していることは前に説示したとおりであるから、損害額の算定に当たつては、昭和四六年一月一日から同年三月九日までの販売分を除外し、同年三月一〇日から同年一二月三一日までの販売数量を明らかにする必要があるところ、本件では各年別の販売数量を示す資料しか見当たらないから、結局この資料をもとに按分比例の方法によつて右期間中の販売数量を算出するほかはない。右の方法により、昭和四六年における侵害品の販売数量七万四〇五二丁に三六五分の二九七を乗じて同年三月一〇日から同年末までの販売数量を算出すれば、六万〇二五六丁となる。したがつて、昭和四六年三月一〇日から昭和四八年七月末日までの侵害品の販売総数量は合計一九万三七三三丁となる。 一方、本件商標の通常使用料率は金切鋏の販売価格の三パーセントが相当であることは当事者間に争いがないところ、前掲甲第二六号証によれば、「盛光」印金切鋏五万六五六六丁の販売による売上高は金六三三六万〇三三五円であつたことが認められ、したがつて、侵害品一丁当たりの平均販売価格は金一一二〇円(円未満切捨)であつたと認めるのが相当であるから、一丁当たりの通常使用料相当額は金三三円六〇銭となる。 そうすると、侵害品の販売総数量に対応する通常使用料相当額の総額は金六五〇万九四二八円(円未満切捨)となり、原告は被告会社の前記侵害行為によつてこれと同額の損害を蒙つたものと認めるべきである。 一〇 なお、原告は、被告会社の販売する金切鋏が粗製濫造のものであつたところから、原告の信用が著しく毀損されたと主張し、被告らに対しては慰籍料の支払を、また被告会社に対しては謝罪広告の掲載をそれぞれ請求している。 しかしながら、被告会社の販売する金切鋏であつて、昭和三〇年代の前半頃に販売されたものについてはともかくとして、前記侵害行為の当時に販売された製品までことさらに粗製濫造のものであつたことを認めるに足りる証拠はなく、したがつて、右の各請求は理由がない。 一一 以上の次第であつて、原告の本訴各請求のうち、被告会社に対しその販売する金切鋏につき被告標章を使用することの差止を求める部分並びに被告らに対し前記損害金六五〇万九四二八円及びこれに対する前記侵害行為の後である昭和四九年三月二一日から支払済みまで民事法定利率年五分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める部分は理由があるから認容し、その余は失当であるからいずれもこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第92条、第93条第1項、 仮執行の宣言につき同法第196条の各規定を適用して主文のとおり判決する。 |
| 裁判官 | 秋吉稔弘 |
|---|---|
| 裁判官 | 佐久間重吉 |
| 裁判官 | 安倉孝弘 |