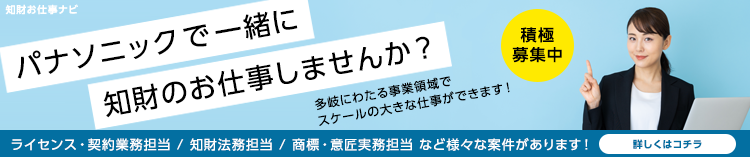| 関連審決 |
審判1967-12 |
|---|
| 関連ワード | 指定商品 / 著名な略称 / 周知性 / 混同を生ずるおそれ(混同を生じるおそれ) / 著名商標 / 顧客吸引力(グッドウィル) / 希釈化(ダイリュージョン) / 称呼(称呼類似) / 取引の実情 / 出所の混同 / 国内 / 他人の名称 / 無効審判 / 外国 / 継続 / 非類似 / 多角経営 / 商号 / |
|---|
| 元本PDF |
裁判所収録の全文PDFを見る
|
|---|
| 事件 |
昭和
50年
(行ケ)
100号
|
|---|---|
| 裁判所のデータが存在しません。 | |
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 判決言渡日 | 1977/06/01 |
| 権利種別 | 商標権 |
| 訴訟類型 | 行政訴訟 |
| 主文 |
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 この判決に対する上告期間につき、附加期間を三月と定める。 |
| 事実及び理由 | |
|---|---|
|
当事者の申立
原告訴訟代理人は「特許庁が昭和五〇年四月二日同庁昭和四二年審判第一二号事件についてした審決を取消す。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決を求め、 被告訴訟代理人は主文第一項と同旨の判決を求めた。 |
|
|
請求の原因
原告訴訟代理人は、本訴請求の原因として次のとおり述べた。 (特許庁における手続)一 原告は、「セブン アツプ」及び「SEVEN UP」の各文字を別紙記載のように左横書きしてなり、第二二類「アツプシユーズ」を指定商品とする登録第六六〇六七五号商標(昭和三七年八月二五日出願、昭和三九年一二月五日登録」につき、その商標権者たる被告を被審判請求人として、昭和四二年一月一〇日商標法第4条第1項第8号及び第一五号違反の理由により登録無効審判の請求(特許庁同年審判第一二二号事件)をしたところ、特許庁は昭和五〇年四月二日右請求は成り立たない旨、本訴請求の趣旨掲記の審決をし、その謄本は同月二五日原告に送達された。なお、これに対する出訴期間について三か月を附加された。 (審決の理由)二 右審決の理由の要点は次のとおりである。 「SEVEN UP」または「セブン アツプ」の文字はわが国において審判請求人(本件原告)の商号(THE SEVENーUPCOMPANY)の略称として広く取引者、需要者に認識されているとは認められないから、本件商標は他人の名称の著名な略称を含むものということはできない。 また、仮に審判請求人が清涼飲料について使用する商標「SEVEN UP」が本件商標の登録出願時すでに世界各地において周知著名な商標であつたとしても、 本件商標の指定商品「アツプシユーズ」は、「清涼飲料」と、その原材料、製法について著しい差異があるばかりでなく、用途、用法はもとより、生産者、販売者等の取引系統をも全く異にしているから、本件商標をその指定商品について使用した場合、取引者、需要者においてこれを「7 UP」(SEVEN UP)の商標を附した商品「清涼飲料」と同一の出所に係るものと混同するおそれがあるとは認めがたい。 したがつて、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第8号及び第一五号に違反するものということができないから、これを無効とすべきでない。 (審決の取消事由)三 しかし、右審決は、次のように誤つた判断のもとに本件商標登録を無効とすべきでないとしたものであるから、違法であつて取消されるべきである。 1 そもそも、商標法第4条第1項第8号にいう「他人の名称」とは、規定の趣旨が他人の人格権の保護にあることに鑑みると、必ずしも他人の法律上あるいは登記上の名称に限られるいわれはなく、社会通念上、特定の人、法人その他の団体を表示するものと認められる通称等も含まれると解すべきであるが、商法上の会社について、「株式会社」、「合資会社」等その法律的性格を意味する部分を除いて表示することは一般会社において広く行われているところであるから、原告の商号のうち定冠詞「THE」及び会社を意味する「COMPANY」を除外した「SEVEN UP」及びその称呼たる「セブン アツプ」は右規定の適用上原告の名称そのものと解すべく、したがつて、本件商標は原告の名称(商号)を含み、その登録は右規定に違反するといわなければならない。 しかるに、審決は、原告のその旨の主張に対する判断を遺脱し、ただ本件商標に含まれる「SEVEN UP」、「セブン アツプ」が原告商号の略称として周知著名性を有するか否かについて判断しているだけである。 2 また、本件商標は、その登録出願当時の取引会社における下記のような情況によると、これが使用されると商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。 したがつて、審決がそのおそれを認めず、本件商標について商標法第4条第1項第15号の規定の適用を否定した判断は誤りである。 (一)原告は、一九二〇年以来アメリカ合衆国ミズリー州セントルイス市において清涼飲料の製造販売を継続し、一九二八年からその商品に自ら創案に係る「SEVEN UP」(7 UP)なる商標を使用しているものであるが、これが販売高は逐年増加し、本件商標の登録出願時たる一九六二年には、アメリカ合衆国内において約三〇億本、外国において五億六千万本、日本においても三三四万本、本件商標の登録時たる一九六四年には、アメリカ合衆国内において約四〇億本、外国において約一〇億本、日本において一〇六一万本に達した。それは、原告の企業努力、特に宣伝広告に巨額の経費を使用したことによるところが大きい。ちなみに、原告が米国内、外における宣伝広告のため直接支出した費用は例えば一九六二年には一三〇〇万ドルを超える額に達した。また、その間、商標「SEVEN UP」の登録を受け、または登録出願中の国は日本を含む殆んど全世界の百三十数ケ国に及んでいる。 これがため、原告が「SEVEN UP」なる商標を附して製造販売する清涼飲料は全世界において名声と信用を獲得し、一九六二年頃には、その商標は、原告の商品を表示するものとして、日本を含むほとんど全世界において取引者、需要者間に広く認識されるに至ったものである。もつとも、その日本への輸入は、実際には政府の制限その他の事情によって、一九五九年(昭和三四年)以降となつたが、昭和一三年六月八日旧第四〇類氷及清涼飲料類を指定商品とする「商標」「7 UP」(登録第三〇三〇〇〇号)、昭和二六年一〇月九日旧第四〇類炭酸水、シロツプその他本類に属する商品を指定商品とする商標「SEVEN UP」(登録第四〇三八〇六号)について各登録を受け、また、戦後外国の新聞、雑誌等出版物の流入、当時の駐留軍のラジオ放送、「PX」からの現物の流出等があったことにより、「SEVEN UP」(7 UP)の商標はその商品の輸入前から国内において周知されていた。 したがって、本件商標を使用することは、原告が長年月にわたり多額の費用をかけて宣伝広告に努めた結果獲得した名声と信用に只乗りするものであり、商品「清涼飲料」について、商標「SEVEN UP」のもつイメージを希釈化して顧客吸引力、広告機能を減殺し、その無体財産としての価値を減少させるおそれがある。 (二)審決は本件商標をその指定商品たる「アツプシユーズ」に使用しても原告の商品「清涼飲料」と出所の混同が生じるおそれがあるとは認めがたいというが、清涼飲料の需要者の中にはアツプシユーズの購買者も含まれているのみならず、現代社会においては、広告の普及により、商標はその著名の程度が短期間に向上し、著名の範囲もその商品の需要者の範囲を超えて拡大する傾向があり、また、市場の拡大、多角経営の流行により、同一店舗で販売される商品の範囲、同一系統の取引者の範囲、製造所を同一にする商品の範囲が拡大すると同時に曖昧になっている事例(例えば電気機器の製造業者が自転車を製造して既に確保している電気機器の販売系統で販売し、製薬業者が米穀販売業者を通じて清涼飲料を販売する等)が極めて多いから、本件商標の使用による商品の出所混同が生じる要因に缺けるところはない。 なお、清涼飲料のように若老、男女、職業、階級の別なく使用される商品は、需要者の範囲が限られた例えば専門医のみが使用するある種の医薬品、製品の原料としてしか使用されない化学品等のような商品と異り、その出所について混同が生ずるおそれが多い。 |
|
|
答弁
被告訴訟代理人は請求の原因について次のとおり述べた。 一 原告主張の前掲一、二の事実は認めるが、同三の原告主張の審決の取決事由の存在は争う。審決の判断は、すべて正当であつて、これに原告主張の違法はない。 二 以下、これについて補説する。 1 商標法第4条第1項第8号にいう「名称」には、商号を含み、その場合、登記簿上確定された名称を意味することは学説判例の認めるところである。なるほど、 取引の実際上または日常生活上、商号の主要部分だけで特定人を指向する場合があるが、それは単に限られた範囲の取引関係者の間のことであつて、広く一般に通用するものではなく、右規定がこのように通常限定された機能を有するにすぎない商号の主要部分を名称そのものもしくはこれに準じるものとして保護の対象にしたものとは到底考えられないから、商号の主要部分は右規定の文理解釈上も「略称」といわざるを得ない。したがつて、原告の商号の一部たる「SEVEN UP」及びその称呼たる「セブン アツプ」は原告の名称ではなく、あくまでも略称にすぎない。 なお、審決は、「SEVEN UP」または「セブン アツプ」を原告の「著名な略称」と認められないと判断しているが、それは、右同様の見解に立脚し、原告のこれに反する主張を言外に排斥しているものと解されるから、原告のこの点の主張に対する応答を缺いているとするのは当らない。 2 原告が清涼飲料について使用する商標「SEVEN UP」は、本件商標の登録出願時、著名商標ではなく、また、原告の商号の略称としてこれにより直ちに原告を意識させるほど周知性を有してもいなかった。 仮に、原告の右商標が著名商標であつたとしても、その使用により出所の混同が生じるか否かは、商標の著名度並びにそれぞれの商品や営業の実体に即した取引の実情にかかることであつて、著名商標なるが故にすべての商品について肯定されるものではない。 ところが、(1)原告の商標「SEVEN UP」は少くとも立証を要しないほど高度の周知著名性を有するものではなく、(2)原告が清涼飲料について従来使用している商標はやや図案化された「7 UP」なる標章であるのに対し、本件商標は「SEVEN UP」の英文字を横書きしその上部に「セブン アツプ」というやや小さな仮名文字を配したものであつて、両商標には、構成上著しい相違があり、また(3)「SEVEN UP」の文字は原告の創造語ではなく、殊にそのうち「UP」の文字は一般にアツプシユーズの略称として慣用され、(4)加えて、 原告は、今日まで一貫して清涼飲料の製造販売のみをしている専門的単一企業であり、原告もしくはその系列会社がアツプシユーズ等の製靴業に従事している事実はなく、更に一般に清涼飲料メーカーが多角経営により製靴部門若しくはこれに近接した営業に進出している事実もしくは進出する傾向はない。したがつて、本件商標をその指定商品「アツプシユーズ」に使用しても、商品の出所について混同が生じる余地はない。 |
|
|
証拠関係(省略)
理 由一 前掲請求のうち、被告が商標権を有する原告主張の登録商標につき、原告の登録無効審判請求により審決が成立するにいたるまでの特許庁における手続、商標の構成、指定商品及び審決の理由に関する事実は、当事者間に争いがない。 二 そこで、右審決に取消事由があるか否かについて考察する。 1 原告の商号が「The SevenーUp Company」であることは本件訴訟記録上明らかである。ところが、商標法第4条第1項第8号にいう「他人の名称」とは、法人、組合等の名称であつて、その商号をも含むが、同規定において「これらの著名な略称」と併記され、特に著名性を要求されていない趣旨に鑑みると、法人については登記上の記載全体を指し、商号についてもその例外たりえないものと解するのが相当である。そうすると、本件商標を構成する「SEVEN UP」及び「セブン アツプ」の各文字は、原告の商号である「The SevenーUp Company」の略称ということはできるが、右規定にいう「他人の名称」には当らないといわざるをえない。したがつて、本件商標が原告の名称を含むとし、これを前提にその登録を右規定に違反するとする原告の主張は理由がなく、 右規定の適用を排斥した審決の判断は結局正当といわなければならない。 もつとも、前示一の審決の理由によると、審決は、本件商標が原告の名称を含むか否かの点について少くとも正面から判断を示していないが、成立に争いのない甲第一号証(審決謄本)によると、審決の理由中には審判請求人の右趣旨の主張を掲げていることが認められるから、審決の前示理由は、むしろ、「SEVEN UP」の文字を原告の名称とはいえないという見解のもとに、進んでこれが原告の「著名な略称」に該当するか否かについて判断を示したものと解するのが相当であつて、これにより審判請求人の主張はおのずから排斥されているというべきである。 2 次に本件商標の登録が同条項第一五号に違反するか否かに関連して、その出願時たる昭和三七年(一九六二年)八月二五日当時、原告の商標のわが国における知名の程度について検討すると(右時点を基準とすることについては同条第三項参照)、成立に争いのない甲第四、五号証の各一、二、第六号証によれば、原告は、 一九二〇年以来アメリカ合衆国ミズリー州において清涼飲料の製造販売をし、一九二八年からその商品に「SEVEN UP」(7 UP)の商標を使用しているものであるが、これが販売実績は逐年増加し、その市場も世界的規模に拡張され、また、同商標についても、アメリカ合衆国のほか数十ケ国において商標登録あるいは登録出願がなされ、わが国においても、「7 UP」が昭和一三年六月八日旧第四〇類氷及び清涼飲料類を指定商品として、「“SEVEN UP”」が昭和二六年一〇月九日同類炭酸水、シロツプその他本類に関する商品を指定商品としてそれぞれ登録されていること、ただ、その商品のわが国内における販売は輸入制限その他の事情によつて昭和三四年以降になつたことが認められ、右認定に反する証拠はない。しかしながら、その輸入前にかかわらず、原告主張のように外国出版物の流入、駐留軍のラジオ放送、「PX」からの現物流出等によつて「SEVEN UP」(7 UP)の商標がわが国内において周知になつたことを認めるに足りる証拠はなく、他には右時期に右商標を周知にしたものと首肯すべき事情の介在することについての論証がないから、前出甲第六号証(一九六五年九月二日付の宣誓供述書)に記載の【A】(原告会社関係者)の供述中、右商標は、これを附した商品の外国市場における商況によつて周知かつ著名になつたので、日本国内においても右商品の輸入に先立つて著名商標の資格を取得した旨の部分はたやすく措信することができない。また、同号証の記載に、原告の右商標を付した商品は、一九五九年(昭和三四年)米軍基地への販売という方法で初めて日本市場に輸入され、その後日本における特約店により製造販売されて逐年販売高を累増し、これに平行して日本国内におけるその広告宣伝に多額の出費が続けられたが、このような営業活動は実質的に右商標の著名性に寄与した旨、一九六〇ないし四年各年次における販売高集計、一九六三、四年各年次における広告宣伝費の地区別、方法別集計を引用しての供述があるとはいえ、右供述には、少くとも本件商標の登録出願時たる一九六二年(昭和三七年)八月二五日の基準日までのことに関する限り、原告の右商品が米軍基地を除く日本国内の一般市場において販売された数量及びこれを清涼飲料の一般取引者、需要者間の知名度に換算する尺度並びに右商品の広告宣伝のため同国内において支出された費用及びその効果等に関する資料による裏付けが伴つていない。のみならず、証人【B】の証言により真正に成立したものと認める乙第一ないし第五号証並びに右証言によれば、関西統計調査センターが昭和四一年六、七月東京都、大阪、名古屋、京都、神戸各市、福岡、愛媛、高知、徳島、香川各県の電話番号簿からその頁数に比例して無作為に抽出した三〇〇〇名に対するダイレクトメールのアンケート式によつて調査した結果、その四、五年前すなわち昭和三六、七年頃「セブン アツプ」の商品名を知つていた者は回答者(四七五通)の四%にすぎないこと。また全国の代表的広告代理店四社(電通、第一広告社、大広、協和広告)は昭和三八年五月以前において原告の商品について広告宣伝の代理営業をしたことがないことを認めることができるから、これらの事実に徴すると、甲第六号証記載の前記供述中、原告の商品のわが国における販売及び広告の営業活動が実質的にその商品に附された商標の著名性に寄与した旨の部分はにわかに措信し難く、甲第七、八号証(それぞれ東京、高松各商工会議所発行の証明書)中、「SEVEN UP」(7 UP)の商標を附した原告の商品の周知性を証明する旨の記載も右同様の理由により証拠とするに値しない。 その他原告の商品に附された「SEVEN UP」(7 UP)の商標が右基準時においてわが国内の取引者、需要者間にそのような特定商品の標識として広く認識されていたことを肯認するに足りる証拠はない。 ところが、本件商標の指定商品である「アツプシユーズ」(ゴム底靴の一種)と原告の商品である清涼飲料とがその品質、形状、用途を異にする非類似の商品であつて、通常、その製造者や取引系統をも異にすることはわれわれの経験に徴して明らかであり、現に原告もしくはその系列会社がアツプシユーズに関係のある業務を行うものであるという主張立証はない。 してみると、結局、本件商標の登録出願がなされた昭和三七年八月二五日当時、 その指定商品「アツプシユーズ」が市場に流通した場合、これを「SEVEN UP」(7 UP)の商標が附された原告の業務にかかる清涼飲料と同じ生産者、販売者による商品であると誤認させるおそれが生じる具体的状況にあつたものということはできない。したがつて、審決が本件商標について商品の出所混同を生ずるおそれがないとして、その登録が商標法の前記規定に違反することを否定した判断は正当であつて、この点にも原告主張の違法はない。 三 よつて、本件審決の違法を理由にその取消を求める原告の本訴請求を失当として棄却することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法第7条及び民事訴訟法第89条の規定を適用して、主文のとおり判決する。 |
| 裁判官 | 駒田駿太郎 |
|---|---|
| 裁判官 | 石井敬二郎 |
| 裁判官 | 橋本攻 |