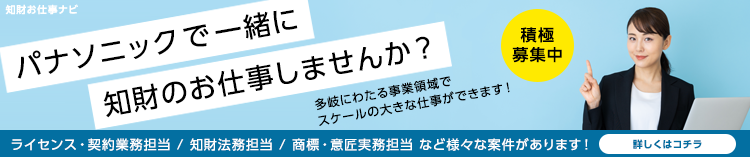| 関連ワード | 独占的使用 / 包装 / 出所表示機能 / 指定商品 / 周知商標 / 周知性 / 不正競争の目的 / 先使用(32条) / 専用使用権 / 取引の実情 / 国内 / 警告 / 差止 / 先使用権 / 継続 / |
|---|
| 元本PDF |
裁判所収録の全文PDFを見る
|
|---|
| 事件 |
平成
3年
(ネ)
4601号
|
|---|---|
| 裁判所のデータが存在しません。 | |
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 判決言渡日 | 1993/07/22 |
| 権利種別 | 商標権 |
| 訴訟類型 | 民事訴訟 |
| 主文 |
本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 原判決主文第一項は請求の減縮により次のとおり変更された。 被控訴人が婦人服に別紙標章目録1ないし3記載の標章を使用する行為について、 控訴人の登録番号第二〇一二六四八号商標権に基づく被控訴人に対する差止請求権が存在しないことを確認する。 |
| 事実及び理由 | |
|---|---|
|
当事者の求めた裁判
一 控訴人(第一審被告) 「原判決を取り消す。被控訴人の請求を棄却する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決。 二 被控訴人(第一審原告) 主文第一、二項同旨の判決。(被控訴人は原判決主文第一項により認容に係る請求中「被服、布製品及び寝具類」との部分を「婦人服」と減縮した。) |
|
|
事案の概要
一 争いのない事実及び争点は、原判決の「第二 事案の概要 一 争いのない事実」及び「同二 争点」に摘示のとおりであるから、これを引用する。 二 当審における当事者の主張1 控訴人の主張 商標法32条1項の規定は、登録主義の例外であるから、「先使用権」の成立を認めるには慎重でなければならず、同項所定の「需要者の間に広く認識されているとき」(以下「周知性」ともいう。)の要件の存在を厳格に判断しなければならない。 本件では対象となる商品がDCブランドの婦人服であるから、「需要者」は当該商標の付された商品を購入する一般消費者であり、卸売業者や小売業者は「需要者」にあたらず、「広く認識されている」の概念も、被控訴人標章が相当広範な地域において一般消費者に知れ渡った結果、本件登録商標により、その使用の中止を求められても例外としてその使用を許さざるを得ない程度の状況を前提としていると解すべきである。 原判決が「周知性」を肯定した根拠とする事実は、被控訴人の関係者及びファッション業界の一部の業界人が知る商品展示会やファッションショー、雑誌に掲載し、その横に小さく「ゼルダ」と記載した説明文をもって、被控訴人標章が一般の消費者に広く認識されるに至ったものとするにすぎない。しかしながら、著名ブランドが常に一定程度存在する以上、被控訴人標章がそういった周知商標に参入し、 一般の消費者にその名を知られるようになるためには、相当の宣伝活動とそれに要する期間が必要であって、被控訴人が、原判決が認定する程度の商品展示会やファッションショーを数回行ない、雑誌に数回作品の横に小さな字で掲載する方法で一般の消費者の間に周知となることなどあり得ないものである。なお、昭和五四年一一月に被控訴人が「ゼルダ」ブランドの婦人服を発表してから同五五年八月までの間の約二億円の売上金額は、ファッション業界内では僅少であって、被控訴人標章が一般の消費者に知られていないことを示すものである。 したがって、原判決の認定した事実では、本件登録商標の出願日である昭和五五年八月四日の時点において被控訴人標章が広く一般消費者に知れ渡るまでに至っていたとは認められず、商標法32条1項に規定される周知性の要件を充足していないことは明らかである。 しかるに、原判決は、被控訴人の「ゼルダ」ブランドの婦人服がいわゆるDCブランドの全盛期(本件登録商標の登録出願日の三年後である。)に人気がでたことと商標法32条1項の「周知性」の要件とを混同した結果、被控訴人標章の周知性を誤って肯定したものである。 2 被控訴人の主張 商標法32条1項が先使用権を認める趣旨は登録商標の出願前において使用され、既に出所表示機能を有していた商標の地位を保護しようとするものである以上、同項に規定する「広く認識されている」とは、必ずしも全国的に知られていることを必要とせず、指定商品との関係において、取引の実情をも考慮して判断されるべきであり、また、商標は、最終消費者に対する関係だけでなく、流通段階においても商品の出所を表示するものであるから「需要者」の中に問屋や一般小売業者が含まれることは当然であり、それらの者の間で広く認識されている場合も先使用者の地位を保護する必要があるのであって、一般消費者の間に知れ渡っていることを要するものではない。 被控訴人標章を付した商品は、いわゆる高級婦人洋装品であって、大型店あるいは、雑貨店向けの大衆品と異なり、デパート等の大型小売店舗内の直営店、あるいはフランチャイズ店で販売されるものである。専門店向けの婦人洋装品の業界においては、製造業者は一般消費者に対する直接の宣伝広告を行なわず、主として小売店である専門店に対する展示会その他の宣伝広告により、有力な専門店を獲得し、 その専門店を通じて間接的に最終需要者である消費者に対し、自社製品のイメージを浸透させるという方法を採るのであって、原判決の認定した事実をもって、周知性を肯定した原判決は正当である。 なお、二億円の売上金額は、高級婦人洋装品である被控訴人標章を付した商品として、また一ブランドの売上としては決して少ない金額ではない。そして直営店八店舗、フランチャイズ店二七店舗という出店は一ブランドとしてかなりの程度に広い店舗展開といえるものである。 |
|
|
争点についての判断
一 争点は、「1 被控訴人標章が本件登録商標に類似するか否か。2 被控訴人が商標法32条1項に基づき、先使用による被控訴人標章を使用する権利を有するか否か、すなわち、本件登録商標の出願日である昭和五五年八月四日の時点において、現に被控訴人標章が被控訴人の販売する婦人服を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたか。」にあるが、仮に、被控訴人標章が本件登録商標に類似するものであるとしても、以下に判断するとおり、本件登録商標の出願日である昭和五五年八月四日の時点において、現に被控訴人標章が被控訴人の販売する婦人服を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたから、被控訴人は、商標法32条1項の規定に基づき、被控訴人の製造販売する婦人服について、被控訴人標章を使用する権利を有するのであって、被控訴人の製造販売する婦人服について、被控訴人標章を使用する行為は、本件商標権の侵害を構成しないものというべきである。すなわち、 二 証拠及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる証人【A】、【B】は原審証人、証人【C】、【D】は当審証人)1 被控訴人は、昭和四六年一〇月、デザイナーである【E】(【E】)が同四二年三月に創業した事業を引き継ぎ、婦人服、紳士服、寝装品、服飾雑貨の企画、卸売及び小売等を目的として設立された株式会社である(甲八、証人【A】、弁論の全趣旨)。 2 【E】は、被控訴人標章の使用の準備を開始した昭和五四年三月頃には、日本国内の服飾関係者間において実績あるデザイナーとして著名であり、被控訴人の社名である「ニコル」も同人がデザインした製品のブランドである「ニコル」に由来する。被控訴人は、主として自社のブランドの製品を直営店での販売、デパートへの卸売又はフランチャイズ契約での委託販売という営業形態をとり、全国の有名デパートあるいは大型のファッションビルに売場(インショップ、ブティック)を開設していたが、昭和五四年に入って、同四九年の入社以来【E】の片腕ともいえるアシスタントデザイナーを務めていた【A】(【A】)をチーフデザイナーとして、被控訴人が販売する主として同人のデザインに係る婦人服に使用して売り出す新しいブランドの創設を計画した。そして、被控訴人代表者である【E】は社内で検討のうえ、そのブランドの名称として、「華麗なるギャツビー」の作者であるアメリカの【F】の妻の【G】の名に由来する「ゼルダ」の名称を採用することに決め、「ゼルダ」の名称が婦人服業界で使用されているかどうか調査することとし、 「ゼルダ」及びそのローマ字表示である「ZELDA」について、弁理士に依頼して、他人が商標登録を受けているかどうかを調査してもらうとともに、取引のある百貨店及び業界の新聞社等を通じて、百貨店及び商業集積施設等に入居している店舗の名称や婦人服の商標に使用されているかどうかを調査したところ、右表示と同一の登録商標はなく、また、右表示が市場において現に使用されていることもないとの報告を得たので、「ゼルダ」を新しいブランドの名称に決定し、「ゼルダ」ブランドを表象するものとして、別紙標章目録記載の標章、すなわち被控訴人標章を採用した。かくて、被控訴人標章を使用した【A】のデザインに係る婦人服は「ゼルダ」ブランドとして、被控訴人の暖簾分けの形で被控訴人の従前のブランドの製品と同様の販売形態で売り出されることとなった(証人【A】、【D】、【C】、 【B】)。 3 被控訴人は、昭和五四年三月頃、同年一一月に開催する予定の翌年度の被控訴人の販売する婦人服の春夏物の展示会において、【A】のデザインに係り、被控訴人標章1及び2を付した婦人服を発表し、初年度の半年間で二、三億円、一〇年間で三〇億円くらいの売上を計上するという事業計画を立てて、その準備を開始し、 著名なグラフィックデザイナーである訴外【H】に「ゼルダ」のローマ字表示である「ZELDA」のロゴタイプの作成を依頼し、そのロゴタイプの付された洋服に付ける織りネーム、包装用の袋、手提げ袋、プライスカードを、一万枚単位、紙類で五〇〇〇枚単位で製造し、「ゼルダ」ブランドの婦人服の宣伝、販売に使用することとした(甲ニ六、証人【A】)。 4 原判決第三の二4を次のとおり、訂正したうえ、引用する。 (一) 原判決八頁八行目の「あった(甲九の一ないし四、甲一一、証人【B】及び同【A】)。」を削除し、「あった。右ファッションショーでは、当時カジュアル志向の若年層の洋服の方が隆盛だった中で、被控訴人標章を付した婦人服はかかる志向から脱却したものとしての印象を出席者に与えた(甲九の一ないし四、甲一一、証人【B】、【A】)。」を付加する。 (二) 原判決一〇頁一一行目、一一頁三、六、九行目、一二頁五行目の「被服」をそれぞれ「婦人服」に改める。 5 被控訴人は、前記4認定のように被控訴人標章を使用して宣伝広告等をし、かつ、被控訴人標章1及び2を付して「ゼルダ」ブランドの婦人服を販売し、昭和五四年一一月に「ゼルダ」ブランドを発表してから同五五年八月までの間に、約二億円の売上げを計上し、また、同月当時には、「ゼルダ」ブランドの右商品の販売のために、大手百貨店を中心に直営店八店舗及びフランチャイズ店二七店舗を出店するまでに至った(証人【A】、弁論の全趣旨)。 6 そして、被控訴人は、その後も、後記7のとおり、昭和六三年一二月から平成元年一月末にかけて被控訴人標章を「MARIKO KOHGA」に変更するまで、被控訴人標章を使用して、「ゼルダ」ブランドの婦人服を販売してきたが、そのころまでに、「ゼルダ」ブランドは日本の他の著名なデザイナーブランドと肩を並べるまでになり、「ゼルダ」ブランドの婦人服を販売する被控訴人の直営店は大手百貨店を中心に四四店舗近く、フランチャイズ店は三二店舗近くになっていた(甲八、甲ニ三、甲ニ四、甲ニ五の一ないし三、証人【A】)。 7 原判決第三の二7を次のとおり、訂正したうえ、引用する。 原判決一六頁九行の「被服、布製見回品及び寝具類」を「婦人服」と改める。 三1 商標法32条1項所定の先使用権の制度の趣旨は、職別性を備えるに至った商標の先使用者による使用状態の保護という点にあり、しかも、その適用は、使用に係る商標が登録商標出願前に使用していたと同一の構成であり、かつこれが使用される商品も同一である場合に限られるのに対し、登録商標権者又は専用使用権者の指定商品全般についての独占的使用権は右の限度で制限されるにすぎない。そして、両商標の併存状態を認めることにより、登録商標権者、その専用使用権者の受ける不利益とこれを認めないことによる先使用者の不利益を対比すれば、後者の場合にあっては、先使用者は全く商標を使用することを得ないのであるから、後者の不利益が前者に比し大きいものと推認される。かような事実に鑑みれば、同項所定の周知性、すなわち「需要者間に広く認識され」との要件は、同一文言により登録障害事由として規定されている同法4条1項10号と同一に解釈する必要はなく、 その要件は右の登録障害事由に比し緩やかに解し、取引の実情に応じ、具体的に判断するのが相当というべきである。 2 そこで、右の点について具体的に検討する。 証拠及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。 婦人服業界において、特定のデザイナーの製品であることを示すブランド(デザイナーブランド)の場合、大規模メーカーが不特定多数の消費者を対象として全国的規模で広告宣伝し大量販売するナショナルブランドと異なり、展示会、ファッションショーを通じて、これら催しに出席した新聞雑誌等のマスコミ関係、百貨店、 小売専門店等のバイヤーに直接そのブランドのイメージの理解をはかり、右ファッションショー等に出席しなかったバイヤー等には出席したマスコミ関係者による記事等を通じて、そのイメージの浸透に務めたうえ、有名デパートあるいは大型のファッションビルにおいて、ブランド単独の売り場(インショップ、ブティック)を獲得したり、地方にフランチャイズ店を構えるなどして、マスコミあるいはこれらの売り場、店舗を通じて、間接的に消費者に、そのブランドのイメージの浸透をはかるほか、特定の顧客には直接ダイレクトメールを送付していること、被控訴人標章もデザイナーブランドであり、被控訴人として前記二3及び4認定のように、婦人服に被控訴人標章1及び2を付するほか、被控訴人標章を使用して各種の宣伝広告をしたり、直営店、フランチャイズ店を構え、そのイメージの浸透をはかったこと、この業界においては、知名度の高い実績の有るデザイナーあるいはそのデザイナーに関係したデザイナーの場合はそのデザイナーブランドの浸透は無名のデザイナーに比し短期間でなされ得ることが認められる(証人【B】、【A】、【C】、 弁論の全趣旨)。 被控訴人標章が【A】のデザインに係る婦人服であることを示すデザイナーブランドであることは右に認定したとおりであり、また、同人が婦人服飾業界においてデザイナーとして実績のある著名な【E】のアシスタントデザイナーであることは前記二2に認定したとおりである。そして、昭和五四年三月頃には、【E】の著名性からみて、【A】が【E】のアシスタントデザイナーであることは婦人服飾業界において広く知られていたものと推認して差し支えなく、さらに、被控訴人に被控訴人標章の使用について不正競争の目的がなかったことも前記二2の認定から明らかであるから、前記二4認定の商品展示会、ファッションショーの開催、その案内状の発送、ダイレクトメールの発送等により、被控訴人は、株式会社ブローニュの本件登録商標に係る商標登録出願の日である昭和五五年八月四日前から、日本国内において、不正競争の目的でなく、右商標登録出願の指定商品の範囲に属する婦人服について被控訴人標章の使用をしていた結果、右商標登録出願の際、現に、被控訴人標章が被控訴人の業務に係る商品を表示するものとして「需要者」としての婦人服のバイヤー、すなわち問屋や一般小売業者の間で広く認識されていたものと認められる。控訴人は、婦人服の需要者は一般消費者である旨主要するが、前記認定によれば、デザイナーブランドに関しては、流通段階におけるバイヤーをその需要者として捉えるのが相当であるから、右主張は採用することができない。 3 次に、デザイナーブランドの場合、その対象とする層によって、多数の消費者に販売することが必ずしも目的とはならず、その売上げの多寡がブランドの著名性と結びつくとは限らないことが認められる(証人【C】)。ところで、三年間の平均利益率が六パーセント以上の高収益レディスアパレル四六社(被控訴人を含む。)の昭和五四年における総売上高の合計は、四六二八億二八〇〇万円であることが認められる(乙三一)ところ、右二5の認定事実によれば、同年一一月から同五五年八月までの間の「ゼルダ」ブランドの商品の売上高は約二億円であり、右売上高は、右のレディスアパレル四六社の同五四年における総売上高の合計額に比して僅少であるが、婦人服業界では、一企業が複数のブランド商品を販売していることが認められる(乙三二)ところからみて、右レディスアパレル四六社の売上高はいずれも単独のブランド商品の売上高ではなく、複数のブランド商品及びブランド商品以外の商品の売上高の合計であると推認できる。したがって、各企業の個々のブランドの売上高を比較せずに右の総売上高と単独のブランドの商品である被控訴人の「ゼルダ」ブランドの商品の売上高を比較することは相当でないといわざるを得ない。これを控訴人関連会社である株式会社ダイヤについてみると、平成三年度の年間売上げ六五億円には、本件登録商標を付した商品の売上げのほか、ラウラ・カポーニ、コンテオブフロレンス、ニキタ・ゴダールの各ブランドの商品の売上げ、国内外の一〇〇社に及ぶメーカーの作品の中から選んだレディスファッションをミックスした商品の売上げが含まれていることが認められる(乙八、証人【D】)から、各ブランドの個々の売上高はさほど多くないと推認され、現に昭和六三、平成二、三年度の控訴人における本件登録商標(あるいはその類似の商標)を付した商品の売上げは、それぞれ、約一億六〇〇〇万円、一億九〇〇〇万円、二億七〇〇〇万円であった(なお、平成元年度は、控訴人と被控訴人との間で本件登録商標の買取り交渉がなされていたため、控訴人が同製品の製造・販売を手控えた経緯がある。)ことが認められる(乙三四、三五、証人【D】、弁論の全趣旨)から、昭和五四年一一月から同五五年八月までの約九か月間約二億円の売上高はデザイナーブランドとしてその周知性が認められないほど僅少であると認めることはできない。したがって、「ゼルダ」ブランドの婦人服の売上高が右のレディスアパレル四六社の同年における総売上高の合計額に比して僅少であることをもっては、先使用権成立の要件である周知性の存在を左右するに足りない。また、株式会社矢野経済研究所が、全国の小売店一〇〇〇店舗に、取引を行なっているメーカー、問屋の総てのブランドの評価をしてもらい、これを集計した「81年版レディスブランドの競争力調査」と題する報告書(同五六年四月二五日発行)(乙三二)には、被控訴人のブランドとして、「ニコル」、「マダム・ニコル」が掲載され、「ゼルダ」が掲載されていないことが認められるが、右報告書は、ビジネスの作業の体制の観点から評価したものであって、必ずしもブランドとしての評価を示すものではないと認められ(証人【C】)、また、右報告書である乙三二に挙げられたブランドの企業名とレディスアパレル各社の売上げ等を調査した前記乙三一に挙げられたレディスアパレル四六社の名前と一部重複しているが、必ずしも一致しておらず、 そのことは、流通経路等の偏りにより右報告書の調査対象にも偏りが生じたことを窺わせるものであるから、右報告書において、ブランドの名前が掲載されていない事実は、被控訴人標章について、先使用権成立の要件である周知性の存在を左右するに足りないものというべきである。 そして、前記二7の認定事実によれば、平成元年二月以降は、ブランド名を「MARIKO KOHGA」に変更して、被控訴人標章の使用を中止しているものであるところ、被控訴人が被控訴人標章の使用を中止したのは、自らの発意によるのではなく、株式会社ブローニュらから、被控訴人が被服、布製身回品及び寝具類に被控訴人標章を使用する行為は本件商標権の侵害になるとして、被控訴人標章の使用を中止するよう警告を受けたため、被控訴人標章の使用を継続することによって、控訴人らから百貨店その他の取引先等に対して被控訴人標章の使用を中止するよう警告がされるなどして、取引先等に迷惑がかかることを懸念したことによるものであり、被控訴人は、本件紛争が解決したときには、婦人服に被控訴人標章を使用する意思を有しているものと認めることができる。そうすると、被控訴人は、右のような相当な理由に基づき、かつ、その限度において、被控訴人標章の使用を一時中止しているにすぎないものというべきであって、このような場合は、商標法32条1項の規定にいう「継続してその商品についてその商標の使用をする場合」に該当するものと解するのが相当である。 五 したがって、被控訴人は、商標法32条1項の規定により、婦人服について、 被控訴人標章の使用をする権利を有するものということができるから、被控訴人が婦人服に被控訴人標章を使用する行為は、本件商標権の侵害を構成しない。 |
|
|
以上のとおり、被控訴人の本訴請求は理由があるから、控訴人の控訴を棄却
し(原判決主文第一項は被控訴人の請求の減縮により主文第三項のとおり変更された。)、訴訟費用の負担につき、同法95条、89条を各適用して主文のとおり判決する。 |
| 裁判官 | 松野嘉貞 |
|---|---|
| 裁判官 | 押切瞳 |
| 裁判官 | 田中信義 |