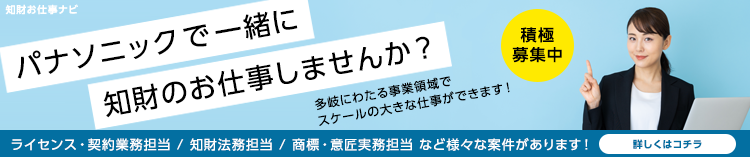| 関連ワード | 識別力 / 出所表示機能 / 識別機能 / 指定商品 / 普通名称(3条1項1号) / 慣用商標(3条1項2号) / 周知性 / 混同を生ずるおそれ(混同を生じるおそれ) / 類似性(類否判断) / 結合商標 / 契約の解除 / 外観(外観類似) / 称呼(称呼類似) / 観念(観念類似) / 差止 / 連合商標 / 防護標章 / 無効審判 / 類似商標 / 商号 / |
|---|
| 元本PDF |
裁判所収録の全文PDFを見る
|
|---|
| 事件 |
平成
11年
(ネ)
2815号
商標権侵害行為差止等請求控訴事件
|
|---|---|
|
控訴人(一審被告) 金盃酒造株式会社 右代表者代表取締役 【A】 右訴訟代理人弁護士 和田好史 被控訴人(一審原告) 菊正宗酒造株式会社 右代表者代表取締役 【B】 右訴訟代理人弁護士 上谷佳宏 同 木下卓男 同 幸寺 覚 同 笠井 昇 同 福元隆久 同 山口直樹 同 今井陽子 同 松元保子 右補佐人弁理士 【C】 同 【D】 |
|
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
| 判決言渡日 | 2000/08/25 |
| 権利種別 | 商標権 |
| 訴訟類型 | 民事訴訟 |
| 主文 |
一 本件控訴を棄却する。 二 控訴費用は、控訴人の負担とする。 |
| 事実及び理由 | |
|---|---|
|
当事者の求めた裁判
一 控訴人 1 原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。 2 被控訴人の右部分に係る請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。 二 被控訴人 主文と同旨 (以下、控訴人を「被告」、被控訴人を「原告」という。また、略称については原判決のそれによる。) |
|
|
事案の概要
一 本件は、被告の標章使用行為等が、① 原告の有する複数の商標権を侵害し、 ② もしくは被告がその地位を承継した亡【E】と、原告との間の和解(和解契約もしくは訴訟上の和解)の合意に違反し、③ または不正競争防止法2条1項1号、二号に該当するものであるとして、原告が、被告の右標章使用行為等の差止めを請求した事案である。 二 前提となる事実 1 前提となる事実は、原判決四頁九行目から一三頁八行目までに記載されたとおりであるから、これを引用する(ただし、原判決六頁一行目の「発表した」を「発表し、その広告の中で、『金盃菊正宗』という文字を、活字にて、縦書き(明朝体)及び横書き(ゴシック体)に記載した。」と、同八頁五行目の「なる標章」を「のみからなる文字標章」と各改める。)。 2 なお、右前提となる事実の概要は次のとおりである。 (一) 原告は、清酒の醸造、販売を業とするものであるが、原判決別紙商標権目録(1)ないし(38)の各商標権の権利者である。 被告は、【E】が「本高田商店」の屋号で行っていた清酒の醸造、販売業を、昭和一〇年四月二〇日に、法人化したものである。 (二) かつて、原告と【E】との間で、商標権を巡る争いがあったが、昭和四年六月一五日、【E】が有する被告商標(第八六〇二六号)を図形としても、称呼としても使用せず、他人にも譲渡しないことなどを内容とする和解契約が締結され、同月二二日、神戸地方裁判所において、右と同内容の訴訟上の和解が成立した(いずれの効力についても争いがある。)。 (三) 被告は、平成九年一〇月から、原判決別紙標章目録(一)及び(二)記載の標章を用いた原判決別紙物件目録(一)ないし(三)の各商品、原判決別紙標章目録(三)記載の標章を用いた原判決別紙物件目録(四)の商品を製造、販売し、「[金盃菊〈正宗〉純米酒]販売のご案内」等と題したパンフレットを小売店に配布した。 三 争 点 1 被告の各行為は、原告商標権の侵害行為に当たるか。 2 本件和解契約及び本件訴訟上の和解の効力は被告に及ぶか。 3 被告の各行為は、不正競争行為に当たるか。 4 差止めの必要性等 四 争点に関する当事者の主張 争点に関する当事者の主張は、次に付加、訂正するほか、原判決一四頁二行目から四九頁八行目に記載されたとおりであるから、これを引用する。 1 原判決一五頁三行目の「表示されており」から同頁五行目末尾までを「表示されている。」と改める。 2 原判決一五頁七行目冒頭から一六頁四行目の「そして」までを削る。 3 原判決一七頁一一行目の「直裁」を「直截」と改める。 4 原判決二二頁四行目の「被告文字標章」の次に「及び『菊正宗』という文字の表示(『金盃菊正宗』、『金盃菊〈正宗〉』等の表示を含む。)」を、「同標章」の次に「等」を各加える。 5 原判決二二頁六行目の「文字標章」の次に「等」を加える。 6 原判決二四頁二行目の「金盃菊正宗」を「キンパイキクマサムネ」と改める。 7 原判決三三頁八行目及び末行の各「株式会社」の前にいずれも「当時」を加える。 8 原判決三五頁五行目の二つの「与」をいずれも「ないし」と改める。 9 原判決三六頁一一行目の「解すべきである」の次に「(債務については、 重畳的に引き受けられたとみることができる。)」を加える。 10 原判決四四頁一二行目の「三三八年」の次に「(平成一〇年の提訴時)」を加える。 五 被告の当審における主張の要旨 1 商標の類否について (一) 特許庁の審査基準(「正宗」には自他識別力がなく、「菊」に自他識別力がある。)や、原告自身「キクマサ」の称呼を生じることを自認していることに照らしても、原告商標(14)の要部の称呼は、「キク」もしくは「キクマサ」であり、「キクマサムネ」ではない。原判決が、原告商標(14)につき、「菊正宗」全体が要部であるとしたことは誤りである。 一方、被告標章(二)や被告の登録商標である「金盃」からは、「キンパイギク」「キンパイ」の称呼を生ずるが、加えて、被告は、原審口頭弁論終結後の平成一一年四月九日、「金盃菊」という漢字三文字からなる商標の登録を得た(登録第四二五九四四五号、乙二〇)。そのため、被告文字標章は、右登録商標である「金盃菊」と慣用商標である「正宗」とを結合させたもので、その要部は「金盃」もしくは「金盃菊」であり、その称呼は「キンパイ」もしくは「キンパイギク」となり、原告の「キク」「キクマサ」のいずれとも「キンパイ」の有無という顕著な差があり、称呼において類似することはない(仮に、原告商標の要部の称呼が「キクマサムネ」であったとしても、類似しない。)。 (二) 被告の商標「金盃」の周知性について 次の事情を併せ考えると、被告の商標「金盃」は周知であって、その結果、「金盃菊正宗」と「菊正宗」が観念において類似することはない。 すなわち、【E】は、先駆けて酒屋チェーンを開設し、その後、酒造メーカーに転身して一代にして有数の蔵元となり、昭和二年には大手並の造石高一万石を記録し、昭和三八年には、【E】の営業を承継した被告が、四季醸造を手掛け、業界内でその先駆性が高く評価されていた。 (三) 被告の新規登録商標 被告は、図形商標(被告標章(二)と同じ)と文字商標(被告標章(一)と同じ)とを組み合せた商標(被告商品(一)ないし(三)に使用されているものとほぼ同様)について、平成一二年四月一三日付けで登録査定通知を受けた。 これは、特許庁が被告商標(被告標章(二))の使用につき何ら問題がないとしたものである。 2 和解の効力について (一) 本件和解契約及び本件訴訟上の和解は、【E】の代理人によるものであるが、いずれの和解においても、【E】の授権が証明されておらず、また、 【E】は当時脳溢血により正当な判断をできる状況になく、意思能力を欠いていたのであるから、右本件各和解を有効と認めた原判決の判断は誤りである。 また、本件和解契約において支払われた和解金一万四〇〇〇円(当時)は、あまりにも低額であり、【E】本人が右和解を了承したとは考えられない。 右和解金が、現在の貨幣価値に換算した結果五八〇〇万円であったとしても、商標使用の対象となる日本酒を基準とすると、高々一一五〇万円程度であり、また、当時の本高田商店の年間売上高の〇・七パーセントに過ぎず、更に、右和解契約後、被告商標を使用できなかった期間で割ると、一年当たりの金額は僅かである。 (二) 本件和解契約の解除 本件和解契約8条には「本契約により成立せる和解の精神は、以後双方間において徳義を以て尊重す」とあるところ、原告は、平成三年春ころ、被告の大口二次卸として「金盃」印商品のみを取り扱っていた合資会社月の友(茨城県北茨城市<以下略>)に対し、その事情を知悉しながら原告との特約店契約をさせた結果、被告は、右月の友との取引高、ひいては首都圏を中心とする東日本地区での売上が大幅に減少するという損害を被った。原告の右行為は、本和解条項に違反するので、被告は、原告に対し、平成一一年九月二四日付準備書面(平成一一年一〇月五日送達)をもって本件和解契約を解除する旨通知した。 (三) 被告商標は、【E】が灘酒造家の中でも最も古い名家である「松屋」から取得したものであり、松屋の有していた登録商標は、原告のものより古いものであるから、【E】が本件各和解をするはずがない。 なお、前記「松屋」から譲り受けた商標の金盃の中には「菊」と「鶴」が入っているのに、本件各和解の対象となった商標の金盃には「鶴」がおらず、重大な差異がある。 六 原告の当審における主張の要旨 1 商標の類否について (一) 被告は、特許庁の審査基準(「正宗」には自他識別力がなく、「菊」に自他識別力がある。)を理由に、原告商標(14)の要部が「菊」であると主張するが、特許庁の商標登録の審査において、「菊」と「菊正宗」とは類似商標とは解されておらず、原告商標(14)は、一体として著名な商標であり、識別力を有するのは「菊正宗」全体である。なお、原告商品を「キクマサ」と称呼される場合があったとしても、「菊正宗」が原告商品であるという出所表示機能を有している。 (二) 被告は、「金盃菊」の商標登録を得たことをもって「金盃菊正宗」と「菊正宗」との称呼上の類否が否定されると主張するが、「菊正宗」について「菊」と「正宗」とを分離することを前提としており、右主張は誤りである。 なお、被告が大正末期から昭和初期ころ本高田商店において使用していたという通いつぼ(検乙一)には、金盃菊正宗と記載されているが、中央の「正宗」の図柄を隔て、右側に「金盃」、左側に「菊正宗」という配置となっており、 当時の本高田商店ないし被告の認識においても、「金盃菊」と「正宗」の合成という構成ではなく、「金盃」と「菊正宗」の合成という構成を有する標章であると把握されていたというべきである。 (三) 被告の新規登録商標について 被告の新規登録商標は、格子状の図柄をベースとし、右側に縦書きで「清酒の正統復興」、上部に横書きで「金盃菊正宗」の文字が記載され、中央には特殊な書体による「正宗」の文字、その文字に一部が隠れた状態で盃と菊の花が描かれたものである。 右商標の構成の中で最も大きく表示されているのは中央の「正宗」の文字であるが、一般の需要者がこれを判読することはおよそ不可能であり、この部分からは称呼が生ずることはない。仮に一般の需要者においてこの部分を「正宗」と判読できた場合、それは慣用商標であるから、識別力を発揮するものではなく、出所表示機能はない。また、その後ろにかくれた状態の図柄も、需要者の注意を引き付けるような態様ではなく、一定の称呼を生ぜしめるものでないことは明らかである。更に、「清酒の正統復興」の文字部分については、ある程度の識別力は認められるとしても、未だ一定の出所を表示するものとして広く知られているという状況にはない。 したがって、右商標の要部のうち、需要者がその出所を判断するにあたり、拠り所とする部分は「金盃菊正宗」の部分であり、この文字部分に出所表示機能が存することを否定できない。 一方、被告は、右商標登録出願より前(平成九年一〇月一七日)に「金盃菊正宗」という文字のみからなる商標登録出願を行っているが、これについては、平成一一年四月一九日に、原告商標(11)などを引用商標とし、これらと類似するとして、拒絶査定がなされている(甲三六の1ないし12、三八)。 そうすると、右登録査定は、商標法4条1項11号に該当する商標について登録査定がなされたものにほかならず、違法であり、取り消され、あるいは無効とされるべきである。 2 和解の効力について (一) 原告と【E】との間の「金盃菊正宗」に関する紛争は大正一三年に端を発しているが、本件訴訟上の和解時までに訴訟代理人の代理権が消滅したことを窺わせる事情は存しない。 また、本件各和解については、紛争が円満に解決したことを当時の大手新聞社四紙に掲載公告がなされており、【E】がこれを知らずにいたとは考えられない。 また、一万四〇〇〇円の和解金は、和解内容に比して、決して低額とはいえない。 (二) 原告が、平成三年、本件和解契約の和解条項に違反した事実はない。 (三) 被告は、「松屋」から取得した登録商標が、原告のものよりも古いというが、原告が商標権を有していた登録第四八六四四号の原登録日は明治二四年八月一四日であり、被告の主張は前提を欠く。 また、「松屋」の有していた商標に「鶴」は記載されていない。 |
|
|
当裁判所の判断
一 争点1(被告の各行為は原告商標権の侵害行為に当たるか)について 1 商標の類否について 被告文字標章と原告商標のうち原告商標(14)との類比について以下検討する。 (一) 原告商標(14)について (1) 証拠によれば、次の事実が認められる。 ① 原告は、江戸期から清酒の製造、販売業を営んでいた嘉納家の本家(「本嘉納」と称されていた。)の営業を法人化する形で設立された会社であるところ、本嘉納は、その製造、販売に係る清酒に「正宗」の荷印を付けていたが、明治一七年の商標条例(太政官布告)の公布により、酒名を「菊正宗」とし、以来これが原告に引き継がれ、各種の登録商標にアレンジする形で使用されてきた(乙三、弁論の全趣旨)。 ② 日刊経済通信社の調査による全国の上位清酒メーカーの銘柄酒の出荷状況は、原告の「菊正宗」は、平成七年度は、上位から①「月桂冠」、②「白鶴」、③「大関」、④「松竹梅」、⑤「日本盛」、⑥「黄桜」に次いで第七位の出荷量(三万九七〇四キロリットル)であり、平成八年度は、右①から⑤の上位五銘柄に次ぐ第六位の出荷量(四万〇二二七キロリットル)であった。 これに対して、被告の「金盃」は、平成八年度は、第五五位(三一四八キロリットル)であった(甲九)。なお、被告は、平成七年一月一七日発生した阪神淡路大震災の被害を受け、製造量が減少していたが(甲九、弁論の全趣旨)、右震災前の「金盃」の製造量については、売上高(年間約三〇億円)から、 約四五〇〇キロリットルであったことが推計できる(一・八リットル一二〇〇円として換算、乙二三ないし二六)。 ③ 原告は、原告商標(14)を含め、「菊正宗」の文字を含む登録商標を三四(原告商標(4)、(6)ないし(38))有し、その他「キクマサムネ」(原告商標(1))、「KIKU-MASAMUNE」(原告商標(2)、K、S、A、Eが飾り文字となっている。)、「きくまさむね」(原告商標(3))という登録商標を有しているが、これらの中で最も古い登録は、大正七年七月二六日に遡る(なお、乙二九によると、原告商品の代表的なラベルは、昭和四一年までは、白菊の図柄に「正宗」の文字を組み合せたものであったが、その後、原告商標(11)、(21)、(33)と似たラベルに変更されたことが窺える。)。 また、AIPPI・JAPAN作成の「日本有名商標集」にも「KIKU-MASAMUNE」及び「菊正宗」が掲載されている(甲四三)。 ④ 原告は、原告商標(14)について、指定商品以外の化学薬品等二四類の商品に関して防護標章登録(商標法64条・商標が周知著名なものであることを登録要件とするもの)を受けている(最初の出願昭和六三年六月二九日・最後の登録平成九年九月一二日、甲一一)。 (2) 右認定事実によれば、「菊正宗」は、相当古くから、原告が製造販売する商品の著名な標章として、取引者及び一般需要者の間で広く認識され、また、 原告の製造販売する「菊正宗」の標章を付した清酒商品は、一般需要者によって「キクマサムネ」と称呼されていたものと認められる。 したがって、原告商標(14)は、全体が不可分一体のものとして、「キクマサムネ」の称呼を生じ、原告の製造販売に係る原告商品を観念させるものとなっていると解するのが相当である。 (3) 被告は、原告右商標について、「正宗」に自他識別能力がなく、その要部は「菊」であるから、「キク」の称呼を生じるとか、原告自身が「キクマサ」という称呼であることを自認していると主張する。 しかし、前記(1)で認定したところに加えて、日本酒造組合中央会出版(平成八年一〇月出版)の「日本酒読本」(乙二)によると、当時、日本酒の銘柄として「正宗」を使用するものが一七一銘柄ある一方、「菊」を使用するものも一六一銘柄あることが認められ、これによると、「菊」だけで出所識別機能を有するとは考えられず、「菊正宗」との表示によって、初めて出所識別ができるといわざるを得ない。 そして、原告商標(14)を含め、原告商標が「キク」と呼ばれていることを認めるに足る証拠はなく(被告は、原告商品を酒造業界では「キク(さん)」と呼ぶと主張するが、これを認めるに足る証拠はない。)、「キクマサ」については、これが「キクマサムネ」の称呼に比べ、一般的なものであると認めるに足る証拠もない。 (二) 被告文字標章(「金盃菊正宗」)について (1) 被告文字標章は、いずれも「金盃菊正宗」なる文字を横書き(被告標章(一))、もしくは縦書き(被告標章(三))したものであるが、右標章が、前記原告の「菊正宗」のように、被告の製造販売する商品の標章であると一般に広く認識されるに至っているとまで認めるに足りる証拠はないから(被告が「金盃菊正宗」の文字からなる被告文字標章を使用した商品を製造販売するようになったのは平成九年一〇月ころ以降であったことは前述のとおりである。)、右の標章全体が不可分一体のものとして一つの称呼、観念を生じるということはできない。 そうすると、被告文字標章は、金製の盃を意味する「金盃」と原告商標である「菊正宗」とを結合した標章といわざるを得ないのであって、前記(一)で説示したところによれば、「菊正宗」の部分からは、「キクマサムネ」の称呼及び原告商品の観念を生じるというべきである。そして、仮に「金盃」の部分にも自他識別力があるとしても(後記(2)①参照)、「菊正宗」の自他識別力の方が大きいことは明らかであり、被告文字標章が原告商標(14)の指定商品である清酒に使用された場合には、「菊正宗」の部分が取引者、需要者に対して商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるから、右の部分が被告文字標章の要部に該当することは明らかである。 (2) 被告は、「正宗」は清酒の慣用商標であり、被告文字標章の要部は「金盃菊」であると主張するので、以下検討する。 ① 被告は、明治三一年以来、本高田商店の屋号で行っていた清酒の醸造、販売業を昭和一〇年に法人化したものであるが、その主力商品は「金盃」の銘柄の清酒であり、現在の被告の商号は「金盃酒造株式会社」である。そして、被告の出荷量は、原告のそれには遠く及ばないものの、平成八年度は全国第五五位(三一四八キロリットル)であり、平成七年の阪神淡路大震災の被害を受ける前は、それ以上の出荷量を有していたことが認められる(前記(一)(1)②)。なお、被告文字標章のうち「金盃」の二文字は「」という特殊な書体で記載されている。 そうすると、清酒業界において、「金盃」の標章は、被告商品の標章として、需要者の間で広く認識されるに至っていたものと認められる(なお、被告は、「金盃」が昔中国で皇帝から賜った盃を意味することは広く書物で喧伝されている旨主張するが、被告が指摘する乙三によっても右「金盃」が右被告主張のような意味で広く書物で喧伝されているとまで認められない。仮に、被告の主張どおり認められたとしても、右の意味を有するからといって、そのことから当然に自他識別力を有するとは考えられない。)。 ② しかし、右のことは、一方で、「金盃」には出所識別力があることを意味しても、「金盃」と「菊」とを結合させる必然性を導くものではない。 たしかに、「金盃」と「菊」とは清酒の商品表示としては不自然な取り合わせとはいえず、「金盃菊」という表示により、金盃と菊の図柄が一つになったものを観念することもできる。また、被告は、「金盃菊」について平成九年商標登録出願し、平成一一年四月九日登録されたことが認められる(乙二〇)。 しかし、「金盃菊」なる表示は、「金盃」と「菊」からなるが、両者が常に併存して観念されるべきものとはいえず、また、「金盃」は、「金製または金メッキの盃」の意味で普通に用いられる語であり、「菊」も、それだけでは植物の菊という観念を生じるに過ぎない。 被告は、菊の図柄と金盃の図柄を含む商標(被告標章(二))についての商標権を有しているが、少なくとも昭和四年六月の本件各和解以降、これを使用しておらず、被告が「金盃菊正宗」の文字からなる被告文字標章を使用した商品を製造販売するようになったのは平成九年一〇月以降であったことは前述のとおりである。 ③ 一方、「正宗」が清酒の慣用商標となっており、それ自体としては自他識別力はないことは被告主張のとおりであるが、前記(一)記載のとおり、「菊正宗」が原告商品の標章として著名性を獲得するに至っていると認められるのであるから、「正宗」が清酒の慣用商標となっていることを理由として、「菊」と「正宗」を分離して観察することは相当でない。 ④ そうすると、被告文字標章のように、「金盃」「菊」「正宗」と続けて記載し、清酒の商品表示とした場合、「菊正宗」の商標が清酒の商標として著名であるため、「菊」と「正宗」が不可分一体のものとして称呼、観念され、また、一方、「金盃」自体一つの観念を生じ、必ずしも「菊」と一体化することがないことから、前述したように、「金盃」と「菊正宗」と分離して観察されるのが通常であり、それ以上に、また、それ以外に、分離して観察されることは通常考えられないというべきである。 したがって、「金盃菊」が被告文字標章の要部であるとの被告の主張は採用することができない。 (三) 以上によれば、被告文字標章は、その要部において、原告商標(14)と同一の称呼及び観念を含んでおり、外観(文字構成)においても類似しているといえるから、原告商標(14)に類似するものと認められる。 なお、原告が主張する「菊正宗」の表示(「金盃菊正宗」、「金盃菊〈正宗〉等の表示を含む。)のうち、「金盃菊正宗」なる文字表示については、被告文字標章と同様のことがいえるが、「金盃菊〈正宗〉」については、「正宗」が〈 〉内に記載されているため、見る者をして、「金盃菊」と「正宗」とに分離されて観察され、「正宗」が清酒の慣用商標といえることも考えると、むしろ、右表示の要部は「菊正宗」ではなく、「金盃菊」というべきであり、被告文字標章と同一視することはできない。また、被告が「菊正宗」の文字のみからなる表示を使用したことを認めるに足る証拠はない。 (四) 被告は、酒類の流通ルートや販売方法から出所の誤認混同を生じることはないと主張する。しかし、酒類の流通ルートや販売方法が被告主張のとおりであるとしても、各社製造の酒類商品が、大手スーパー、百貨店等の量販店の酒類販売コーナーや一般酒類小売店の店頭において広く販売されていることは周知のところであり、「菊正宗」が原告の商品の標章として著名なものであるのに対し、「金盃」あるいは「金盃菊正宗」が被告の商品を表示する標章として「菊正宗」を越える著名性を獲得しているとは認められないことを併せ考慮すれば、被告文字標章が使用された商品は、少なくとも一般需用者には、原告の製造販売に係る商品ではないかとの誤認混同を生ずるおそれが多分にあるものと認められる。 更に、被告は、朝日新聞に、被告標章(一)を使用した「金盃菊正宗」を被告の商品であることを明確に表示して広告を掲載し、また、被告は、ウエスティンホテルで開催された一般需用者向けの「灘の酒新春味めぐり」に被告標章(一)を有する被告商品(一)、(二)を出品し、そこには原告の「菊正宗」も出品されたが、 いずれについても、誰からも被告の商品が原告の商品と誤認混同のおそれがある旨の苦情が寄せられたことはない旨主張する。なるほど、被告が、平成九年一〇月二三日及び同月二九日の二回、朝日新聞に、被告標章(一)とその下に被告標章(二)を配した標章及び被告商品(一)、(二)の写真を掲載して、これが被告の商品であることを明示して広告し(甲四の1、2)、また、ウエスティンホテルで開催された「灘の酒新春味めぐり」に被告商品(一)、(二)を出品したこと(乙七、弁論の全趣旨)が認められるところ、仮に、右被告主張のとおり右広告、出品につき苦情が出されなかったとしても(もっとも、原告が被告の被告標章の使用に異議を述べていることは明らかである。)、そのことによって被告文字標章と原告商標(14)との類似性が否定されるものではないというべきである。 したがって、被告文字標章は原告商標と類似しない旨の被告の主張は採用できない。 2 被告の新規登録商標について 乙五二によると、被告は、被告商品(原判決別紙物件目録(一)ないし(三))に用いられているものとほぼ同様の、被告標章(一)と被告標章(二)を組み合わせた商標(結合商標)について、平成一二年四月一三日、登録査定の通知を受けたことが認められる。 しかし、被告の右商標は、格子状の図柄をベースとし、右側に縦書きで「清酒の正統復興」、上部に被告標章(一)と同じ文字が記載され、中央やや下寄りには、被告標章(二)と同じく、特殊な書体による「正宗」の文字と、その文字に一部が隠れた状態で盃と菊の花が描かれたものからなっている。 右商標の構成の中で最も大きく表示されているのは中央に表示された「正宗」の文字であるが、前示のとおり、それ自体は清酒の慣用商標であって、識別力を発揮するものではなく、また、その背後にある金盃と菊からなる図柄から「キンパイギク」の称呼が生じることが考えられなくはないが、それは一般的なものとはいえないから、識別力としては弱いというべきである。更に、「清酒の正統復興」の文字部分についても、一定の出所を表示するものとは認められない。 一方、右商標の構成の中で「金盃菊正宗」の文字は、中央に表示された「正宗」に比べ読みやすく、かつ比較的大きな文字で記載されており、右商標のうち、需要者の注意を惹くものとしても、需要者がその出所を判断するにあたり、最初に拠り所とする部分は「金盃菊正宗」の部分であり、この文字部分に出所表示機能が存するというべきであり、その称呼は、「キンパイキクマサムネ」である。 しかし、原告商標(14)と被告文字標章が類似していることは前記2で説示したとおりであり、現に、被告は、「金盃菊正宗」の文字を書してなる商標について、商標登録を出願したところ(商願平09ー168759)、平成一一年四月一九日、原告商標(14)を含む原告登録商標を引用商標として、呼称において類似するとの理由で拒絶査定がなされているのであるから(甲三六の1ないし12、三七、三八)、被告新規登録商標の登録査定は、商標法4条1項11号に該当するとして無効の判断がなされる可能性があるといわなくてはならない。 また、右「金盃菊正宗」とともに被告の新規登録商標を構成する図柄は、 被告標章(二)とほぼ同一であるところ、後記二のとおり、これを被告が使用することは本件各和解に抵触する行為である。 以上を総合すると、被告が、右被告文字標章と被告標章(二)の結合標章というべき被告の新規登録商標について、登録査定を受けたとしても、これを本件で抗弁として主張することは、許されないというべきである。 3 以上によれば、被告文字標章及び「金盃菊正宗」なる文字表示を使用する被告の各行為は、原告商標権(14)を侵害するものと認められる。 二 争点2(本件和解契約及び本件訴訟上の和解の効力は被告に及ぶか)について 1 当裁判所も本件各和解は有効になされ、いずれの効力も被告に及ぶと考える。その理由は、次に付加、訂正するほか、原判決六〇頁八行目から六七頁五行目までに記載されたとおりであるから、これを引用する。 (原判決の訂正等) (一) 原判決六〇頁一二行目の「大正五年一二月二四日」を「大正六年五月三一日」と改める。 (二) 原判決六一頁三行目の「菊枝」の前に「『金盃菊』の文字よりなる商標(第一二四五六三号)、」を加える。 (三) 原判決六五頁一二、一三行目の「同昭和三一年三月三〇日民集一〇巻三号二四二頁」を削る。 2 当審において付加された主張について (一) 本件各和解が締結されたころの【E】の意思能力については、これが欠けていたと窺わせるに足る証拠はなく、有効に授権がなされたうえ、本件各和解が締結されたものと認めることができる。 なお、被告は、本件和解契約において支払われた和解金一万四〇〇〇円が低額に過ぎるとか、【E】に内密に締結されたものであると主張するが、本件各和解では、当時の有力新聞社に和解を発表することが約されており、実際に、その旨の掲載がなされている(甲三九、四〇)。したがって、【E】に内密でなされた和解であるとは考えられない。 また、和解金については、これを【E】が知らなかったと窺わせる事情もなく、和解が有効に成立し、これが公表されていることを考えると、和解金が当時の経済的価値に照らし、妥当な金額であったか否かについて、検討を加えるまでもなく、本件各和解の効力に影響を及ぼすものでないことは明らかである。 (二) 本件和解契約の解除 被告は、原告が、平成三年春ころ、被告の大口二次卸として「金盃」印商品のみを取り扱っていた合資会社月の友に、その事情を知悉しながら原告との特約店契約をさせた結果、被告は、右月の友との取引高、ひいては首都圏を中心とする東日本地区での売上が大幅に減少するという損害を被ったと主張するが、右の事実を認めるに足る証拠はなく、また、被告主張の事実のみをもって、原告の右行為が、本和解条項に違反するとも解せられない。 被告の右主張は理由がない。 (三) なお、被告は、被告商標が、【E】が灘酒造家の中でも最も古い名家である「松屋」から取得したものを譲り受けたもので、松屋の有していた登録商標は、原告のものより古いものであるから、【E】が本件各和解をするはずがないと主張する。 しかし、前記引用の原判決六〇頁九行目から六二頁一二行目に記載されたとおり、【E】は、被告商標の登録を受けた後、連合商標として「金盃菊正宗」の文字からなる商標等九件の商標の登録を受けたところ、原告が、右商標登録無効審判の請求をし、特許局が、大正一五年四月一日、右連合商標として登録された商標を無効とする審決をし、その上告審は上告棄却の判決をしたこと、【E】は、大正一一年一一月一五日、清酒を指定商品として「金盃菊正宗」の文字を横書きした商標の出願が登録された後、原告が、右商標登録無効審判の請求をし、特許局が、 昭和二年一月一四日、右商標を無効とする審決をし、その上告審は上告棄却の判決をしたことがそれぞれ認められ、本件各和解はこのような経緯を受けてなされたことを考えると、いくら由緒のある「松屋」から譲り受けた商標であるからといって、本件各和解をすることが不自然であるとは到底いえない(なお、甲四六、乙四九によると、松屋の商標の登録が原告のそれより古いとは認められない。)。 また、被告は、「松屋」から譲り受けた商標の金盃には「鶴」が入っているのに、本件各和解の対象となった商標の金盃には「鶴」が入っていないと主張するが、被告が「鶴」と主張するのは、他の菊の図柄と照らし合わせても、菊の枝を切り取った切り口としか認められず、その主張の前提を欠く。 三 争点3(被告の各行為は不正競争行為に当たるか)について 被告の各行為のうち被告文字標章及び「金盃菊正宗」なる文字表示の使用は、前記一のとおり原告商標権(14)を侵害する行為と認められるが、それのみならず、不正競争防止法2条1項1号、二号にも該当する。 1 原告の商品表示とその周知性 前記一2(一)のとおり、原告は、江戸期から清酒の製造、販売業を営んでいた嘉納家の本家の営業を法人化する形で設立された会社であり、当初、その製造、販売に係る清酒に「正宗」の荷印を付けていたが、明治期以降、酒名を「菊正宗」とし、各種の登録商標にアレンジする形で使用されてきた。 原告は、「菊正宗」の表示を含む三〇件以上の原告商標(以下「原告表示」ともいう。)についての商標権を有し、原告は、右原告商標を用いて清酒の製造及び販売を行なってきており、AIPPI・JAPAN作成の「日本有名商標集」にも「KIKU-MASAMUNE」及び「菊正宗」が掲載されている。 原告の「菊正宗」の出荷量は、平成七年度は全国第七位、平成八年度は全国第六位である。 これらの事実から、「菊正宗」なる原告表示は、わが国において原告の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されてきたことは明らかであるのみならず、原告表示は、不正競争防止法2条1項2号の「著名な商品表示」にも該当する。 2 被告の商品表示 被告は、被告商品の販売等につき、被告標章を表示し、また、「金盃菊正宗」及び「金盃菊〈正宗〉」という表示をして清酒の製造及び販売をしようとしている。 被告文字標章及び「金盃菊正宗」なる文字表示の要部は、前記一1のとおり、「菊正宗」の部分であるが、被告表示のうち「金盃菊〈正宗〉」なる表示については、前記一1(三)のとおり、「金盃菊」と「正宗」とに分離されて観察されるから、右表示の要部は「菊正宗」ではなく、「金盃菊」というべきである。また、 被告標章(二)についても、金盃と菊の図柄が一体の図柄として観念され、「菊正宗」の観念、「キクマサムネ」の称呼を生じず、「菊正宗」が要部であるとは認められない。 3 両表示の類似、混同について 原告表示と被告文字標章及び「金盃菊正宗」なる文字表示を対比した場合、いずれも「菊正宗」を要部とし、外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似しているというべきであり、誤認混同のおそれが認められる(なお、不正競争防止法2条1項2号の適用にあたっては、誤認混同のおそれは要件ではない。)。 なお、被告表示のうち「金盃菊〈正宗〉」の要部は「金盃菊」であり、 「菊正宗」と別の観念を生じ(金盃と菊とが併存する図柄等)、その称呼は「キンパイギク」もしくは「キンパイキク」であり、「菊正宗」と対比した場合、類似していると直ちにはいえない。 また、被告標章(二)についても、前記2のとおり、原告表示と対比した場合、類似しているとはいえない。 四 争点4(差止の必要性等)について 当裁判所も、原判決主文の限度で、被告の表示の使用を差し止める必要があると考える。その理由は、原判決六七頁七行目から七二頁四行目までに記載されたとおりであるから、これを引用する(ただし、原判決六七頁一〇ないし一三行目(三箇所)、六八頁一、三ないし五、一一ないし一三行目(七箇所)、六九頁二、 六行目(二箇所)の「被告商標」をいずれも「被告標章」と、七〇頁二行目の「といえる」を「といえるが、『金盃菊正宗』の文字表示については、『』という特殊な文字を使用しておらず、全体がゴシック体もしくは明朝体の活字で記載されている以外は、被告文字標章と同じであり、前記一、三に説示したとおり、原告商標権(14)もしくは、原告の周知商品表示と類似し、使用差止請求には理由がある」と、同頁一二行目の「普通名称」を「慣用商標」と各改め、七〇頁末行の「『キンパイキクマサムネ』あるいは」及び七一頁五、六行目の( )を各削る。)。 五 以上によると、原告の請求は、原判決主文第一、二項掲記の限度で理由があるから認容し、その余は理由がないから棄却すべきところ、これと同旨の原判決は相当である。よって、本件控訴を棄却し、控訴費用の負担につき民事訴訟法67条、61条を適用して、主文のとおり判決する。 |
| 裁判長裁判官 | 鳥越健治 |
|---|---|
| 裁判官 | 若林諒 |
| 裁判官 | 山田陽三 |